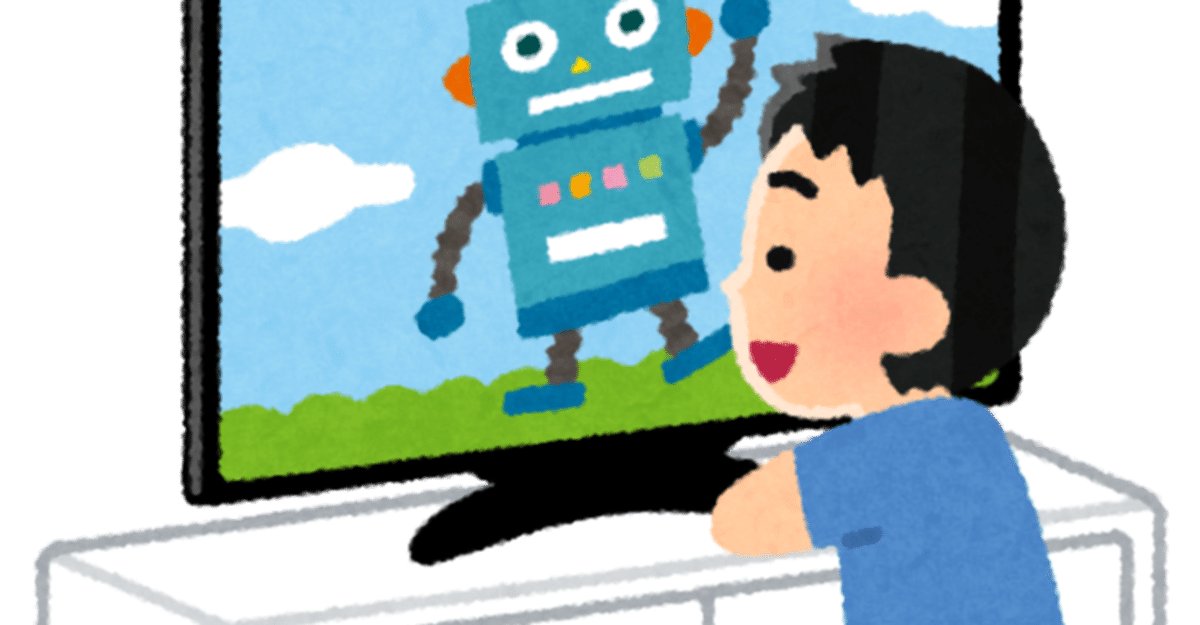
知能指数が高い人はどんなテレビ番組を見ますか?Quoraでの回答を書きました
知能指数が高い人々がどんな番組を好むのかは知らないのですが、逆の人々のことは多少は知っているので参考になれば幸いです。
結論を先に書いておくと、テレビジョンとは無意識にひとを受け身にする装置であり、受け身の姿勢だとひとは真に充実を感じられないものです。
私は中度~重度知的障害の方を支援する福祉施設で働いています。
彼らの日常を観察しているとIQが低下するにしたがって、テレビ番組の嗜好が言語による情報を分析しなくてもよいものになる傾向があると感じます。
経済などのニュースは言うに及ばず、小学生レベルの教育番組ですら視聴するには耐えないようです。代わりに歌や踊りなどの非言語的な番組や、児童向けの予定調和で構成された番組を、ストーリーに注目するのではなくフンイキで観るようになります。
私の受け持ちは下は20代半ばから上は50代後半までなのですが、50歳を過ぎてもお母さんといっしょを観ている姿をみかけると、名状しがたい哀しいキモチになります。
そしてさらに障害が進むとそれすらも理解できなくなるのか、ただ画面を眺めているだけになり、日常の行為全般にも自発性がほぼなくなります。そしてIQ20近辺では自分でテレビのスイッチを入れることも、部屋の電灯を点けることも難しくなります。彼らの知的環境は彼ら自身の気質と、習慣という反復活動によって負のスパイラルを形成しているように見えます。
おもうにテレビジョンを視聴する習慣とは、繰り返し発信される情報に対して受け身となり、無防備のまま記憶をさせられているに等しいといえます。
製作者側は人間心理を駆使して番組やCMを構成し、巧妙にスポンサーのサービスを視聴者に買わせなくてはならないからです。そのためにはミームとして情報を無意識下に刷り込んでおき、いざ視聴者がなにか商品やサービスなどを選択する機会に際して、トリガーとしてその候補のひとつに選ばせる必要があります。
具体的に商品名を含んだフレーズや歌や映像を、そのサービスの快適さや楽しさ、新鮮さ、いかに得をするかのイメージを感情としてありありと想起してもらいたいのです。
政府広報などもこれに然りで、情報を選択し供給できる立場の視点から見ると、その優位性を保つためには我々の考え方をできるだけ受け身のレベルに留めておきたいのではないでしょうか。なぜなら発信された情報から提起される相互の関係性や利害構造に疑問を持つなどのメタ的な自発思考は、彼らの考え方、彼らの目指すべきところ、彼らの利権を我々が選ばない可能性があるからです。これはGoogleなどの検索サービスにおいても言え、彼らは別に我々の味方などではなく、情報のエコシステムから発生する利益がいまはただ合致しているだけではないでしょうか。

ここで受け身でなにかをしているときのことを思い出してください。
行かなければならない学校や職場。
そこへ行くために乗らなけらばならない満員電車。
やらなければならない学習や仕事。
参加しなければならない会合や飲み会。
そしてそれらの場所で味わう雰囲気。
結論としてひとは受け身においては、真に充実を感じないものです。
思考と精神の姿勢が主体的であれば、学校や職場にいる時間は充実するのでしょうが、それには情熱を注ぐ必要があります。
テレビ番組をただ漫然と視聴する、つまり情報を受け身で消費する意味は、自身の好奇心をいたずらに浪費しているのであり、集中力と情熱が霧散しているのです。
情熱とは読んで字の如く『感情』から発せられる『熱』であり、成長する行動のだいじな原動力です。
そして情熱の源とは好奇心なのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
