
衆院選の第二弾です。
衆院議員になるには、ハードルがずいぶん高いので、市会議員になるには、どうしたらなれて、いくらお金必要かを調べてみました。
市会議員に、どうしたらなれるのか
調べてみましたが、拍子抜けするほど、条件は厳しくありませんでした。
下記の2項目が満たしていれば、立候補出来ます。
① 満25歳以上の日本国民
② 3カ月以上、立候補する市内に住んでいること
しかし、立候補は出来ますが、選挙で当選しなければなりません。
さらに、供託金30万円が必要になります。
この供託金は、一時的に選挙の時に預ける現金のことです。
さらに、この供託金は、「有効投票数÷定数×0.1」の票を獲得しないと没収されるそうです。
<有効投票数とは>
投票総数から無効投票数を差し引いた票数。白票や候補者の氏名以外を記入した票、複数の氏名を記入した票などは無効票となる。有効投票数は法定得票数の算出基準としても用いられる。
<供託金没収のシュミレーション>
20万都市で、有権者が16万人いて、選挙の得票率が40%であれば、
16万人×40%=6万4千人が有効投票数、議員に定数が28人であれば
6万4千人÷28人×0.1=228票が、供託金の没収されないギリギリのラインです。
それなりの応援してくれる母集団がないと、供託金の没収はまちがいないと思います。

なぜ、選挙で供託金があるのでしょうか
総務省の説明によりますと、「総務省「乱立を防ぐため」だそうでうす。
供託金制度は昨年12月に町村議選(15万円)にも導入され、全ての公職選挙に広がった。なぜ必要なのか。総務省は「当選を争う意思のない人が売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐため」と説明する。
これが、今回の衆院選ともなりますと、なんと供託金は小選挙区300万円、比例代表は600万円。
2017年の前回衆院選では、小選挙区で174人分の5億2200万円、比例は10団体の9億9000万円が没収されたとの事です。
今回の衆院選挙でも、供託金合計15億円ほど没収され、国庫に入っていると思います。
しかし、立候補した時に、選挙運動用ポスター製作費や選挙カーのレンタル代・燃料費といった費用の一部を公費負担する「選挙公営」制度があるそうです。
しかし、議員さんのユーチューブを見ますと、この選挙公営制度だけでは足りなく、持ち出しも多いため、一般的な市議会議員選挙の費用は200万円~800万円。
衆院選挙ですと、6,000万円以上とも言われています。
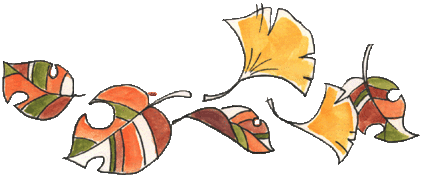
どんな費用でしょうか
選挙事務所の賃料、電話代、ハガキや封筒などの郵送料(ここは、公費負担)や、FAX、電話代。
選挙ハガキ(法定ハガキ)や選挙ポスター、選挙ビラの印刷代(公費負担)
選挙カーの看板や事務所の看板、拡声器代や新聞広告代など。
画鋲やボールペン。運動員の弁当代、お茶・お菓子など。
宿泊費、選挙に用いた手袋、ガムテープなど。
意外とこまごまして、そんなにかからないような気がしますが、選挙の運動員が延べ1日50名×1週間=350食
昼食の弁当代だけで、なんと350食×仮に500円=17万5千円です。
他の雑費も同様でしょう。
やはり市会議員は、一定の資産をもち、応援してくれる組織を持ち、地域(市会議員の場合)のために、貢献したい方でないとなれないことがわかりました。
さらに、くわしく知りたい方は、下記ユーチューブ動画をご覧ください。
茨木市議の占部相馬市会議員のYouTubeから
議員になるには・報酬は
では、次回からは、選挙も一段落しましたので、本題の三種の神器「転職」「投資」「健康」に戻って掲載してまいります。
よろしくお願いいたします。
よろしければサポートお願いいたします。今後の記事の取材費にさせて頂き、 さらに魅力ある記事を掲載いたします。
