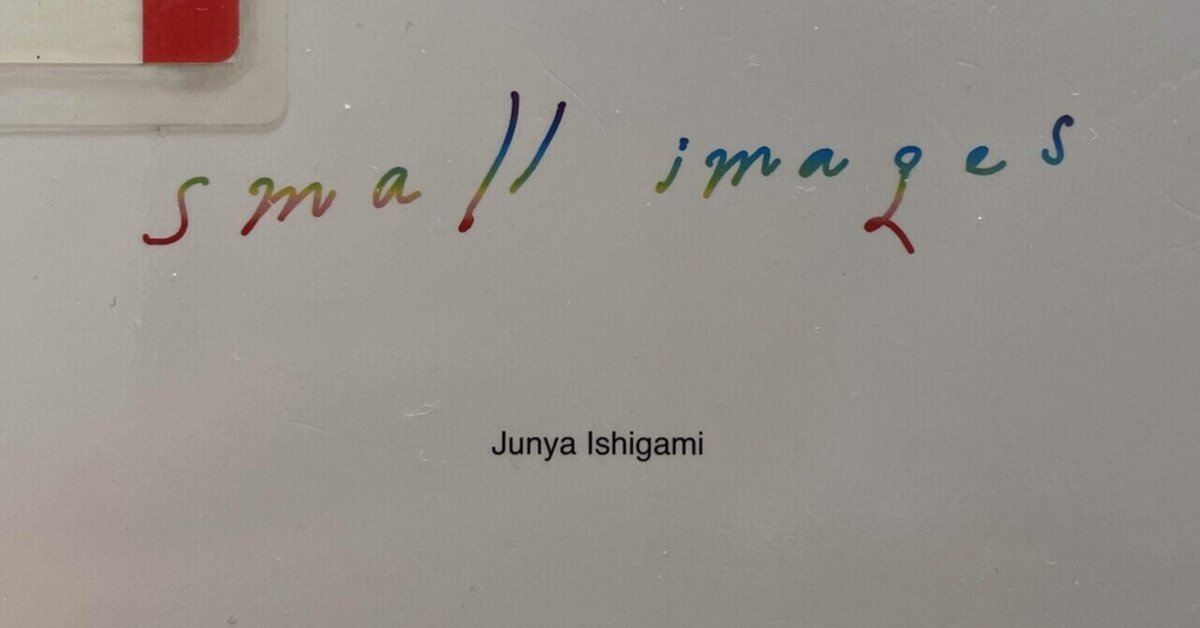
石上純也 / ちいさなまとまりから建築について考えたこと
読書感想文2個目を書くぞ〜
まとめ方は同じように、本の中のセリフ、ポイント、考えたこと、とかをまとめていこうかなって考えています
それでは
小さな建築のようなテーブル。
その小さな建築を、与えられた既存の空間を敷地と見立てて、建築を敷地に配置するように置いていく。
石上純也さんはテーブルというものは、家具というはどちらかと言うと建築に近いのでないかと考えている。
狭い部屋に巨大なテーブル(50㎡)が目の前にあったとき、
恐らくここら辺が自分でエリアということは認識できるのだと思う。
だから壁で区切る必要はなくて、間には植物などをおいて置けばいいよっていう考え
現代のソーシャルディスタンス?のような感じがして自分自身はとても面白いし魅力的だなぁ〜って感じた。
もしあったら行ってみたいというわくわく感も
僕は、このテーブルを設計するときに。これ自体がどのように成立しているかがなるべくわからない方が良いと思った。
理由はその直後に記されていて
【構造的に特殊なことをしているけれど、その構造の原理は極力見えないほうが、使う人にとっては居心地がいいと思ったからである。】
確かに、頭を使わずにそういうこともあるよなって感じで受け入れられたらそれが理想だと思う。
日頃使っているiPhoneとかMacとかもわざわざこれがどうプログラムされてるとか考えないし、
とりあえず使ってるって感じをしているな。
それを感じさせないためには、
やっぱり圧倒的なデザイン力が必要だよなぁ🥲
僕は自然のよさというのは、ルールがあるようで実はルールが見えないところだと思う。
具体的も一緒に
「たとえば、日常生活のなかで、天気を気にしている人は多いと思うが。そのシステムまで気にしている人は少ないと思う。
一瞬は驚くのだけれど、それについて特に解明されなくても、「まあ、そんな日もあるかな」
と、そんなかんじで受け入れる
そういうことは、日常生活のなかで普通にある気がする。その日常的な普通さ、あるいは、自然のなかに溶け込んでいくようなものを考えたい」
そう書いてあった!
どう成り立っているか分からないけれど、ここにこうやってあるんだからまあいいや
コンセプトや価値観があるので、そう思えてしまうようなもの、あいまいなものを
作り上げていくプロジェクト。
これはまあ美術館とかアートでしか通用しないよな〜まあ、絶対に普通の店舗とかでやると
Instagramのスポットとかになって資本主義のいい餌になっちゃうから絶妙なバランスを保ちつつ
天気のような普通さを出すのがとても大変そうだし、ふらっとそれを見た時に流されないで、
その美しさを感じ取れるように普段から
感性を磨いていきたい
家具や道具や植物など、建築以外のいろいろな具体的な要素な入ってきても、どこまでも壊れないような抽象性を考えたいと思っていた。
開かれた抽象性
これは「神奈川工科大学 KAIT工房」でのお話
あいまいで、かつ具体的な空間を計画するにはどのようにしたらよいか
例えば、いま乗っている電車は均等均質な素材、配置で座席が並べられそれで完成をしている。
そこで1つの座席の位置を少し広く壊して、新しくそこにスペースを作ったとする。
そこは、広い荷物や少しや本などが置ける机が新しくおかれ、その分ドアは1人が通るようのものになるだろう。
つまり、ここでは
現代において固定されている考え(座席の配置)
これが具体的というものを通り越して
1種の抽象性もったものとなっていて
それは少しの配置やものが置かれても
決して電車という役割を壊すことなく
全てを受けて入れてくれるということ、、、
といった感じなのだろうか💦💦
本当に言いたいことは、その空間の作り方であったり、魅力的な建築を生み出すためのメソッドなのだろうが、たとえば
天井を露出させる
トップライトから空が見えるように
といった操作の事だろう。
思考の余白
建築を設計するときに、しょうりゃくについていろい考えることがありその省略を
「思考の余白」と呼ぶこととする。
具体的には。壁が出来上がれれば
その壁の向こう側にある空間は隠れ、
その2点の間にある空間は省略される。
省略とは、建物を抽象化する行為の1つだと思う
と石上純也さんは考えている。
これ自身は建築を設計する上での美学に繋がっているように感じる。
本の返却が近づいてきたのでこの辺で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
