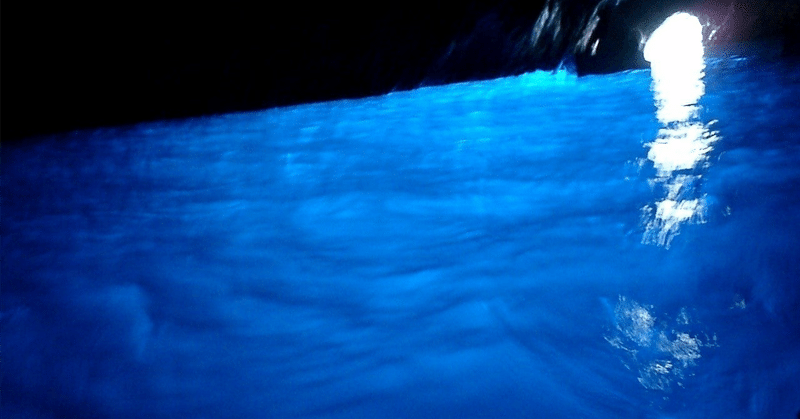
コンクール審査員が好む作風
お疲れさまです。
このところ、
応募してもいない脚本コンクールの、
審査員の選評をむだに漁っています。
脚本コンクールにおいては、
対策は存在しない、
と捉える向きもあって、
ある側面から見ればそうなのでしょうが、
審査員の好みがある以上、
それに応じた対策もあるのでは、
と自分は考えています。
コンクールの傾向と対策に関して、
以前別の記事で書きましたので、
今回は番外編となります。
高いリアリティラインを好む
当たり前ですが、
コンクールの審査員の方々は、
リアリティのある作品を評価をします。
リアリティがあるだの、
リアリティがないだのは、
選評でよく飛び交うフレーズです。
これはコンクールに限った話ではなく、
映画レビューでもそうした言葉は多く見られますし、
自分としましても、
リアリティが評価されることについては、
何ら異論ありません。
それを踏まえた上で、
では、
(審査員のいう)「リアリティがある」って具体的に何を指すのだろう、
といった話をしたいのですが、
https://www.nhk.or.jp/osaka/event/radiodrama/senpyou.html
BKラジオドラマ脚本賞の審査評(上記リンク)にて、
興味深い選評を見つけましたので、
引用いたします。
審査会では「21歳で引退はリアリティーがない」「スランプの主人公が何故その神社に行ったのかの理由がない」「引退してまでこの少年を指導したいと思った動機がわからない」との声が出ました。
オーディオドラマ脚本としてのこれらの欠点に反論の余地はありません。ですが、僕は最後までこの作品を推しました。
というのも、最初に書いたようにアニメや漫画の世界で想像すれば(二人を貞本義行のキャラクターで想像し、二人が出会う神社を山本二三の描く背景で想像し、二人のちぐはぐな会話を有名声優の声で想像すれば)、これらリアリティー不足の部分はほとんど許せてしまうような気がしたからです。
上記選評は、
最終候補作「海を滑る子」に対するもので、
審査員の方は、
候補作へのリアリティ不足を指摘し、
アニメ的だと評した上で、
しかし一方で、
アニメとして捉えるなら、
そうしたリアリティでも成立する、
といっています。
この選評の意味を深く読み解くには、
まずはリアリティラインについて触れる必要があります。
ストーリーには、
リアリティラインという、
少々ややこしい用語があり、
簡単にいえば、
ストーリーがどの程度リアルに忠実か、
そのパーセンテージを示す言葉です。
たとえば、
リアルそのものを写し取った私小説などは、
リアリティラインが高いストーリー(=リアルに忠実なストーリー)です。
反対に、
バトルやファンタジーを題材にした少年漫画などは、
リアリティラインが低いストーリー(=リアルとはかけ離れたストーリー)となります。
映画でいえば、
同じ宇宙を舞台にストーリーでも、
ディティールに傾いた内容の「アポロ13」はリアリティラインが高く、
非現実な設定を持つ「アルマゲドン」はリアリティラインが低いストーリー、
といえるでしょう。
ただし、
一つ補足として、
「リアリティラインが低い」と、
「リアリティがない」は、
混同しやすいですが、
違います。
この点が、
先述したように、
少しややこしいところなのですが、
リアリティには「リアル」のほかに、
「説得力」の意味もあり、
たとえば、
逃げる犯人を刑事が追うシーンがあったとして、
逃げる犯人が偶然雷に打たれたため、
捕まえることができた、
そういったご都合主義のシーンなら、
アニメであろうと、
漫画であろうと、
リアリティのない描写となりますが、
(つまり説得力を持たない描写)
一方で、
逃げる犯人の正面から偶然ランニング中の柔道部員たちがやってきて、
捕まえることができた、
そういったシーンであれば、
確かにご都合主義で、
リアルではありませんが、
「名探偵コナン」などの、
リアリティラインの低いストーリーでなら、
描写として成立するはずです。
あるいは逆に、
もし犯人が偶然雷に打たれた、
が実際に起こった出来事で、
それを写し取っているのであれば、
それはリアルな描写となりますが、
描写に説得力はありません。
(俗にいうリアリティのないリアル)
したがいまして、
リアリティラインとは、
低いから悪いわけではなく、
高いから偉いわけでもない、
リアルに忠実か否か、
単にその度合いを示しているだけのもの、
といえます。
以上を踏まえ、
先ほどの話に戻しますと、
先にあげた候補作「海を滑る子」は、
選評を読む限り、
アニメなら成立するということなので、
リアリティがないのではなく、
正確には、
リアリティラインの低い作品だったのだと思います。
リアリティラインを野球のストライクゾーンに見立てると、
応募作は球です。
リアリティのない応募作がボール判定になるのは当然ですが、
しかし一方で、
投げられた球が枠の中に収まる限り、
高めだろうと、
低めだろうと、
等しくストライクであり、
どんなコースをよしとするかは、
その人の好みの問題でしかありません。
そう考えたとき、
審査員はストライク判定が厳しく、
低めの球に対しては、
ボール判定をくだす傾向があるのでは、
というのが一つの推測となります。
もちろん根拠はありませんが、
自分の応募作が落ちる要因の一つが、
それだと思います。
ストライクゾーンぎりぎりの、
低めいっぱいの、
いちばん際どいコースに、
自分としては球を投げているつもりですが、
審査員は低めを好まないから、
たぶん全部ボール判定されているのだと思います。
(実際ほんとにボールなのかもしれませんが)
不思議なのは、
なぜ映画やテレビドラマでは、
リアリティラインの低いストーリーが、
往々にして、
漫画的(アニメ的)だといわれ、
ダメなストーリー扱いされるのか、
という点です。
理由の一つとして、
リアリティラインの低いストーリーを受け持つ場として、
漫画の媒体が存在しており、
そうしたストーリーなら、
漫画を読めば事足りるから、
があると思いますが、
しかし、
それをいうなら、
リアリティラインの高いストーリーだって、
純文学を読めば事足ります。
あるいは、
映画やテレビドラマは生身の人間が演じるものだから、
リアリティラインの低い、
漫画的な設定やタッチのストーリーだと、
チグハグな世界観になってしまう、
そうした理由も思いつきますが、
前述したように、
「アルマゲドン」や「ティンカップ」など、
映画でも漫画的な作品って少なからずありますし、
近年は漫画を実写化した(リアリティラインの低い)映画も多いので、
生身の人間が演じる媒体だから、
はいまいち納得のいく説明ではありません。
結局、
リアリティラインの低いものを嫌うのは、
コンクール特有の傾向のような気がします。
唯一、
フジテレビのヤングシナリオ大賞のみ、
審査員のストライクゾーンが広い、
つまり、
幅広いリアリティラインから作品を選んでいるように感じますが、
なににせよ、
低めに投げて、
わざわざ落とされるリスクを高める、
そうした必要はないので、
コンクールでは、
低めを避けるに越したことは、
ないかと思います。
原石感を好む
今あげたヤングシナリオ大賞ですが、
去年の暮れに受賞作が発表されました。
https://www.fujitv-view.jp/article/post-1034115/?amp
以下は、
ヤンシナに限った話と前置きして、
「原石感を好む」は、
審査員の方々の過去の発言などから、
ほぼ確かといっていい、
信用に値する傾向といえます。
去年の受賞作の中で、
気になった作品の一つに、
佳作「イージーライフ」があります。
上記リンク記事の受賞インタビューにて、
作者の方が「受賞作は処女作だった」とおっしゃっており、
それを知ったことによる先入観もあることは否めませんが、
「イージーライフ」を読んで、
西川美和監督の「蛇イチゴ」を連想しました。

この作品は、
西川監督のデビュー作であり、
一言で感想をいえば、
才能の片鱗を感じさせる人が、
構成度外視で、
感性だけで書いたみたいな、
そんな感じの作品であり、
(その後の作品を見る限り、
西川さんは構成術を学んだのだと思う)
「イージーライフ」も、
構成面から見ると、
考えづらいタイミングで回想が挿入されていたり、
不備がないとはいえないのですが、
しかしそれがかえって、
小手先ではない部分で人間ドラマを書いている感じを、
ふしぎと作品にもたらしています。
何年か前にヤンシナ大賞を取った「サロガシー」を読んだときも、
同様のことを思いました。
たぶんですが、
審査員の方にとって、
ストーリーを刀とするなら、
構成は鞘みたいなイメージなのかもしれません。
抜き身であることを最良とし、
構成の技術を用いると、
その魅力が失われてしまう、
そうした捉え方なのではないでしょうか。
自分は刀がストーリーなら、
構成は砥石のようなもので、
刃の切れ味を鋭くするためにあるものだと考えていますが、
構成理論を用いず書かれた人間ドラマからは、
確かに抜き身のような凄みを感じます。
なので、
原石感のある脚本に対して、
自分みたいな人間が、
回想のタイミング的にどうなんだろうか、
など下手に口を出した場合、
たとえそれが的確な指摘だったとしても、
その通りに直してしまうと、
審査員がよしとするものが失われてしまうことになりかねません。
(繰り返しますように、
ヤンシナに限ってですが、)
その意味で、
応募作は下手に直さず、
粗削りのまま勝負したほうがいいかと、
自分は考えます。
推察するに、
コンクールの審査では、
文学的であることを重んじているのではないでしょうか。
自分などは、
小説を読んで育ってきたから、
リアリティラインの高いストーリーは、
純文学で間に合う、
と思ってしまいます。
あるいは、
脚本から作者の息づかいが聞こえてくる、
作家と作品が地続きになったような、
そうした作家的な作品も、
小説のほうが向いていると思うので、
映画やテレビドラマでは、
作者と作品が完全に切り離された、
純粋な娯楽作品を見たいと思っています。
でもそれをいうと、
脚本とはかくあるべし、
という話になってしまうし、
この記事で書いてきた、
審査員の好みに対する疑問の、
ブーメランに他なりません。
別に純文学のような脚本があってもいいし、
あるいは、
作者の息づかいを感じさせる、
映画やテレビドラマがあってもいい。
結局のところ、
やはり好みの問題でしかない気がします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
