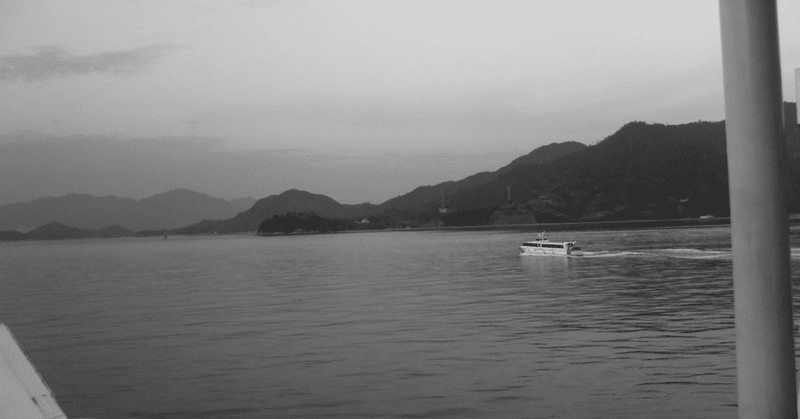
「インドの歴史 多様の統一世界」 近藤治
講談社現代新書 新東洋史 講談社
1977年初版本。なので、研究はその後45年も進んでいるわけで、その辺注意。
この本の特徴として、通史に移る前に「インド史再考」として2つの章を割き、インダス文明とカースト制度、国家と民衆を論じている。通史の最初と最後というわけ。なかなか意欲的な構成なのではないか。
インダス文明
その中でインダス文明のところを少し。近藤氏はインダス文明を先史時代と歴史時代(鉄器時代)の中間に位置付けている。
インダス文明を担った民族としては
1、地中海沿岸に住んでいたドラヴィダ族がだんだん東進し、インダス川流域を経て、最終的に南インドに来た
2、シュメール文明となんらかの関わりがある人々
の可能性を挙げている。後藤氏の「メソポタミアとインダスのあいだ」(だっけ?)を読んだ身としては2に賛同(あるいはイラン高原の民族)なのだけど、1も楽しい? だいたい、ドラヴィダ族って地中海沿岸に住んでいたというのは初耳。
インダス文字はサンプルが少ないので解読できないが、印章にある動物は各都市の象徴(モヘンジョダロはこぶ牛)で、その上に都市連合の象徴としての動物(一角獣)というのは確からしい。
(2022 04/11)
インダス文明と歴史時代が接続しているのか、については諸説あるが、例えばグジャラート辺りでは接続が確認できる、とか、自分の直観より関係はありそう。
カースト制と時代区分
カースト制は、古代のヴァルナ制(バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ)と、中世の出生と職種が不可分となって成立したジャーティの合成したもの。ヴァルナ制は同一氏族内での婚姻を禁じた文化人類学でよく見るもの(そいえば、古代インドにも「エディプス王」みたいな話がある)。
一方、ガズナ朝のビールーニー(972-1048)の「インド誌」によると、身分が下の者が神への苦行していただけで(身分にふさわしくないとされ)殺された、という事件が驚きとともに書かれている。
インドに古代-中世-近世-近代-現代という時代区分を持ち込むのが妥当かどうかの問題もあるが、この本ではとりあえず近世をムガル帝国、近代をイギリス占領(一応セポイの乱くらいから)、現代を独立以降、としている。一番さまよっている?のが古代-中世の区分。マウリヤ朝後という区分、グプタ朝崩壊後、イスラム化後、など。この本ではグプタ朝崩壊後という区分で行くようだ。
(2022 04/12)
インドの歴史地理
カブールからパンジャブ-デリーへの道を始めとして、インドに侵入するあるいはインド内を移動する道はかなり特定なものに限定されるという(ウマイヤ朝のイスラーム勢力だけは海沿いに来たので例外)。特にパンジャブからインド中原までは砂漠と山地で狭められ、数々の戦いがそこで起こっている。インドの街は多くの場合、こうした道筋の交点に存立する。
第3章「古典文化の展開」
16国→4国→マガダ国→マウリア朝と統一されていく。この歴史は中国の諸子百家時代と同じく、思想的にもこれまでのバラモンを中心にした宗教、祭祀儀礼主義のような宗教から脱しようとする宗教が出てくる。仏教もそのうちの一つ。仏教は宗教であるよりまず学問なのだ、という。
すべての人民は王の子であるという考え方と、このように、ギリシア的な意味の奴隷が一般的には存在しなかったという事実と、この二つの側面の統一的把握のなかにこそ、実は、ギリシア的古典古代とは異なるアジアの古代の特質があったのではなかろうか。そしてこのような一般民衆の存在形態と、その対極にある古代的な専制君主との関係こそが、まさしく「総体的奴隷制」ではなかったのか。
(p105)
この本をインドの真ん中に、北に前田耕作「バクトリア王国」、南に家島彦一「インド洋海域世界」を置いて読めば、インドが立体的に理解できる、はず…
(2022 04/19)
時系列編から古代インド史
マウリア朝から、シュンガ朝、それから北のクシャーナ朝と南のサータヴァーハナ朝(アンドラ朝)、そして古代集大成のグプタ朝。クシャーナ朝はカニシカ王と仏教庇護者、ガンダーラ美術、サータヴァーハナ朝はデカン高原と海上交易、ヒンドゥー教・美術。それらが統合しグプタ朝が成立。「シャクンターラー」のカーリダーサとアジャンターの石窟の芸術。
(2022 04/21)
インド中世史
ラージプト(王族の息子という意味)は貴族からの独立組という点でも、尚武の気質という点でも、また各々が独立闘争しまとまりなかった点でも、日本の平安期の武士団に共通していると思う。ラジャスタンはこのラージプトから来ている。
このラージプト達が争い、三国鼎立時代に最終的になったのが、6世紀のヴァルダナ朝滅亡後からイスラーム進出までのインドの歴史。
というわけで、第2章でも述べられたハイバル峠-パンジャブ-インド中原というコースで、イスラーム勢力が侵入してくる。まずガズニ朝マフムードが1019年に、この時は先程の三国のうちの一つの王国グルジャラ=プラティハーラ朝の王は(元のヴァルダナ朝の都カナウジで)七重に囲まれた城壁にいながら、何もせずに逃亡し捕まる。グジャラートではヒンドゥー寺院を破壊し、残骸を粉にして地元のモスクの参道に撒いたという。
続いてゴール朝ムハンマド、一回(1191)は人海戦術と象軍で勝利したインド側ラージプト連合だったが、戦術を練り直し挟撃作戦に出たゴール朝軍に最終的に敗れ(タラーインの戦い、1192)、結果ベンガル地方までイスラーム勢力下となる。
(2022 04/23)
インドの南北朝
第4章「中世世界の形成」読み終わり。1206年(デリー・スルタン朝)から1526年(ムガル帝国)くらい。北のデリー・スルタン朝と、デカン高原のイスラーム勢力バフマニー朝、そして南端のヒンドゥー勢力ヴィジャヤナガル朝。北では一時インド大半を抑え亜大陸中央部に新都を建設しようとしたが資金が尽き、かえって弱体化してしまったり、それから一時的ではあるがティムール軍が来たり(1398)。バフマニー朝では北よりムスリムが少数派だったため外部からムスリムの移住を奨励したが、国の勢いがなくなるとそれらの外部からの人々と元々の人々との抗争が激しくなっていった。ヴィジャヤナガル朝はインド洋交易などで栄えたが、最盛期を過ぎると、北のバフマニー朝との戦争に敗れ衰退していく。
ところで、この本では、ヒンドゥーの下層民がイスラームを自らの解放につながるとして歓迎した、と書いてあるのだが、実際どうだろう? そこまでは言い過ぎのような気も。
シク教徒とムガル朝
シク教徒は「インドのプロテスタント」? カースト制の否定、イスラームのスーフィズムから取り入れた神は唯一で人間は平等である、という思想。これ以降もそうした思想は、ヒンドゥー、イスラーム双方から出てくる。
ムガル朝の繁栄(農村部から支配階級の富吸収、貿易、流通、市場制度)と、政権衰退による近代化失敗
19世紀前半インドは、近代思想が発展するか、イギリス支配が確立するかの瀬戸際、競争状態だった?
(2022 04/25)
ムガル帝国の官僚制。郡までは中央から派遣。農民からの年貢は金納制。時代が降るに従って経費が膨大に。ここも日本の江戸時代の官僚制と比較できるのでは。と思うのはまだ自分に個別の知識が足りないからだろうけど。
(2022 04/26)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
