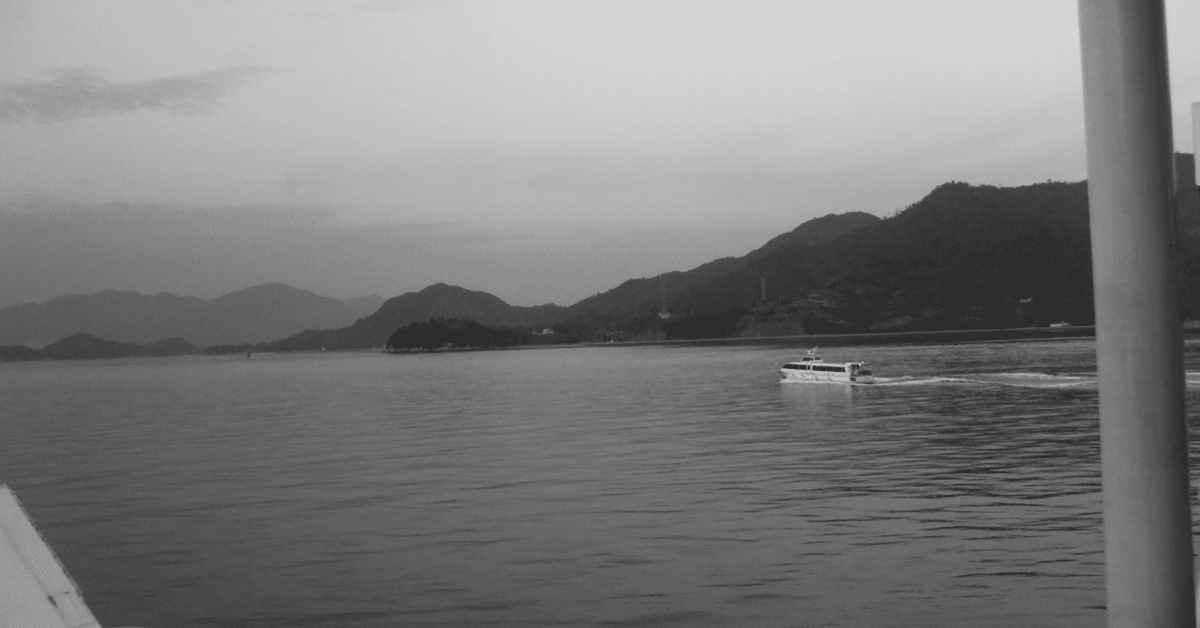
「死体は誰のものか -比較文化史の視点から」 上田信
ちくま新書 筑摩書房
第1、2章 中国
(この著者のメインフィールドでもある)。
主に、死体を公権力との闘争の武器にして、役所の玄関先に死体を置くとかそういう現代中国の抗争。それを思い起こさせるような清代の科挙に合格できなかった人々などが「訟師」となって関わり、積極的に抗争する「図頼」という事象。これは、果ては行き倒れなど身元不明者なども、相手先の玄関において「恨みがあるからここまで来たんだ、弔え」というもの。
あとは、気や風水の思想が儒教に取り入れられた北宋と南宋の境目の朱熹。「霊幻道士」のキョンシー(実際の中国の死者の弔いに結構依拠している)など。
森羅万象、あらゆるものには上下の序列があらかじめそなわっている。その原理原則を明らかにし、その序列に従って互いに譲り合って動いていけば、そこに自ずと秩序が生まれる。その秩序は、宇宙の星々から国家間の関係、さらには社会や家族など、ありとあらゆるところに立ち現れ、そしてそれを支える原理は共通するはずだ。
(p51)
だから、平等という考え方は存在しない。
儒教の考え方。孔子は巫女の子だったらしく、「葬式ごっこ」をして遊んでいたという。
第3章 チベット
チベットでは天葬(鳥葬)と水葬とがあり、チベット高原や青海省では前者、四川省や雲南省では後者が主に行われるが、青海省では通常は天葬だが不慮の事故や長患いなどの場合は水葬にもされるという。水葬地域のチベット族は魚を食べない。
天葬について、チベットの天葬は実際に葬場にハゲワシ等が来て切り刻んだ死体を食べ終わるまで遺族や僧侶が儀式をする。チベットに仏教が伝来する前はポン教という宗教で、現在も残っている村があり、チベット仏教の村とそのポン教の村は、後者が古層を伝えるものとしてつながりをもっていたという。
第4章 ユダヤ、キリスト教
ユダヤ教では死体をこまめに洗浄するため、ペストの時に死者がキリスト教の人々に比べて少なかった。そこで、逆に「ペストはユダヤ人が毒を流したのだ」と、虐殺されることになる。
キリスト教では、死者の復活と週末の時がなかなか訪れないため、煉獄というほとんどの人が行く世を設定した。一方、地獄の存在は否定しない、それは人間に自由を認めるため、高い叡智であえて地獄をめざすという人間をも想定しているためだという。プロテスタントには煉獄の概念はない。カトリックもプロテスタントも世界各地に広まる現代、現地にあった判断をし始めている(例えば日本における献花など)。1985年の御巣鷹山の日航機墜落事故の時、韓国やイギリスの遺族は、日本人に比べ遺体回収にこだわらなかったという。
第5章 日本
古事記から九世紀の「日本霊異記」までの「もがり」(死体を一定期間(皇族などは7日間、その他は3日間というのが多い)埋葬せずにとどめおくというもの)を中心とした記述。これが鎌倉時代の浄土宗等の新仏教によって、仏教が庶民の間に入り(それまでは仏教は国家の宗教で庶民とは縁がなかった)、「もがり」も消えていく。先の中国の「図頼」を思い起こさせる「らくだ」や死体は誰のものかという問いに直結する「黄金餅」などの落語。
明治期、終戦後、臓器移植問題期での「死体はものか、誰のものか」についての諸派。現在まで臓器移植においては日本は死者の生前の意思表示があろうとなかろうと遺族の意思が尊重される。欧米では逆に本人の意思重視なのだという。
著者上田氏の経験と考え
著者の父が熱心なカトリック(それも終戦後、自分自身の意志において)だったため、著者もカトリック信徒として成長した。けれど、(教会には隠れて?)離婚したともいう。そんな著者の死生観(というか生命観)は、
ビックバンとともにエネルギーが放出され、様々な物質が生成され渦をまいて拡散される。銀河団も渦をまき、一個の銀河も渦をまき、そのなかの太陽系も渦をまき、地球もまた渦をまく。地表では様々な生命が、物質とエネルギーとを受け渡している。渦をまきながら。
そして、「私」という存在も一個の渦だと、私は想念する。私の身体は、その外部からエネルギーと物質とを取り込み、廃熱と排泄物としてそれらを外部へと放り出す。
水面から渦を取り出すことができないように、ビッグバンから今日まで続き、明日へと引き継がれるエネルギーと物質の流れのなかから、この身体を取り出すことはできない。
(p221-222)
「全知」の存在、それは全知ゆえに変わり得ない、そんな存在から見られつつ、変化する存在としての自分の渦をどうまくことができるか、ということで著者は変化を見る学問歴史学を研究している、という。
(2021 02/07)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
