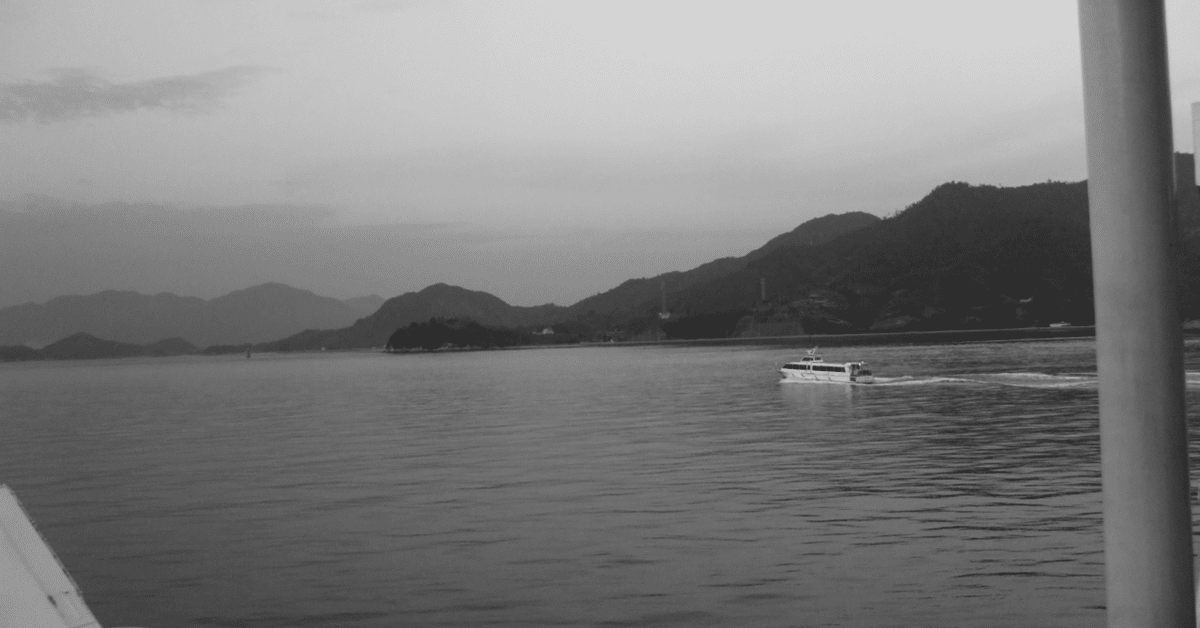
「ザッヘル=マゾッホの世界」 種村季弘
平凡社ライブラリー 平凡社
ザッヘル=マゾッホの出自
マゾッホの父系(ザッヘル(ザッハー)家)は祖父の代にルヴォフの製塩所長として当地に来た。父親は警察署長。母系(マゾッホ家)の祖父はこの地域にコレラが発生した時にユダヤ人地区に入り(当時はタブーだった)蔓延を阻止、ただ一人息子をその為に亡くした為、孫の代に自らの家の名前も継がせた。それが作家ザッヘル=マゾッホとなる。
「醜の美学」の章やゾラとの対比もある。
(2016 02/27)
1846と1848
マゾッホ10歳の頃、親類の家で覗き見てしまった夫人の情夫の連れ込みと、夫が逆に平手打ちにあったり、みつかってしまった少年自身も鞭打ちにあうという話…かなり脚色されているのではと種村氏は見ている…この話があったのは1846年。この年ポーランド貴族の独立反乱が起き、その失敗でかっての主人であるこれら貴族達をルテニア農民が虐殺する…この事件と同じ年。
その後一家はルヴォフからプラハへ移住するが、そこでは1848年3月革命の騒乱に巻き込まれる。こうした上が下に下が上にという騒然とした記憶と、その前にルテニア人乳母から聞いた民話の記憶が重なりあって、ザッヘル=マゾッホの小説世界ができあがっている。
というところまで、昨夜は読んだ。
虚構の帝国とギリシャ人
「ザッヘル=マゾッホ」の続き。
妹ローザの死の直後のギムナジウムの大学入試資格試験の論文で、担当教授に「これはもう試験答案というものではない。一人の作家の、ザッヘル=マゾッホの作品だ」と言わしめた。
その後マゾッホ一家はプラハからグラーツに移り、この街で安定した生活に入る。後の作家レオポルトは一回拒否した父の勧めの法学を専攻し、ドイツ史の私講師(学生が払う授業料で生活)となり、論文か文学作品かわからぬ文章を作り出していく。
論文の主なテーマはハンガリーのマリーア。この人はカール5世の妹であのフワナ(夫の死後狂気へ)の娘。マリーアの夫ハンガリー王ラヨシュ2世をモハッチの戦いで亡くすが、母のように狂気にはならずにネーデルランドを任せられる。ガンの市民叛乱を冷酷に鎮圧したりもした(この辺がマゾッホ好みか)。
「小ヨーロッパとしてのオーストリア」実現が成就しなければ、過去の歴史をも含めて一切は水泡に帰し・・・(中略)・・・そもそもの成立ちからして虚構であった架空帝国オーストリアは無惨に崩壊して渾沌たる野生のアジアにもどるだろう。すなわち文明は無に帰するだろう。
(p78)
「小ヨーロッパ・・・」はマゾッホの作品「密使」から、中略の先は「もう一つの世界」のアルフレート・クビーンから引いている。だから「アジア云々」はこの時代の空気から来ている。それはともかく、虚構の架空帝国というとカカーニエンのムージル。こうした中、マゾッホ自身はガリチアとかオーストリアとかを越えて、一世界市民としての自覚に立っている。
続いて、アンナ・コトヴィッツとの同棲生活。このコトヴィッツ氏と離婚して生活費をマゾッホにたかろうとする生活の中で、マゾッホは自分の作風を作り上げていく。その作品の一つ「毛皮を着たヴィーナス」を彼はアンナに読ませる。
すくなくともマゾッホの側では作品を読ませることによって意図的に共犯行為を促していた。それは夢想によって生活を、イデアによって現実を律し、場合によっては生活を破壊することも辞さぬまでに過激にイデアを加熱させることによるエロティシズムの純粋実験だった。
(p87-88)
「醜の美学」でもそうだったけど、この作家なんか自作(等)を他人や登場人物に読ませるの好きだよね。これは一つには彼の演劇を意識した態度の為なのか・・・でも、実験は失敗し、「毛皮を着たヴィーナス」で出てくる「ギリシャ人」みたいな第三者が出てくる(これもマゾッホ特有の流れ)。
この「ギリシャ人」という存在は、後のフロイトのエディプスコンプレクスの「父親」と共通する面が多い、と「死後」の章にはある。
(2016 03/08)
ドン・キホーテを待つ風車
「ザッヘル=マゾッホの世界」から待機の章。
ポイントだけ少し。真のマゾヒストたるもの教育者であり、拷問者を自らの志向に応じてしむけなければならないそう。「毛皮を着たヴィーナス」の契約書がそれであり、「ロリータ」やキルケゴールの「ある誘惑者」などはその系列。
でも、そうなるといつでも彼らは官能の只中には入ることのできない冷静さを持ち合わせることとなり、それを種村氏は標題のように名付けた。待機、もしくは旅の系列。これもまたカフカやホフマンスタールを経て、ベケットやブルトンに至る。マゾッホはそれらの「祖先型」なのだろうか。
(2016 03/09)
ビスマルクの恋文
第6章「女の世界」まで進み、「醜の美学」読んだ後にそこだけ読んだ第7章の同名章に繋がった。14章のちょうど半分(終章は抜きにして(笑))。いま目次見て気づいたのだけど、この本の各章の副題、3・6章以外は○○体験と名付けられている。
で、第6章はザッヘル=マゾッホの話題というより、その時代背景みたいなところ。中心はオーストリア皇太子ルドルフと情婦の心中?事件。でも自分が一番興味をひいたのはそれではなく、ビスマルク(マゾッホが毛嫌いしていたプロイセンの)の恋文。
貴女の思うがままに私を使い、利用して下さい。私を外面的にも内面的にも虐待して下さい。
(p138)
ビスマルクとその時代って、後の皇帝だけの時代より均衡的な時代だよね。ビスマルク自身もひょっとしたらマゾッホとそんなに離れてはいないのかもしれない。
さて、マゾッホについての記述からも少し。空想社会主義のパンフレットから、恐らくは作り出されたマゾッホの社会の理想の記述から。
理想をいまここで理想として実現するのではなく、苦痛を通して内部に屈折させ、肉体と心理の迷路のなかに秘匿することの方が問題だった。
(p135-136)
屈折という表現がなかなか。マゾッホの作品に含まれている要素を取り出したような箇所。
(2016 03/11)
反復横飛び?
昨日読んだ「ザッヘル=マゾッホの世界」から。
つまり反復はいまや何物にも拘束されておらず、かつてあったいかなる快楽とも無関係であって、それ自体が観念となり理想となっているのだ…(中略)…快楽と反復がその役割を交換してしまったのである。
(p207)
ドゥールーズの「ザッヘル=マゾッホ紹介」からの引用の箇所。反復というものも一つの快楽らしい…というか、前にも書いた学習スケジュールの強化の影響じゃないかな。
こうしたドゥールーズ等の紹介もあって、マゾッホはドイツ語圏よりフランス語圏で研究が盛んらしい。
(2016 03/15)
アリストテレスに馬乗り
マゾッホはグラーツからブダペストに移る(1年くらいで次はライプツィヒみたい)。えと、内容はマゾッホ自身というより1880年代の社会とゾラの「ナナ」が中心。
マゾヒズムの源流はもちろんマゾッホ自身よりはるかに古いのだけど、一つの物語の型(特に「ナナ」の馬乗りの場面の祖先)は13世紀頃成立したらしい、アリストテレスと若きアレキサンダーの情人との話。
アリストテレスに情人のことを父親に告げ口されたアレキサンダーは、老哲学者に刺激を与える為にそのフィリスという女をアリストテレスの元に行かせる。のぼせ上がった老哲学者に馬乗りしてはいどうどう…という話らしい。
13世紀といえばアリストテレス哲学が流入し全盛期になりつつある時代。この話のこれまた原型は古代インドみたいだけど、哲学者という知の要素とキリスト教的価値観がそこに加わった。こういう物語の型みるのも楽しい。中務氏の「物語の海へ」も思い出す。
ほんとはこれからゾラの話やナポレオン3世帝政期の話、マゾッホの文章の特徴とかいろいろあるのだけど、時間ないので、またのちほど…
ナナとプルーストとマゾッホ
まずナナの娼婦性から
女はたしかに見世物であり慰み物であるとはいえ、男はその女を完全にはモノにしていない…(中略)…決定権があるのは購買者ではなくて、商品の方なのだ。
(p262、ヴェルナー・ホフマン「ナナ、神話と現実」から)
兌換可能な、すべてを平板に相対化する金を価値基準にした社会は、後にマルセル・プルーストも暴露したように、にわか成金と贋貴婦人の仮装行列とならざるを得ない。
(p264)
地域的制約もあって、マゾッホではゾラやプルーストの次元には至っていないが、実生活ではその渦中にいた。例えば「風紀委員会」では、ワンダ母娘をモデルにしたような女工一家が中心となるが、ナナのように男たちを破滅させはしない。
プルーストについての文章も作品全体の社会的概観がはっきり見えてくるもの。
続いて、マゾッホ作品の文章の特徴を。
彼には個々の問題を通時的に分析記述することができない。事物を共時的に羅列して、事物のいつ果てるともないオンパレードをくり広げるのである。
(p268)
自分もマゾッホの短編読んでいてそんな印象を受けた。強いて言えばゴーゴリの「死せる魂」に似ているようなその感じを種村氏はビザンチン的祝祭空間と名付けている。
歴史小説といってもそんな印象が稀薄な小説世界を。
(2016 03/16)
マゾッホは晩年。パリのツルゲーネフ化するより、フランクフルト近郊の農村でトルストイ化した。離婚と再婚?そしてマゾッホを利用しようとした最後の「ギリシャ人」のジャーナリズムでの栄光と転落…
第二のマゾッホ
「ザッヘル=マゾッホの世界」をとりあえず読み終えた。マゾッホとギリシャ人のセットは、20世紀に入って、性的なものから言語的なものへと広がっていく。第二のマゾッホであるフロイトはギリシャ人として父親を据えてエディプスコンプレクスを語る。これまた第二のマゾッホたるカフカはいつまでたってもたどりつけない言語の迷宮をギリシャ人の代わりに建てる。
動くだけ、喋るだけ、言語という制度の構造はみるみるバベルの塔のように雲突くばかりに成長し、どこまで逃げても行く先々に蜘蛛の巣のようにひろがった一味の手先が待ち受けていることだろう。出口はない。逃走そのものが監禁を強化するのだから、彼は逃げくたびれてやがては横死するだろう。
(p329-330)
一つ一つの文章を理解できているとは到底言えないけれど、種村氏の文章は気になることが多い。逃走が監禁になるのであれば、自らの跡を言語行為によって示し同じ自分の中にいる監禁者に見せているようなことかな。
(2016 03/17)
関連書籍
マゾッホの小説作品
エミール・ゾラ 「ナナ」
