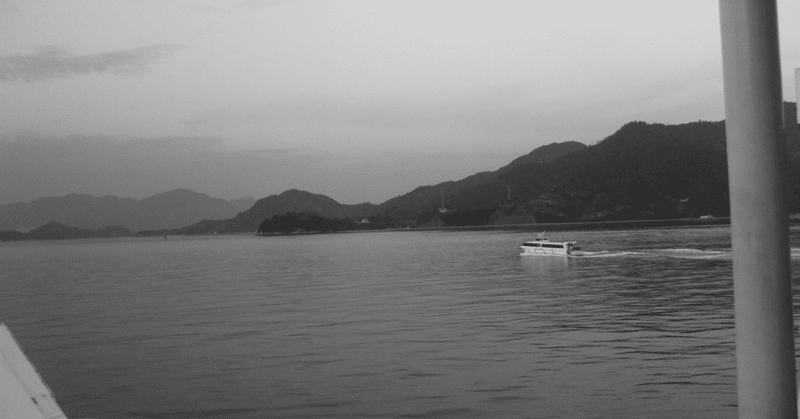
「時間の比較社会学」 真木悠介
岩波現代文庫 岩波書店
二つのテーマにおける古代断絶
昨日は日曜日に買った「声の文化と文字の文化」と「時間の社会学」を半々で読んでいた。別に狙ったわけではないのだが、ホメロス辺りまでの古代とギリシャ哲学辺りからの古代の間には人間の考え方全般に転換が訪れた、というのがなんというか両者の似ているテーマ。前者は書き言葉(母音文字を加えたことが記号化を促進したという)、後者は時間(振幅する時間ー円環時間ー直線的時間)。
(2013 09/24)
図と地
(実は月曜日読んだ箇所)「時間社会学」から。
原始人にとって意味があるのは、くりかえすもの、可逆的なもの、恒常的なものであり、一回的なもの、不可逆的なもの、うつりゆくものはその素材にすぎない。近代人にとっては逆に、くりかえすもの、可逆的なものの方が背景となる枠組みをなして、この地の上に、一回的なもの、不可逆的なものとしての人生と歴史が展開する。
(p62)
両者は実は同じ外界を見ている、という。ただその地と図の反転が人間の時間観に影響する。
(2013 09/25)
書くことと時間
オングの「声の文化と文字の文化」から。
印刷物によって、書くことが人びとのこころに深く内面化されるまでは、人びとは、自分たちの生活の一瞬一瞬が、なんであれ抽象的に計算される時間のようなもののなかに位置づけられているとは思ってもいなかった。
(p202 オング「声の文化と文字の文化」より)
時間が先か書くことが先か、という問題はさておくことにして。抽象的な暦で今が何日であるかなどはほとんどの人が気にしなかったらしい。それは生活の背後で流れ続ける均等な時間というものを意識していなかったため。彼らには彼らの時間の考え方があるのは時間社会学で読んだばかり。
(2013 10/10)
よみがえりたいですか?
「時間の社会学」は万葉集からみた古代の時間論。壬申の乱で灰塵となった近江京の辺りを直後に訪れた歌と、それから約20年後に訪れた人麿呂の歌。古代のあの世とこの世の振幅する時間観に生きていた直後の人は亡くなった人に会うことを歌に詠むが、そこが断然してしまってきた時間観の人麿呂は否定する。
だが、人麿呂の場合まだ共同体の歴史と一体となっているが、大伴家持の場合はそこからも離れて個の意識、個の時間を持つに至る。例えば連作の歌を作った後もう一度見直しているというが。
(2013 10/13)
書くことから時間
昨日で「声の文化と文字の文化」を読み終えた。
で、並行読みしていた?はずの「時間の比較社会学」(実際は半分くらいまで)に切り替え。原始共同体の反復する時間観から近代社会の時間観になるまで、ヘレニズムの数量化ゲマインシャフト化の側と、ヘブライスムの内面化現世否定の側と、どっちも合わせて?至るらしい。ヘレニズムは円環時間観、ヘブライスムは終末論的時間観。
(2013 10/24)
カルヴァンからプルーストへ、自己解体リレー
彼らの存在感は、たえずあらたに風を送らねば消えはててしまう炎のように不安定なものだ。信仰や思惟や感覚は、このような炎をたえずよみがえらせる生命の風のさまさまなかたちに他ならない。
(p207ー208)
カルヴァンの信仰、デカルトやモンテーニュの思惟、ロマン派からプルーストの感覚…対象は変化しても近代社会の自己は常に解体の危機にさらされていてそれに対抗するためにこうした対象をみつけた、というのがここでの論点。この瞬間と次の瞬間の自分は実は違うのではないか、という不安。その原因は時間感覚の急速化による。
現代はそれよりもっと早くなり、自己解体もなんだか当たり前化しているけど…
だから、そうした問題が出始めた近代を見る必要があるのでは。
(2013 10/25)
共同性と現代
彼らはそれぞれの共同性を、未来であるかぎりにおいて求め、現在であるかぎりにおいて嫌悪し、過去であるかぎりにおいて愛惜する。いずれにせよ彼らは現在を愛していない。
(p248)
近代的自我の〈現在〉は、その虚無を支えるたしかな〈時〉を求めるひとつの飢えだ。
(p252)
真木氏の進め方にちょっとついていけなくなった感もあるけど、プルーストの「失われた時」というのはこういう「時」なのだということらしい。それが近代(あるいはちょい前)から始まりその前は共同性が支配的であった、という考え方は多少留保すべきなのかもしれないけど。こうした考えはルカーチの「小説の理論」ともつながりそうだ(まだ読んでないけど(笑))
等価のないもの
場所や生活などの事物を「等価のないもの(かけがえのないもの)」として信じさせる感情の力を失い、対象的世界のすべてを交換可能な「単なる景物」としてながめるということによって、じつはそのながめる主体としての個我が、唯一の「等価のないもの」として絶対化されているのだ。
(p306)
構造変換が起こったわけではなく、価値観の移動が起こったわけですね。この文逆に読めば、近代以前の人々の考え方もわかってくる。自分という個人は別にかけがえのないものではないから。
あとは、終章と後書き…
(2013 10/27)
存在と時間
なんだかハイデガーチックなタイトルだが(笑)、そうではなく「時間の比較社会学」を読み終えた。
存在のうちに喪われたものを、ひとは時間のうちに求める。
(p315)
この文は、時間というものは決して客観的にあるのではなく、人間の存在感情の一バリエーションとして成立していることを意味している。そのバリエーションが多数派となって人々の間の共通事項となってからも、それがバリエーションにすぎないのならば、個人個人その内部において別のバリエーションを持つこともできるのではないか。
(2013 10/29)
関連書籍
並行読みしてた「声の文化と文字の文化」はこちら ↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
