
【障害受容】リハビリ専門職が知っておくべき!患者の心理と対応を「段階理論」で解説
病や障害を負ったことによる「喪失体験」をどう受け入れ、どのように立ち直っていくのか。
*「喪失体験」について詳しくはこちら ↓
人が受けた大きなショックから回復し、前に進んでいく心理的なプロセスを「障害受容」といいます。
障害受容の具体的な進み方は「階段理論(Stage Theory)」が一般的。段階理論は精神科医のキューブラー・ロスが臨死患者から得られた知見をもとに提唱したものです。
今回は「段階理論」にそって、病や障害から回復する心理的プロセスをご紹介します。
否認
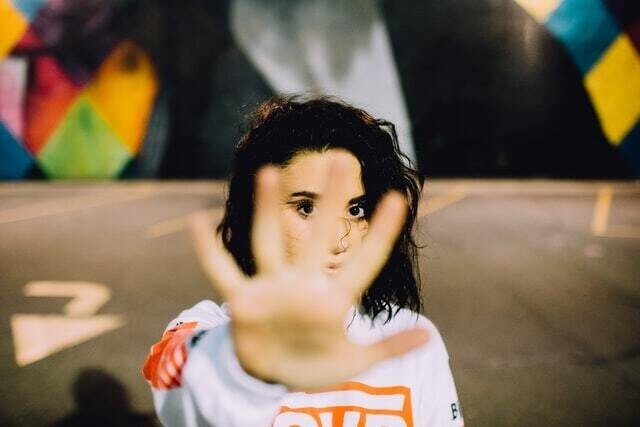
病気や障害が残ることになったとき、患者はまず「(病や障害の存在を)認めたくない」という心理がはたらきます。
例えばリハビリテーションの中でも、麻痺そのものを回復させる訓練に対しては患者自身積極的に行うが、残存機能や代償手段を使う練習−車イス操作、利き手交換など−に拒否的となることがあります。
医療スタッフや家族は、この時期に現実を直視させる説得するのは効果がありません。むしろ"障害を否認していたい"という願望を尊重し、自己防衛の気持ちに寄りそいましょう。
怒り

否認に続いて、どうにもならない怒りや憤り、うらみを周囲の人間や自分自身へ向ける時期。終始イライラしたり、大きな声で怒鳴ったり、物にあたったりなどの言動がみられます。
この「怒り」は特定の人に向けられたものではなく、本人の行き場のない怒りが発散されています。医療スタッフや家族はまず本人の立場にたって理解を示しましょう。
怒りを鎮めさせたり、言動をたしなめたりする説得には反抗的になることが多いです。生活でのさまざまな決定権を本人にゆだねるようにするとよいでしょう。
取り引き

取り引ときは障害の自覚を少しでも先延ばししようとする心のはたらき。
一般的には良心的なこと、しかし現実にはほとんど意味のないと思われる約束を行おうとします。例えば、神仏にすがったり、善行を行ったりなど。
医療スタッフの対応としては、この約束があまり現実的でないからといって、無下に無視してはいけません。本人にとってその約束を果たすことで心が安定し、前を向くきっかけにもなりえます。
かといって患者の約束に振り回されないように。あくまでも本人が現実を理解するほうへ促すのが大事です。
抑うつ

「取り引き」の段階で自分の罪悪感を感じたり、障害を避けられないことがわかるとあきらめや悲観、むなしさ、憂うつ、絶望といった気持ちが支配して、抑うつ状態へ陥ります。
障害受容の過程では「本人の回復を信じて、その傍にいる人」の存在が重要。外出を促したり、社会参加のきっかけとなる情報に触れたりなど、気分が引き立つような関わりをしていきます。
過度な干渉を嫌がられる場合には、そっと見守っておくことも必要です。
受容

最終的に「あるがままの自分」を受け入れる段階。リハビリテーションのなかで、家族の支えや同じ障害を持った人との交流により、自分自身の障害の存在をみとめ、情緒が安定します。
これまでの価値観や見ていた世界とは異なった次元があることを理解し、新しい生き方を発見。目標に向けて前向きに努力をするようになります。
まとめ

人が価値あるもの−健康、幸せ−を失った後の心理の移りかわりが「障害受容」。
ただ障害受容のプロセスは決して一直線に進むものではありません。障害受容は「段階理論」の各ステップを“らせん”のように進行し、それをくり返しながら進んでいきます。
ご自身が重度なケガや病気、手術を経験したことのある方ならおわかりでしょう。身体の回復とは別に、気分が上がったり、また落ち込んだり。感情が激しく揺れ動き、自分でもコントロールの仕様がないことがあります。
患者は新たに自分がおかれた状況に対して、心理的に「適応」していこうとします。セラピストは患者の生活場面に近い存在として、そのプロセスを信じて寄り添うことが大事ですね。
本記事がセラピストと患者の心の橋渡しとなり、リハビリテーションの良好な進行へ役立てば幸いです。
参考書籍など
・健康長寿ネット「障害受容」
・上田 敏:特別寄稿「障害の受容」再論−誤解を解き、未来を考える−.The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 57,2020.
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
