
亡くなった人について語る時、私の語ること。
幸福について言えるのは失って初めて幸福だったと気づくことだ。言い換えれば自分たちが幸福だと思うことはあるかもしれない。だけど本気で信じていないんだ。
些細な戯言、次の仕事、なんでもいいから集中するんだ。
幸福がどんな感じか本当に理解するのは、振り返ってみて、そのあとに待ち受けているものと比較する時だけだ。
高架下。痛んだしおり。折れた傘。ぬるくなった缶ビール。クラゲ。水溜り。寂れたビル。リストカットされた手。鶯谷。フィッツジェラルド。
もしすべては存在しないのだとしたら、存在しないかのように、単にまだ死んでいないというだけの意味で、あるいは生き続けることも可能かもしれない。しかし、これも欺瞞なのだろうか。
8月22日シュンの訃報があった。
Instagramで当時、それを見て、どう思ったか。
俺は驚いただけだった。なんと言ったかは覚えてないが声も出た。
4月1日でないことだけ確認した後、何分かその画面を呆然と眺めていた。
どういう感情だったかうまく理解できなかった。何も感じないというほどドライな感情でもなかったと思う。それより、もっと困惑に満ちていた。どうすればいいのだろう、というような感じで。
どう感じればよかったのだろう。その時湧き出た印象を、印象として受け取るぐらいしか俺には出来なかった。
ひどく困惑していたと思う。
訃報のあったInstagramの投稿には10件ほどのコメントがついていた。それは全て、英語で書かれており、彼の死を悔やむコメントだった。
Rest In Piece
と書かれたコメントが多数見受けられた。
ご冥福をお祈りします。というニュアンスの言葉だ。
彼はその誰にでも好かれる性格を、留学先でも存分に発揮していたんだろうな。と思わせられた。それは尊敬にも近い感情を俺に抱かせるのに十分すぎるほどのものだった。
しかし、日本語のコメントは1つもなかった。それについて、俺は何も思わなかった。これは単なる文化の違いだった。
彼の訃報があった後、何人かサークルの友人と連絡をとった。
その際、彼の訃報があったことについて言及があった。
「シュンのことだけど」 「落ち着いたらお墓参りに」
という感じで。
ただ、それ以上深く踏み込んだ事は言おうとしなかった。
亡くなった人について語ろうとする事はしばしば、我々の中で憚られた。そういったことはかなり神経質な物事だった。一歩間違ったことを言ってしまえばひどい非難を浴びてしまうと感じられた。無意識に、まるで腫れ物のように扱ってしまっていた。
実際、俺も彼について、こちらから話題に出すような事はしなかった。ただこの沈黙については、発話を拒否するという意思としての意味をほとんど持っていなかったように思う。
さらには、訃報があった翌々日には普通に何事もなかったように仕事に行った。この時、コンビニで朝飯にするためのパンとコーヒーを買い、オフィスに向かっていた時、訃報を見て感じた、あの形而上学的な観念についてしばしば忘れていた。ひどく衝撃的な事実だったので頭の片隅にあったが、日常生活を送るにあたって、いくらか悲観的な事実から目を逸らした。
そして数日がたった今、衝撃的だった事実に慣れた。忘れたというわけじゃない、慣れてしまったんだ。
俺たちにはまた前を向いて現実を見るために、そういうのがいくらか必要だったんだと思う。
しかし俺はよく、その現実的なことより、亡くなってしまった人のことを考えた。
自分が死んだその数日後には、生きていた人はそのことを忘れ始め、他の何かに集中し始める。まるで、自分なんか世界に必要じゃなかったみたいに。
考えすぎかもしれない。死んだ先は無だ、と高を括って、それ以上踏み込んだことを思う事はやめる方がいいかもしれない。
どちらにせよ俺たちは、もう少し、彼と彼と過ごした数々の日常について、物語ってもよかったかもしれない。例えば、彼との一番の思い出をSNSに投稿なんかしたりして。
でも俺たちはそれをしなかった。少なくとも俺の観測した範囲では。
それは別に非難されるようなものではなかった。亡くなってしまった人について語ろうとする事は、とりわけ日本おいてはあまり歓迎されることではないのだと思う。
このような現象について日本の宗教的背景や文化的背景がどのように作用しているのかは知らない。しかし、とにかく、亡くなった人については静かに口を閉ざしおくのが我々のやり方だった。
おそらくここで本題に入るのだが、そのことで最も懸念していた事は、亡くなった人について、ここではとりわけシュンについて。それを誰も口にせずにいることで本当の意味で彼は徐々に死んでいってしまうんじゃないかという不安だった。
これは直観的なものだった。しかしそれでもそれは確信めいたものでもあったように思う。
俺はそのような疑念を持ち始めてから、この文章の執筆にかかった。頭の中に残っていることをなるべく正確にボールペンでノートに書き留めた。それは今、この瞬間にやり始めるべきことだった。記憶が抽斗の奥の方にしまわれてしまう前に。
まず、俺が彼について語れることはそれほど多くはない。仲が良かったわけでもないのかもしれない。
だけど、それなりに身近な人間だった。(と思う。)
彼は大学のサークルの後輩で、俺にとって気を使わず話すことのできる数少ない人間だった。気を使わずにいられた、というのも彼は正直随分といい加減なところがあったからだ。
俺たちは内容のある話はおそらく全くしなかった。互いの思いのうちを話すような事はなかった。他の人間が彼とどういう話をしていたか知らない。少なくとも俺は彼の思いのうちを知るような機会はなかった。
実際のところ、彼と最後にあったのがいつかも思い出せない。この文の執筆に入る時、俺は今まで彼とどんなやりとりをしていたかSNSを見返していた。その際、LINEでもやりとりしていて、それは3回ほどのやりとりだったのだが、一回のスクリーンショットで収まってしまうほどのものだった。
彼は大学3年の頃外国に留学に行った。彼が帰国した後、サークルの何人かは彼と何回か会っているようだったが、俺は会う機会がなかった。
そもそも、彼が俺のことを覚えているのかさえ怪しかった。それくらい長い時間が経っていたように思う。
ただ、また何かの機会で会うだろうなとも思っていた。俺をそれをいくらか心待ちにしていたのだと、今になって気付かされた。
BattleFieldというシリーズのゲームがある。FPSというジャンルのものだが、要は銃を持って戦争を疑似体験できるゲームだ。
それが俺と彼との繋がりだった。


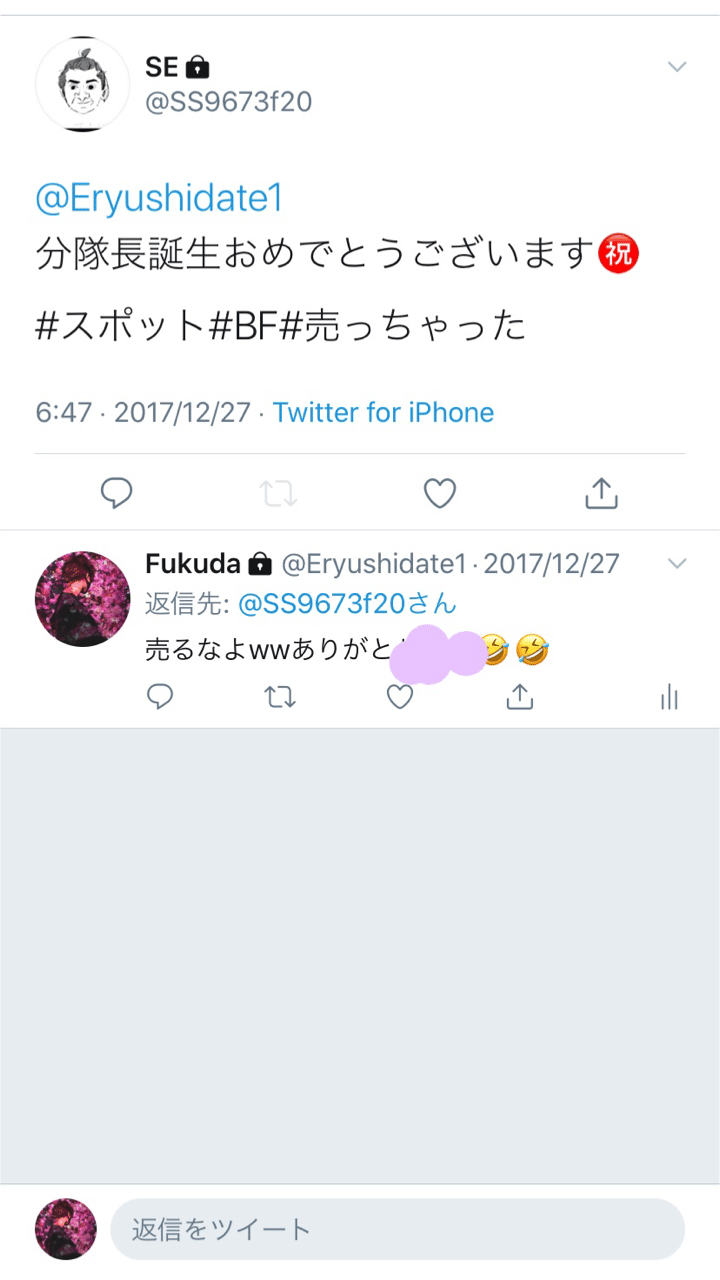
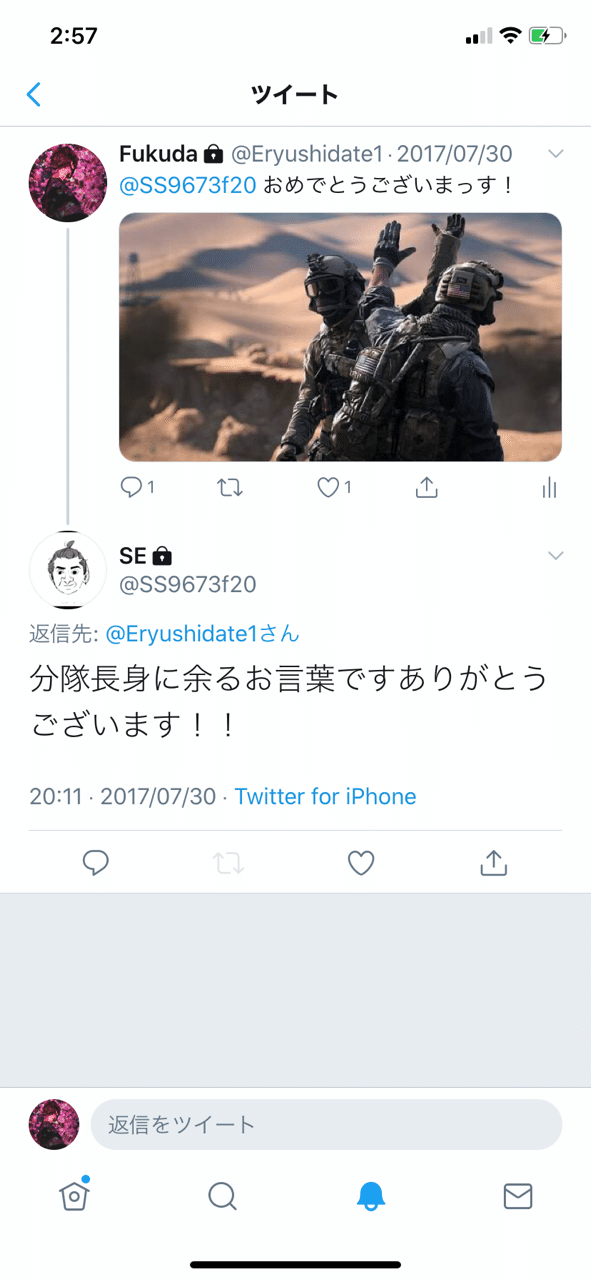
BattleFieldは5人ほどのチームを組み、(この時は)最大64人対戦をすることができた。その際、チームリーダーは分隊長と呼ばれる。


「スポット」もBattleField内で使われる機能のことだ。

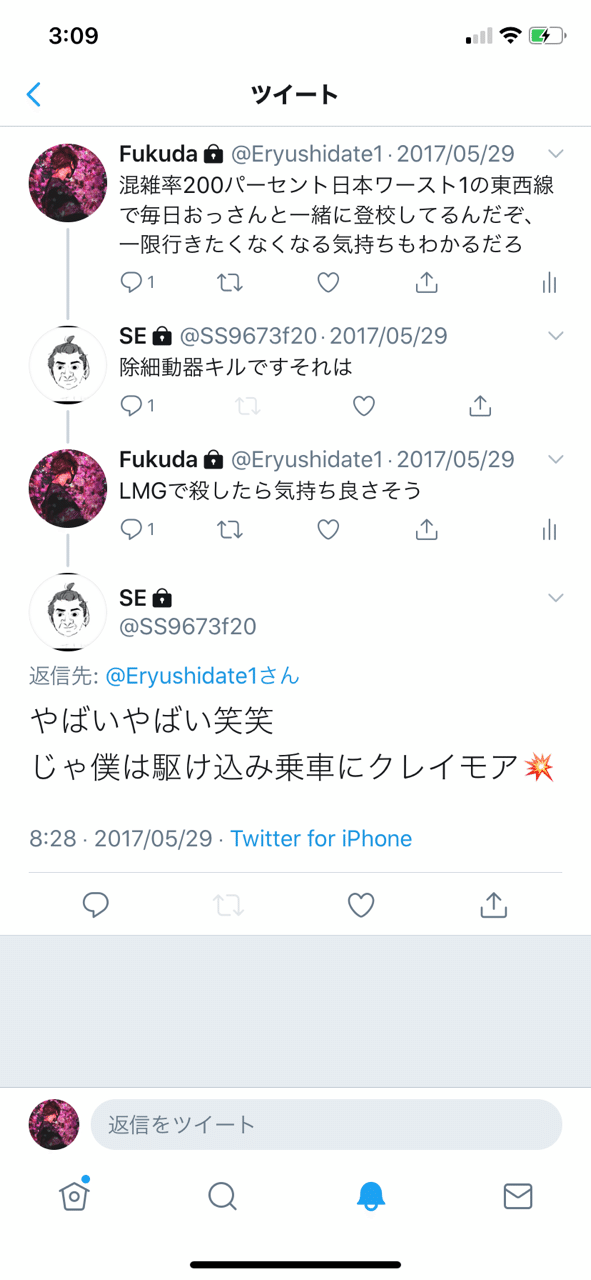
こちらもBattleField内での武器の話をしている。
生前も彼はBattleFieldシリーズの新作をプレイしており、そのプレイ動画をSNSに上げていた。それを見てると、まだここに彼が生きてるんじゃないかと思わされる。俺はそんな想像をする。
(そのプレイ動画をキャプチャしてきたのだが、どうやらこのnoteは動画は載せることができない仕様らしい。なんて不便なんだろう。)
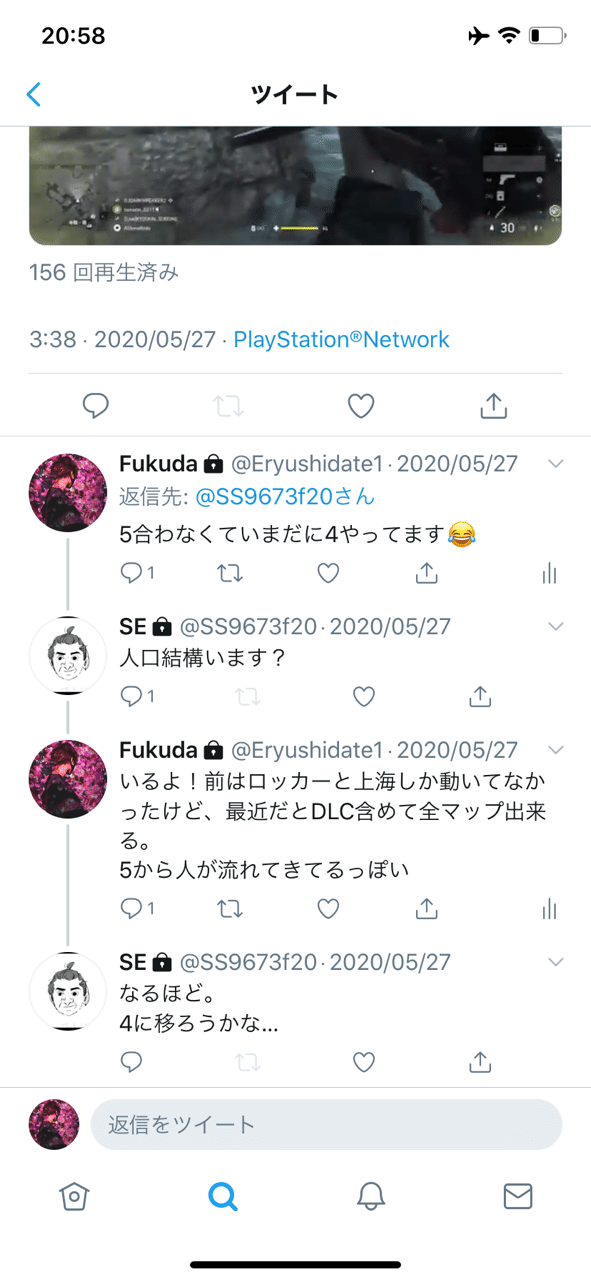
BattleField”4”は俺たちにとって青春そのものだったかもしれない。そこにまた戻ろうとしていた。
見返したところ、俺とシュンは全てBattleField関連の言葉を使い会話をしていた。
彼は友人と一緒にBattleFieldをプレイしていたようだったが、逆に俺は基本ゲームはずっと1人でプレイしており、ましてや男臭いBattleFieldシリーズをプレイしている人など知人には誰もいなかったのだ。彼以外。
だから、俺は彼と会うことをいつも楽しみにしていた。ゲームをプレイして、そのことで彼に話しかけた。彼はいつも笑顔で、またそのいい加減な口ぶりで、言葉を返した。そしてよく「分隊長」
と言ってくれた。それが多分嬉しくて彼に話しかけていたんだと思う。そして、最近VC環境を揃えたおれは、一緒にVCを繋げてゲームをやろうと彼を誘おうと思っていたのだ。
彼に会った時、それをずっとずっと言おうと思っていた。多分彼はそれを快く了承してくれたと思う。そのいい加減な口ぶりで。
-----------------
終わり
この記事を執筆するにあたって
これから先の記述は本題とは関係ありません。
書いてしまったため、載せているだけです。
ご遺族の方は読むことをご遠慮ください。
8/31 (スペシャルサンクス・共著)咲良朱莉
この記事の執筆中、亡くなった彼と、それにまつわることについて執筆するのをやめてしまおうと思ったことがあった。俺は大学を卒業してから、色々と文章を書いてきたのだが、執筆は大体において中途半端なまま終わった。執筆中、最も危険な敵は
「今書いていることはどのような見方をしても一切の価値すら見出せないものなんじゃないか」
という心の声だった
実際文章の9割は完成しなかった。しかし大体に置いてその中で、唯一、と言っていいくらい完成率が高くなる条件があった。
咲良朱莉に文章の感想をもらうつもりで書いていた時だ。
俺はシュンをLINEの中で探し出し、メッセージを送った。久しぶり、スポットしてる?というメッセージとともに。
これは一生返ってくることのないLINEなのかもしれないな、と思っていた。が、実際には数時間後に連絡が返ってきた。それはご遺族からのもので、こういったメッセージだった。
「
シュンの家族の者です。
8月22日にシュンは、亡くなってしまいました。
久しぶりにシュンに連絡して来てくださったのにこのようなご連絡となってしまい申し訳ありません。
シュンとはどのようなご関係だったのでしょうか?
仲良くしてくださっていたのであれば、ありがとうございました。
」
(一部改変してます。)
LINEもご家族の方が全て見られてるらしかった。想定していなかったことなので対応に困り焦って下記のようなことをすぐ伝えた。
訃報を見たうえで連絡したこと
俺と彼がどういった関係だったか
またそのことについて執筆していることを伝えた。
既読はついたが、連絡は返ってこなかった。俺は執筆を続けていいかどうかも確認をとった。
これも返信はされなかった。
このことがあって俺の中で彼が亡くなったことがより現実のものとして感じるようになった。また、執筆を本当に続けていいのか不安になった。ただの自己満足になってるような気がしたからだ。
その際、俺は自分の行為をなんとかして肯定したいと無意識に画策しており、咲良にご家族の方とのやりとりと、当時書き始めたばかりの文章を見せLINEでこう尋ねた。
「自分のやっていることが本当に正しいことなのか(やるべきことなのか)分からない。自己満足なんじゃないかって。」
と。この時俺は自分の行為をあっさりと肯定してもらえるとどこかで信じ込んでいた。この執筆に入る前、俺は咲良の誕生日に手紙のプレゼントを渡した。その時文章も、かなりひどく自己満足で、自己中心的で、雑な文章が書かれていた。
俺はこの時も、直前まで手紙を渡すかどうかを迷っていた。どう文章を見てもほとんど咲良を祝うのに不適切なものとしか思えなくなっていたからだ。
だけど渡した。迷っていたが、帰り際に渡した。すると、どうだったか。4000字ほどの文章を彼女はすぐ読み終え、その内容に触れながら楽しかったという趣旨の感想をLINEで送ってくれた。
さらに彼女は
「もう二回も読んじゃったよ」
と連絡をよこした。
この時ほど文章を書いてよかったと思う時はなかった。
今回もそういうのを彼女に期待していたんだと思う。咲良に肯定してもらおうと身勝手に考えていた。
しかしながら、非常に聡明で、察しのある彼女はこう答えのだ。
「ごめん。。これは自己満だと思ってしまうよ」
俺は今朝このメッセージを見て鼻で笑った。うまく言えないんだけど実際にはこの時俺はひどく傷ついたと思う。第一志望の大学からメールを開いた先に自分の受験番号だけがすっぽりと抜けていることに気づいた、あの時のような感じだ。心臓を後ろから鋭利な刃物刺されたような感覚を覚えた。このとき、心っていうのは本当に心臓のことを指しているんじゃないかと感じさせらた。
でも俺はつい笑ってしまっていた。まあ、そう言うに決まっているよな。という笑い。自分自身でも自己満足だと薄々思っていて、俺はそれをわかっていて、さらに別の答えを咲良から引き出そうとしていたのだ。身勝手な自己満足の、その背中を咲良に押してもらおうと考えていた。咲良のごめん、という枕言葉と俺を気遣うようなその言い方が余計に彼女の否定的な想いを強く俺に印象付けた。
満足するために思考している自分の手合いを見かけたとき、痛ましいものを見た、と思う。
俺は昨夜送信したものをすぐ取り消し、その後彼女のLINEをブロックした後テーブルに置いてあったハサミで数回、白いパジャマの上から、思い切り太腿に目掛けて刃を突き刺した。太腿にはかなり目立つ跡が残り、紫色に痣のようなものができた。パジャマが血で染まってしまえばいいのにと思ったが意外とうまくいかないものだった。俺の身体だけは頑丈で健康な素材で構成されていた。痣もすぐ治るだろう。
けれど、
結局のところ、この世の自己満足ではないものはなんなんだろうか。
そんなことについてひとしきり考えた後、自己満足にならないように考えることも結局ある種の自己満足だということに気づかされ、考えるのをやめた。
夕飯を適当に食べた後、咲良の誕生日を祝った時に買った煙草を近くの公園まで吸いに行った。
咲良の意見を無視して俺は再度執筆に取り掛かった。今度は自己満足を承知して書き始めた。意味を見出せなくなっていたが、それは完全なものではなかった。つまり、何もわからなくなってしまったが何もわからないから書くしかなかったのだ。そのうえで後々必要ないと判断すれば公開せずにこの俺の頭の中にしまっておけばいいのだ。そう考えた。
俺が咲良との連絡を絶った後、彼女はさらに、俺のやろうとしていることをやめさせようと最も適切な言葉を選んで諭しているかもしれなかった。それは本来俺の手元に届いておくべきものだったかもしれない。
俺はその日から幾らかの間仕事の休みをとり、その間ずっとシュンと死のことについて考え、それを言葉にした。
これは今回の執筆にあたって、最も象徴的な出来事だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
