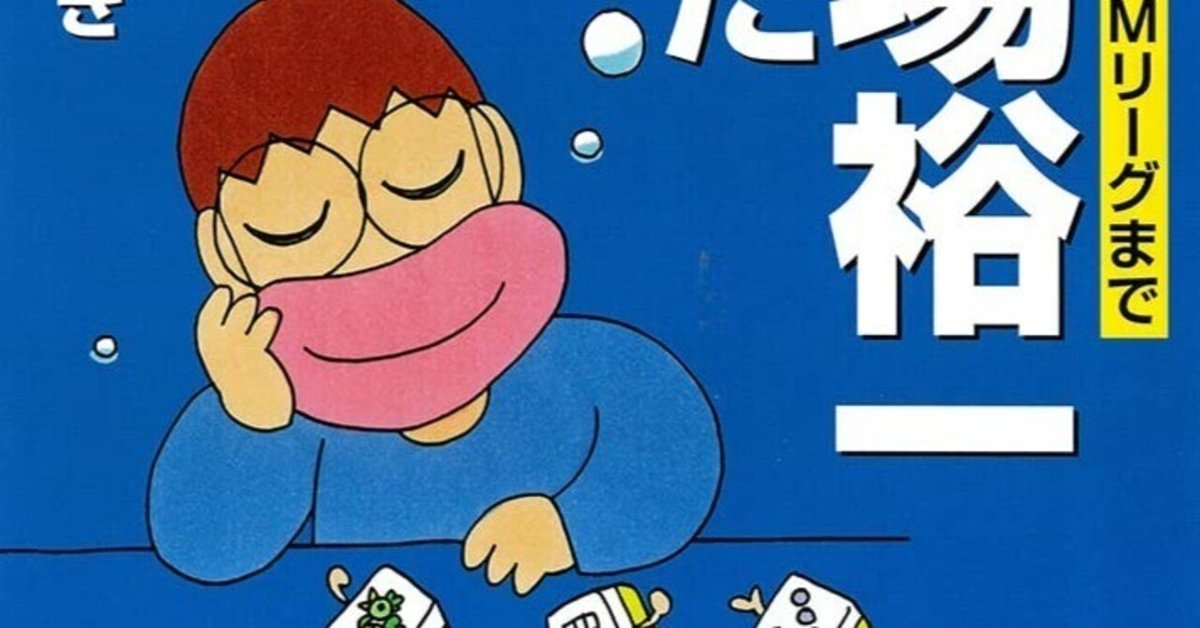
『馬場裕一の見た夢』を読む
個人的な感想を
読んでみたら本としての出来は非常に良かった。ふつうの文章、対談、インタビューなど、いろんな形式の文章が詰め込まれており変化が多い。なのでサクサクあっちゅーまに読める。
漫画の収録も多い。4本。全部「スーパーヅガン」からの再録。読んだことない人は面白いと思う。
片山さんのイラストがいっぱいある。いろんな麻雀プロ(ほぼ古い人)の写真がいっぱい。資料的な画像もある。そういうビジュアル系の要素が多い。
台割(目次)を尾沢工房さんが組んでると思う。そのいい部分が出てるわ。
全体として面白かった。都合いいように語ってやがんなー!と思う部分は少なかった。ただ、「ようするに自分が大昔から女子プロ人気を予見しリードしてきたと言いたいわけ?」みたいな箇所もなくはなかった。
Amazonでは600位台と、まーまー売れてるようで何よりだ。
値段が1100円。これでどうやって採算取れるの? 内容的に部数が多いようには思えないけど、なぜこんな値段が可能なのかわけわかめ。
さて、俺も時代遅れ側で、こういう本の感想を書くのがミッションと言える立場なので、順に見ていこう。
* * * * * * * * * * * * * *
プロローグ
黒木さんが書いたんだと思われる。上手い。面白い。
歴史の授業では決して教えてくれなかった 誰も書かなかった日本麻雀史‼
よくまとまってる。
「軍国主義の暗い影が徐々に日本全土に忍び寄っていた」みたいな、まっとうな歴史語りみたいな文章が意外で、これは尾沢さんが書いた文章じゃないかと思った。しかしバビィが書いたらしい。
昔の文献から表現を抜き出してつなげたから、こういうレトロな表現になったんだろうね。
昭和40年代の麻雀ブームを、五味康介から阿佐田哲也で語る典型的な馬場史観だ。五味さんの本は確かに馬鹿売れしたけど、それ以前から本屋には天野大三さんや村石利夫さんの本は山ほど並んでたからね。
バビィが嘘を言ってるって話ではなくて、世代によって歴史を語り始める発端は変わるということ。バビィにとっては阿佐田哲也さんなんだよね。たとえば浅見了さんは天野大三さんや村石利夫さんも重要と見てたから。
馬場裕一が足を踏み入れたプロ麻雀黎明期
バビィが10代後半に足を踏み入れた麻雀プロ業界の変遷。
最高位戦八百長事件は詳しく説明し、麻将連合、協会、機構、RMUができた経緯をさらっと。こういうのはめちゃくちゃ書きにくい。激しい喧嘩があって意見の相違があるわけだから。それを上手くまとめてると思う。
サラッとしすぎてて、もっとドロドロしたガチな部分を書けよという気持ちと、こういうのがバビィの持ち味だからなというのを両方感じる。
これは私見になるかなって思うけど、麻雀プロ団体が分裂していく理由って、2種類の人たちが混ざってるからなんだよね。①雀荘の経営者、居酒屋の経営者など、すでに食えてて、納得いく競技麻雀を打ちたい人たち、②雀荘メンバーなどしていて、麻雀でなんとか浮かび上がりたい人たち、この2種類だ。
プロ活動に求めてるものが違ってて、①の人たちはメディア活動に積極的じゃない、②の人たちはとにかくメディアに出たい。①の代表は新津さんであり、②の代表は井出さんなんだけど、①から②が集団独立していくのが、だいたいの分裂なんだよね。
プロ連盟もそう、麻将連合もそう、協会もそう。機構とRMUはちょっと違うかな。
こういう説明を抜きにして、分かれていった経緯を説明しても、何をゴチャゴチャやってんの?と思うだけじゃないかなー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
