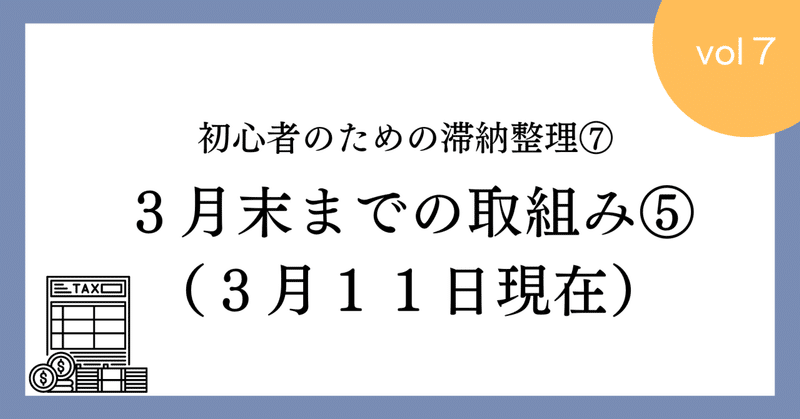
3月末までの取組み⑤(3月11日現在)
知人から令和6年度4月1日付けの異動内示が届きました。この時期異動内示が出ると慌ただしくなりアッという間に3月末を迎えることになります。今回は管理監督者の皆さんに改めて令和5年度の組織目標(滞納整理実績見込み額)に向けて一度税収の見込みを出していただきたいと思います。この見込み額を算出することで、4・5月の出納閉鎖期間の取組みも検討しなければなりません。
職員の半数が異動するような状況であれば、なるべく現体制で組織目標に近づく実績としなければ新しい体制ですぐに実績を求めることはなかなか難しいことです。ましてや経験のない職員や新規採用職員では、4・5月の出納閉鎖期間に期待すること自体問題です。そのため現体制で当初の目標額になるべく近い実績を積み上げる必要があると思います。
改めて部下職員に対して現在受命している滞納事案の中で、収入が見込まれる滞納事案がどれだけあるのか各自積算して報告をさせてみてはどうですか。この見込み額の積算はこれまでの交渉や接触等を考慮した上で検討してもらいます。具体的には、3月の給料で納付するという約束がとれている滞納者などが見込み額に入れるということです。
各職員の見込み額を集計した段階で組織としての3月末実績見込み額が予想できます。滞納繰越分の年度当初目標額を上回る見込み額であれば、とても嬉しいのですが現実はそうはゆかず見込み額を下回るというものです。
さて当初見込み額を下回る場合にどのような取組みを組織として実施するかが重要なことです。ただし、3月末までの期間としては3週間しか残っていないという前提の中で行わなければなりません。
大口滞納事案で財産調査が判明しているのであれば最優先で差押処分すべきです。既に大口滞納処分が処理されているのであれば、大口滞納事案に次ぐ滞納事案をリスト化して1件毎に確認することです。大口滞納事案については、それぞれの自治体の財政規模に拠りますので一概にいくら以上ということはできません。それぞれで判断してください。もしかすると催告で納付が見込まれるのであれば、職員総動員でまずは電話催告をすることです。
委託業務の場合は事前に委託会社と催告業務が行えるか確認することです。出来るのであれば徹底して催告をしてもらうことです。民間の金融機関では午後3時以降(窓口が閉鎖してから)焦げ付きの融資に対して電話催告をノルマで毎日30件と聞きました。これは私の友人の息子さんの事例です。このことを考えると私たちがそれ以上の電話催告ができるのは当然だと思います。しかし、自治体においてその切迫感はあまり感じることはありません。限られた時間の中で何ができるか考えながら取組むことも組織の一体化に繋がると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
