社会はどう進化するのか――進化生物学が拓く新しい世界観
デイヴィッド・スローン・ウィルソン (著), 高橋洋 (翻訳) 亜紀書房 (2020/1/24)

著者について
デイヴィッド・スローン・ウィルソン
1949年生まれ。アメリカの進化生物学者でビンガムトン大学(ニューヨーク州立大学ビンガムトン校)教授。マルチレベル選択説の提唱者。
主著『Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society』は大きな反響を呼んだ。邦訳書に『みんなの進化論』(日本放送出版協会)がある。
目次
この生命観
社会進化論をめぐる神話を一掃する
ダーウィンの道具箱
生物学の一部門としての政策
善の問題
加速する進化
グループが繁栄するための条件
グループから個人へ
グループから多細胞社会へ
変化への適応
未来に向けての進化
※下記は特に断り書きがない場合は著書からの引用(強調は基本的に引用者による)
人間的事象との関連でダーウィニズムを研究している現代の学者ジェフリー・M・ホジソンは、学術誌の電子データベースJSTORで、「社会進化論」という言葉のあらゆる用法を追跡するとい う途方もない課題を遂行している。それによって彼は、その用語が一九世紀終盤に使われ始め、使わ れている文脈は現在とまったく同じであることを明らかにしている。彼が述べるように、「このレッテルはおもに、左翼の人々が政敵に貼るために使っている」
ホジソンはまた、一九四四年に歴史家のリチャード・ホフスタッター(一九一六~一九七〇)の著書 『アメリカにおける社会進化論 (Social Darwinism in America)』 によって広められるまで、この用語がほとんど使われていなかったことを発見している。つまり、アメリカやイギリスにおける優生学的政 策、第二次世界大戦時のホロコーストに至るナチスの政策など、社会進化論に結びつけられている悪事の多くが発生した時期に、それらの政策の支持者も反対者も、「社会進化論」という言葉をめった に使っていなかったということだ。
端的に言えば、「社会進化論」という言葉は当初から終始一貫して、強者があの手この手を尽くして弱者から巻き上げることを正当化する政策を揶揄するための中傷として使われていたのだ。自分で自分を社会進化論者と呼ぶ人はまずいないし、そのレッテルを貼られて非難を浴びた人々も、実際に ダーウィンの理論を用いて自分の立場を正当化することはほとんどなかった。かくしてダーウィンの 理論は、誤解に基づいて過剰に非難されてきたのである。
第一の問いは、「ある特徴に機能があるなら、それはいったい何か?」「他のあり得るさまざまな特微を差し置いて、なぜその特徴が存在しているのか?」である。 第二の問いは、「その特徴の世代を 超えた進化の歴史はいかなるものか?」である〔系統発生〕。第三の問いは、「対応する身体のメカニ ズムは何か?」だ。行動特性を含めたあらゆる特徴には、機能に加え、解明されるべき身体的基盤が存在する。そして第四の問いは、「その特徴は個体の一生を通じていかに発達するのか?」である。 ダーウィンの道具箱の基本コンセプトは、これら四つの問いをそれぞれ別ものとして認識し、相互に組み合わせながらそれらを解明していくことから成る。
たとえば手は、物体の把握(【機能】)に関連して、脊椎動物の一部の系統に沿って自然選択によって進化した適応器官であり、解剖学的に魚類の鰭に類似する(【系統発生】)。身体組織という点では、 物体をつかむのに最適なあり方で筋肉、骨、腱、神経が組み合わされている(【メカニズム】)。そして 手は、早ければ妊娠後五週目で出現し始める (【個体発生】)。手に関する完全な説明は、このように四つの問いのすべてに答えることから成る。
ここで、アボカドキューバー、鳥の羽、襲いかかるクマについて考えるあり方を「機能的推論モ―ド」と、また、雪の結晶、天候、転がり落ちてくる丸石について考えるあり方を「物質的推論モー ド」と呼ぶことにしよう。私たちの誰もが、生涯にわたり両モードの推論を行ないつつ生きている。 しかし私たちは、両者を取り違えやすい。たとえば雪の結晶のような純粋に物質的な事象を、鳥の羽 のように機能的に設計されたものとしてとらえることがある。逆もまたしかり。あるいは、アボカドキューバーをアスリートの急所プロテクターと取り違えるなど、機能的に設計されたものとして正しくとらえながら、その物体に間違った機能を見出すこともある。…
ダーウィンの進化論が登場するまでは、その種の誤りが壮大なスケールで生じていた。キリスト教の世界観では、全宇宙が慈悲深い全能の神によって創造されたとされる。 小さな昆虫から天空の星々に至るまで、神の偉大な計画のなかで割り当てられた役割を演じているのである。また人間の苦しみ や悪の顕現にさえ目的があり、私たちはその解明に努めなければならない。だからマルサスは、飢饉や疾病を、道徳にかなう振る舞いをするよう人間に教えるために、神が課したものと見なしていたのだ。今日の知見に基づけば、それらの誤りのほとんどは、純粋に物質的なプロセスを設計されたプロセス〔と取り違えていたことによる〕。
帝王切開によって分娩された子どもは、通常の方法で生まれた子どもに比べ、 アレルギー性疾患を発症する頻度が高い。明らかに新生児は、産道通過時に母親のマイクロバイオータの接種を受けるものと考えられる。
妊婦の抗生物質の服用は、生まれた子どものアレルギー性疾患の発症率を高める。このケースで は、産道を通過した新生児であっても、母親の正常なマイクロバイオータの接種を受けることができない。
母親の妊娠中、もしくは新生児期間に農場の環境に接すると、 子どものアレルギー性疾患の発症率が低下する。
一〇~一五歳の頃まで自然環境に接していると、後年になって多発性硬化症を発症する可能性が低下する。
屋内での殺菌剤の使用は、 アレルギー性疾患の発症率を高める。九九・九パーセントの細菌を殺すのは、賢明とは言えない!
寄生虫を含め、マイクロバイオームのより自然な種構成を取り戻すことは、成人の健康に、ただちに恩恵をもたらしてくれる。
慢性炎症性疾患は、先進国でより多く見られる。また先進国内でも、農村地域より市街地で多く見られる。それには、炎症が関与しているにもかかわらず、多くの人々がその事実を認識していない、うつ病、統合失調症、自閉症も含まれる。
発展途上国から先進国への移住民は、炎症性疾患を経験しやすい。それに関するもっともすぐれた研究には、貧しい国で生まれ、スウェーデン、アメリカ、イスラエルなどの先進国の家族のもとに養子に出された子どもを対象に行なわれたものがある。これらの子どもたちは中流、ならび に上流階級の家庭で育てられており、よって受け入れ国の貧困が原因で炎症性疾患に罹患したとは考えられない。
子ども部屋の塵を採取して行なった研究によって、塵に含まれている微生物の多様性と喘息を発症するリスクのあいだに負の相関関係があることが判明している。微生物が多様であればあるほ ど、喘息になりにくいということだ。
フィンランド、ロシア両国をまたがる国境地域で暮らす遺伝的に同質な住民を対象に、自然実験に基づく研究が実施されている。この研究の結果、ロシア側よりフィンランド側のほうが、1型糖尿病の有病率が四倍高いことがわかった。この差異は、屋内で採取された微生物の多様性の著しい差異に符合する。
動物実験では、内臓に宿る微生物の多様性の低下と劣悪な炎症コントロールのあいだに正の相関関係が頻繁に見出されている。
施設に収容されている高齢者はマイクロバイオータが減退している。この現象は、炎症性疾患に よる健康の悪化と相関する。
以上の事例や他の事例は、人間が宿すマイクロバイオームを「昔馴染み」と呼ぶ、微生物学者グラ ハム・A・ルークによる二〇一三年の論文に要約されている。 マイクロバイオームは、悠久の時を超 えて人類と共存しているので、私たちはそれなしでは暮らせなくなっているのだ。彼は二〇一五年に行なわれたラジオインタビューで、「私たちは個人ではありません。皆さんにはショックに感じられ るかもしれませんが、実のところ私たちは生態系なのです」と述べている。たいていの人は、生態系を森や湖のような屋外にある何かとして考えている。また、原野などのもっとも自然で見た目にも美しい生態系は、私たちの体外に存在すると考えている。環境保護論者は、惑星規模に至るまで地球の 生態系を守る必要性を説いている。この背景に照らすと、各人が環境保護を必要とする一個の惑星で あるという考えは、誰にとっても新奇なものに思える。
多数の研究によって、幼稚園で実施されている教育関連プログラムと、年齢にふさわしい遊びを促進するプログラムが比較されている。教育関連プログラムは一般に、限定的かつ短期的な教育効果をもたらした。 しかしこの効果は一年から三年で拭い去られ、逆転するケースもあった。つ まり、幼児向けの教育関連プログラムは有効でないばかりか、裏目に出る可能性さえあることを 示す証拠が得られている。
幼児向けの教育関連プログラムは、長期的な観点から見ると、社会的、情動的な発達を阻害する 可能性があることを示す証拠が存在する。一九七〇年代にドイツで実施されたある研究は、遊び を重視する幼稚園に通っていた五〇人と、ダイレクト・インストラクション〔規定された指導要綱 に従った読み書き、算数の教育〕に基づく教育重視の幼稚園に通っていた五〇人を比較している。教育重視の幼稚園に通っていた生徒は、短期的な学業成績の伸びを示したが、四年生になる頃には、遊びを重視する幼稚園に通っていた生徒より、成績がかなり悪くなっていた。読み方と算数ではあまり進歩が見られず、社会的、情動的側面では、うまく適応できていなかった。この研究成果も一部影響して、ドイツ政府は教育政策を変え、遊びを重視する幼稚園を推奨するようになった。
一九六七年にデイヴィッド・ウェイカートらが始めた注目すべき研究は、ミシガン州イプシランティ市の極貧地区で暮らす、六八人の同年代の子どもたちを二三歳になるまで追跡している。子どもたちは、トラディショナル(遊びを重視する)、ハイスコープ(おとなの指導を受けた遊びを重視する)、ダイレクト・インストラクション(ワークシートやテストを用いた読み書き、算数の学習を強調)という三タイプの保育園のいずれかに割り当てられた。加えて家族は、子どもたちが保育園で受けているものに類似する家庭向けガイドブックを渡された。他の研究同様、ダイレクト・インストラクション・グループの子どもたちは、短期的な成績の向上を示したが、長くは続かなかった。 一五歳の時点では、学業成績に関しては三つのグループのあいだに差異はなかったものの、社会的、情動的発達に関しては大幅な差異が認められた。たとえばダイレクト・インストラクショ ン・グループの生徒は、他の二つのグループと比べ二倍以上の「不品行」を犯した。 二三歳の時点では、差異はさらに劇的なものになった。保育園に通っていた頃にダイレクト・インストラク ションを受けた青年は、情動的な問題を抱えているケースがより多かった。たとえば他の二つの グループの青年に比べ、結婚して夫婦で暮らしている人の割合が少なく、犯罪に走る可能性が 高かった。三九パーセント(他のグループは一三・五パーセント)が重罪で逮捕された犯罪歴を持ち、一九パーセント(他のグループは○パーセント)が暴行容疑で法廷に召喚されたことがあった。
二歳未満の子どもにとって、本や映像が呈する二次元イメージは、三次元の物体(それには人間も 含まれる)に比べると、学習ツールとしてはるかに効果が薄い。 二次元イメージは、人類の進化の歴史におけるほとんどの期間、非常に小さな役割しか演じてこなかったが、現代では至るとこ ろに見出せるようになった。 明らかに私たちは、それを理解する能力を発達させることができるし、またそうしなければならない。しかしこのプロセスを加速させようとすれば、他の重要な発達プロセスを阻害するかもしれない。
乳幼児向けの教育用DVD/ビデオ製品は、巷の人気や宣伝とは異なり、その有効性を裏づける証拠が得られていない。 生後一二~一八か月の乳児を対象に一年間行なわれたある研究は、次のような四つのグループを比較している。① 乳児は、親と単語学習用ビデオを見る。 ② 乳児は、同 じビデオを一人で見る。 ③ 乳児は、ビデオを見ずに親と話す。④ 特に何も指示しない(対照群)。 乳児が対照群より多くの言葉を覚えたのは③のケースのみであった。
乳幼児向けの教育用DVD/ビデオ製品は、効果がないばかりでなく、それらの製品が伸ばすと 謳っているまさにその能力を遅滞させる可能性がある。二〇〇七年に生後八~一六か月の乳児を対象に行なわれたある研究では、単語学習用DVD/ビデオ製品を一時間見るごとに、語彙が六 ~八語少なくなるという結果が得られている。(※強調は著者)
あらゆる種類の背景メディア(テレビなど)によって、実行機能(計画を立て、自分の行動をコントロールする能力)を含めた、乳幼児のさまざまな能力の発達が阻害されることを示す証拠が集まりつつある。その証拠は非常に明快であり、米国小児科学会は一九九九年以来、 二歳未満の乳児 をテレビやその他の背景メディアにさらさないよう勧告している。ボストン・メディカル・セン ターのジェニー・S・ラデスキーらによる二〇一四年の研究では、生後九か月の乳児を長時間メディアにさらすと、怒りっぽさ、注意散漫、性急さ、注意をある課題から別の課題に移すことの困難につながることが示されている。 なお、両親や他の家族構成員の特徴は統計的にコントロールされている。
おとなの監視を最小限に抑えた昔ながらの遊びが、実行機能の発達に向けて重要な役割を担っていることが明らかになりつつある。遊びは、安全で安心できる環境のもとで、子どもが他者に対する自己の行動の調節を学ぶ機会を提供する。 子どもは、遊びに対する強い動機を持っている。 子どもに遊び方を教える必要はない。しかし現代では、自由な遊びをする機会がめっきり減っている。そのことは学校ばかりでなく、決まりきったレクリエーション活動や、おとなの監視なしで子どもが遊ぶにはあまりにも危険になった近隣社会に関しても当てはまる。
これで、政策を生物学の一分野と見なすべきことを例証する三つ目のストーリーの幕を閉じる。こ の事例は、他の二つの事例に何をつけ加えるのか? 最初のストーリーは、一般に「生物学」という 用語に結びつけて考えられている事象に相当する。目や脳の視覚処理の発達が生物学的な事象ではないと主張する人などいないだろう。しかもその種の生物学的知識は、乳児の白内障をいつ除去すべき か、あるいは現代における近視の流行にどう対処すればよいのかなどといった重要な政策決定を下す際にも必要とされる。 疑い深い読者も、少なくとも、白内障や近視をめぐる政策は、目の発達に関す る生物学に基づかなければならないという私の論点を受け入れてほしい。
脊椎動物の免疫系の発達を取り上げた二つ目のストーリーも、たいていの人が「生物学的」と呼ぶ事象にきっちりと当てはまる。しかし免疫系の機能不全のなかには、不安、うつ病、自閉症スペクトラム障害など、行動的なものとして顕現するものもある。したがってこの事例は、半世紀以上前に ティンバーゲンが指摘した、「行動の研究は生物学の一分野である」とする見方を裏づける。いかなる形態で免疫系の機能不全が起ころうと、ただちにその原因を把握し、何らかの処置をする、すなわ 生物学的知識に基づいて的確な政策を考案する必要がある。
鳥類における感覚能力の発達を最初に取り上げた三つ目の事例も生物学から始まるが、行動的な側 面を強調して幕を閉じる。 家庭で子どもを育て、子どもに学校教育を受けさせることを行動的でない〔と言う人はいないだろう。〕
グループ内では利己主義が利他主義を打ち負かす。利他的なグループは利己的なグループを打ち 負かす。それ以外はすべて、つけ足しにすぎない。
私たちの目的にとって重要なのは、個人としての学習能力と、免疫系の先天的、ならびに適応的な構成要素のあいだには類似性が認められるという点だ。 この比較から得られる知見がいくつかある。
第一に、そしてもっとも重要なこととして、急速に進化し、生きている限り環境に適応していく独自のシステムとして、自分自身を考えられるようになることがあげられる。自分の本性を決定づけるおもな要因は、(開かれた学習を可能にする遺伝子を除けば))遺伝子ではなく、環境と、遭遇した困難を解決するためにこれまで選択し適応を遂げてきた行動様式である。 そしてあなたは、過去の環境にうまく 適応してきたように、現在の環境が呈する課題にも適応できる。このように、自己を積極的に変え、 変革する能力をもあなたは備えているのだ。
だからといって、意識して自分用の抗体を選択することなどできないのと同様、あなた個人の進化 が「何でもあり」であることを意味するわけではない。開かれた学習を可能にするメカニズムは非常 に複雑であり、そのほとんどは意識的な気づきの埒外で生じる。意識して進化を導きたいのなら、そ のメカニズムを理解し、徹底的に探究しなければならない。
さらに言えば、遺伝的進化の事例に見てきたように、進化的な意味での適応は、必ずしも規範的な意味における「よきこと」「正しいこと」を意味しない。遺伝的進化は、「私」や「私たち」にとって は都合がよくても、「あなた」や「彼ら」にとっては都合の悪い適応、あるいは自分にとって短期的 には有益でも長期的には有害な適応をもたらすことが多々ある。開かれた学習によって獲得された行動にも、それと同じ限界がある。というより、行動適応は遺伝的進化よりさらに先見の明を欠く。なぜなら、自らの行動に由来する直近の損得は、長期的な結果より見えやすいからだ。やせたいのに、 ポテトチップスについつい手が伸びるなどといったたぐいの経験は誰にもあるだろう。世界平和を 願っていても、会社のライバルを出し抜くためなら何でもするかもしれない。このように学習能力を個人や社会の長期的な目標に合わせるためには、相当な賢明さが必要になる。
私たちはまた、免疫系と同様、学習システムの適応的な構成要素が、生得的な構成要素、すなわち外界からの刺激によって引き起こされる一連の固定的な行動反応と組み合わさって機能するという点に留意しておかねばならない。 最初の進化心理学者は、人間や動物の心のモジュール性を強調した点 では間違っていなかったが、心が適応的な構成要素を含み得ることを否定した点では間違っていた。 人間の学習システムの生得的な構成要素を正しく評価するために、あらゆる生物が、その進化の歴史を通じて穏やかな状況と厳しい状況の両方を経験し、…外界からの信号によって引き起こされる何らかの反応を適応によって獲得するに至ったことを考えてみよう。人間以外の生物は、状況が悪くなっても取り乱したりはしない。困難な 状況に適応し、それにふさわしいあり方で振る舞うのだ。鳥類の多くの種では、ストレスに満ちた環境下に置かれると、メスはコルチコステロンの濃度が高い卵を産む。実験でホルモンの濃度を操作すると、他の点ではあらゆる条件の等しいヒナが、異なる成鳥へと育っていく。発達期に高濃度のホルモン分泌を経験した個体は、低濃度のホルモン分泌を経験した個体に比べ、飛翔筋がより迅速に発達し、身体のサイズがより小さいうちに巣立ち、飛行成績がすぐれる。またエサを探すとき、より活発に活動し、積極的に高いリスクをとろうとする。これらの行動は、ストレスによって引き起こされた欠陥ではなく、試行錯誤に基づく学習によって獲得されたものでもない。そうではなく、それらの行動は遺伝的進化の結果によって得られた、ストレスに満ちた環境への適応であり、適切な信号が外界から入ってくることで発現するのを待っていたのである。実を言えば、開かれた学習のプロセスでさえ調節される。ストレスに適応した鳥には、親から学んだ行動を軽んじて、自己の経験や同種の他 の個体から学んだ行動を選好する傾向がある。どうやら母鳥がストレスを受けているのは、他の鳥が知っていることや、子どもの鳥が自力で学べることを知らないからなのかもしれない!
研究室で行なわれたラットを使った実験によって、ストレスを受けている母親は、幼獣をなめるのにあまり時間を費やさないことが判明している。実験的な手段で母親が幼獣をなめる量を操作したところ、それ以外の点では他の個体と変わらない幼獣が、他と異なる成獣へと成長した。 たとえば母親 にあまりなめられずに育ったメスの幼獣は、他のメスより社会的に優位な地位を占め、オスにとって魅力的で、妊娠しやすい成獣へと育った。また、母親にあまりなめられずに育ったオスの幼獣は、若い頃攻撃的な遊びを好み、成獣になるとけんか早くなる。要するにメスもオスも、できるだけ早く繁殖に入れるよう適応するのである。これらの行動はよく理解できる。なぜなら、ストレスのかかった 環境下では、もしかすると明日はないかもしれないからだ。これは鳥の事例に似ているが、こちらで は環境からの信号はホルモンではなく母親の行動によって与えられる。
人間の子どもの発達が、鳥類や人間以外の哺乳類と同様、ホルモンや行動による信号の影響を受けていると考えるべき理由はいくらでもある。そもそも私たちは哺乳類の一員であり、人類が進化の歴史を通じて獲得した特徴は何であれ、より古い生物系統の上層に積み重ねられている。貧困、保護者による放置、暴力、栄養不足などの厳しい状況を経験してきた子どもは(平均して)、より温かい環境 のもとで育った子どもとは異なるおとなに成長する。そのような子どもは、おおざっぱに言えば、 ストレスに適応したラットが獲得したものと同じ一連の、早期の生殖に向けた社会的、性的戦略を発達させる。彼らの開かれた学習の能力は変容し、長期的ではなく短期的な報酬を得ようとする問題解決 能力が強化される。そのような環境で育つ三歳児に人形劇のシーンを思い出させると、よいできごとより悪いできごとをよく覚えていることがわかった。また、一つの活動から別の活動へとすぐに注意が移り、リスクが高い状況のもとでよい成績を収める。
子どもの発達の研究では、その種の性格の相違が、さんざん報告されてきた。しかしそこに提示されている解釈は、現代的な進化論の観点を欠いているため問題を孕む。ほとんどの発達心理学者は、「子どもは温かい家庭では順調に発育し、厳しい環境下では、荒地で故障する車のごとく成長が阻害される」と仮定している。そのため、壊れたものを修理し、いわゆる「危険にさらされている子ども」を「正常な」子どもに近づけることが課題だと考えられているのである。これは、「何が観察可能なのかは、理論によって決まる」ことを示す格好の例だと言えよう。つまり「壊れた車」モデルに照らしてものごとを見てしまうと、ストレスに満ちた環境下では、個体は適応的な行動を示すという考えが、見えにくくなる。
〔ダーウィンに先立つ欧州の知識人の多くは「人類は同〕種のメンバーである」という、人類の統合性に関する信念を抱いていた。また、スペンサーに見たように、「人類は完成に向かう途上にある」と見なす、 進化による進歩という考えを共有していた。彼らは当然のことのように、ヨーロッパ人が先頭を歩んでいると考え、そのヨーロッパ人が、他の文化に属する人々を手助けし「より文明化」すべきだとする姿勢をとっていた。
ダーウィンはおおむね彼らの見方を共有していたし、いずれにせよ一九世紀後半から二〇世紀前半 にかけて誕生した人類学や社会学の諸分野に属する主要な思想家たちと舞台を共にしていた。この見方に反対していたのは、フランツ・ボアズとブロニスラフ・マリノフスキーの二人であった。ボアズ は当初、物理学を専攻し、北極圏における光のさまざまな効果を研究するために、若い頃にバフィン島に行ったことがあった。そこで彼は、厳しい環境のもとで暮らし続けているイヌイットの能力に強 い印象を受け、彼らを人間存在の連鎖の下位に位置すると見なすことなどとてもできなくなった。彼らは北極圏という特異な環境のもとにおける生存と繁殖に、他の誰よりも長けていたのだ。そしてすべての文化を、それと同じ観点から見るべきではないかと、彼は考えた。彼のこの見方は、ダーウィンの進化論と強く整合する。ボアズは、(彼が支持する)ダーウィニズムと、(彼が否定する)漸進的形態 の進化を十分に区別していた。
マリノフスキーは、第一次世界大戦中に太平洋に浮かぶトロブリアンド諸島で過ごしたときに、先住民の文化に精通するようになった。またボアズ同様、野蛮から文明に至る直線上のどこかに先住民を置くのではなく、彼らが暮らしている環境という文脈のもと、彼らの視点から世界を見ることの重要性を理解するようになった。この考えはやがて、現地の人々と暮らし、各文化をその文化の言葉で理解するよう努めるという人類学の伝統を形成していく。この伝統に基づくと、いかなる理論的な視点も、早計なものとして意図的に回避され、もっとも重要なのは、できるだけ客観的な手段を用いて 情報を収集し、かくして収集された情報を、理論を適用して分析することだった。二〇世紀中盤に活躍したイギリスの高名な人類学者E・E・エヴァンズ=プリチャードが述べているように、人類学という仕事の全体が翻訳作業であり、調査対象の文化の構成員が見ているように当の文化を見ることに その目的がある。
人類学におけるこの伝統は、「人類は完成に向かう途上にあり、世界各地の文化に関する情報の蓄積へと至る」という根拠薄弱な見方を改善するものであった。しかし 理論的枠組みなくしては、情報を整理する方法もなかった。同じことは、別の分野として発展してきたが、人類学と同様、あたかも統一的な理論的枠組みなどあり得ない と考えているかのように、おおむね無理論 的であるか、反理論的になることすらある。
うまく環境に適応した、意味のシステムの内部にいれば、私たちは目的感に満たされて毎朝目覚め、自己の繁栄のためにやるべきことを、今まさにやり遂げたいと強く感じるようになるだろう。とはいえ意味のシステムは、少なくと も二つの様態でうまく機能しなくなることに留意されたい。つまり私たちを鼓舞する能力を失う場合 と、間違ったことをするよう私たちを鼓舞する場合の二つである。
伝説的なトークショー司会者、ラリー・キングのインタビューを受けたゲストを対象に実施された研究がある。 この研究では、キングとゲストの関係が分析されている。ゲストのなかにはラリーより 社会的な地位が低い者もいれば、元大統領ビル・クリントンのように高い者もいた。インタビューの音響分析によれば、ゲストがラリーより社会的地位が低い場合にはゲストがラリーの、高い場合にはラリーがゲストの話し方(スピーチパターン)を真似した。
これらの研究をはじめとして、最近増えつつある多数の研究によって、子どもでも、おとなでも、 私たちが他者から学ぶことは、ランダムどころではないことが示されている。私たちは、誰が注目されているのか、誰が誰より社会的に地位が高いのかなどといった手がかりに基づいて判断を下す。 誰かを真似する行動を知性的と呼べるとするなら、それはおもに意識の埒外で生じる知性だと言えよ う。子どもたちは、「あとから入って来た人の注目を浴びているあの人の行動を真似しよう!」など と意識的に考えてはいないし、インタビューを受けたゲストは、「ラリーは私より社会的に地位が上 だから、彼の話し方を真似しよう!」などと考えてはいない。
経済学者が共有地の悲劇という可能性を見落とす理由の一つは、彼らが、個人による自己利益の追求が公共善に資すると固く信じているからである。経済学者がハーディンのたとえ話が示唆する問題を認識した場合でも、彼らが提起する主要な解決策は、(可能なら)共有資源を私有化するか、トップダウンの規制を課すかのいずれかだ。
そのような状況を背景にすると、リンの業績がまさしく革新的であったことがわかる。おもに数式を用いて理論を裏づけようとする主流経済学とは異なり、彼女は共有資源の管理を試みている世界中のグループの情報を集めたデータベースを編纂し分析する取り組みを先導した。それらのグループのいくつかは、私有化もトップダウン規制も行なわずに共有地の悲劇の回避に独力で成功していた。つまり経済学者は、現実世界で起こっている事象が見えていなかったのだ。
彼女の業績の偉大さは、失敗と成功を分かつ八つの中核設計原理(core design principles = CDPs)を引き出したことにある。これらの原理はいかなるグループにも必要とされるものだが、独力でそれを見出したグループは少ない。
能書きを並べることは控えて、八つのCDPを解説しよう。以下の一覧を読みながら、自分の属するグループがその要件を満たしているかどうかを考えてみよう。
CDP1: 強いグループアイデンティティと目的の理解
大きな成功を収めたグループは、利用可能な資源の限界や、誰がそれを利用できるのかについて、またグループの一員であることで与えられる権利と課される義務について熟知している。誰に漁の資格があるのか、どの区画が誰に割り当てられているのかをわきまえているトルコの漁師の事例では、この要件が満たされていることがはっきりとわかる。
CDP2: 利益とコストの比例的公正
誰かにすべての仕事をさせて他の誰かが利益を得ているようでは、そのグループを長期にわたり維持することはできない。うまく機能しているグループでは、誰もが公正な分け前を手にしている。リーダーに特権が与えられるのは、事後の説明が問われる特別な責任が課されるからである。公正さを欠く不平等は、集団による試みを阻害する。トルコの漁師が考案したシステムがうまく機能したのは、ひとえにきわめて誠実に公正さが保たれていたからだ。
CDP3: 全員による公正な意思決定
うまく機能しているグループでは、必ずしも多数決ではなかったとしても、公正と認識されている何らかのプロセスを通じて、誰もが意思決定に参加している。人々は他人にいばり散らされることを好まないが、合意された目標の達成に向けて懸命に働く。加えて、最善の意思決定は、グループの個々のメンバーが把握していてトップダウン規制では得られない局地的な状況に関する知識が必要になる場合が多い。トルコの漁師の事例では、誰もが取り決めに同意しなければならず、彼らのみが海域全体を分割するのに必要とされる十分な知識を持っていた。また、このシステムの完成には数年を要し、グループのメンバーのみが、調整に必要な情報を手に入れられる立場にあった。
CDP4: 合意された行動の監視
グループのほとんどのメンバーが善意をもって振る舞っても、さぼったり、不当に利益をむさぼろうとしたりする誘因はつねに存在し、少数のメンバーが実際にシステムを悪用しようとすることもある。リンのデータベースに登録されているもっとも成功したグループは、トルコの漁師の例に見たように過失や違犯の検知に長けていた。
CDP5: 段階的な制裁
誰かが自分の仕事を果たしていない場合、通常は友好的注意を発するだけで、そのような人を堅実な市民の態度をとるよう改心させるに十分である。だが必要になれば、処罰や排除などのより厳しい処置をとれなければならない。これに関して、また他のCDPに関してもリンが好んで引き合いに出した例の一つは、アメリカはメイン州のロブスター漁師に関するものである。トルコの漁師と同様、ロブスター漁師は海岸の区画の排他的利用権を持つ「ギャング」に組織化されている(CDP1)。ロブスター漁師はブイに各人独自のペイントを施して、互いの漁獲活動を監視し、よそ者を見つけられるようにしている(CDP4)。自分たちの領域によそ者が罠を仕掛けると、地元のロブスター漁師は、ブイのまわりに蝶ネクタイのような結び目を作ることで段階的な制裁を始める。
CDP6: もめごとの迅速で公正な解決
利害の対立は、どんなグループでも発生し得る。リンのデータベース中のもっとも成功したグループは、関係者全員が公正と見なす方法で、もめごとを解決する手段を持っていた。 外部の権威に頼る必要はなくても、協同組合ような組織が必要とされるのはそれゆえである。
CDP7: 局所的な自律性
一つのグループがより大きな社会の内部に包囲されている場合、そのグループには、CDP1-6で略したように、それ自体が社会的組織を形成し、独自の意思決定を下すに十分な権威が 与えられなければならない。トルコの漁師の事例は、明らかにこの要件を満たしている。リンの データベース中の他のグループが共有資源の管理に失敗した理由は、多くのケースではグループにそのような余地が与えられていなかったからだ。
CDP8: 多中心性ガバナンス
多数のグループから構成される大規模社会では、グループ間の関係は、グループに所属するメンバー間の関係を統制するものと同じ規律に従わなければならない。これは、CDPがスケールに依存しないものでなければならないことを意味する。この点は、第8章で大規模社会に目を向ける際に、非常に重要な要件になる。トルコの漁師は、資格の授与、激化した対立の解決などに関しては、(司法制度などの)高次の統治制度(たとえば司法制度)に依拠していたが、CDPを妨害するのではなく、その実施に寄与する方向でそうしていた。
「多芸は無芸」というよく知られた原理のおかげで、自然選択はほぼつねに交換条件(トレードオフ)をともなう。 一つの仕事をうまくこなすことは、他の仕事をぞんざいに済ませることにつながる。たとえばカメの甲羅は捕食者からわが身を守る一方、動きを鈍くする。ペンギンは敏しょうな泳ぎ手だが、陸地でよたまた歩く様は滑稽に見える。色素沈着した皮膚は紫外線から身を守るが、ビタミンDの合成を妨げるいかなる生物も、進化の歴史を通じて作用してきた数々の選択圧力によって形成された交換条件の束なのである。
その個体が生きているあいだにとる行動様式も、交換条件に影響を及ぼす。カメの甲羅は解剖学的な特徴であり、危険を感じると頭や手足を甲羅のなかに引っ込め、危険が去ると再び外に出すのが、カメの行動である。どちらの行動も交換条件という用語で説明できる。解剖学的特徴と同様、行動も進化するという考えは、ニコ・ティンバーゲンによって提起され、『行動生態学』に結実した。
〔丘の前に〕立っているところを想像してみよう。丘をのぼる坂は、どれくらい急なのか? この丘をのぼりたいという意欲がどれくらい強いのか? これら二つの問いは、互いにまったく異なるように思えるかもしれないが、ジムの学部の同僚デニス・プロフィットが行なった実験が示すところでは、それらは私たちの心のなかで絡み合っている。プロフィットは、重いバックパックを背負わせる(背負わせない)、事前に断食させる(させない)、事前に運動をさせる(させない)など、さまざまな条件のもとに置いた被験者に丘の傾斜を見積もらせた。重いバックパックを背負っているときや、断食や運動をしたあとでは、丘にのぼる意欲がそがれることは容易に推察できるが、意外な結果は、それらの条件のもとに置かれた被験者が丘の傾斜を過剰に見積もったことである。つまり丘をのぼろうとする意欲が、丘の知覚に影響を及ぼしたのだ。
その種の事例は、脳が交換条件を評価するとき、個人的な資源を計算に入れることを示している。ところでデニスは、丘の傾斜を見積もらせるにあたって、被験者が友人の隣に立っている場合と、一でいる場合を比較する実験も行なっている。その結果、被験者は友人がそばにいるだけで、丘の傾斜をよりなだらかなものとして見積もった。
誰かを助けようとする人々に囲まれてい る人はさまざまな資質を発達させるのに対し、無関心な、あるいは敵対的な人々に囲まれている人は さまざまな負債を抱えることになる。もちろんこれは、ジム・コーンの研究が示唆するところでもあ る。世界をよりよき場所にし、その成果を社会政策や個人の意思決定に反映させる方法を一つあげるとすれば、それは生涯を通じての、そしてとりわけ誕生する以前を含めた幼少期における愛情のこもった養育を強化することである。
私たちの行動はかなりの程度、それによって生じた結果によって形作られる。そして私たちの行動は、たいてい社会的環境によって選択される。ここまで見てきたように、人類は、その進化の歴史のほとんどの期間を通じて、高度に協調的な小グループを形成して暮らしてきた。私たちは十分に養育され、その返済を期待される。他人にいばり散らしたり、自分の仕事を怠ったりすれば、その態度を改めるよう社会的な圧力がただちに加えられるだろう。共通の目的に寄与すればするほど、それだけ私たちは社会的に認められ、受け取る物質的恩恵も増える。これは、他人を犠牲にして成功しようとする戦略を非常にリスクの高いものにし、他者と協調しながら成功することを、個人としての生存と繁殖を達成するためのもっとも確実な手段にする。私たちは、社会的な承認を追い求め、そのためならどんなことでもするよう遺伝的に適応しているのである。
そうではあれ、進化の歴史においてグループ内の養育がすべてであったわけではない。他人を犠牲にして成功することはリスクの大きな戦略ではあるが、特定の状況のもとでは実行する価値があるだろう。遺伝的進化は、協調のスキルとともに利己的に行動するスキルも私たちに与えた。哺乳類に見出されるもっとも親密な絆、すなわち母子の関係について考えてみよう。この絆でさえ、完全に養育的なものとは言えない。母親は、その生涯を通じて特定の子どもの成功ではなく総体的な繁殖成功度を最大化するよう、また子どもは、母親や兄弟姉妹の幸福より自分の幸福を重視するよう遺伝的進化によって形作られている。さらに言えば、多くの哺乳類の父親はできるだけ多数のメスと交尾し、子どもの養育にまったく関与しないことで繁殖成功度を最大化するよう遺伝的進化によって形作られている。それに関して言えば、すでにいる子どもを殺して別の子どもを設けようとする、幼児殺しという進化的ロジックさえ存在する。
母子間の争いは、子どもが誕生する前から始まっている。胎児は、母親が自然な傾向として与えようとする以上の資源を引き出そうとするのだ。生命プロセスのこの段階における母子の相互作用は、心的ですらない生物化学的な綱引きである。子どもの誕生後、母親やその他の養育者は、厳しい状況のもとでは子どもの養育を控えるよう遺伝的に設定されている。それに対して、子どもは自分が必要な養育を受けていない場合、可能な限り悪さをするよう遺伝的に設定されている。これらの生理的、神経的なメカニズムの多くは、人類が誕生するはるか以前から、それどころか霊長類が哺乳類から枝分かれする以前から哺乳類の系統で進化してきたものである。
事態をより複雑にしているのは、第4章で見たように、グループ間の社会的相互作用が、グループ内のそれとは異なる点だ。メンバーが互いに扶養し合うグループは、状況に応じて他のグループと友好的に接したり、敵対的に接したりするだろう。貿易や結婚相手の交換などの友好関係は進化の歴史のはるか昔から存在していたが、襲撃、食人、他グループの抹殺などの敵対関係にも同じことが当て〔はまる。〕
問題を抱える家族がスーパーナニーの訪問を受けるというリアリティ番組は、台本に基づくとはいえ現実からまったくかけ離れたものではない。『スーパーナニー』の背景をなす科学についてもっとよく知りたい向きには、トリプルP(肯定的な養育プログラム(Positive Parenting Program))というウェブサイトを訪問することをお勧めする。トリプルPでは、世界中の人々が、トニーのような研究者が行なった科学研究を参照することができる。そこで学べるヒントには、「計画的な無視」「質の高い時間を過ごす」「学習環境の形成」などが含まれる。子どもの望ましくない行動に無反応でいることで、その子どもに何か別のことをするよう促せる(「計画的な無視」)。とりわけ質の高い時間を過ごすことができ(「質の高い時間を過ごす」)、粋なことや興味深いことが学べるのであれば「学習環境の形成」)、より肯定的な行動を強化することができるだろう。ヒントの一つ「タイムアウト」は、よき態度を強化するための他の試みがすべて失敗したときにのみ実行すべきものである。家庭生活が円満である限り、それを実行する必要はない。
これらのヒントが子どもを操る戦略であるように思えるのなら、私たちはつねに、何らかの方法で互いを操っているのだということを思い出されたい。そもそも人間は、社会的な相互作用の産物なのだ。「操作」という言葉が、より中立的な用語の「社会的相互作用」に比べて邪悪に響く理由は、それが利己的な目的のために、相手の利益に反して誰かの行動に影響を及ぼすことを含意しているからだ。「操作」の持つこの側面こそ避けるべきものであり、第6章で取り上げたCDPが防ごうとしているものなのである。
精神分析ではない
20世紀の偶像の一人ジークムント・フロイトの考えは、現代の進化論の観点からの相当な書き直しを必要としている。
ネバダ大学リノ校の心理学部教授スティーヴン・C・ヘイズを紹介しよう。スティーヴは、三五冊の著書と五〇〇本の論文を著した、世界でもっとも多産、かつ広く引用されている心理学者の一人だ。彼は、二〇〇六年に『タイム』誌によって六頁にわたり取り上げられた、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)と呼ばれる心理療法でよく知られている。彼が著したACT自己啓発書『自分の心から自由になって人生を送る(Get Out of Your Mind and into Your Life)』は、これまでに五〇万部以上売れている。
スティーヴに会う前の私を含む多くの人々にとって、心理療法は、効果が現れるのが遅く、非効率で、非科学的だという評判が頭に入っている。 私の母親は、フロイトの精神分析の熱心な支持者で、成人してからのほとんどの期間を、一週間に一度精神分析医のもとに通いながら過ごしていた。彼女はその経験から何かを得ることができたと感じていたが、その種のセラピーが科学的に精査されると、牧師や思いやりのある友人と話す以上の効果はないことが証明された。フロイトは医師だったが、彼の方法はまったく科学的ではなかった。彼の無意識の理論は明らかに何かをつかんでいたとはいえ、自分の考えを単なる思索以上のレベルに引き上げることのできる技法を、彼はまったく持ち合わせていなかった。
それとの比較として、ここでスティーヴが書いた一本の論文について考えてみよう。アメリカで学ぶ外国人留学生は、強いストレスを受け、それが不安障害やうつ病となって現れることがある。スティーヴと同僚たちは、ネバダ大学で学んでいる七〇人の日本人留学生を集めて、二つのグループにランダムに割り当てた。第一のグループの被験者は、スティーヴが著した自己啓発書を読み、そこに書かれていることを実践した。第二のグループの被験者は、二か月の待機期間を置いて同じことをした。スティーヴらは、GHQ精神健康調査票や、うつ、不安、ストレス尺度(DASS)などの広く流布している評価ツールを用いて被験者の身体の健康や心の健康の状態を追跡した。
研究に参加した日本人留学生は強いストレスを受けており、ほぼ八〇パーセントがDASSの一つ以上の診断項目で病態識別値を超えていた。両グループに属する被験者とも、スティーヴの著書を読んでその内容を実践したあとでは、ストレスの程度が平均して低下した。
身体やミツバチの巣が見えざる 手の格好の例になるのは、低次の組織が全体の利害を考慮していないにもかかわらず、うまく機能しているからである。そう言い切れるのは、遺伝子、細胞、ミツバチが通常の意味での心を持っていないからだ。人間のグループを遺伝的進化における選択の単位として考えることで、次の組織(個体)が心を持ち、高次の組織(グループ)の安寧に資するべく意識できるようになる可能性が導入される。もちろんそれは可能性であって必然性ではない。その意味では、人間は遺伝子、細胞、ミツバチと同じであったとしてもおかしくはない。しかしその実践が禁止されているわけでもないのである。名声とともに得られる個人の利益ばかりに関心を持ち、グループ全体をまったく気にかけないメンバーで構成されるグループを思い浮かべてみることは簡単だ。そのようなグループでも評判を獲得するには堅実な市民として振る舞うことが求められるのなら、うまく機能することだろう。また、自分の評判だけでなく全員の幸福にも関心を持つメンバーで構成されるグループも、いとも簡単に想像することができる。そのようなグループも、万全に機能することだろう。ではどちらのタイプのグループが、グループ間選択によって生まれやすいのだろうか? これは、グループレベルの機能の基盤をなすメカニズムをめぐる問いである(『メカニズム』)。
自分を神と宣言する専制君主のいばり屋戦術は、社会が一定の規模を超えるとうまくいかなくなる。王にも説明責任を求める比較的公平な社会を築くためには、次のレベルの社会組織、すなわち数百万平方キロメートルの広さと数千万の人口を擁する帝国が必要とされる。いわゆる枢軸時代(おおよそ紀元前八世紀から紀元前三世紀にかけての時代)に進化した宗教、哲学、制度は、そのような大規模社会の維持を可能にする「社会生理」を提供した。それには、インドにおける仏教の、中国における道教と儒教の、そしてローマ帝国におけるキリスト教の拡大が含まれる。これらはすべて、大規模なグループ間競争に勝つために必要とされるグループ内の協調を促進するための、独自の解決手段として誕生したのである。
グループ間選択は、つねにグループ内選択を凌駕するというわけではない。人類史を詳細に分析すると、両プロセスとも作用していることがわかる。帝国は、恒常的にグループ間戦争が生じている地域で成立しているが、グループ間戦争は、協調的な社会の文化的進化のるつぼとして作用する。ひとたび他のグループより大きな規模で協調し合うことが可能な社会が出現すれば、その社会は拡大して帝国になる。すると帝国内で文化的進化が生じ、利己的な行動やさまざまな形態の派閥主義が選好される。やがて帝国は、がんが全身に広がった生物のように崩壊する。ターチンによれば、旧帝国の中心は、協調を欠く不毛な文化的荒野に成り下がる。新帝国はたいてい旧帝国の辺縁地域で誕生し、中心ではめったに生まれない。社会は過去一万年を通して徐々に拡大してきたが、その軌跡は滑らかで連続的な曲線を描いている。
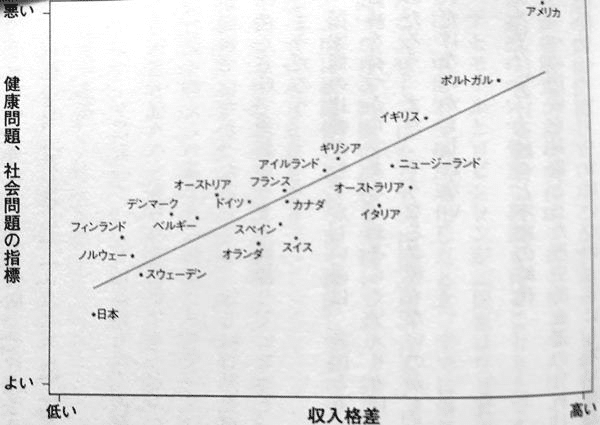

何が機能しないのか
機能しない方法の一つは、自由放任主義である。自由放任とは、社会は放っておいたほうがうまく機能するという考えである。進化が私たちに教えてくれることを一つあげるとすれば、それは「低次における自己利益の追求が、無条件に公共善に資することはない」というものになる。ここまでの各章で見てきたように、進化は、私や私たち、あるいは現世代の人々にとっては善き行動でも、あなたや彼ら、あるいは未来世代の人々にとっては悪しき行動を頻繁に生んできた。最終的には地球全体のレベルで共通善を実現するために社会を管理しようとするなら、その目標に向けて舵取りをしなければならないのは私たち自身である。私たちのためにその仕事を肩代わりしてくれる自然の秩序などありはしない。
もう一つ機能しない方法としてあげられるのは、専門家グループが何をすべきかを決め、かくして立てた一大計画を実施する中央計画である。中央計画がめったに機能しない理由は、誰にとっても理解しがたいほど世界が複雑だからだ。意思決定する人々がいくら賢くても、あるいはいかにすぐれた理論に依拠していたとしても、予期せざる結果を招く可能性はつねにある。このことは、これまでさんざん中央計画が失敗してきた国家のレベルのみならず、変化に対応する指揮統制の試みがうまくいっているとはとても言えない企業レベルにも当てはまる。
何が機能するのか
中央計画と自由放任の中間にはうまく機能し得る方法、すなわち変異と選択の管理プロセスがある。第一に、達成すべき目標がなければならない。ビジネスにおいては、目標は利益の獲得、社会的責任の全う、新製品の開発などになるだろう。地球規模で言えば、それは、堅実な世界経済、大気中の二酸化炭素の削減などといったところになろう。
価値あるグループのメンバーになるべし。 私たちは、自分の行動に対して承認や尊敬が得られることが期待できる協調的な小グループのメンバーになるべく進化によって設計されている。また、活動方針の異なるいくつかのグループに同時に参加できるよう設計されている。人類の狩猟採集民の祖先が行なっていた社会活動は、現代に生きる私たちがさまざまなグループ活動に時間を割くのとそれほど変わらないやり方をとっていた。だから可能な限り多くの時間を、自分の価値観や目標を反映するグループに参加し活動することに費やそう。
CDPやADPを実施することで自分のグループを強くしよう。人類は、小グループを形成して暮らすよう進化によって設計されているのだとしても、そのことは私たちが本能的に正しい設計原理を実施できることを意味するのではない。設計原理の実施の様態は、グループごとに異なり得る。しかもうまく実施できていたとしても、そのグループのメンバーは、正しい設計原理を実施していることに、必ずしも意識的に気づいているわけではない。したがってそこに、いかなるグループであっても、メンバーがグループの進化により大きな注意を払うことで改善を試みる余地が残されている。これは、個人が自己の進化により大きな注意を払う必要があるのと同じである。
訳者あとがきからの引用
なぜ天皇制は、かくも長く続いているのか? のみならず、イギリスやスペインはおろか、カトリックとは異なり共同体より個人の信仰を重視するプロテスタントの影響を強く受け、これまでもっともリベラル的、進歩的な国と見なされてきた北欧三国(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク)、ならびにベネルクス三国(オランダ、ベルギー、ルクセンブルク)で、現在でも君主制が存続している。なぜか? 単にフランスのように打倒する機会がこれまで一度もなかったからなのか? 個人的な考えを言えば、そうではなく、日本にせよ、北欧ならびにベネルクス諸国にせよ、人間の本性や社会のあり方の根源に通ずる何かが、君主制にはあるからなのではないだろうか。ポピュラーサイエンス書の訳者あとがきで、天皇制の是非やあり方について議論するつもりは毛頭ないが、次の点だけは指摘しておきたい。天皇制の議論になると、いかなる立場をとろうがとかく感情的になりがちだが、社会を維持する装置として君主制というシステムがいかに機能しているのか、あるいはしていないのかを生物学、とりわけ進化の科学に基づいてもっと客観的に明確化してから、本書に即してさらに言えばティンバーゲンの四つの問いに答えてから論ずるべきであろう。余談になるが、現代における君主制の様態をわかりやすく解説した本として(ただし進化論的観点はとられていない)、国際政治学者、君塚直隆氏の著書『立憲君主制の現在日本人は「象徴天皇」を維持できるか』(新潮選書、二〇一八年)をあげておきたい。
もう一つトピックをあげよう。昨今世界の至るところで、人権や表現の自由などといった、啓蒙の時代を経て人類が苦労して、 そして血を流しながら手にしてきた気高い理念をいざ実践に適用しようとした途端に、さまざまな問題が噴出し、あつれきを生んでいる状況にある。人権に関して言えば、 たとえばアファーマティブアクションをめぐる問題や移民の問題をあげられよう。表現の自由に関して言えば、最近の日本でもそれに関するいくつかの案件をめぐって、左右両陣営が論争を展開しているのは誰もが承知のはずだ。なぜそのような状況に陥っているのか? 思うに、人権や表現の自由などの普遍的な権利に関する概念であっても、それが実践に適用される際には、つねに特定のグループ(または個人)がその対象になり、それゆえ皮肉にもグループの境界を際立たせるというパラドックス に陥ってしまうからではないか。たとえば、あるグループを人権の適用の対象とすれば、別のグルー プがその範囲から逸脱せざるを得ず、その時点で普遍性を失ってしまうのである。
ここでそれに関して、昨今改正をめぐる議論がかまびすしい日本国憲法に即して考えてみよう。日本国憲法において、基本的人権は第一一条で、 そして表現の自由は第二一条で保障されている。しかしながら第一二条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、こ れを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉 のためにこれを利用する責任を負ふ」とある。端的に言えば、第一一条と第二一条は個人の普遍的な 権利の保障に関する規定であるのに対し、第一二条はそれを実践面に適用する際の条件を規定し、その後半では公共(共同体=グループ)の福祉に対する配慮に明確に言及されている。個人にはグループ の維持や安寧に資する社会的責任があるとするその見方は、とりわけ協調の進化に関する進化論の世界観とも符合する(本書ではとりわけ第6章を参照されたい)。したがって第一二条の後半の記述を無視して、言い換えると進化論の知恵を等閑に付して無条件に人権や表現の自由をふりかざせば、人間の本性が発露せざるを得ない実践面で、さまざまな問題が噴出してしまうのである(そもそも人権と表現の自由でさえ、実践面では相互に対立し得る)。その意味で、そのような態度は非科学的だとさえ言えよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
