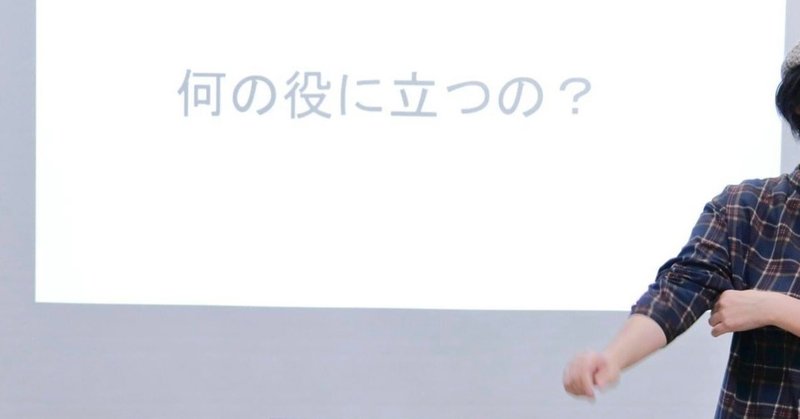
役に立たないもの
カコタイム!
カコタイムをしました。
<カコタイムとは>
ボランティアメンバーや外部講師がそれぞれの特技や関心を活かした発表を行い、子どもたちが新しい考えや見方を身につけるきっかけをつくろうという企画です。
スタサポ(エルプラザ拠点)の活動時間の一部(15分~20分)を使って、不定期に行っています。
マンガ、特に少女マンガについてお話ししました。
大学で少女マンガの研究をしていたのですが、よく言われたのがこれ!
「それって何の役に立つの?」
この問いには最後に答えるよ、ということで二点、絵画の影響とモノローグについてお話しました。
最初にいわゆる少女マンガと少年マンガを比べると、少女マンガには「後ろに花がある」「心の声ともちょっと違うモノローグが多い」という特徴があることを説明。
少女マンガの後ろに花があるのは戦後、華やかなものを人々が求めたのもあるけど、ミュシャの影響が大きいとか。
最近、大流行の鬼が出てくるあの漫画はたぶん葛飾北斎を意識している気がするいうお話しました。
モノローグは少女マンガの発明とも言えて、単なる心の声でなく読者に向けての独白のこと。
例えば『タッチ』はモノローグがないと言っていい!(表情や間のみで心情を表している!)
『三月のライオン』など羽海野チカさんのマンガは縦書きと横書きや色も使い分けてモノローグ盛り盛り!
『鬼滅の刃』は少年マンガにしてはモノローグも日記形式や手紙形式で多い、など。
(余談ですが、少女マンガを中心にお話ししたのにカコタムのメンバーたちには「逆に『タッチ』読みたくなった」「『タッチ』読み返しちゃいました」と言われて嬉しいもののちょっと誤算でした(笑))
モノローグを効果的に使うけれど公開媒体は少年マンガというものもあるし、少年マンガや少女マンガというくくりではもうなくなってきているのかもね、なんてことを話しつつ。
さて、最後には冒頭の「何の役に立つの?」の問いの答え。
戦争後には貧しさゆえにシンデレラストーリーに憧れ、女性の社会進出が進むとスポ根ものが流行り、現代では少年や少女でジャンルをくくれなくなってきている、など。今の世相や影響がわかるよ、ということ。
でもそれってお金にも何にもならないじゃん、っていう人もいるかもしれない。正直その通り。
けど、私の大学の先生が言ってました。
「確かにお金にはならないかもしれない。空気や水のように絶対必要なものじゃないかもしれない。でもね、人生には役に立たないものが必要なんだよ」
勉強でもイヤになってくると「これ何の役に立つの?」とよく言ってしまいがち。
(ここで子どもたち、うんうんと頷いていたり、頭を抱えて「わかっては……いるんだよ……!」という子も(笑))
でも、葛飾北斎とか、学校の勉強でやったものがマンガという自分の好きなものにつながったときに私はすっごく楽しい!
だから、「役に立つ」ことを判断基準にしないで、いろんなことに目を向けてみてね。
そんな話をしました。
やはりマンガというジャンルの性質上、子どもたちの食いつきがよくて嬉しかったです。
私を構成する5つのマンガ
というわけで、このカコタイムで紹介したマンガたちが「私を構成する5つのマンガ」だなあと思うわけなのです。
①『はいからさんが通る』大和和紀
そもそも少女マンガに興味を持ったきっかけは、母が持っていたこのマンガです。
いろいろなタイプの男性が出てくるけれど、主人公・紅緒が無個性ではなくて、とてもはちゃめちゃでみんなが惹かれてしまうのがわかる……!
シリアスとギャグの高低差もこの作品のらしさかなあと思います。
鬼島軍曹の番外編、幼少期の話が大好きで何度も読みました……。
大和和紀さんのマンガはラストがモノローグで締められていることが多いので紹介しました。
②『11人いる!』萩尾望都
宇宙船の中に、本来10人のはずが11人いる。ミステリー仕立てのところも大好きなのですが、登場人物のひとり、両性具有のフロルというキャラクターが大好きです。
自分の望みは自分で決める、その姿勢に惹かれます。
少女マンガの全盛期にはバックに花が描かれていることが多い、ということで、花の24年組の作品を紹介しました。中でも萩尾望都さんの作品が大好きです。
『私の少女マンガ講義』の中で、萩尾望都さんは「子供の育つ力とか、子供がこれから作る未来をもっ と信じたほうがいいんじゃないか」とおっしゃっていたのですが、彼女が本当にそれを信じていることが作品を通してわかるところがいいです。
③『青のフラッグ』KAITO
大学の勉強で三角関係の作品についての授業をとっていたことがあります。
男2女1の三角関係は「ひとりの女を巡って争った結果、男ふたりの友情が深まるというパターンが多くみられる」のに対し、女2男1だとそれはあまり見られない……のようにやったことを覚えているのですが。
この作品はその固定パターンをガンガン崩していてものすごく面白いんです!
少年マンガ媒体の連載だけど、たくさんのモノローグや大胆なコマ割りなど、少女マンガ的な手法もたくさんあって、もちろんストーリー的にも新しい今の時代のマンガだ、と思います。
先日最終話の更新がされたのですが、終わりまで本当によかった……!
最近は少年マンガでも、モノローグは出てくるよ、という説明で紹介しました。
発表の際に「これは三角関係の話で……」と紹介したら、終わったあとに『青のフラッグ』を読んでいる子どもから「三角関係の話ってだけじゃ不十分じゃない?」と指摘を受け、人間関係の相関図を書いて「これは……何角形だ!?」という話になりました(笑)。
④『スピカ』羽海野チカ
短編集ですが、表題作の「スピカ」が大好きです。
好きなことを好きでいることの難しさとまっすぐさが描かれていて……。
最初に「夏になると見かける花」についてのモノローグが出てくるんですが、後からヒロインが泣いているときにこの花が描かれたコマがあるんです。
どうしてここでこの花が出てくるのか?を考えたり、後から出てくるヒロインが渡される「花束」と比べるとエモくて、しかもラストには主人公とふたりで「花火」を観に行くんです。
この三種類の「花」が出てくるのが映画や文学のようで、たまらなくて大好きな作品です。
横書き縦書き、黒く塗りつぶして白い字など、モノローグの演出の仕方もいろいろある、という話でこの作品を紹介しました。
⑤『四月は君の嘘』新川直司
『いちご同盟』が大好きなので(上記の三角関係を取り扱う授業で、私は『いちご同盟』で発表したくらい)まさかまさかと思いながら読んでいたら、とてつもなくテンションが上がった作品。
そういえばこれも三角(四角?)関係の話ですね。
モノローグの割合と、出てくるタイミングがとても好きです。
この作品も好き、と最後に紹介したときに子どもから「あ〜!」と声が上がって嬉しかったです。
こうしてみるとモノローグが本当に好きなんだなあ、自分……と思います(笑)。
そして、今
カコタムでは現在、拠点での活動を休止中のため、月に一度くらいの頻度で行っていたカコタイムもできておりません。
そこで、オンライン・カコタイムという取り組みを始めます!
カコタムのメンバーが、自宅からカコタイムをお届け、ということで、それぞれのメンバーが独自のテイストで動画を撮影し、カコタムの子どもたちに向けて提供します。
(URLを知っている人だけの期間限定の限定公開です)
「こんなときだからこそ!」と気負ってしまいがちだけれど、何か「役に立たない」かもしれない(でも場合によっては「役に立つ」かもしれない)ことに時間を使ってもらうのもいいんじゃないかな……と思いつつ。また、今は会えない子どもたちに向けて、会えないけれどここにいるよ、と伝わるものになったらなあと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
