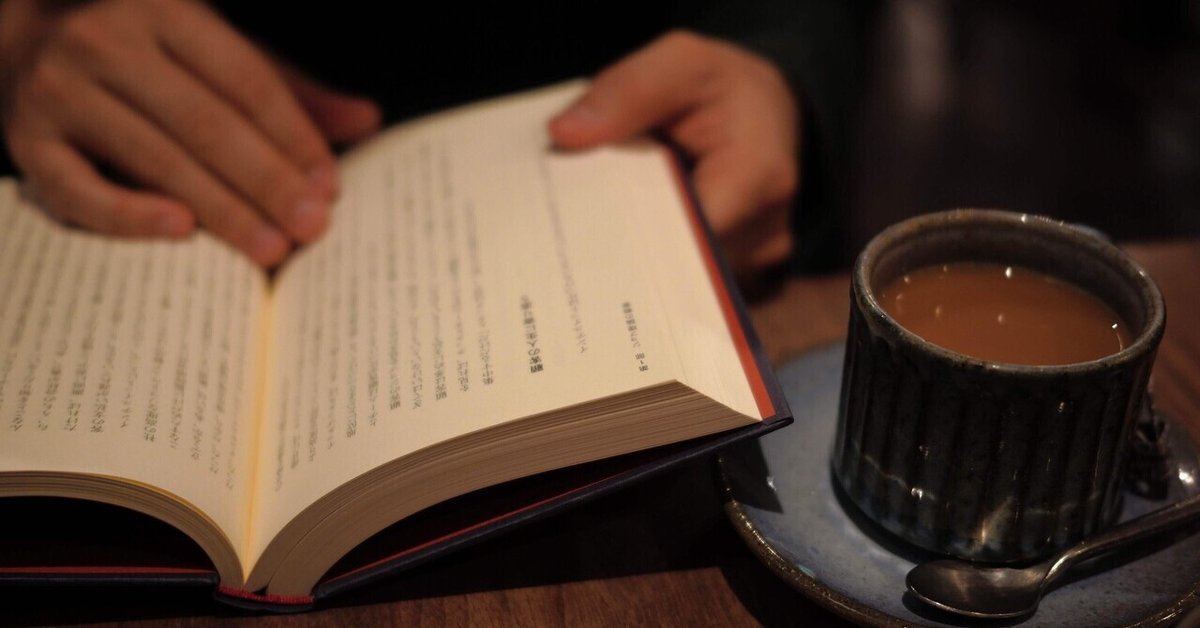
#vol.5 会社はこれからどうなるのか。
サラリーマンになり、会社に勤めてはや三年。ずっと気になっていた岩井克人さんの著書「会社はこれからどうなるのか」を読んだ。
学者の方から、改めて構造を整理した上で会社という仕組みを鳥の眼で俯瞰して捉えてくれているおかげで、会社内にいる人間としての実感と仕組みをなんとなく理解することができた。
新型コロナウイルスにより、良くも悪くも会社という形態が変わろうとしているいま、今後の会社のあり方も含めて考える良いきっかけになった。
株式会社とは、株主が会社をモノとして所有し、その会社がヒトとして会社資産を所有しているという二重の所有関係を基本構造としています。(p.101)
本書の本題は第3章、会社の仕組みを概観するところからはじまる。
ただ、建前上存在する上記制度は、こと日本社会においては日本の会社の在り方の特質が浮かび上がってくるのであることを鋭く指摘している。
会社法の上では、従業員とは会社の「外部」の人間です。かれらは、法人としての会社と雇用契約という契約を結んでいる存在にすぎません。(中略)「社員」という言葉は、会社法を読むと、ほんとうは会社の所有者である株主のことを指す言葉なのだが、日本では本来は会社の外部であるべき従業員にたいして使われているという、不思議なことが起こっているのです。(p.141)
日本社会の二重性がここにも見られる。本来は契約関係でしかないもの(外部の人間)であるが、僕らの実感値としても会社の内部の存在として会社に受け入れられていると考える方が肌感覚に近いのではないかと思う。
筆者もp.179でより詳しく言及しているが、日本のサラリーマンは「会社人間」と揶揄されるように、会社に自分自身を同一化している存在であり、社会一般からも会社の内部の人間としてみなされているという実情があるのだ。
なぜ日本社会はこのような仕組みがうまれていくのか。筆者は「家」制度と法人の関係の中で次のように述べている。
人間がなにか組織を作り上げようとするとき、人間はまったくの白紙の状態からデザインをするのではなく、意識するにせよしないにせよ、それぞれの文化に固有の「文法」というべきものにしたがうことになるのです。(中略)文法とは、家族の構造であり、家族に関する概念は人間の基本的な言語構造のなかに深く深く入り込んでいるのです。(p.211)
いうまでもなく、戦後日本社会の雇用システムを特徴づけてきた終身雇用制・年功賃金制・会社別組合は、このような組織特殊的な人的資産の蓄積をうながすための制度的な仕組みにほかならないということなのだ。
そして右肩上がりの工業化社会を会社が生き延びていくには、この構造が時代にあっていたとも言える。「家」という概念を会社に持ち込むことで、社員は会社に守られた中で幸せに働き、一方で会社は社員が離職しないという前提の元でその人的資産を活かしながら会社を発展させていくことができたからである。
ここから先は、上記を前提とした中で成り立ってきた構造が、ポスト産業資本主義社会の中で、前提が変わっていく上での構造変化を推察していくことになる。まず第一にポスト産業資本主義の3つの側面は”グローバル化””金融革命””IT革命”であり、消費者にとっては所得さえあれば、世界のどこで生産されたモノでも買うことができ、世界中の消費者が、同じ消費のメニューを手にするようになった。
産業資本主義の時代においては、おカネはモノを支配することによって、ヒトをも支配していました。だが、ポスト産業資本主義の時代が幕開けしたいま、おカネとヒトとの力関係が、大きく変わり始めているのです。(p.311)
産業資本主義時代においては、企業組織のデザインは比較的簡単でした。機械制工場が利潤の源泉であり、その潜在的な規模の経済や範囲の経済をいかに現実かしていくかが、至上命令であったからです。(中略)産業資本主義的な企業の多くは、上から下へと命令が通達されていく大掛かりな階層組織を築き上げることになりました。これに対し、ポスト産業資本主義的な企業においては、機械設備はその中心性を失い、経営者の企画力や技術者の開発力や従業員のノウハウこそ企業の中核を占めるようになっています。(p.334)
企画力や開発力やノウハウなどは、経営者や技術者や労働者の頭脳や肉体のなかにあり、おカネで買うことも、外部から直接コントロールすることもできません。おカネが唯一できることは、優秀な経営者や技術者や労働者が企業を魅力的に感じ、企業のなかでノウハウを蓄積していき、それらを企業の利益に貢献するような形で発揮してくれるような環境を作り上げていくことしかありません(p.335)
上記で言っている内容が本書の中でも中核を占めることとなる。
特にIT企業やデジタルといった領域では、人材の流動性がはやく、特定の企業に居続けることが必須ではなくなっているからこそ、企業は従来の方法では人材やノウハウを自社に貯め続けることができなくなっているのだ。
筆者は最後に次のように本書を締めている。
すなわち、ポスト産業資本主義時代における会社とは、まさに専門経営者や科学技術者や熟練労働者といった知識志向的な従業員が自由に創意工夫をおこなえる仕事の場の提供者としての役割をはたすようになるはずなのです。(p.358)
場の提供者として、と言葉をひねりだしているが、まさにそうで、どのような案件や企画を担当できるのかがひとつの会社を選ぶ基準であったりするだろう。人によって裁量権がもっと欲しいと思う人もいるだろうし、一方で業務量は抑えて良いので自分の時間が欲しいという人もいるはずだ。
企業として人材の流動性がより高まっていく時代の中で、時代に即した経営が必要になっていることは火を見るよりも明らかなのだ。
それでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
