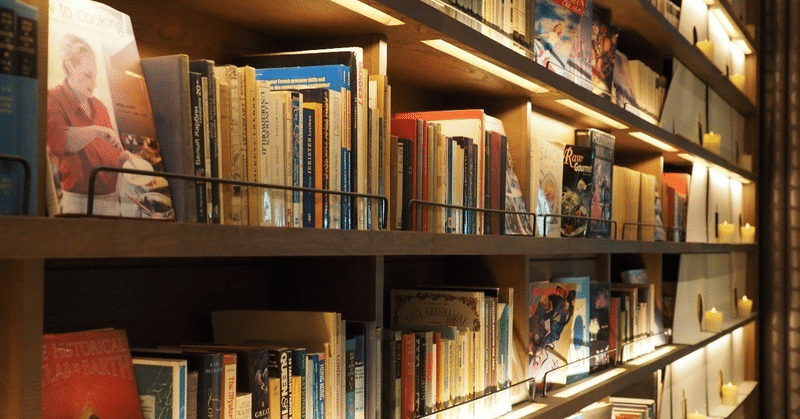
【読書日記001】美術に浸った1月。小説から美術史まで。
こんにちは。
読んだ本をまとめておくことはきっと未来の自分の役に立つと思う。
だから、ぽすたが読んでいる本の記録。
#001.【文藝春秋】2022年の論点100
毎年年末に購入するのが恒例行事になっているが
これを読むことで世の中の論点を概観することが目的。
自動車メーカーの半導体不足から「心」のデータ化、ウェアラブルデバイスを用いた新しい健康管理社会の提案まで様々な視点を取り込めた。
#002. サロメ-原田マハ著
とんでもない小説にまた出会ってしまったという感想だ。
芸術と犯罪の紙一重の領域を人間模様とともに美しい日本語で書き上げる。この原田マハという小説家の凄みを強烈に感じた一作。
ちなみに、距離を表現するときに「スープが冷めない距離」と表現しているのが素敵すぎてマハさんの世界観に惹き込まれそう。
「君がやるべきことは、たったひとつ。地獄に落ちることだ。ーこの私と一緒に。」
#003. 群集心理-ギュスターヴ・ル・ボン☆
大衆の反逆(オルテガ)に近い気がするが、
現代人が読むべき一冊だろう。
Twitterのタイムラインがなぜ炎上するのか、
立場の高い人がなぜ袋叩きに合うのか
ゾッとしながらページをめくり続けた。
群衆の一般的特徴は、
暗示を受けやすく
物事を軽々しく信じ、動揺しやすく、
善悪の感情が誇張されること。だ。
また群衆は本能的に向かうため、
そこに個人の意思が介在することは極めて困難。
久しいあいだ威厳を保つことのできた人々は、決して論議をゆるさなかった。群衆から賞賛されるには、常に群衆をそばに近づけてはならない。
#004. 〈日本美術〉誕生-佐藤道信
日本画を理解するために、ことばに着目し
改めて整理しなおした一冊。
前提知識がない僕には理解できた部分とちんぷんかんぷんな部分と。
それにしても、「日本画」を語る時に岡倉天心はとても出会う機会が多い。五浦に拠点を移した理由なども記載されており、発見があった。
福沢諭吉の「脱亜論」とか、
岡倉天心の「東洋の理想」とか
この辺は読んでおかなくちゃいけないのだろう。
日本という国は難解だし紐解けば紐解くほど
奥が深くて沼る。
※沼る=のめりこむ
読書欲が再燃してます。
読むぞー2月も。
それでは!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
