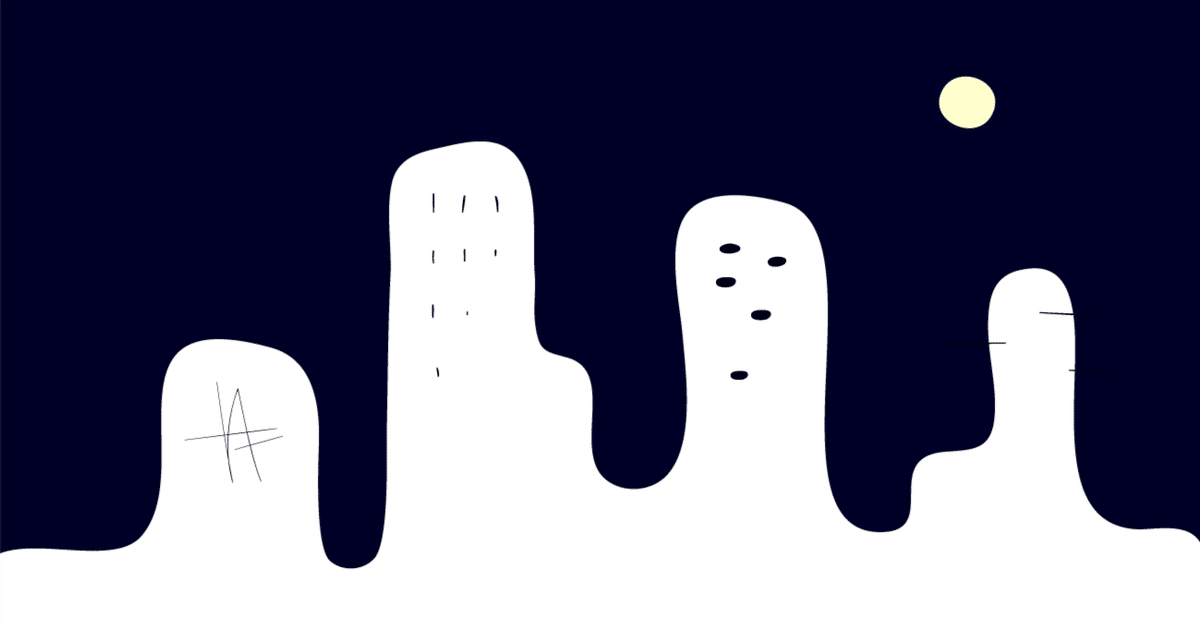
鷲田清一「社会の壊れる時ーー知性的であるとはどういうことか」 解説
高校3年生向け
現代文B
論点「社会」
1. どんな話なのか
社会の崩壊を防ぐためには、「煩雑さ(摩擦)に耐える耐性」が必要であり、この耐性をもつことが知性的な状態である。
社会は、
1. 特定の理念の共有を強いられること。
2. 相互理解を拒否され、分裂すること。
によって崩壊するため、異なる文化同士が共存しなければならない。
共存に伴い摩擦が発生するが、これは社会への刺激として必要なものである。現代人は摩擦に耐える力を身につけよう。
2. 本文の「核」

3. 各段落の解説
① A段落
相互理解の重要さ。人同士が対立することは問題ではない。問題なのは、相互理解を拒む状態となってしまっていることだ。
② B段落
「話しても分かり合えない」ことはある。が、相互理解を拒むことが社会の崩壊へつながる。
崩壊には2つのかたちがある。
1. 他からの力によって、社会に生きる人がバラバラになるかたち。
2. 社会の中で分裂が起きるかたち。
社会が崩壊する可能性は常に潜んでいる。なぜなら、社会は異なる者同士が寄り集まってできたものだからだ。
それでも、社会の決定的な崩壊が起こらないのは、人々が「共通の理念」をもっているからである。
この「共通の理念」は勢力をもつものが他集団へ強制してはならないものである。しかし、西欧化にともなう「近代性」はまさにそれで、さまざまな軋轢(あつれき・仲が悪くなること)を産んだ。
③ C段落
「近代性」にともない、西欧以外の文化が排除されてきた(「多様性の喪失」)。それゆえに、社会を構成するうえでは、「複数文化の共存」が重要となる。
「共存」には「摩擦」が関係する。「摩擦」ときくとネガティブイメージをもつかもしれないが、これが消去された社会は緊張感をなくし、崩壊へ向かう。「摩擦」は社会に対する刺激となり、「共存」に有利に働くのだ。
④ D段落
このことから、社会に生きる現代人は「摩擦」への耐性が必要となる。知性を身につけると、物事を考える際の基準が増え、かえって社会の煩雑さ(「摩擦」)が増すだろう。その煩雑さに堪える耐性を身につけていることこそが、「知性的」なのだ。
4. テストに出そうな重要箇所
① 「『私』が『私たち』を僭称する」とはどういうことか。
「僭称」は「自分を超えた称号を名乗ること」という意味。よって、ここでは「『私』が勝手『私たち』を代表して意見すること」をいう。
② 「社会に常に伏在して」いるのはなぜか。
直前の文がそのまま答えになる。「そもそも社会が……統合されたもの」だから。
③ いくつかの重要語句
・逡巡(しゅんじゅん) 決断を迷うこと。
・僭称(せんしょう) 自分を超えた称号を名乗ること。
・乖離(かいり) 離れ離れになること。
・軋轢(あつれき) 仲が悪くなること。
・イデオロギー 社会的に定められた根本的なものの考え方。
・恒常(こうじょう) 変化がなく一定の状態が続くこと。
④ 「崩れには二つのかたちがあります」とあるが、二つのかたちとは何か。
直後の文章に注目し、「かたち」を手掛かりに探せばよい。正答は「一つは……かたち」、「今一つは……かたち」となる。
⑤ 「野蛮と頽廃」とは何を指すか。
少し前にある「過度の統一は野蛮に……過度の分割は頽廃に起因する場合が多く」という箇所を手がかりにする。この部分は、B段落の「崩れ」の二つの形に対応している。「近代性」がそうだったように、「野蛮」とは「外部から思想の共有を強いること」を指す。五・一五事件がそうだったように、「頽廃」とは「相互理解することを拒むこと」を指す。
⑥ 「知性的」とはどういうことか。
最終段落に「この世界が壊れないためには、煩雑さに耐えることが何より重要です」「そのことが……耐性を身につけていることが、知性的ということなのです」とあるので、まとめる。
よって、正答は「社会の煩雑さに耐える必要性を理解し、煩雑さへの耐性を身につけていること。」となる。
5. おわりに
この単元は、難しい。内容もそうだが、筆者の難解な言い回しで混乱する学生も多いだろう(ちなみに、鷲田清一氏は大学入試における問題文採用率がダントツでナンバーワンだ)。
とはいえ、「社会」という論点と、評論語を理解していれば対応できる。B段落で「西欧」「近代性」「共同体」「軋轢」などの言葉から、「西欧化を強いたことで、多様性が排除され、軋轢を産んだ」ことを読みとれれば、難解に思えた文章も一気にクリアになる。この部分が「社会が壊れる一つのかたち」であるなら、五・一五事件の「問答無用」が「相互理解を拒否すること」であり、「社会が壊れる今一つのかたち」であるとわかる。
語句や言い回しに悩む場合は、知っている語や身近なものに置き換えればよい。例えば、学校行事の際、教員の圧力によってクラスのムードが悪くなったり、男女間でクラスが空中分解したりした経験は誰しもあるだろう。これは本文でいう「社会の崩壊」が「クラス」で起こっているということだ。この例えでいうなら、「異なる共同体の共存」は「違う中学校出身者同士がクラス内で仲良くする」ことだし、「摩擦」が「有利に働く」とは、「異なる性質のクラスメイト同士の化学反応によりクラスが活性化」することである。
このように置き換えれば、腑に落ちる部分も多いだろう。自分の身近なものでイメージしながら再読してみてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
