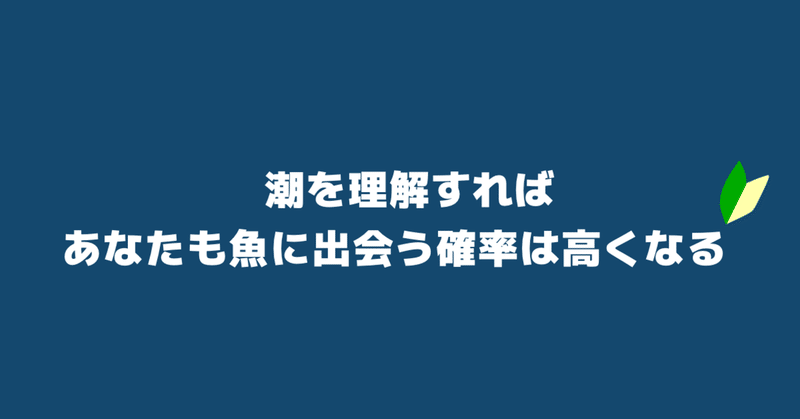
潮の基礎知識と応用。
こんにちは、こんばんは、カツオです。
今回は潮の基礎知識と応用についてご紹介いたします。
潮の動きは、魚の活性や回遊に大きな影響を与えるため
釣りにおいて非常に重要な要素です。
この記事を読んでいただければ潮や潮の流れを理解することができ
魚が釣れるようになると思いますので
最後まで読んでいってください。
🌕 潮汐について
潮汐は、太陽や月の引力が地球の海水を引っ張ることで起こる
海の満ち引きのことです。
約6時間ごとに満潮と干潮を繰り返し、1日2回
未来永劫、潮汐が起こります。
基本的に魚は、潮が動かなければ釣れません。
その潮が動くかどうかは、月で決まり
覚えておくべき、前提知識があります。
------------------------------------------------------------------------
大潮(おおしお):潮が最も動く 魚の活性が高い
中潮(なかしお):潮がやや動く 魚の活性もやや高い
小潮(こしお):潮があまり動かない 魚の活性が低い
長潮(ながしお):潮が動かない 魚の活性が低い
若潮(わかしお):潮がやや動く 魚の活性がやや高い
上げ潮:干潮から満潮までの間の海面が上昇すること。
下げ潮:満潮から干潮までの間の海面が下降すること。
------------------------------------------------------------------------
この前提知識を知った上で
さらに覚えていただきたいことが3つあります。
------------------------------------------------------------------------
海が荒れているときは上げ潮で行く
晴れた日は下げ潮、雨の日は上げ潮の時間帯に行く
満潮・干潮時刻の2時間前後を狙う
------------------------------------------------------------------------
海が荒れているときは上げ潮で行く

海が荒れると、波が海水を押し上げますので
下げ潮の力が弱くなります。
実際下げ潮のタイミングで、荒れているとき釣りをすると
ルアーが全然流れないんですね。
一番顕著に出るのが川釣りです。
河川(川)と海は繋がっています。
下げ潮は、川の水が海に流れて出ていくので
波が高いと、その波の威力で川の水が流れ出にくくなります。

なので海が荒れているときは、上げ潮で行くと
釣果に繋げやすいですね。
晴れた日は下げ潮、雨の日は上げ潮の時間帯に行く

晴れた日は、高気圧に覆われており
雨の日は、低気圧が近くにあります。
すると潮はどうなるのかというと
高気圧の場合は、下げ潮がよく動き、上げ潮はあまり動かない
低気圧の場合は、上げ潮がよく動き、下げ潮があまり動かなくなります。
どういうことかというと
高気圧の場合、海水に圧力をかけ、海面を押し下げるので
下げ潮がよく動きます。
想像してみてください、水いっぱい溜めたバケツの上から
蓋のようなもので押さえつけたらどうなると思いますか?
水がバケツの中から出て行くと思います。
一方低気圧の場合は、気圧が低いので
海水から圧力を奪い、海面を押し上げるため
上げ潮の方がよく動くのです。

なので晴れた日(高気圧)は、下げ潮の時間帯
曇っている日や雨の日(低気圧)は、上げ潮の時間帯の方が
釣果に繋げやすいと言えます。
満潮・干潮時刻の2時間後を狙う
上げ潮(干潮から満潮になる潮)と下げ潮(満潮から干潮になる潮)の
始めが魚の活性が高くなるとされています。
これは、「上げ3分下げ7分」といい
------------------------------------
上げ3分:干潮から約2時間後
下げ7分:満潮から約2時間後
-----------------------------------------------
なので、狙い目です。
この上げ3分下げ7分を知っておくことで
釣れる時間、釣れない時間の見切りをつけることができます。
特に夜の釣りは時合(釣れる時間帯)がわかりませんので
上げ3分下げ7分を知っておくと
「あ、もう下げ7分の時間通りすぎて
そろそろ釣れなくなってしまうから、休憩にしよう」とか
「お、上げ3分の時間通りすぎていて
釣れなくなりそうだから、今日は帰ろう」などと判断でき
無駄な体力を使わずに済みます。
なかなか上記に挙げた3つを狙って行くことは難しいと思いますが
休日などの時間があるときに、意識して狙いに行ってみてください。
🌕 タイドグラフは当てにしない
釣り人は、上記の大潮や小潮、上げ潮や下げ潮の知識を知った上で
釣行前にタイドグラフと呼ばれるもので潮の変化を見ます。

しかしこのタイドグラフは、あまり当てにしないようにしましょう。
なぜなら場所によって、タイドグラフの図のように
潮が動くときと動かないときがあるからです。
それは先ほど紹介した、気圧の状態だったり
釣り場の地形だったりが関係してきます。
一般的に大潮は、潮が大きく動きますが
必ず潮が大きく動くわけではなく
水深がある場所や障害物が何もない場所は、動かないときもありますし
逆に水深が浅い場所やテトラポッドの間とかは
潮止まり状態でも動いていることがあります。

筆者自身もタイドグラフはあまり見ておらず、潮の変化は
実際釣り場に行って、確認するようにしています。
見るとすれば、年に5、6回行く沖釣りのときかなくらいです。
なのでタイドグラフで潮の変化を見るよりも
実際に潮が動いている場所を探していく方が重要だったりします。
🌕 満月周期の潮回りと新月周期の潮回り
1ヶ月を通して2週間だけ満月周期の潮と
新月の周期の潮があります。
この満月周期の潮のときと新月周期の潮ときで
釣果に違いが出るということを覚えていただきたいです。
満月周期の潮回りは夜に行く

満月周期の場合
月の明かりで、夜でも少し明るくなります。
明るくなると、プランクトンやベイトフィッシュを見つけやすくなり
捕食魚が晩御飯として食べるため、活性が上がります。
実際よくお世話になっている遊漁船の
夜のタチウオ釣りの釣果を比べてみたところ
2023年の10月14日の新月の日と
2023年の10月29日の満月の日で
10月14日の釣果は、船中39匹〜59匹。
10月29日の釣果は、船中32匹〜72匹で1投目から入れ食いと
明らかに釣果に違いがあります。

逆に満月周期の潮回りは、夜のうちに餌を食べてしまっているため
夜は釣れやすくても、朝は釣れにくくなります。
なので月を意識して釣行予定を立てるといいでしょう。
新月周期の潮回りは朝に行く

満月周期と逆の説明になります。
新月の場合は、夜真っ暗で何も見えませんので
魚もプランクトンやベイトフィッシュが見えづらくなっています。
すると夜のうちはエサを食べず、朝方にエサを食べるので
朝に活性が上がりやすく、釣れやすくなるのです。
🌕 潮を読み解き魚を釣る方法
今までは、魚が釣れる潮回りについてお伝えしてきました。
ここからは実際釣りをするときに役に立つ
潮の流れを知るテクニックをご紹介します。
これから紹介するテクニックを使っていただければ
釣果に大きく繋げることができると思いますので実践してみてください。
1.海面を観察する

まず釣り場についたら海面を観察しましょう。
海面を観察して、潮がどっちに流れているのか把握し
わからない場合は、ルアーや仕掛けを投げてみます。
ルアーフィッシングの場合は
底がよく取れるルアーでないと潮の状況がわからないので
メタルジグやジグミノー、ワーム等を使うといいですね。

まず真正面に投げてみて
表層をただ巻きするかアクションをつけて潮を確認します。
自分の立ち位置より、右に流れていけば右に流れていますし
左に流れていけば、左に流れています。
もし真正面に投げて、だいたい自分の正面に帰ってくるなら
潮があまり動いていない証拠です。
2.ルアーか仕掛けを底まで沈めて流れを見る

次に底潮が通っているのか確認するようにします。
ルアーをキャストして沈め
そのとき、フリーフォールで落とすのではなく
リールのベールを返して落とします。
フリーフォールで落とすと糸が張ってないので
潮の状態が分かりにくいです。
そして沈めたとき、表層の潮と同じ方向に綺麗に流れている場合は
しっかり表層から底まで潮が通っている証拠であり
反対に流れている場合は、底潮が通っていない
あるいは表層と底の潮の向きが違う2枚潮である証拠です。
また2枚潮の場合、底にトンってつくのではなく
ふわっと着くような感じで、着底が分かりずらいときがあります。
3.ルアーか仕掛けで潮の向きを確認し動かす

ルアーや仕掛けを動かす(誘っていく)ときは
------------------------------------
引き抵抗・持ち上がり
どっちに流れていくのか
------------------------------------
を確認します
ミノーやバイブレーション等のルアーの場合、引き抵抗があまりないときは
潮があまり効いていない可能性があり
やたらと引き抵抗がある(巻き感が重い)ときは
潮が効いている可能性があります。
特に巻き感が重たかったのに、いきなりフッと軽くなった場合
何らかの流れの境を通過した可能性があり
その境に魚がいる可能性もあるので、意識的に狙ってみるといいでしょう。
メタルジグやワーム、仕掛けの場合
底からしゃくりあげた後すぐに底につく場合は
底潮が通っていない、あるいは2枚潮である可能性があります。
底潮が通っていないとか、2枚潮とかの場合は
ラインが「つ」の字を描いてしまっているため
大きくしゃくっても、弛んでたラインが張っただけで
ルアー(ジグ)や仕掛けがあまり動きません。

結果、着底が早くなってしまうのです。
4.キャストする場所と方向を決める

今までは表層の潮と底潮の通りを確認し
状況を探している段階でした。
最後は、キャストする場所と方向を決めます。
事細かく説明すると頭がパンクすると思いますので
完結にまとめると
------------------------------------------------------------------------
ルアーや仕掛けが着水してから3秒〜8秒以上かかる場所
ルアーや仕掛けを動かして、すぐ着底しない場所
左に流れているなら左、右に流れているなら右に投げる
------------------------------------------------------------------------
このように
「1」か「2」の場所で、「3」の投げ方を意識すればOKです。
🌕 潮が動いていないときこそ動かしてやる

最後に潮があまり動いていないときにやる行動について
ご紹介いたします。
やはり普通に働いている方は、潮が動いている時間を
ピンポイントで狙いに行くことが難しく
仕事に行く前とか仕事終わりに1時間ほどやって帰るみたいな
そのときに、たまたま潮が動かないときって絶対にあると思います。
まず潮が動いていないと、魚のスイッチが入らず釣れません。
そのためルアーを派手に動かす、エサ釣りの場合は
つけエサを動かしてあげる。などをして
魚にスイッチを入れてあげる必要があります。
具体的にルアーの場合は
------------------------------------
音を出す
でかいルアーを使う
振動が強いルアーを使う
------------------------------------
などをして、魚の側線部に刺激を与えてあげる。
たとえばラトル音入りのルアーを使ったり
バイブレーションを使ったりするのがおすすめ。

エサ釣りの場合は、ただじっと待つのではなく
意識的に誘いをかけたりする。
潮が動いていないときこそ
ルアーや付けエサ(仕掛け)を動かしてあげるのがポイントです。
逆にルアーやエサを小さくしたり
振動が弱いルアー(ワーム等)を使ったりするとよくないです。
なので、とにかく適切にルアーやエサを動かすことを意識することで
潮があまり動いていない状況でも、釣果に繋がる可能性は高くなりますよ。
🌕 まとめ
------------------------------------------------------------------------
1.晴れ予報の日は下げ潮の時に
曇りや雨予報の場合は、上げ潮の時間帯に行く
2.タイドグラフをあまり当てにしない。
3.満月周期なら夜に、新月周期なら朝に行くのがおすすめ。
4.釣り場に通い続けて、潮を読み魚を釣る
5.潮が動かないときこそ、ルアーやつけエサを動かしてあげる
------------------------------------------------------------------------
潮の動きは、釣りにおいて非常に重要な要素です。
潮を理解することで、釣果を大きく左右することができます。
次の釣行の際は、ぜひ潮を意識して
その潮の動きに合わせた釣りをしてみてください。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
