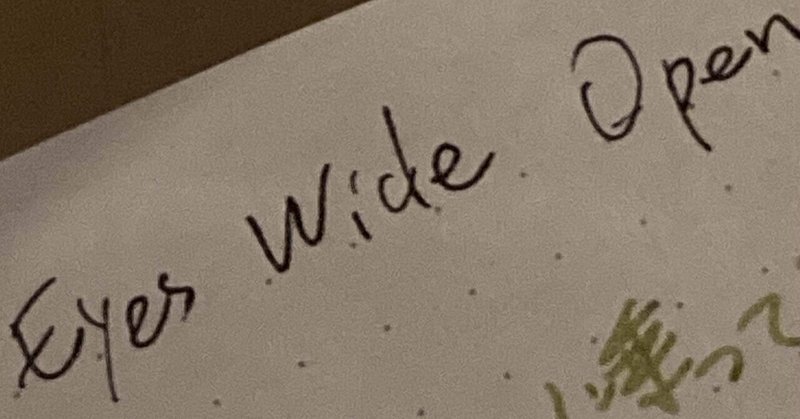
三十歳の日記(1/4-1/21)
一月四日
昨日はタイムスで日記を更新するとそのまま帳面を開いて短歌の続きを書いた。
帰宅して、iMacの前に座り、スクリブナーを起動する。iPhoneのメモ帳をAirDropでiMacに飛ばす。ワードを開いて、そこにとりあえず放り込んで行く。十四万字。膨大すぎて完全に頭が追いついてない。帳面を開いて、プロットの整理。コーマック・マッカーシーのおかげで自由さを取り戻したというか、好きに書いていいんだなというか、自分がおもろいと思う文字をただ書けばいいだけというシンプルな気持ちに戻ってきた。『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』でシガーがガソリンスタンドで店員にコイン投げをやらせるシーンがある。表裏を当てられなかったら殺す、という場面。店員は表裏を当てられなかったら殺されるということを知らずにわけもわからずその変な客の言う通りにコイン投げに付き合う。シガーはモスを探している最中で、つまりこのシーンは物語を前に駆動させながらもシガーがどんな奴かを表している、一場面に二つ以上の役割を持たせている場面だった。これは脚本的なアプローチで、自分はそういうところにおもろさを感じるということは、俺はやっぱり脚本とか映像(目に見えるもの)から来た人間だということをもうちょっとちゃんと意識した方がいい。マッカーシーはこの物語を話す上で麻薬取引とそれにまつわる現金持ち逃げの件から何があろうと軸足を離さない。それがとてつもなく肝心だ。あくつさんから初稿を読んでもらった時に「ゲームのことを軸にすれば?」と言われたのはまさにそこを突いてくれていたアドバイスだった。書いているとなぜか離れてくる。離れているのに書いてしまう。それによる混乱。それを一回元に戻さないと行けない。ということで、帳面を開いて、伝ちゃんがゲーム上でぶつかる困難、具体的に乗り越えないといけないプレイ上の問題、を羅列していく。伝ちゃんが二十歳から八年かけて乗り越えていく課題が数珠繋ぎの蛇になっていき、かなり視界が拓けた。不要なシーンも見えてくるし、逆に不要だと思ってた部分も、伝ちゃんが前に進みながらそれらと付き合うのなら共存可能な場面もある。フレデリック・フォーサイス『ザ・フォックス』も例のごとく途中で読むのをやめた本だったが、あれは半分ぐらいで読むのをやめた。しかしあの本は物語の軸自体は明確で、フォーサイスもずっと軸足を離さずタイヤが真っ直ぐなまま物語が進んでいたが、その速度とかブレーキの踏むタイミングや強さが合わず、車酔いしてしまった。情報機関や国の組織やらの説明が長くて、それは物語を真たらしめる根拠として提示されるので、フォーサイス的には必要な時間だったかもしれないが、読み手としては本当かどうかなんて全然どうでもいいというか、嘘を読みに来てる。マジっぽさを担保する手段として実際にある固有名詞を挙げるのは確かに有効だが、これも塩梅だ。『ザ・フォックス』ぐらい緻密に、ノンフィクションものと同じぐらいの真実さで語られる方が好きな人もいるだろうが、今の俺には合わない運転だった。『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』にも確かに実際にあるショットガンの名前や弾丸の種類が出てくるが、その出てくるタイミングも文量も今の俺にはちょうどよかった。そしてこう思うとあのコーエン兄弟による映画は本当に素晴らしい映像化だった。シガーは本だともうちょっとちゃんと人間というか、あの映画ほど人間から離れていない。本にはシガーの目玉が青いという描写があった。マッカーシーは結構シガーのことを美少年的な雰囲気で捉えていたのかもしれない。映画にする時にその不気味さだけ抽出するのはかなりナイスワークだ。肝はそこにある。理不尽さの不透明な感じ。大好きな佐伯一麦さんの小説ではPCのなんやようわからん専門用語やら、電気技師の配線がどうのこうのなどがよく出てくる。あれらの読んでいてもよくわかんないのに伝わってくる何かというのは、自然に発露されなきゃいけない。物語を駆動させていく上で不要ならいくら言いたくても切るという判断。そのニュートラルさ。『デリケート』では無意識にできていたことを、今『味方の証明』で意図的に操れるようになったら、それが身についたということであり、所持する技術になる。そうしなければならない。
一月五日
またもや朝の七時に眠るような無茶苦茶なリズムになっているので、戻さないといけない。しかし重たい体を引きずって、馬鹿みたいに今日も夕方に起きた。
働き終え、家に帰るとすぐに風呂を溜めて米を炊き、その間にコンビニに行く。テキトーに色々買い、帰宅、風呂。『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』を読みながら浸かる。おもろすぎて長風呂になった。風呂から上がるとすぐに寝た。
一月六日
昼前には起きて、無理矢理リズムを正しく戻す。Apexやったり短歌書いたり。もう二十首ぐらいはできた。五十首連作しか書いたことないから三十首連作のテンポ感がまだわかってない。もっと早めに展開するというか、いや展開もクソもないんだけど、ちゃんと三十回しか歌えないことをもっと踏まえた上で放たないといけない。推敲する時にごそっとこいつらは消されるかもしれない。働きに。
帰宅。風呂に浸かりながら『ノー・カントリー・フォー・オールド・メン』を読む。もう三分の二ぐらい来てしまった。終わりそうだ。あまりにもおもろすぎてガブガブ読んでいる。しかしこのおもろさは映画で一度見てるからかもしれない。いやそんなのは関係ないかもしれない。映像が立ち上がるスピードは確かに速いが、多分これは映画を観てなくてもこの速度でやってくる。何か他とは明確に違う、これは、この本は俺の人生変えちゃうな、という出会いだ。寝る前の羽毛布団の中でAmazonに「コーマック・マッカーシー」と入力する。『ブラッド・メリディアン』を頼んだ。本当に全作読むつもりらしい。そしてなぜかもう既に全作読み終わったあとの寂しさを感じている。Wikipediaを見る。デビュー作の『果樹園の守り手』はマッカーシー三十三歳の時に書かれた小説だった。そこからぽつぽつと、二年おきとか五年おきとか七年おきとかで小説を書いていた。コンスタントに書いていたタイプの作家じゃなかった。大のインタビュー嫌いだったけど、初めて公に姿を見せたときのインタビューで、「何より自分のやってることが好きだから続けてるだけだよ」と言っていたらしい。最高すぎる。自分があまり書かなくなっている時というのは読むのも停滞している時で、それはつまり俺は定期的に小説にぶちのめされないとパワーが出てこないようだ。
一月七日
昼前に起きる。落合から「ぐちやまの名前出てたよ」とゆる哲学ラジオのリンクが送られてきていた。なんだ? と思い、その映像を見る。今からもう何年前だろうか、バナナムーンのヒロメネスのコーナーに送った俺のメールをきっかけに、ゆる哲学ラジオのパーソナリティーの平田トキヒロさんが哲学に目覚めた、という話をしていた。そんなことあんの? と笑った。送ったメールはこれだ。
想像してください。あなたは今、トイレに行こうとしています。しかしトイレは清掃中で使えません。しばらく待っていると中から掃除の人が出てきました。はい、あなたが想像した掃除の人、おばさんじゃありませんか? 今リスナーが想像したおばさんは、全員同一人物。
覚えていた。このメールは。初めて聴いたゆる哲学ラジオはとってもおもろい番組だった。あの時から八年とか九年が経っていた。みんな元気だろうか。自分が良いパフォーマンスを発揮するのは、自分の言うことなんて誰も聴いてない、と心から思えてる瞬間なのかもしれない、と考える。ラジオにメールを送っていた時、これは自分だけが聴いてると思って好き勝手送っていたし、短歌も、どうせ誰も読まないと思って書いてる。デリケートもそう書いた。そういうものほど良いリアクションをもらえている。あれ、これ、マジでそうじゃないか? と気付いてからそれはどんどん確信的な気持ちになっていく。その気持ちを発動させるためには物理的に一人で過ごす日々が必要だった。文字を書くことのムズさは文字を書くまでの状態にほぼ全てがある気がするのは、俺が素直になるのに時間も労力もかかるタイプだからかもしれない。誰の目も気にしない、と一口に言ってもこの言葉はみんなが思っているよりも深い。五万人の前でその視線を感じずにいるには「気にしちゃダメだ」と思っている時点でそれは失敗だから。必要なのは自分の動きへの集中とかですかね。それが色んなことを忘れさせてくれる気がする。「書くことの必要条件でありながら充分条件は、丸裸であることだ」と砂浜に打ち捨てられた自販機に書いてあったんですが、この「丸裸」を達成するのはみんなが思っているよりも随分と難しい。ただ本当のことを書けばいいとかそういう話じゃない。書かれる内容が本当だろうが嘘だろうが、それが自分の心臓を絞って指の隙間から溢れる血かどうかの話だ。それをありえないぐらい厳しい両目で審査し続ける、みたいな、そういう感じだ。魂を全部削ってやろうと腕力の全てを使ってステンレスのおろし金にかけて、それでも削れなかった、それでも消えなかった何かを放ち続けることが肝心だ。仕事が忙しすぎて全く休みなく働き続けていた友達があるタイミングからハプニングバーに通いまくって、見知らぬ人たちを相手に性別も関係なしに交わりまくっていた。その話を聞いたとき俺はなんだか少し嬉しかった。じゃあそれがあなたが本当に求めてることなんじゃない? と思ったからだ。彼はその時期のことをあんまり覚えていない。圧倒的な疲れは自分が本当に求めてるものを顕在化させてくれる。しかし、馬鹿なのかよ山口慎太朗は。ちゃんと、明日死ぬんだと思えよ。本当に思ってんのか? ずっと書けるわけじゃないんだぞ。チャンスはこれで最後。弾丸は一発しか残ってない。お前は明日死ぬんだから。本当にそれでいいの? 素直になんなかったら絶対後悔するよお前、いいの? 言えよ。さっさと。思ってることを言え。本当に思ってることを言え。今日で終わりなんだから。撃たないはない。この一発をぶち込みたい相手に向かって、今すぐ、引け。馬鹿が。引き金を引かなかったら俺は絶対に後悔する。外れてもいい。とにかく絶対に撃て。
働き終え、帰路、荻窪での乗り換え時に、「わたし腰悪いのに! 腰悪いのに!」と叫びながら走る女の人二人組とすれ違う。中央線の終電を目指しており、腰が悪いのに走らなければならない、走ってしまう、走っている、と、そのことを言語化しているかわいらしい人だった。
一月十一日
起きてすぐ篠原紙工さんに向かう。さよぴぃと新島さんと岩谷さんと表紙の具合の確認。割とすぐにオーケー。一月二十三日に自宅に届くことになった。こっから本屋さんに置いてもらう流れ、俺は頑張れるんだろうか。不安だ。そして突然湧いてくる実感。横でかわいらしく呑気に音を立てている活版印刷機。二十四歳の時に書いた。三十歳になった。あまりにも長い六年だった。俺は美工藤さんとかヤンヤンとかタナカイズミみたいに生きられているのだろうか。
新宿に移動して、さよぴぃとピースに入ってあったかい紅茶を飲んだ。
一月十三日
仕事の休憩中にセブンイレブンに行き、コーヒーを淹れる。琥珀色の液体が好きなように輝きを放ちながら素晴らしくグングングングン・オラオラオラオラと垂れていきカップに溜まる。後ろのコピー機でおばちゃんの店員さんがどこかに電話しながら、若者にコピー機の使い方を教えようとしていた。しかしその青年は日本語が全くわからないようだった。おばちゃんの店員は「日本語がわかる友達とか連れてきてくれる? おっけー?」と優しく尋ねているが、日本語がわからないんだからそれもきっと伝わっていない。青年はよくわからないがわかったフリをしてうんうん、と頷き、店員のおばちゃんはバックヤードに消えた。コーヒーの抽出を終えた山口慎太朗はカップにプラスチックの蓋を装着すると振り返り、「へいへい、プリントしたいの? コピー?」と聞いた。青年は自分のiPhoneの画面をこちらに見せた。それは自転車譲渡証明書の画像だった。コピー機とiPhoneの同期が上手くいっていない。セブンイレブンマルチコピーのアプリは入っている。「俺やるね」と熊本弁と標準語の二か国語しか喋れない馬鹿な男は断りを入れ、マルチコピー機を操作する。そして彼のiPhoneからその画像をQRコードにしてあとは飛ばすだけなのだが、肝心のその画像は彼のiPhone本体のカメラロールには入っているようだが、マルチコピーアプリ内にはまだ取り込まれていなかった。なるほど、と思う。「ちょ、一回触らして? いい?」と聞き、彼のiPhoneを触る。英語のようで英語ではない何かよくわからない言語がたくさん表示されていた。カメラロール内のその画像を開いて、そこからマルチコピーに転送する経路を通ろうとするも、設定で他アプリの干渉がオフになってるのか何なのか、その道は通させてもらえなかった。というところでコピー機を使いたいお姉さんが後ろからやってきて、「大丈夫ですか?」と聞いてきた。「あ、うん、多分大丈夫です」と答えたが、今思うとこのお姉さんからはきっと二人組に見えていたんじゃないか。俺がひとりごとみたいに「あ〜、これダメなんか」「なるほどね」「設定開ける? ホーム画面、ホーム」などと言っている様子を見て察してくれたのか、そのお姉さんが中国語で彼に話しかけた。ほにゃららら、と。きっと「中国語は喋れますか?」的なことを聞いた。しかし彼は無視した。中国語を喋れるお姉さんは「中国語じゃないか」と言って、俺が彼に「ワッツ、ランゲージ?」と尋ねると、青年は「ベトナム」と言った。さっきのiPhoneの文字はベトナム語か、とわかった。お姉さんも「これ本体の設定から変えないとですね」と言うが、ベトナムの彼はそもそもiPhoneを使いこなせていない様子で、俺が自分のiPhoneの画面を見せながら「ホーム画面から設定行って、こう、ほら、こうやって」と教えても、従おうとせず、彼はコピー機と格闘していた。カメラロールから印刷するという意識のせいか、普通紙プリントではなく写真紙プリントを選んでいたりしていて、言語がわからないのもあるだろうが、そもそもこういうメカがあまり得意じゃなさそうだ。そこで俺は「これ俺がAirDropでもらって印刷すりゃいいじゃん」と声に出して言うとお姉さんが「あ、それナイスアイデアですね」と頷いてくれた。「ただ彼が嫌がりそうだなぁ、どうかな」と言いながら「AirDropオーケー? で、俺がやるわ。マイ。マイプリント。オーケー?」と尋ねると、意外にもこれはすんなり「あ〜、オーケー」とAirDropで自転車譲渡証明書を譲渡してもらった。そして俺のiPhoneからテキパキ進めて、「A4? A4でいい?」「おんおん。ツー」「あ、二部? 二枚ね? はいはい。ここに二十円いれて」と、プリントが完了すると彼は急に嬉しそうになり、「サンキュー、サンキュー」と言った。お姉さんに「ありがとうございます。助かりました」と言ってセブンイレブンから出ようとすると俺の前を歩くその青年が出入り口の扉を開けてくれて、「先にどうぞ」とやってくれた。さっきまで結構ドライだったのは、やっぱり急に知らない国で知らない言語で知らない奴から自分のiPhoneを触られたりすることの恐怖感というか、自分の予期できない何かをされるかもしれない可能性、そしてその答え合わせは最後にしかできないことが関係していたんだろうきっと。無事にプリントが完了した途端彼はるんるん気分になり、その誰かから貰ったのか今後誰かに渡すのかの黒いママチャリに乗ってどこかへと去った。俺はコーヒーを啜りながらやたら寒い西荻窪を歩いた。
落合に電話する。元気かどうかの確認。落合は夜勤の仕事と養成所の行き来で十九歳みたいな日々を送っていた。「ぐちやまはどうなん?」と聞かれて、「早くこの生活から抜け出したい」と応えていた。それは脊髄反射的に出てきた言葉だった。あまりにも素直。今の仕事とか環境とか関わる人が嫌とかは全くなくて、むしろみんなに大感謝しかないのだが、それでもそう思っている。多分これを俺はずっと言う。何やっても満足できないだけ。「じゃあ元気だな」と落合はすぐに理解した。
一月十四日
自分より背の高い女の人がコンビニで弁当を眺めていた。珍しすぎる。百八十以上ある。うわ、でかっ、と思って少しドキドキする。
一月十五日
疲労困憊で頭が痛い。不気味だ。家に帰ってすぐにイブクイックを探したがもうなくなっていた。Amazonで頼む。
一月十六日
いっぱい寝たら治った。働きに向かうバスで『スクールバック』の一巻を読む。めちゃめちゃ良い漫画。最後の伏見さんの発言がちょっと怖くてそれもまた良い。どういう意味だろう。
働き、帰路。短歌研究新人賞の連作。二十七首。早い。この感じか。五十と全然違うな、と思う。もっとコンパクトに脇を閉めてバットを振らなきゃいけない感じだ。
一月十七日
起きてすぐにコインランドリーに。待っている間、回転寿司に行く。北口の喫煙所でタバコを吸っていると、金髪のおじさんが灰皿の周りにいる人たちに怒鳴り散らしていて、みんなが引いていた。その近くには杖を高く振り翳して絶叫しているおじいちゃんもいる。ポン中の巣窟じゃねえか、と爽やかな気持ちになった。あゆみブックスに入ったけど『スクールバック』の二巻は置いてなかった。ランドリーに戻って服を全て畳み、帰宅。コーマック・マッカーシー全作品制覇に向けて二冊目『ブラッド・メリディアン』に突入していたのでその続きを読む。七十ページぐらい読んだところで、うーん、となる。これは何に向かっていってる物語なんだろう、と文庫本の後ろを読むと、その目的もない放埒な暴力の点在の話のようだった。今の俺は、目的が明確な話しか受け付けられない。一旦辞めることにして、次の『すべての美しい馬』に移行。主人公が牧場を自分のものにするべく両親と交渉する日々があった。これこれ、これよこれよ、と思う。
一月十八日
働き、帰路、久しぶりに『more & more』のfancamを見る。人間を辞めないと到達できないダンスだな、と思う。Wikipediaを開いて「TWICE」と入れる。初めてのワールドツアー開始とほぼ同時に『Feel Special』が発売されて、ツアーが終わってすぐに『more & more』が始まり、そのあと『I can't stop me』になる。いつもここの三連発に感動する。ワールドツアーが始まる前に『Feel Special』を収録して、その期間中に『more & more』の制作を進めて、ツアー終わった瞬間すぐに録って解禁、みたいな動きだろうか。プロモーションが完璧すぎる。そして一体どんな地獄のスケジュールだったんだろう。ジョンヨンが「忙しすぎる……」と泣きながらVLIVEをやっていたのもここら辺の時期だった。ミナとジョンヨンを持ってかれてるのにそれでも尋常じゃない速度で進み続けるのが馬を使った戦争みたいだ。人を喜ばせるために命の全部を焚べて、しかもそれが当たり前みたいな顔面をしている。それはこちらの姿勢を正してくれる。「お前はここまでやってるか?」と問うてくる。この九人より歌もダンスも上手い人なんか地球上にはいっぱいいるだろうが、この九人が同時に歌って踊ったら途端に誰も勝てなくなる。それでそのままLine Distributionの動画をぼーっと眺め続けていた。関連関連でどんどん九人の歌の配分を、冬の海を見ているみたいな気分で眺めていた。
一月十九日
アダルトビデオを見ていたら女の人のお股から大量に水が出てきた。その飛沫がカメラのレンズにぶつかり、フォーカスがその飛沫に合い、奥が完全にぼやける、というシーンがあった。「なんでオートフォーカスで撮ってんの?」と思わず声が出た。すぐにジャンプカットが入って、レンズの飛沫は拭き取られていた。きっと撮影は一回中断されたに違いない。それはシリーズもののアダルトビデオだったので、気になって同じシリーズの他の作品も見てみると、このシリーズの作品全てで同じミスを繰り返していた。なんで誰も注意しないんだろう。「もうええわ!」と言ってiPhoneを放り投げて居間に移動すると、おいしくもなければまずくもないテキトーなコンビニの弁当をテキトーに食いながらさっきのAVのフォーカスがおもろかったので人に話す時にどう話すかを頭の中で整理する。
一月二十日
起きてすぐにLogicを立ち上げて、エンヤとの曲を進める。長いことその作業に没頭して気付くと窓の外は真っ暗だった。そのあとは九時間Apexをやった。ちりニキとKGさんと。ほぼほぼ五位以内に入るというかなり高いアベレージを出したものの、一位以外無意味という昇格戦のシステムに苦労した。内部レートはどんどん上がっていき、最後の二時間ぐらいはプレデターたちを相手に戦っていた。対面が強すぎて全く勝てない。家から一歩も出なかった日。
一月二十一日
起きてすぐ風呂に入り、コーヒーを飲んでタバコを吸い、着替えて外に出る。兄がくれた立派な紫のパーカーと緑のズボンを履いた。路面が濡れている。雨が降っていたようだ。駅のホームに降りてベンチに座って電車が来るのを待った。何か叫びながらうろうろしているおじちゃんがいて、俺の隣の席には子ども二人をあやすお父さんの大きな声があり、なんだか心がザワザワしてくるというか、頼むからみんな静かにしてくれ、と怒りのような何かがあった。不思議だったのは発狂しているおじさんよりも子どもをあやすお父さんの声の方をうるさく感じていたことだった。ヘッドホンで爆音で音楽を聴いて、みんなの声が聞こえないようにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
