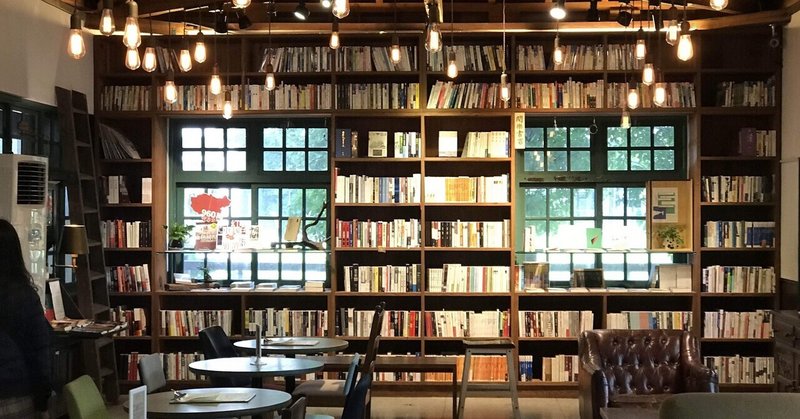
ボルヘス『詩という仕事』に寄せて
ボルヘスにとっては言葉が存在し、その言葉によって詩を織り上げられるという事実こそが悦びであり、そのことが本書では、「生涯でもっとも重要」なことでありあらゆる生活上の実際の経験に勝るとさえも賞揚されている。こうした彼の思想は幸いなことではないか。言葉は、詩は、現実の経験と違い誰に対しても開かれているということだからだ。

言語が表そうとする「物そのもの」であるとか形而上学で想定されたありのままのイデアなど存在しないがそれでも我々が「イデア」という観念にことよせる心情はいかにも真実のようである。また「物そのもの」を置き去りにしたところで言葉それ自体に美を見出し酔いしれる、そういうことは言葉の持つ響きや韻律かもしれないし、われわれが言葉から想起するイメージかもしれない。それがたとえ意味をなさないものであったとしても。言葉や言葉によって構築された世界から得られる悦びは、たとえ形而上学の自明性が否定されようと確かなものなのではないだろうか。例えば外国語の響きというものに心地よさを覚えることがある。この一連の講演の中でたびたびボルヘスはスペイン語の詩を朗読している。聴衆が英語話者であろうとも韻律や響きの美しさを伝えたいかに見える。
言葉の韻律や音節に心を配るということはもしかすると、言葉そのものを玩味する行為といえるのかもしれない。そうしてみると言葉から得られる悦びは散文より韻文が適してもいよう。

ロセッティの詩にしてもホメロスの”the wine-dark sea”という言葉にしても現代読まれると、使われるとそれはもはや当時の意味とは違ったものになってしまう。それは当時と現代ではコンテクストが違うからであるが、時間の隔たりがなくともロラン・バルトの『作者の死』のように解釈は作者の手を離れて読者に委ねられ、同じ読者であってさえ今日の読みと明日の読みではまた意味も変わってくるというようなこともあるだろう。ボルヘスは読まれ方が変わることに肯定的であろう。そこに新たな詩趣が芽生える契機があるからにほかならない。「受容理論」や「読者反応理論」にも通じてくるだろうが、立場として作者であるよりも読者であろうとするボルヘスのこうした考えは救いですらあるかもしれない。誰もが詩の前では平等であるからだ。たとえて言うならば民芸運動家の柳宗悦が誰でも手に入れられる雑器の美をこそ仏の救済になぞらえたように。

われわれが初めて新たな語彙を獲得していった幼い頃のことを思い浮かべてみる。それは一回性の得難い経験である。言葉の韻律であったり文字の形であったり、意味とはかけ離れた部分で心地よく思われるか、硬質に思われるのか、楽しげか、といったように様々な印象を愉しんでいたように思う。我々は日常言語の使用を通じて言葉にも手垢がつき、言葉自体の精彩を失っていく、そうした過程のただなかにいるように思う。ボルヘスによるとはるか昔、「night」の一語にさえ印象的で異様な魔術的な感覚を人々は受けていたであろうと考えられるが、現在のわれわれは屈折した技巧を凝らした詩句を作り上げなければこうした魔術的なるものを呼び覚ませていない。
詩人は言語が本来持っているそうした魔術めいたものを喚起するために詩を作るのであろう。二つの異なるものをつなげることで我々の普段の思考の埒外のイメージを作り出すシュルレアリスムも失われた言葉の魔術を取り戻す試みの一つであろう。意味との切断によって魔力を生み出すという試みであり、「意味は詩にとってお添えものではないか」というボルヘスの思想にも近しいように思われる。「三重の夜の竪琴」という詩句を巡り、解釈はむしろ詩情を損ない、そこにある謎、それだけで十分だとするのも同じ態度であろう。そうした言葉の源泉にある魔術は、抽象的で論理的な日常言語ではなく、具体的で感情的な詩的言語においてこそ見出される。
「われわれが詩を読むたびに、芸術はたまたま産まれる」とボルヘスは言う。詩情は偏在しているようだ。

ところで、ボルヘスは自身の詩集、『創造者』の末尾に自作の詩をさも古今東西の様々な詩を引用したかのように装った。存在しないものからさえもそこには虚構の歴史をはらみその虚構のコンテクストの厚みから我々は詩情を汲み取っていってしまう。

また彼の短編集、『伝奇集』は“Ficciones”、すなわち英語で言うfictionsであり、「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」において架空の文明にかかわるあらゆる事象を包摂する百科全書の物語が繰り広げられている。
架空の話としてしまうなり、奇想天外ながらも空しい虚構ともとれるがここで現れる架空の宇宙、文明は現実をも規定していくシミュラークルともなろう。
ボルヘスは実生活のあらゆる体験よりも読書から得られる経験を人生の重大事といった。そうしてみるとこのシミュラークルであり、言葉から生み出される世界をとりわけ重要視していたのだろう。

そこで思い出されるのが『伝奇集』や『夢の本』で彼の引いている荘子の「胡蝶の夢」の話だ。ここでは夢の中の世界と目を覚ましているときの自分のいる世界が、裏返ってしまった世界、胡蝶である自分の世界が現実であるそんな可能性が現れ、そのどちらが本当の私なのかわからない未決定な状態が立ち現れてくる。
ともすればシニフィアンの群れが織り成す世界も、シニフィエの総体たる世界よりも我々にとってははるかにリアルであり、はるかに蠱惑的なのではないだろうか。
現実が侵食され、オリジナルが別の何かにすり替えられていく。そのことに彼は抗うどころかそんな虚構をこそ愉しみ詩情を汲み取りもする場としていたようにも思われる。
虚構の典拠も現実の攪乱もボルヘスがインド人の歴史感覚の欠如から感得した時間を超越した詩行があるはずという確信に基づくもので、コンテクストを離れたところでそれを実現しようという実験でもあるのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
