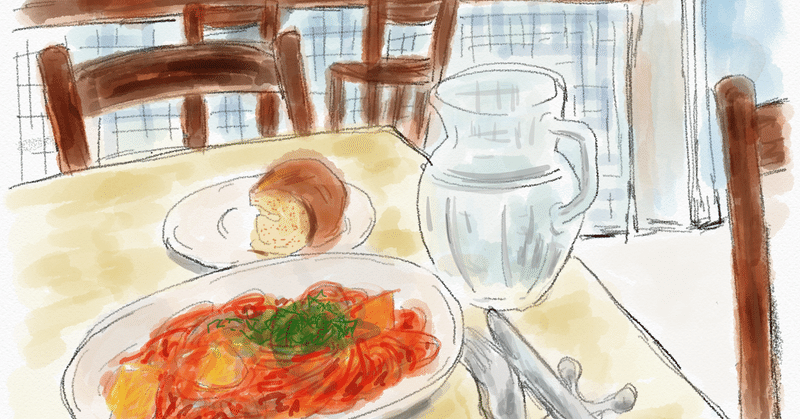
「業」の深淵から浮かび上がる違和感の行方
石井妙子さんを動かした違和感
石井妙子さんの『女帝 小池百合子』(文藝春秋)が話題だ。私もようやく手に入れて読み始めた。まだ序盤なのと、すでにいろいろな人が感想を語っているので中味はさておき、石井さんが小池百合子知事に関心を持つきっかけが面白いと思った。
2016年の夏、都知事選のなか、小池知事は街頭演説で対抗馬の鳥越俊太郎氏のことを「病み上がりの人」と呼んだことがあった。この発言はメディアにも「明らかな失言」と指摘された。そして、石井さんの記憶に強く残ったのは、その後のテレビ討論会での小池知事の振る舞いだった。番組で鳥越氏が小池知事に「私のことを『病み上がりの人』と言いましたねっ」と詰め寄ると、彼女は「いいえ、言っていませんねえ」と答えた。「どんな言い訳で切り抜けるのだろう」と見ていた石井さんは、まったく想像もし得なかった小池知事の対応を長く忘れることができなかったという。
石井さんが感じた違和感。その感覚は、私にも馴染み深い。おそらく、ライターであれば同様な感覚を持っているだろう。記事の大小やテーマにかかわらず、私たちは、違和感の正体を突き止めるため、取材をしたり、資料を調べる。そして、入り組んだ糸をほぐし、筋をつなげていくのが仕事の一つだからだ。
隠れていたものを違和感が引っ張り出す
とはいえ、この違和感はライターだけに備わった特殊能力でもなく、仕事だけで発揮されるものでもない。誰にでも備わっている。とくに女性は鋭い。普通に生活していても、他人の言動や行動につじつまが合わないと気づくことはよくある。あの感覚だ。
理由はいろいろ。ちょっとした誤解から生じていたり、なんらかの秘密から生まれていることも。そして、違和感を覚えても、日々のできごとに紛れて忘れてしまうことのほうが多い。いちいち追求していたら身が持たないし、忘れたほうが良好な人間関係を保つのに役立つ。
だが、ときに何度も浮上してくる違和感もある。どうしてもあることがひっかかるのだ。そういう違和感は、何かの拍子に爆発し、隠していたものを表に引っ張り出すきっかけになりやすい。
今、世の中で新型コロナウイルスの感染拡大を機に、違和感の下に隠れていたものがあちこちで吹き出している。人、あるいは社会が何度も沈め、隠そうとしてきたものが、どうにも抑えきれず、吹き出しているような状態だ。その兆しは、2017年の暮れから少しずつ起きていた、と私は思う。
10年近く続いていた足元がおぼつかず、視界不良の生活
日本で言えば、東日本大震災の衝撃はいまだに尾を引いている。生活の立て直しが思うようにいかない人だけでなく、平穏に戻り、震災が過去のできごとに感じている人にも、足元を大きく揺さぶられた衝撃は続いていた。私たちはこの約10年、震災に体を大きくひっくり返され、空中に放り出され、足元がおぼつかない、ふわふわとした生活を送ってきたと思う。そして、その生活には、体を安定させるため、寄りかかったり、掴むんだりできるモノがとても少なかった。
私たちは地面に激突しないように、あるいは水中で溺れないように、必死で足を漕ぎ、手をバタつかせ、生き延びようとしてきた。しかし、その生活は新型コロナウィルスによって強制的に止められた。1カ月半ほどの短い間だったが、それでも人々の行動が止まったことで、かき回されていた空気は沈み、私たちの体も地面すれすれまで足が着きそうなほど、下に降りることになった。
渦を巻くような今までの生活は、何かを隠したい人にはとても都合がよかった。人々が焦り、必死になってかき回すことで、ほこりや汚れが大量に舞い上がり、視界をさえぎってくれたからだ。
だが、これからはそうはいかないだろう。空気が静まったことで、視界がよくなってしまった。そして、人々は地面に足をつけようとしている。生きるために何を大切にすべきなのか、何を理想として生きるのが人間としてのあり方なのか、思い出そうとしているからだ。
隠されていた「業」と向き合わざるを得ない人たち
おそらくこの変化は社会だけでなく、個人の関係にも起きていると思う。人に違和感を与えていたもの、その人が覆い隠したいと思っていたことが、本人の好むと好まざるにかかわらず、露呈されることが増えるのではないかと思う。隠されているものが表に出ることは悪いことばかりでもない。表面化したことで、周囲の共感を呼び、連帯につながることもある。
やっかいなのは、本人が隠す自覚もなく隠してきた場合だ。その根をたどっていくと、育ってきた環境や家族を含めた周囲との人間関係、理想の自己像などが混ざり合った「業」につながっていく。これが掘り起こされるような状態は、場合によっては命に関わる。
自分の根本を支えてきたもの、見たくないと思っていたものも見ざるを得ず、しかも、その経験は一方通行で逃げ道がない。「業」と向き合うことになるか否かの選択肢は当人にはなく、気がつくと叩き込まれ、ある程度の時間を経て、通らなければならない道を通り、やり遂げるまで出口はない。
今、起きている変化は、社会においても、個人の場合でも、新しい方向に進むのだろうか。それとも旧来の隠したい力によって、せき止められるのだろうか。この夏はその分岐点になるかもしれない。そして、新しい価値観のほうが優勢になった場合、生き延びるには、自分だけでなく、他人にも誠実になるしかないのだろう。
全米に広がる抗議デモに比べ、日本は変化が少ないように思える。しかし、じつは日本も巻き込まれ、水面下では地滑りのように変化が起きている。時代の価値観が大きく変わるのか、あるいは旧来の価値観が続くのか。その綱引きの行方を戦争以外の形で体験できていることこそ、21世紀なのだと思う。
嘘をつかないこと、人の道に外れたことは、どんなに感情や欲望が強くても許されないこと。それは理想の世界のようにも一見、思えるが、人によっては自分の「業」と向き合わざるを得ず、甘えが許されない厳しい時間を過ごす必要が出てくるかもしれない。
仕事に関するもの、仕事に関係ないものあれこれ思いついたことを書いています。フリーランスとして働く厳しさが増すなかでの悩みも。毎日の積み重ねと言うけれど、積み重ねより継続することの大切さとすぐに忘れる自分のポンコツっぷりを痛感する日々です。
