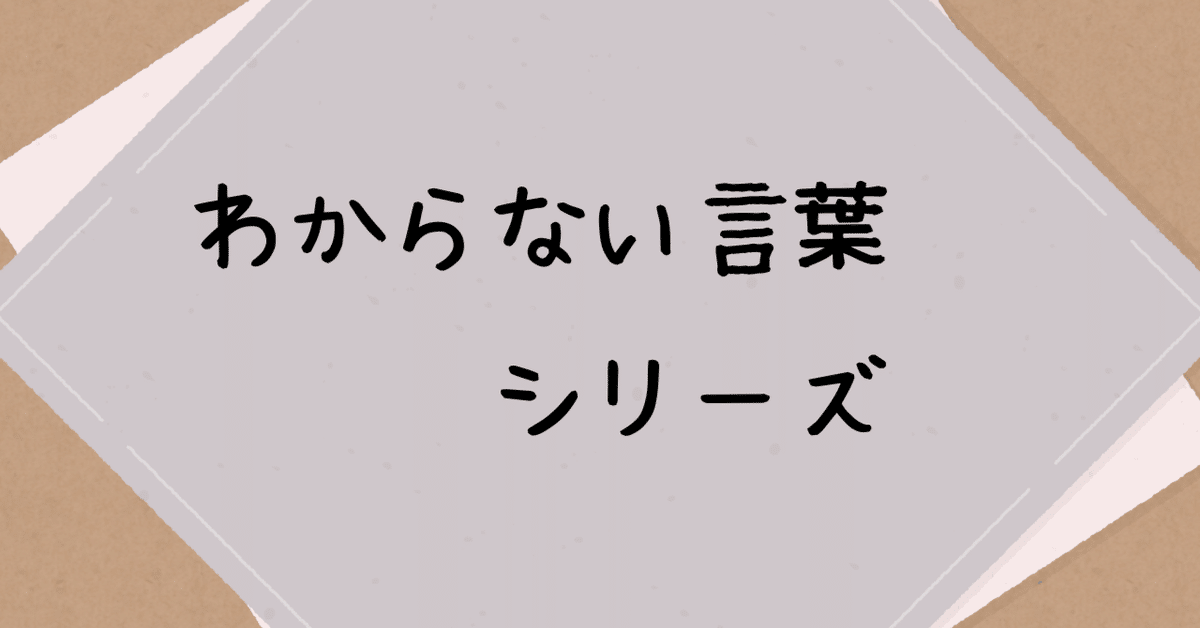
キャンセルカルチャーとは何なのかを再確認する。
はじめまして、わすれなぐさです。
今回が初のnote執筆となりますので、読み難いなどありましたらご指摘頂きますと幸いです。
みんなが当たり前に使っている言葉、でもそれってちゃんと理解して使ってますか?残念ながら私は浅学ゆえよく知らずになんとなくでしか捉えていません。しかしそのままにしておいてはいけません、言葉と共に気持ちがすれ違わないように、きちんと調べ直さねば。
今回はキャンセルカルチャーについて取り上げて参ります。
※2022/6/26 11:15 誤字修正
※2022/6/27 9:05 「9. 追記」を追加、一部表現修正「付け加えるならば、」→「加えて」
1. キャンセルカルチャーの事例
しばしば耳にするキャンセルカルチャーという言葉、私が印象深いのは先日の第94回アカデミー賞での事件。俳優のウィル・スミス氏が脱毛症を患う妻ジェイダ・ピンケッタ・スミス氏を揶揄されたことをきっかけに司会のクリス・ロック氏を平手打ちしました。
この出来事は大変な波紋を呼び、多くの人々から非難の声が上がりました。行為の是非についてはここでは論じませんが、結果として同賞を主催する映画芸術科学アカデミーはウィル・スミス氏に対し、関連するイベントへの出席を今後10年間禁止する処分を発表。そして同氏はアカデミーを自ら脱退することとなりました。すなわち、キャンセルされたのです。ウィル・スミス氏はキャンセルカルチャーの対象となり、排斥されたといって良いでしょう。
2. キャンセルカルチャーの定義
では、キャンセルカルチャーとは一体なんなのでしょうか?まずはキャンセルカルチャーという言葉の定義から確認していきます。
Wikipediaから引用すると以下の通りです。
キャンセル・カルチャーとは、主にソーシャルメディア上で人物が言動などを理由に追放される、現代における排斥の形態。多くの場合、芸能人や政治家といった著名人を対象に、過去の犯罪や不祥事、不適切な言動(未成年だった頃の喫煙・飲酒など)とその記録(写真、動画、雑誌の記事、SNSの投稿とスクリーンショットなど)を掘り起こし、大衆に拡散、炎上を誘って社会的地位を失わせる運動や、それを良しとする風潮を指す。
要約すると、「主にソーシャルメディアで人物が、素行などを理由に排斥される」ことのようです。原因となる素行が広く拡散され大衆の反感を買い、社会的地位を失う。それがキャンセルカルチャーなのです。
3. キャンセルカルチャーの問題点
では、キャンセルカルチャーは何が問題なのでしょうか。
ひとつは、キャンセルカルチャーによって排斥される対象の権利が侵されることです。大衆の非難によってなされる排斥は、往々にして数の暴力となり、少数派を封殺します。
また、ソーシャルメディアの発達によって情報の伝達速度が上がり、多くの人々が一斉に対象を非難するようになりました。浴びせられるような非難の声は議論の余地を奪います。同時に情報伝達の正確性にも欠き、理不尽な排斥が起きやすいといえるでしょう。
ひとつは、自由な表現を萎縮させることです。自分がいつキャンセルカルチャーの対象となるか分からない、その恐怖から人々は非難を受けかねない言動や表現を避けるようになります。ひいては議論や文化の衰退を招くでしょう。
4. それはキャンセルカルチャー?それとも違うの?
前述の通り、キャンセルカルチャーは大きな問題となっています。私達は対策を練り、キャンセルカルチャーが起こらないように防いでいかねばなりません。そのためか、ネット上でしばしばキャンセルカルチャーに関する議論を目にします。
SNS上では悪質なデマを拡散する人が現れることしきりです。その人物(以下発信者とします)に対し、発言の誤りを指摘し、広く拡散することでデマを防ごうとする場面はよく見られます。しかし、この行為は一種のキャンセルカルチャーなのではないか、という議論です。
誤りを指摘する声が多く集まりデマの拡散防止に成功すれば、発信者は「デマを流した人物」ということになり、社会的地位を失い排斥されます。その時、いかに正しい指摘であろうとも、浴びせられた指摘の数々は発信者にとっては非難の声に他なりません。構造としては先のキャンセルカルチャーの定義と同じなのです。
この意見に対し、キャンセルカルチャーにあたらない、という人の主張はこうでした。
集まった声は発言の正誤を問うものであり、発信者そのものの排斥を求めていない。また誤りを指摘し拡散した人物も情報の受け手に判断を委ねており、こちらも排斥を求めていないので、これはキャンセルカルチャーではない。
つまり、対象を排斥をするという意図や要求があることがキャンセルカルチャーの構成要件として含まれるというのです。
ここで私は分からなくなってしまいました。だって、先ほど確認した定義にはそんなことが書かれていないのです。
"大衆に拡散、炎上を誘って社会的地位を失わせる運動や、それを良しとする風潮を指す。" の部分が該当すると思うのですが、結果として排斥されたのならばそれは社会的地位を失わせる運動というに十分であり、排斥の意図の有無は関わりないように思えるのです。
5. キャンセルカルチャーとコールアウトカルチャー
そこで改めて定義を確認すべく、英語版のWikipediaを確認してみました。すると、以下のように記述されていました。
Cancel culture or call-out culture is a phrase contemporary to the late 2010s and early 2020s used to refer to a form of ostracism in which someone is thrust out of social or professional circles – whether it be online, on social media, or in person. Those subject to this ostracism are said to have been "cancelled". The expression "cancel culture" has mostly negative connotations and is used in debates on free speech and censorship.
(キャンセルカルチャーまたはコールアウトカルチャーとは、2010年代後半から2020年代初頭にかけての言葉であり、オンライン、ソーシャルメディア、または個人を問わず、誰かが社会的または職業的サークルから突き放される排斥の形態を指すのに使われる。この排斥の対象となった人々は、「キャンセルされた」と言われます。キャンセルカルチャーという表現は、ほとんどが否定的な意味合いを持ち、言論の自由や検閲に関する議論に使われる。)
The notion of cancel culture is a variant on the term call-out culture. It is often said to take the form of boycotting or shunning an individual (often a celebrity) who is deemed to have acted or spoken in an unacceptable manner.
(キャンセルカルチャーの概念は、コールアウトカルチャーという用語の変形である。それはしばしば、容認できない行動や発言をしたとみなされた個人(多くの場合、有名人)をボイコットしたり、敬遠したりする形をとると言われている。)
ここで馴染みのない言葉が出てきました。コールアウトカルチャーとは一体?コールアウトカルチャーについては以下のように記述されています。
"Call-out culture" has been in use as part of the #MeToo movement. The #MeToo movement encouraged women (and men) to call out their abusers on a forum where the accusations would be heard, especially against very powerful individuals. Additionally, the Black Lives Matter Movement, which seeks to highlight inequalities, racism and discrimination in the black community, repeatedly called out black men being killed by police.
("コールアウトカルチャー "は、#MeToo運動の一環として使用されてきた。MeToo運動は、告発が聞き入れられるような場で加害者(特に強力な個人)を呼び出すことを女性(および男性)に奨励した。さらに、黒人社会における不平等、人種差別、差別を強調しようとする「ブラック・ライブズ・マター運動」は、黒人男性が警察に殺されたことを繰り返し訴えた。)
コールアウトとは「呼び出す」という意味です。つまり、"告発が聞き入れられるような場で加害者を呼び出す" という部分が肝となるわけです。転じて「加害者を衆目に晒し、槍玉に上げて告発すること」と言ってもいいかもしれません。そして、ここでは告発の結果までは言及されていません。
以下は別のサイトの引用です。辞典からの引用が出来なかったため正確性に欠けるかもしれませんがご容赦ください。
Unlike cancel culture, the aim of call-out culture is to recognize what was offensive and why it was considered offensive. Conversely, cancel culture focuses more on bringing down the offenders for their actions, without focusing much on “solving” the issue, such as sparking a conversation and bringing more knowledge to the offender.
(キャンセルカルチャーとは異なり、コールアウトカルチャーの目的は、何が不快で、なぜそれが不快とみなされたのかを認識することです。逆に、キャンセルカルチャーは、その行為によって違反者を陥れることに重きを置いており、会話を喚起し、違反者にもっと知識をもたらすなど、問題を「解決」することにはあまり重点を置いていない。)
先述の定義とあわせて要約すれば、コールアウトカルチャーとは、
「人物の問題点を広く周知し、何が問題であったかの認識を共有することで問題の解決を図ること」
対してキャンセルカルチャーは、
「人物の問題点を広く周知することで反感を促し、対象を排除すること」
と言えそうです。つまり、排斥の意図や要求はコールアウトカルチャーと区別するために必要ということなんですね。
キャンセルカルチャーとコールアウトカルチャーを区別しないという説もあるようですが、私としてはこの区別がしっくりきますので、分けて考えていこうと思います。
6. キャンセルカルチャーの再定義
ここまでをまとめてキャンセルカルチャーを再度定義するならば、
「ソーシャルメディア等で人物が、素行などを理由に排斥されること。主に大衆の力により対象人物を排斥することを目的とする」
といったところでしょうか。
加えてコールアウトカルチャーの定義を、
「ソーシャルメディア等で人物が、素行などを理由に告発されること。主に大衆の力により告発された問題の解決を目的とする」
としたいと思います。
そして、上記定義に照らして考えれば、デマ拡散防止の例もはっきりします。誤りを指摘した人物に発信者を排斥する意図はなく、デマ拡散防止という問題解決を目的としています。よって、キャンセルカルチャーでなくコールアウトカルチャーといえます。はー、すっきり。
7. コールアウトカルチャーの危うさ
定義がはっきりしたところで、問題提起をしているに過ぎない、コールアウトカルチャーだから問題ない!と安心してしまって良いのでしょうか?私にはそうは思えません。
発信者を陥れる意図はなく、ただ問題の解決をしたいだけだとしても、急速に拡散する情報は容易に排斥運動に繋がります。それは、発達したSNSの構造的な問題が大きいと私は考えていますが、コールアウトカルチャーの仕掛人に責任はないのでしょうか。
コントロールしきれないコールアウトカルチャーの末路は、キャンセルカルチャーと全く変わりがないのです。
ネット上では様々な議論が展開しています。その中で、多くの人への呼び掛けを必要とすることは多々あるでしょう。しかし、その呼び掛けは排除運動を引き起こすトリガーとなり得ること、尊ぶべき人の権利を侵す恐れがあることを自戒する必要があるのではないでしょうか。
8. 最後に
今回の記事では、キャンセルカルチャーという概念の成立に伴う、思想的な部分を意図的に省いてあります。それは、起きた結果によって物事をきちんと捉える必要があると考えるためです。
人は思想によってしばしば目が曇ります。自らが正義の側に立つと信じることで、相対する人の気持ちや権利を容易に踏みにじられてしまうのです。
議論が白熱した時、ちょっとだけ省みてほしいのです。今自分はやってはいけないことをしてはいないかと。そうすれば、世界は少しだけ優しくなると思うのです。
権利などよく知らない初心者の記事ですので突っ込みどころも多々あると思います。その際はここはこうだよ、ここはこうした方が良いよ、とご指摘いただければ助かります。皆さんの考えの齟齬をなくし、共通のお話をするための叩き台になれれば幸いです。
記事を書くのは初めての経験で、これを書くだけでへとへとになってしまいました。次々とnoteを上げてみえる諸氏は本当にすごいなぁと改めて実感しましたね。次回があるかは不明です。
まとまりのない文章をご覧いただき、ありがとうございました。
9. 追記
今回の記事の定義は、私が納得できる、私にとっての定義です。「これが正しい定義です!」と主張するつもりはまったくありません。
比較的新しい概念、かつもともと定義が曖昧で諸説ある単語ですので、他の定義で認識している方は大勢いらっしゃると思います。
「コールアウトカルチャーなんて、キャンセルカルチャーとまったくかわらない。排斥の意図があってもなくてもキャンセルカルチャーだ。」
という方もいれば、
「コールアウトカルチャーは問題がない。キャンセルカルチャーとコールアウトカルチャーは明確に区別すべき。」
という方もいるでしょう。
「明確に悪影響を振りまく相手を排除できないなんておかしい、キャンセルカルチャーを悪だと断じることは欺瞞だ。それこそ言論の自由を奪っている。」
という方だっているかもしれません。
重要なのは議論のさなか、相対する人がどのような意図で言葉を用いているかです。主張したい思いを伝えるために言葉を使っているはず。そこで、「キャンセルカルチャーだから悪に決まっている!」というのも思考停止ですし、ましてや「いや、キャンセルカルチャーはこうだから」と定義の正しさを取り合っても相手の意図は伝わらないと思うんです。
また、「これはどういう意味ですか?」と尋ねられたとき、拒否反応を返される方がみえます。「そんなことも知らないの?」「勉強してからきてくださいね」「それを聞いたらどうなるの?」
質問は、あなたとお話がしたいという意思表示です。あなたを陥れる人ばかりではありません。頑なにならず、あなたの想いを伝えていただけませんか。
会話や議論には、伝える側にも受け止める側にも、ちょっとの努力が必要だと思っています。
記事公開時、キャンセルカルチャーについての参考記事をご紹介いただきました。ベンジャミン・クリッツァーという方がキャンセルカルチャーについてまとめられた記事です。
「批判が必要だって気持ちは分かるけど、やっぱりキャンセルカルチャーはよくないことだと思うし、うーん……。」という、もやもやする気持ちのところを背景を交えて大変詳しく、分かりやすくまとめてみえます。ぜひご一読ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
