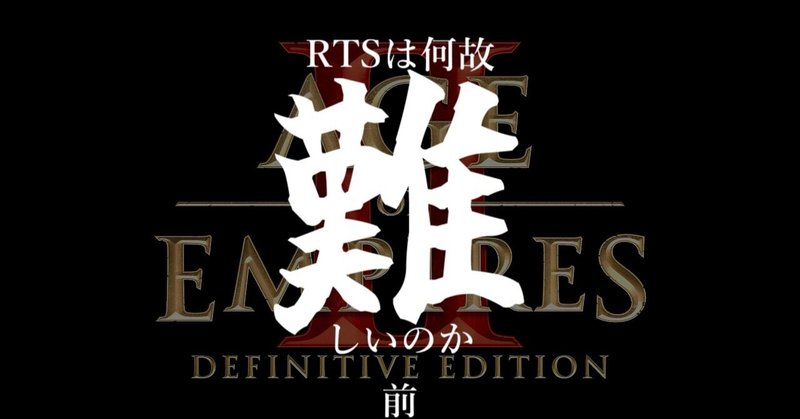
RTSは何故難しい? 前編
前回はAOE2とAOE3の比較をし、それぞれの特徴や各要素がプレイヤーにとってどう作用するかを考察しました。
主に面白いと思っている点を中心に書きましたが、では逆に難しい点、ストレートに言うと良くない点は何でしょうか。
悲しい事ですが客観的に見てRTSは廃れたと言って間違いないジャンルです。
今回はAOE2を題材に何故RTSは廃れてしまったのかという事を、プレイヤー、動画制作、実況観戦という3つの立場から考えてみます。
すでに語りつくされたことかもしれませんが、AOE4が出る前に何がダメで何故こんなことになったのか、一度書き出しておきたいのです。
なおAOE2はRTSの金字塔、代表作といって差し支えないとは思うので、基本的にはRTS=AOE2として考えます。AOE2以外のRTSは語れるほど詳しくないのもの理由の一つですが、AOE2ほどプレイ人口を獲得したゲームも思いつきません。
AOE2がRTSというジャンルを支える役割を担ったと同時に、廃れさせる原因となったタイトルであるのではないか、ということです。
前回の記事で"2と3で大きな違いが沢山あってそれぞれ別のゲームだ"といったばかりです。AOE2をテーマにしてしまうと他タイトルには当てはまらないことももちろん出てきてしまうとは思いますが、なるべく普遍的な事柄を扱っていきたいとは考えています。
コラム記事全般に言えることですが今回も長めです。あまりにも長くなってしまったので、今回は分割し、プレイヤーから見た難しさに絞ります。
■プレイヤーから見た難しさ
RTSが難しいというゲームだという事に異論はないでしょう。それはプレイしてみた人誰もがそう思うはずです。私にとっては格ゲーや音ゲーの方が難しく感じますが、客観的に見てRTSは難易度の高いジャンルです。
・難しさの種類
難しいと言っても色々な種類があります。
一般的に難しいゲームと言えば、ダークソウルシリーズが挙げられます。ステージもボスも高難易度で鬼畜ゲーと名高く、何度も死にながら攻略方法を探していくゲームデザインとなっています。私も実況動画は好きでよく見てましたし、3は自分でやってみました。
ダークソウルシリーズは難しいのにそれが売りになっていますし、ソウル系という新たなジャンルを生み出しました。
ダークソウルシリーズの持つ難しさと、RTSの持つ難しさは種類が違います。それはゲーム性という明らかな部分だけにとどまりません。正体不明のぼんやりとした難しさを、RTSをプレイした人はおそらく誰もが感じることでしょう。
それは実績の解除率を見てみると分かります。
例えばダークソウル3の中盤辺りのボス(DLC除いて21体中11体目)を倒すと解除される実績よりも、AOE2の基礎中の基礎と言われるイノシシを2体食べる実績の方が達成率は下です。

(なお、初のセーブポイントにたどり着く実績は9割、チュートリアルボスの撃破は8割、1面のボス撃破は6割程度。AOE2DEでもっとも高い解除率は船を近接攻撃で倒す実績で、ケルトでの勝利と共に5割前後。)
"チュートリアルの一番初めの項目をクリアしただけで解除される実績の達成率が6割を切る"というゲームもありますので、Steamの実績解除がどういう基準でカウントされていくのかは分かりません。
買っただけで全体数に含まれる可能性もありますし、いや起動しないと全体数には含まれないという噂もあります。難しくて投げた以外にも飽きたとか思ってたのと違った、自分のPCでは動かなかったなど理由も様々でしょう。
しかし、それはともかくとして、ダークソウルの実績達成率はAOE2と比べて明らかに高いのです。
ダークソウルは鬼畜ゲーとは言いますが、実績解除率を難易度の指標として見るならば、AOE2よりは簡単ということになります。もちろん実績解除は諸々の理由で下がっていきますが、たいていの場合難しさと実績解除率は比例するはずです。
ですが"ダークソウルよりさらに難しいゲームがRTSですよ"というのはねじれているというか、次元の違う話だというのは直感的に理解できる点です。そこにあるのは単純な難しさだけではないでしょう。
AOE2の実績達成率がこうなってしまった理由はなんでしょうか。
RTSを難しく感じさせてしまう原因は大きく分けて4つあると思います。
・とにかく忙しい
最も低次元な話をすれば、これに限るでしょう。
RTSである以上、何をするにしても時間は常に流れていき、そしてすべて自分でやらなければいけないのです。
時間の流れは強制的に行われ、プレイヤーが今起こっている事を把握したり、観察したり、思考したりするための専用の時間はありません。
様々なことをやっている中で判断していかなければいけないのです。
人気のゲームを見ていると、プレイヤーはキャラを選択しそのキャラの役割、"ロール"に従ってプレイすることになります。攻撃役、補助役、支援役と言うくくりです。前衛中衛後衛でもなんでもいいですが、やることはある程度はっきりしていて、それを達成するための条件や手段もはっきりしています。
AOE2は戦略単位ではともかく、1プレイヤー単位としては内政建設戦闘を全て自分でやらなければいけません。今どき1vs1がゲームとして成立する珍しいゲームです。
前回の記事でも書きましたが、考えなければならない項目はある程度少ない方が良いのです。考えなくて済むようにパターン化するなどプレイヤー側で対策できることもありますが、それも限度はあります。
AOE2はDEになって畑の更新が自動になったり斥候に自動探索機能がついたり研究が予約できるようになったりしましたが、そういう話では収まらないほど、RTSは思考面でも操作面でもタスクが山積みになりがちです。
・ミクロとマクロの繋がりが見えづらい
AOE2をゲームとして見た時の重大な欠点として、"ミクロとマクロの繋がりが見えづらい"ということが挙げられます。
マイクロというとAOE2では限定的な意味合いになってしまう気がするのであえてミクロといいます。
日本語で書くなら"因果関係が分かりづらい"、私自身の言葉で詳しく書き直すなら、「目の前にある判断と全体的な判断が強く結びついている癖にそれがすぐに分からない」となります。
これは判断ではなくミスでも同じことなので、例えば何か一つミスをしたときのことを考えてみます。
ドラクエでもダークソウルでもポケモンでもAPEXでも、なにかミスをすれば、それがどういう形であれ、その結果はすぐ次の瞬間に現れます。RPGなら大きくHPを失いますし、チーム対戦なら人数を一人失います。そしてそれはすぐさま未来を予想させます。
これがAOE2だとどうでしょうか。
例えばイノシシを狩るのに失敗して町の人を一人失ったとします。
「序盤の町の人一人が如何に大きいか」というのが、そもそも始めたばかりの人にはわかりづらいですが、今後10分間につき約200の資源差がつくと考えてください。
つまり町の人を一人失ったからと言って、すぐ次の瞬間負けが見えるかと言ったらそういう訳ではありません。10分20分とゲームが続いていく中で、じわじわと差がついてくるのです。
20分経って資源差400と言えば騎士3体分に相当します。
騎士3体の差は戦況を左右するほどの要因となり、そう考えれば負け確定のようにも思えますが、そこに行くまでに戦闘に勝利して相手の町の人を2人倒せれば話は変わってきます。
これを挽回のチャンスがいくらでもあると考えるのか、時間制限がついたと考えるかは置いておいて、全てにおいてAOE2は結果が遅れてやってきます。
目の前に勝てそうな敵がいたとしてもその勝敗だけを考えればいいわけではない、というのはすべての対戦ゲームに言える事ではあります。そこで勝利しても次の敵にやられてしまうのはよくある展開です。
しかしAOE2はそれがやたらと遠いのです。
損耗と10分後の状況を考えなければいけませんし、もっと言うなら、そこに勝てそうな軍を揃えるのかそれとも被害承知で軍を出さずに5分後にカウンターするのかという判断が必要になります。
もっとも短いところで言っても、「相手が騎馬文明だった場合に領主に上がってすぐ槍兵を生産するかしないか。もし生産しなければ約2分後に不利になるかもしれないがもしかしたら5分後に有利になるかもしれない」ぐらいのレベルです。
ある程度経験則や知識でパターン化できるとは言え、こんなことを到底考えていられませんし、その5分10分にも様々な事柄が起き、因果を分かりにくくします。
音楽の世界では一定間隔でビートが刻まれていると認識できるのは12秒が最長だという研究があります。ゲシュタルトが形成されるのには時間的な限界があるのです。
そしてさらに面倒なことに、AOE2は細かな操作、マイクロ技術によって戦闘結果が変動するゲームです。
操作によってユニットの性能が変わってしまうので、ポケモンでは良くネタにされる、"よけろピカチュウ!"が成り立つのです。
それが戦術戦略をよく表した面白い部分でもあるのですが、雑に軍隊をぶつけるだけでは勝てない、つまり状況的には勝つはずなのに負けてしまうという事態を生み出します。
このような因果関係の複雑さは勝敗が付いた時に不条理だという感情を生み出してしまいます。
・攻略しづらい
因果関係の複雑さ、遠さは上達に関わってきます。
前回、PDCA(計画、実行、評価、改善)を回すことがゲームを攻略するということならば、AOE2は評価を得られるまでの時間が長いから攻略しづらいゲームだと書きましたが、ここに因果関係の複雑さも加わってきます。
因果関係が複雑であるゲームほど、プレイヤーは"勝てないけど何が悪いのか分からない"という状況に陥りやくなります。トラブルシューティングを起動してもなにも解決できないPCのようなものです。
例えばダークソウルで勝てない敵がいたら、行動パターンを把握して避けたり防御する、弱点属性を見つける、レベルや装備などを整える、攻撃を弾く練習をするといった解決策があります。
これらを見つけ、自分に合った方法を選び、実行するのは簡単です。攻略サイトを見て、時間をかけてレベルアップすれば良いのです。攻略サイトを見たくなくても自分でどうにかできる範囲です。
ポケモンなら相手が取る戦術に負けてしまった時、その戦術が流行ってるのかたまたま出会って狩られてしまったのか判断できれば、次の対戦に活かせます。
FPSだとすこし難しくなりますが、ランクで棲み分けがされてるので解決策は比較的容易に見つけることができるでしょう。
ところがAOE2は違います。
どこで負けたのか、なぜ負けたのかが分かりづらいので、攻略情報を見てもどれを実行すればいいのか分かりませんし、攻略情報も「練習しよう、場合による」が大部分が占めます。
これでは「あの時どうしたら勝ってたのか」を考えることが難しいのです。
誰しも相手より自分が弱かったのは分かっていますが、ではどう弱かったのか、どうすれば改善できるのかは多くの場合見えてきません。
それなら人に教えてもらって上手く行くかというと、そういうわけでもありません。それで上手く行くのであれば、そもそも攻略情報はもっと出しやすいのです。
良い選手が良い教師であるかどうかは別の問題です。多くの業界で教えるのに免許や専用の職業があるように、教えるにも技術が要ります。人口が多くメソッドがある程度確立された業界ならばこの分離は上手く行くでしょうが、AOE2はそういうわけでもありません。
因果関係が分かりやすいゲームならまだ話は分かりやすいのですが、そうでないなら「問題はそこじゃない」が良く起こってしまうことでしょう。
・プレイしていて地味
これは攻略という観点からは外れるのですが、AOE2はプレイしていて感覚的に気持ちのいい瞬間というのがあまりありません。
槍兵満載の破城槌を敵の城に突っ込ませるとか、騎士の一団を内政地に放り込むとか、投石機が射手にクリティカルヒットしたとか、そういった意識上の類です。
デジタルゲームとして見た時、気持ちのいいタイミングで気持ちのいい音が鳴る、丁度いいタイミングで光るだとかカメラがズームするなど、そういった感覚に直接訴えかける演出は必要不可欠です。
AOE2にはそれらが全くありません。むしろ、印象に残るのは転向や攻撃されたときの警告音といった不快な音の方が多い印象です。
好みの問題というか慣れれば気になりませんが、デジタルゲームとして見た時これは致命的な欠点です。
この問題はAOMやAOE3ではかなり意識されている一つの部分だと思います。
ファルコネット砲が軽歩兵を吹き飛ばしたとき+6の数字が大量に出るだとか、優勢な時、ピンチな時には音楽が変わるといった変更が見られます。
AOE3の革命の曲だとか、AOMで隕石を降らせているときのエフェクトは、プレイヤーのテンションをぐっと引き上げます。
プレイしていて感覚的な快感が得られるのは重要です。それをもう一度味わいたいと思うからです。
RPGで退屈なレベル上げが我慢できるのも、アクションゲームでコンボやパリィを練習できるのも、もちろん得られる効果に期待するとこもありますが、達成、成功した時の気持ち良さを得たいからです。
そういった意味で、AOE2はプレイしていてつまらないゲーム、飽きてしまうゲームだと言えるのではないでしょうか。
・おわりに
今回はここで終わりますが、話はまだ途中なので、解決策だとかまとめと言ったことはやらないでおきます。
次は動画制作、実況解説という場での難しさを考えてみたいと思います。
面白かった、役に立ったという方は"スキ"ボタンのクリックやフォローなど、よろしくお願いします。モチベーションアップにつながります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
