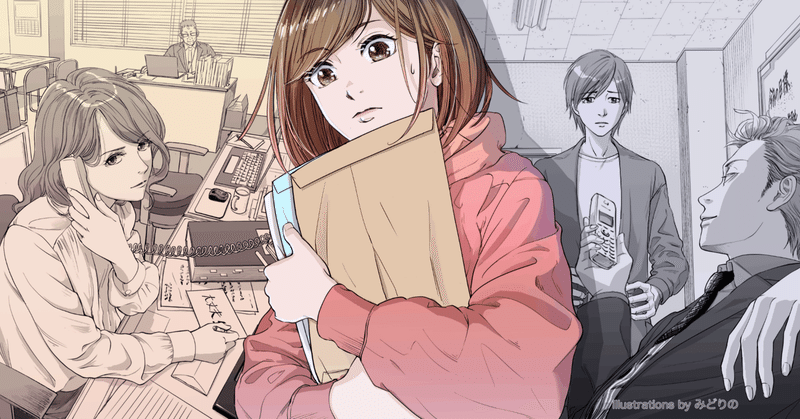
第1話[22]~[最終回]まとめ/小説「やくみん! お役所民族誌」
第1話「香守茂乃は詐欺に遭い、香守みなもは卒論の題材を決める」
【前回】
[22]二次面接
*
池袋は落ち着かない街だ、と充は思う。正直あまり好きではない。
上京した当初こそ、茗荷坂のアパートから一番近い「大都会」としてもの珍しく、週末になると足を運んだ。しかし、それも二ヶ月もすれば飽きた。生活に必要なものは身近で済むし、何より池袋は人が多すぎる。人が多ければ、充が苦手とするタイプの人間とすれ違う機会も増える。直接関わりがなくとも、腕や顔に大きなタトゥーを施した大股大声の男たちを見かけるだけで、充は呼吸が浅くなるのだ。
池袋は華やかな表通りから幾筋も路地が左右に伸びている。用事があるわけでもないのに足を向けようとは思わなかったけれど、立ち止まって路地の奥を覗き込むことは、しばしばあった。風俗店、アダルトグッズ、雀荘、バー。路上にも頭上にも扇情的な色の看板が並ぶ猥雑な風景は、何かしら充の眼を誘うのだ。しかし、興味よりも恐れの方が遥かに勝り、先日までこうした路地に足を踏み入れたことはなかった。
先日──そう、意を決してアンゴルモアを訪れた日。今日は二度目になる。
雑居ビルの入り口から廊下を奥へと進み、扉の前に立つ。紫色を基調とした頭上の看板には「Angolmois」の装飾的なアルファベット、その下に小さく「アンゴルモア」と仮名書きされている。そして「休憩中 開店15時から」の札、時間のみ手書きだ。
これは、入ってもいいのだろうか。それとも邪魔してはいけないのだろうか。哲さんはここを指定した。なら入っていいのか。もし哲さんの話が通ってなかったら。グルグルと思考が拡散しまとまらずに、30秒。こうしていても仕方がない。混乱したまま、ドアノブを捻る。
鍵はかかっておらず、僅かに開いた扉の隙間からハーブの煙が鼻をくすぐった。
そのまま扉を引いて中を覗き込むと、室内で立ったままパンを頬張る長髪の男と目があった。頭には濃緑のバンダナ、淡い青のスウェット上下。先日のコスチュームとは違う地味な出立で一瞬分からなかったが、よく見れば龍神ズメウだ。
「あ、こんにちは」
充は目線を据えたまま軽く頭を下げる。龍神は片手を上げて充をとどめ、少しの間モゴモゴとパンを咀嚼し飲み込んでから、口を開いた。
「やあ、いらっしゃい。どうぞ中へ」
充は歩みを進め、後ろ手に扉を閉じた。
「哲さんはもう来てるよ。今日は悩み事相談じゃないから、奥の事務室でね」
言いながら、龍神はパンを持った左手の甲でカーテンを開き、右手で奥の扉をノックする。そうか、まずノックをするんだった、と充は先ほどの自分の行動の非礼に思い至り、非常識な奴だと思われたのではないかと胸が苦しくなる。
扉の向こうから「どうぞ」の声がした。
龍神は右手でドアを押し開き、「香守くん、来ましたよ」と中に声をかけてから、振り向いて充を中へと促す。
その部屋は、ものものしく黒ビロードに覆われた占いの部屋と対照的な、簡素な事務室だ。広さは15畳ほど、奥の扉がさらに別室があることを窺わせる。事務机が三台、そのうち二台は向かい合わせに島を形成している。残る一台は少し離して二台を見守る位置にある。
部屋にいたのは二人。まずドアのすぐ脇に、昨日もいた高身長の男──マサトシが立っていた。哲さんは部屋の隅の小さな応接セットに腰を下ろし、充の顔を見ると笑って手招きをする。
「じゃあ、俺、あっちにいますね」
龍神の言葉を、哲さんは「どうせなら、一緒に聴いてよ」と留めた。
「そうですか、なら」龍神は上埜の横に腰を下ろす。代わりにマサトシが無言のまま扉の向こうに消えた。無人になる占い部屋で侵入者に備える。ボディガードとしての振る舞いだ。哲さんも龍神もそれが分かっている、だから無言の行動でいい。
充は二人の対面に座った。明るいグレーのファブリックは適度なクッションで、手で触れるとざらりとした感触。昨日大崎のオフィスで座ったものと比べて、金額は半分の質素な作りだ。
「じゃあ、質問に答えるよ。なんでも聞いて」
「昨日おっしゃっていたこと、もう一度はっきり確認させてください。大事なことなので。みなさんは、犯罪者なんですか?」
一瞬、龍神の頬が膨らみ、哲さんから顔を背けた。笑いの衝動を堪える仕草だ。しかし哲さんは真面目な顔で頷いた。
「俺や、昨日君が会った連中は、そうだよ。この人」と龍神を指差し「は違う。違法な商売はしてない。だよな?」
「……そのつもっ、つもりっ、ぶははははっ」
龍神が決壊した。「何笑ってんの」という哲さんにも笑いが少しだけ感染する。
「いや、ぶははっ、だって、初手からどんだけストレートな質問なのかと。ひー、腹痛え」
龍神はほとんどソファから屑折れそうに身を捩って痙攣した。
充は、どこが笑えたのかよく分からなかったけれど、悪い空気でないことは分かった。歪んだ嘲笑ではない、龍神の素直な反応。それで肩の力が抜けた。ここに向かう道すがらから焦燥で頭脳が空回りしていたのが、ゆっくりと、ギアが噛み合う。
「犯罪者は、嫌い?」哲さんが笑いながら問うた。
「嫌いです。でも、もっと嫌いなタイプがあるので、相対的にはマシです」
最後の一言がまた龍神のツボに入り、ついにソファから床に転がった。しかし、哲さんはもう笑わない。
「もっと嫌いなタイプって?」
ふっ、と龍神の笑いが引いた。哲さんは彼の核心に触れようとしている。
「ん、ん……」と少し考えてから、充は口を開いた。
「うまく言えないんですけど、他人を見下す人間とか」
哲さんは黙って続きを待つ。その気配を察して、充はまた少し考えた。
「自分ができるからって、できない他人を馬鹿にする人。馬鹿にされた方がどんな気持ちになるか、分からない人。分かっていてそれを楽しむ人。大嫌いです」
「犯罪者の中にも、そういう奴はいるよ。もしかすると、一般社会より多いくらいかも知れない」
「でも、犯罪者かどうかは法律の問題です。人格とはカテゴリーが違う」
哲さんは黙って充を観察している。2秒の沈黙を破ったのは、ソファに戻った龍神だ。
「はは、日常会話でカテゴリーなんて言葉を使う奴、哲さん以外に初めて会ったかも──あ、これは馬鹿にしてるんじゃないよ。頭の回転に追いつくように言葉を続けようと思ったら、ニュアンスの深い単語になる。そういうことだと、俺は思ってます、よ?」
最後は確認するように哲さんの顔を観た。しかし哲さんが反応するより前に、充が嬉しそうな声を上げた。
「そうなんです、言葉にすると、そういうことなんです!」
充の笑顔は子供みたいだ、と上埜は思う。この表情は、彼の警戒心と緊張が緩んでいることを示す。言葉にならない自分の胸の内を的確に言い当ててもらえた時の喜びだろう。
龍神を同席させてよかった。もともと人好きのする性格に加えて、占い師のキャリアが長いだけに、彼の対人スキルは様々な場面で有効に働く。
「最初の質問で、深網社が犯罪組織だと確認できた。それを踏まえて、次の質問が続くのかな」
「はい。哲さんたちは、どうして犯罪を犯すんですか?」
少し前の雰囲気なら、龍神はまた笑いの発作に襲われていただろう。しかし、もう空気が変わった。
哲さんは思案顔で宙を仰いだ。
「難しいことを訊くなあ。うーん、ここまでの歩みを順序立てて説明するのは、きっと、君の聞きたいこととは違うね──そうだな、さっきの君の言葉に繋げるなら、社会から見下されてきた者が社会を支配できる手段が、犯罪だった。弱者が強者に勝てる下克上の手段が、あらかじめ犯罪とされていた」
一旦言葉を切る。充はまっすぐにこちらを見つめ、表情は変化がない。言葉の意味を受け止めようと脳が集中しているのだろう。多少小難しい話をしても、ついて来れる。そう踏んだ。
「犯罪とは何か。君はさっき、法律の話だといったね。そう、そこに本質がある。人は本来自由だ、何をしてもいい。しかしそれでは不都合があるから、法律で様々な規制をする。刑法や個別法で一定の行為を禁止し、違反者に刑罰を課すルールを定めた。その行為が、犯罪と呼ばれる。犯罪に対しては警察の捜査が及び、逮捕起訴されれば裁判を経て刑に服する。前科が記録され、その後の人生にも様々な制約が付きまとう。それが嫌なら犯罪行為をするな、というメッセージだよ」
ここで哲さんは言葉を止めた。充は促されているような気がして、「誰の、ですか?」と尋ねた。
「強者だよ。法律を制定する者は、選挙で多数派の信任を勝ち得た政治家だ。その原案を作る者は、競争試験をくぐり抜けた公務員だ。政治家、公務員、有権者の多数派。それは強者だ。つまり法律とそれが支える社会は、強者に都合良くできている。けれども、そのように美しく整えられた法律や社会では生きづらい弱者が、世の中にはいる。弱者として、苦しみながら生き続けるか、それとも、苦しみから逃れるために自ら命を絶つか」
充の目元が痙攣した。
「それとも、社会のルールを踏み越えて、自分らしく生きるために戦うか。どの道を選ぶのが正解なんだろう。誰にでも通用する正解なんて、ないさ。俺たちは戦う道を選んだ。その中に、犯罪とされる行為も含まれていた。以上、君の問いに対する答えになっていたかな?」
「あ、はい、まあ、大丈夫です」歯切れが悪い応答に聞こえるが、充に他意はない。「昨日のお話で分かりにくかったところも、よく分かりました。あと──暴力行為はありますか? 社員同士でも、会社の外の人に対しても」
「ないよ」
哲さんは即答した。隣の龍神も表情を変えずに、伏し目で聞いていた。
「あの、不良の人とか、乱暴するじゃないですか。この会社では、そういうのはないんですね?」
「うん、ない。そこは安心して」
先ほどまでの饒舌から一転した端的な回答、それ以上の説明はなかった。
「次は給料の話だね」哲さんは自然に話題を先に進める。「グループのどこに配属するかにも依るけど、目安としてフルタイム勤務で固定給月30万、税務申告なんてしないから手取りだよ。仕事の役割に応じた臨時歩合給は上限なし。0円が続くこともあれば、五十万とか百万の時もある」
充の表情に驚きが浮かぶ。父からの毎月の仕送りは12万円、システム会社のデータ入力のアルバイトは時給1,200円で月5万円ほどになる。社会人経験のない充にとって、提示された額は大金だ。
「でも、君は大学生だ。一年生だと授業も多くてそれほど時間の余裕があるわけじゃあないだろう。お試しを兼ねて、まずはアルバイトということでもいいよ。その場合は、そうだな、固定給15万、歩合は役割に応じてということで。不足に思うなら、いくら欲しいか言ってくれ」
「不足なんて、そんな」
「そう?」
金が目的というわけではないらしい、と哲さんは分析した。ならばやはり。
「今度は逆に、尋ねてもいいかな。君は深網社の仕事に興味を持ってくれたみたいだ。俺たちの仲間になって、これまでの弱者の生き方を変える、その決心は、ある?」
「……迷って、ます」
充は前屈みに目線を伏せた。軽い緊張と自己防衛の体勢、深追いはできない、と哲さんは判断し、充の言葉を待った。
3秒、4秒、5秒。昨日のような場面緘黙とは雰囲気が違う。
テーブルに置かれていた哲さんのスマホが鳴動したのはその時だ。画面には発信者キイチの名。いいタイミングだ。
「ちょっとごめんね」
哲さんはそういってスマホを手に取った。
[23]澄舞と東京、姉と弟
*
インターンシップ二日目午後。午前中に検討した法令違反事例をもとに30分ほどディスカッションを続けた頃、二階堂に電話が入った。
「ちょっと外します。その間、そうね、明日作る啓発素材について二人で相談してて」
二階堂がパーティションの向こうに姿を消すと、みなもは隣の小室に真面目な顔を向けた。
「あらためて。えふん。──昨日は我が家のことでバタバタしちゃって、ごめんなさい。啓発素材の話し合いがほとんどできなかった」
「謝らなくていいよ。香守さんも、おばあちゃんも、悪くない。悪いのはナチュラリズムの連中でしょ」
「そういってもらえると、助かります」と頭を下げてから、みなもは両手を口の前に広げて小さな声で「いよっ、男前」と付け足した。本人は気づいていないが、深刻になりそうな時におちゃらけて場を和ませようとするのは、父しゃん由来だ。
これに対して小室は胸を張って軽く手を挙げ「君い、本当のことをいっても世辞にはならんよ」と低い作り声と微笑を返し、すぐに真顔になる。
「もう時間がないから、決めてしまわなきゃね。エシカル消費で行く? ぼくはそれで構わないよ」
「あ、ごめん、気が変わった。あのね、やっぱり悪質商法でやりたい」
小室は、へえ、という顔をした。そのままみなもが言葉を継ぐ。
「おばあちゃんが詐欺だの悪質商法だのにやられちゃってるの見たら、他人事じゃないもの。テーマは悪質商法被害防止、どう?」
「オッケー、同感だ。興味を持って取り組めるのが一番だよ」
テーマが決まると、次は具体的なモチーフと啓発媒体だ。モチーフはすぐには決まらなそうなので、先に媒体を考えることにした。
「読みやすさという点ではマンガが一番なんだけどなあ。小室君、絵、描ける?」
「描けるように見える?」
「見える見える」
「描けないって。美術は五段階の2だったよ。香守さんは?」
「描けるように見える?」
「うーん、無理かなw」
「むっ。そういわれると、私の画力を見せたくなるなあ」
みなもはおもむろに緑のボールペンを握り、ルーズリーフの白紙を開いて小室を睨みながらペンを動かし始めた。どうやら小室の似顔絵を描こうとしているらしい。小室の目の前で、緑の線が重ねられていく。
「……ぷっ」
小室が吹き出した。みなもも笑いながら、それでもペンを動かし続け、やがて「似顔絵」が出来上がった。
「くはははは、いやあ、香守さんは画伯だったかあ」
「目があって鼻があって口があって、ほらそっくり」
「やめ、やめて……腹が痛い……」
小室は声を押し殺して笑い続けた。つまりは、そういう絵だった。歪んだ線が不揃いなパーツ構成の記号的な顔を象る、前衛作品だ。
「残念ながら私たちコンビでは、マンガは諦めるしかないね」
こくり、こくりと小室が痙攣しながら頷く。
「あ、それともこの絵で推して参る?」
はははははっ、ひいっ、と小室が決壊した。
「君い、インターンシップ中にそんなに大笑いしてはいかんよ」
みなもは先ほどの小室の口調を真似た。笑いのツボに入った相手には追い打ちを掛けていくスタイル。
そこに二階堂が戻ってきた。机に突っ伏す小室とその横で誇らしげなみなもを見て「え、なになに?」と笑いながら、イスに腰を下ろす。
少しの間、2人が落ち着くのを待って、二階堂は口を開いた。
「ごめん、ちょっと作業中断ね。今の電話、ナチュラリズムのオカダさんだった。この後、上司から大事な連絡をするって。掛かってきたら返金交渉再チャレンジするから、また横で聴いてて」
*
哲さんとキイチとの通話は短かった。「澄舞県消費生活安全室にアポ取りました、担当者の二階堂主任が対応可能です」というだけの内容だからだ。
午前中にキイチから香守茂乃の件で澄舞県消費生活センターが動いていると聞き、哲さんは少し思案をした。充が社員になる気があるのなら、祖母をハメるわけにはいかない。充の様子と、センターの反応、そのふたつから対応を判断したい。そう考えて、充が来ている間にセンターに連絡が取れるよう、キイチに調整を命じていた。
哲さんは充に向かって微笑んだ。
「この後、ちょっと仕事の電話を掛けなきゃいけない。少し待っていてもらっても、時間は大丈夫かな?」
充は壁に掛けられた時計を見た。1時45分。
「授業があるから2時半にはここを出たいんですけど」
「うん、わかった」
哲さんは応接から事務机に移動した。
「電話借りるよー」
哲さんの声がけに龍神が「あ、白いコードレスが転送掛けてます」と応えた。幾重にも電話転送サービスを噛ませて発信番号を偽装するのは、悪質商法の基本だ。アンゴルモアは深網社グループでも違法性を帯びない部門だが、顧客の身辺調査の便などから一応そうした回線を確保していた。
哲さんは受話器を手にとり、ふと思い出したように充に尋ねた。
「ところで香守君は、大学は続けたい、ということでいいのかな?」
「あ、はい」
端的な返事がすぐに返ってきた。哲さんは真意を測る眼差しで充を見た。タイミングを外した質問は、心の隙を突いて反応を見る技法だ。充の反応は、極めて自然なものだった。
充の匿名ブログには、学友や教官への恨み言が綴られている。人間関係としては、大学にも居場所はないと感じているように思ったが──。
まあ、その洞察は後回しだ。
「今から電話をかける先はね、香守君。偶然なんだけど、君の故郷の澄舞県の県庁だよ」
充の祖母の案件であることは、ひとまず伏せておく。後日家族経由で知る可能性は想定している。もしかすると、これから掛ける電話で相手方から祖母の名が出てくるかもしれない。仮にそうなってもなお、彼の心を乱さない対応を、示しておく必要がある。
「私たちの仕事は、消費生活センターとの交渉が欠かせない。いずれ君にもそういう機会が訪れるだろう。様子を聴いておくといい」
*
机上の電話が鳴り、二階堂は受話器を取り上げるのと同時にスピーカースイッチを押した。音声は周囲に聞こえるが、こちらからの声は受話器を通じてのみ送るモードだ。これで傍らにいるみなもと小室、周囲の室員にも会話の内容が伝わる。
「はい、澄舞県消費生活安全室、二階堂です」
会話時より少し低いトーン、他所行きの声。受電時に所属と氏名を名乗るのは澄舞県庁の標準作法だ。
「二階堂さんですね。私はナチュラリズム健康革命協会のシモガキと申します」哲さんの偽名のひとつだ。
「シモガキさん。社長さんですか?」
「いえ、主に渉外系の顧問を務めております。弊社のオカダから、二階堂さんとトラブルになっていると聴きました。何か法律上の問題だそうですがよく理解できないというので、私が代わりに承ります。特商法の関係ですか?」
特定商取引に関する法律の消費者行政現場での略称「特商法」を、シモガキと名乗るこの男はさらっと口にした。少しは話が通じそうだと、二階堂は思った。
そこから3分あまり、主に二階堂から、これまでのやりとりの要点を説明するフェーズが続いた。
哲さんの電話機もスピーカーモードにされていて、会話は充にも聞こえていた。姿の見えない相手の声に意識を集中する。高校では政治・経済ではなく倫理を選択していたから、法律や行政についてはあまり知識がない。それでも、深網社傘下の会社が独り暮らしの高齢者に大量の健康食品を売りつけたことが「とくしょうほう」の「かりょうはんばい」に当たる違法行為として問題視されていることは理解できた。
「なるほど。おっしゃる事は大体分かりました」流れを受けて哲さんが口を開いた。「うちのオカダから聞いた話といくつか食い違っているので反論もしたいんですが、まずそちらの用件の中心を聞かせてください。澄舞県庁は、うちに何を求めているんですか?」
「違法な行為は止めてください」
「ふむ、返品を認めよ、ではなく?」
「具体的な返品・返金は消費生活センターの相談員が別途交渉しています。私は本庁の特商法担当として、事業を適法に行っていただくようお願いをしています。ただ、過量販売には取消権が認められており、これを妨げることは違法ですので」
消費者行政における相談員と行政職員の職務は、明確に区切られている。個別の消費者被害の救済支援は相談員の役割で、行政職員は法令違反の是正指導を担当する。
そもそも消費生活センターに配置される相談員は、国家資格「消費生活相談員」またはそれに準ずる資格を持つスペシャリストだ。比較すれば、まったく関係の無い部署から異動してきて3年後にはまた外へ出て行く行政職員は、素人みたいなものといえる。もちろん公務員試験と入庁後のキャリアを基盤として、どのような所属に移動しても短期間で職務関係知識を深く身につけて行くが、それも自分の担当職務に限られる話だ。
「わかりました。うーん、そうだなあ……取り敢えず、反論しますね?」
哲さんはにっこり笑ってそういった。もちろん電話で話をしている二階堂にはその表情は分からない。目の前で哲さんを見ていた充は、なんだか楽しそうだな、と思った。
「特商法の過量販売規制は承知をしています。訪問販売と電話勧誘販売が対象で、当社の通信販売は対象ではない筈ですが?」
「そこは先ほども申し上げたように、最初の注文は通信販売でも、途中から電話勧誘による販売に切り替わっています」
「それ、いつからかご存じです?」
さらっと哲さんが発した言葉に、二階堂は言い淀んだ。茂乃からの聞き取りでは販売形態の切り替え時期までは特定できていないからだ。
2秒の沈黙からそうと察した哲さんが、言葉を継ぐ。
「確かにこのお客さんには、最初は毎回ハガキで注文票をいただいていたのを、新製品のお薦めを機会に電話で承るようにしました。でもそれ、二ヶ月前ですよ? それ以前とは別の商品を、御家族を含めて五人分を一ヶ月分ずつ、まだ二ヶ月。これのどこが過量なんですか」
「……御家族?」
「ええ、息子さん夫婦と、お孫さんが二人。同居ではないけれど近くに住んでいるとお聞きしています」
二階堂は受話器を耳に当てたまま、みなもを見上げた。弟の充は東京にいるから、家族構成は正しい。みなもは小さく「合ってます」とささやいてそれを伝えた。
シモガキと名乗る男は、丁寧な口調のまま流暢に主張を並べた。過量販売規制をはじめ特商法の規制については社員教育を行っていること。通信販売の段階から、家族みんなで健康になりたいからといわれて、商品を購入されていたこと。定期的に「食べ残しはありませんか」と確認するなど丁寧に聴き取りをして、商品の販売量などが適正かどうかを判断していたこと。
もちろんこれは、哲さんの嘘だ。キイチから聴き取った状況をもとに、適法な状況をでっち上げる。多くの商品を販売したとしても、正当な理由があれは、違法性は問われない。認知症が進んでいるとの報告から、行政も詳細な証言は得ていない筈だと踏んでのことだ。
「当社はこのように認識しています。違法性があるなら改めますが、正確な要件事実を指摘していただけませんか」
要件事実──午前中に聞いたばかりの言葉だ。法律に詳しく一筋縄でいかない相手なのだと、二階堂は知った。
同じ事をみなもも感じていた。相手はこちらの家族のことを知っている。悪質業者なのだとしたら、それは怖いことだ。そうではなく善良な事業者なのだとしたら、おばあちゃんの認知症は日常生活に支障のあるレベルで、相手に迷惑をかけたことになる。どちらにしても、雰囲気は相手方に有利な気がした。
みなもは無意識に体を緊張させ、手にしていた資料封筒を胸の前でかき抱いた。その身じろぎを見て、二階堂は彼女の表情に目をやり、動揺を察した。受話器を左手で耳に当てたまま、机上にあった古封筒の裏に黒のボールペンで「大丈夫?」と記す。それでみなもは自分の緊張に気づき、慌てて頷いて無理に笑顔を作った。
一方、シモガキと名乗る哲さんの傍らでは、充がやりとりに聴き入っていた。この人は凄い、役所の人の論難に一歩も引かず、むしろ言い負かしそうな勢いだ。基礎となる法律知識、論理の適用と展開。間違いなく、頭がいい。そして意思の力。自分にはないもの、自分が憧れ求めるものを、この人は持っている──。
澄舞と東京、消費生活センターと悪質事業者。距離も性質も隔たる両者の側で、姉弟がそれぞれの想いを抱いていた。
「要件事実を明確に示せないのであれば、今日のこのお電話は行政指導の段階ですね?」
「──そういうことです」
「つまり行政手続法に基づいた任意の協力を求めておられると、こう理解してよろしいですか?」
「そうなります」
法律に詳しいなら話が早いと最初に思ったが、これは早すぎる。未調査で確実な違法性を指摘できない今の段階では、強制力のない行政指導しかできないと、シモガキは分かっている。今日はこれ以上追及できない、来週後藤さんに行政調査を掛けてもらって──。
「では、協力しましょう」
「えっ」
二階堂はシモガキの言葉の意味を捉えかねた。
「法律に触れるかどうかは別として、このお宅では当社の商品が食べ切れず大量に余っているという事実を、今こうしてお聞きしました。発送準備中のものは差し止めて、今後も契約はしません。未開封のものの返品返金は、消費期限の問題もあるので全てというわけには行きませんが、可能な範囲で対応するようオカダに指示しておきます。具体的な話は、オカダとそちらの相談員の、ええと、久米さんとで詰めていただくということで、よいですか?」
「あ、ええ、はい、ただ──」
「二階堂さんのお役目は、我々に適法な商売をさせることでしたね。他のお客さんも含めて状況をあらためて確認させて、改善を要するものは改善を図ります。社員もあらためて教育しておきます。他に何かありますか?」
急転直下の展開に二階堂は肩透かしを食らった気分だが、悪い方向ではない。
「いえ、分かっていただけたのであれば、いいんです」
それから二言三言言葉を交わし、受話器を置く。それからみなもを見上げた。
「状況、分かった?」
「解決したんですか?」
「そうみたいね」
みなもの体から緊張がほどけた。はああ、と大きく息を吐いて上半身を前に傾ける。
「……よかったあああっ」
先程までの不安な気持ちが嘘のようで思わず大きな声を出してしまい、みなもは口に手を当てた。二階堂は笑ってポンとみなもの腕を叩いた。その掌の暖かさが、みなもには心地良かった。
「でも、返金額の交渉はこれからだから。久米さん、お願いね」
二階堂は低書架の向こうから上半身を乗り出して聴いていた久米に言った。
「はい。こんなにうまく行くなんて信じられない。二階堂さん、ありがとう」
「私は、あー、ほとんど何もしてないというか」
「そうだね、手玉に取られたね」野田室長がいつの間にか傍らに立っていた。
「ですね、向こうは関係法令をよく理解している。実はまっとうな業者だったのか、それともよほど巧妙な悪質業者か。……行政調査は中止ですか?」
「そうだなあ。今のやりとりを踏まえると、違法な過量販売を繰り返している悪質業者という心証はないねえ」
香守茂乃の案件は和解の道筋が見え、コンプライアンスの徹底も約束された。こうなると、他の被害相談が出てこない限り、特商法調査案件としての優先順位は低くなる。
「まあ、結論は来週後藤さんが出てきてからにしようか」
「わかりました」
二階堂は壁の時計に眼をやる。
「時間が押してきたね。さっきの続きに戻ろうか」
二階堂の言葉に、みなもと小室は頷いた。
*
「どうして、返金を約束したんですか? 交渉は哲さんの方が有利に聞こえました」
充の言葉に、哲さんは通話を終えた受話器を軽く振って見せた。
「有利な状況を作った上で、戦略的撤退をしたのさ。これで向こうは調査する理由がなくなる。ナチュラリズムは規制に触れる商売はしてるけれど、詐欺じゃないからね。行政との駆け引きは、まっとうな企業の顔をしたまま、引くべきタイミングで引く。それが商売を続けるコツだよ」
受話器を机上に置き、哲さんは立ち上がると充の正面に立った。充は自分より少し背の低いこの男に真っ直ぐに見つめられ、眼を泳がせた。
「香守君。世の中で他人に支配されずに生きる術を、君に与えよう。深網社に入ってくれるね?」
充はおずおずと頷いた。
「よし、決まりだ」
哲さんが差し伸べた右手を、充は握った。哲さんの掌の冷たさが、適度な距離感を感じさせて、充には心地良かった。
「今日はもう時間がないね、これからのことはまた夜に電話するよ」
「はい。……それでは、失礼します」
充はぺこりと頭を下げて出口に向かう。その背に哲さんが声をかけた。
「あ、ひとつだけ」
充は足を止め、上半身だけ振り向いた。
「大学は、可能な限り続けたまえ。つらくなったら辞めていい。それまでは、教育資源を享受できる大学生の身分を手放さない方がいい。そこで学ぶ様々な知識は、必ず俺たちの仕事の役に立つ。いいね?」
充は一瞬とまどいの表情を見せたが、素直に「はい」と頷いて、ドアノブに手をかけた。
[24]二人のアナウンサー
*
澄舞県庁の退勤時間は17時15分。二日目のインターンシッププログラムを終え、みなもは県庁前のバス停から澄舞大学行きのバスに乗る。すぐ先の県民会館がバス路線の結節点になっているので、この時間帯は次々とバスが来て、大勢の人を乗せていた。
Lineで秋宮秀一に帰宅の目安を尋ねると、ノー残業デーの水曜日なので19時くらいには帰れるという。ならばと大学近くのスーパーで食材を買い込み、頃合いを見計らってグリルで鮭の切り身を焼き始めた。
「ただいまー」
「おかえり。うん、ナイス自分」
「どしたの?」
「秀くんレーダーが優秀だから、ちょうどお魚が焼き上がるところ」
今夜の2人の食卓は、炊きたてのご飯と焼き鮭、出来合いの牛蒡サラダ、それにオニオンスープ。小さな正方形の座卓、対面ではなくL字方向に並んで座る。食器の配置は難しいけれど、少しでもくっついていたいから。
食事をしながら、みなもはこの2日間のあれこれを話し続けた。秀一は適度にコメントを挟みながら、まるで小学校であったことを一所懸命話す娘に相対するお父さんのような、慈愛の面持ちで耳を傾けた。
今日、二階堂とナチュラリズムの交渉で茂乃への返金の方向性が決まった後、みなもはすぐに朗に電話をした。朗は仕事を休んで茂乃とともに警察で事情聴取に臨んでいた。みなもの知らせを朗から聞かされた茂乃の歓喜の声が、スマホを通じて聞こえていた。
「インターンシップ先が消費生活センターじゃなかったら、こんな風におばあちゃんを助けることはできなかった。なんて運がいいんだろう」
「日頃の行いがいいんじゃない?」
「それ。おばあちゃんがいう信心のおかげって奴ね」
茂乃は熱心な仏教徒で、朝夕に仏壇にお経を上げ、檀家寺の月二回のお参りを欠かさない。みなもは法事くらいしかお寺に行くことはないけれど、早くに夫をなくしたおばあちゃんの大切な心の拠り所なのだろうと感じていた。
食事を終え、秀一が洗い物、みなもはお風呂の用意を分担する。手を動かしながら話は続き、二階堂から聴いたインタビュートラブルの話に及んだ。
「ああ、それ、うちにも話が来たよ。使うなと言った映像を放送したって」
昨日、生活環境総務課の河上補佐が広報課を訪れ、生活環境部として今回の事案は看過できず、広報課を通じてすまテレに抗議して欲しいと申し入れていた。広報課の仕事柄、各局の朝・昼・夜の報道番組は三台のレコーダーに分けて毎日録画している。課長の求めで秀一がリモコンを操作し問題のシーンを再生した。「見た感じはむしろ勢いがあるし、全体にいい構成だけどねえ」と広報課長は言ったが、約束違反を見過ごせないという生活環境部の意向にも筋はある。広報課マターとしてすまいぬの件もあり、合わせて抗議するに至った。
もちろん、職務で知り得たデリケートな情報を庁外で軽々しく話すわけには行かない。気を遣いながら、秀一は話を最小限に継いだ。
「柳楽アナは、一昨日の朝のテレビでも、すまいぬにちょっと強引なインタビューしてたでしょう。問題が続く時には続くね」
「問題なのかなあ。家で放送見てたけど、二階堂さん、カッコよかったよ?」
「あ、それは俺もそう思った」
「そういえば、明日すまテレに行くよ。ラジオ収録の見学」
「へえ、俺もすまいぬの収録ですまテレ行くんだ。何時頃?」
「午前中、時間はわかんない」
「もしかすると会えるかもね」
ジャスミンティーを入れて、二人はあらためて座卓につく。白磁のカップを口元に近づけると爽やかな香りが鼻をくすぐり、ひと口含めば口中に温かなものが膨らんで、喉から胸、お腹へとゆっくり落ちていく。
「あー、沁みるなあ」みなもは緩んだ笑顔を秀一に向けた。「昨日今日、ずっと緊張してたんだって、今更気付くよ」
「大変だったでしょう。お疲れさま、あと一日だね」
「あと一日頑張るために、秀くん分を補給しなきゃ」
カップを置き、すすす、と修一にくっついて両腕で抱き締めた。そのまま鼻先を秀一の首の横に押し当てる。すうっ、はふう。微かにツンとしたものが混じる香り。
「んー、一日働いた後の秀くんの匂い。これはこれでよしっ」
「えー、変態ちゃんですかあ」
「へへへ、吸わせろー」
くんくんくんくん、と犬のように首筋の匂いを嗅ぐ。たまらん。そういや昨日、母しゃんも父しゃんの匂いを嗅いで悦んでたな。遺伝かな。
「俺も働いて疲れたー。みなちゃん分を補給しなきゃ」
今度は秀一がみなもを抱きしめて首筋に顔を埋める。そのままみなもは身を横たえ、秀一が上から覆いかぶさる体勢になった。
「一昨日の朝から我慢してたっけね」とみなも。
「お預けは、もうおしまい」と秀一。
みなもの首筋にキスを、二回、三回。顎から頬へと移って、唇が触れ合い、舌を絡める。粘膜を弄りあうと、甘美な痺れが脳と全身にゆっくりと沁みていく。
秀一の掌が服の上からみなもの胸を包んだ。恋人の手に体を触れられることの心地よさ──。
おぱーい、といいながら母しゃんの胸に手を伸ばして邪険に撃退される父しゃんの姿が脳裏をよぎった。
「……ぷっ」
突然みなもが吹き出したので、秀一は怪訝な顔をした。
「なに?」
「いやあ、なんでもなあい。こっから先は、お風呂の後でね」
若い二人の夜は、始まったばかりだ。
*
インターンシップ最終日。
二階堂の運転するロシナンテは、今日は機嫌の良いエンジン音を鳴らしていた。
松映市街地は、広大な澄鶴湖(すんずこ)から東の央海(おうみ)へ流れ込む平均川幅140mの央梁川(おうはしがわ)によって、南北に分割されている。橋北地区には県庁・市役所などの官公庁や国宝・松映城などの歴史景観地区があり、橋南は松映駅を中心に商業地区を構成している。
駅から橋を渡ってすぐの央梁川北岸に澄舞テレビジョン本社屋が新築移転したのは、わずか三年前のことだ。みなもは中学生の時に学校行事で街外れの旧社屋を見学したことはあるが、中心市街地の新社屋は初めてだ。屋外駐車場で車から降りると、秋晴れの空の下、広い敷地を生かした低層の真新しいビルが鈍い黒銀に輝いていた。
二階堂を先頭に、みなもと小室は玄関に向かう。玄関前には、台車で大きな荷物を運ぶ若い男女の姿があった。男は紺のスーツ姿、女はゆったりしたベージュのズボン、白のブラウスの上から水色の作業着のような上着を羽織っていた。
「あ、見覚えあるな。県の広報課の人だよ」
二階堂がいうより先に、みなもは男が秀一であることに気付いていた。待ち合わせたようなタイミングに頬が緩む。秀一もみなもに気付いたようだ。
「おはようございます!」
二階堂が二人に歩み寄りながら挨拶すると、二人も口々に挨拶を返してきた。
二階堂と秀一は互いに面識がない。敢えて言えば、秀一は問題の録画を見ていたので、二階堂の顔はそれと分かった。
女性の方は広報課の非常勤嘱託職員で、仲村静佳という。真っ直ぐに揃った前髪に隠れ気味の、少し陰のある瞳が印象的だ。消費生活室と広報課の書類のやりとりなどで時折り行き来があり、二階堂とは顔見知りだ。とはいえそれほど親しく会話を交わしたこともなく、二階堂は小さな声で「お疲れさまです」といって通り過ぎることになる。
すれ違いざま、みなもが秀一に小さく手を振り、秀一も同じように返した。
玄関に入ってから、二階堂がみなもに「知り合い?」と尋ねる。「今年県庁に入った、大学のサークルの先輩です」とだけ、みなもは答えた。
階段を上がり二階の渡り廊下を進んだ先が、スマイレイディオのテリトリーだ。
テレビと同じく澄舞・魚居両県をカバーするスマイレイディオでは、ウィークデーの10時から14時まで自主制作番組「すまいっと通り」を放送している。そのうち月に2回、金曜11時頃から5分間が、澄舞県消費生活センターのスポンサードコーナーだ。生放送ではなく前日までに録音・編集したものを流す。今日は明日放送分の収録だ。
「江戸川さん、できれば原稿差し替えたいんですけど」
二階堂は挨拶もそこそこに、メインアナウンサーの江戸川欣二に書類を手渡した。60歳手前、キャリアは長くアナウンサー部の部長職にあるが今も現役だ。
「えー、そうなの? 今の原稿に絡めて渾身のギャグを仕込んどいたんだけどなあ」
「県内で起きたばかりの事件があって、県民にすぐに伝えたいんです」
二階堂は香守茂乃の事件を受けて、高齢消費者被害の防止のために家族や地域の見守りを呼びかける原稿を昨日のうちに書き上げていた。江戸川アナと二階堂の掛け合い体裁による、県民向け注意喚起。説明の主体は二階堂で、プロである江戸川の合いの手はある程度お任せだ。それだけに、収録直前の差し替えは普通は厳しい。調整室の技術スタッフの二階堂を見る目も怪訝な色だ。
「難しければ、来週に回しますけど、できれば明日流したいなと」
「んー、ちょっと読ませて」
江戸川はシナリオに目を走らせた。一度頭から終わりまで読み、再び頭へ。眉に皺を寄せた真剣な表情から、彼の脳が高速回転していることが窺えた。
「……ぷふっ、ふひゃひゃひゃっ」
江戸川は突如破顔して両手を打ち鳴らす。
「うん、いいギャグ思いついた! この原稿でいきましょう。」
「ありがとうございます。で、どんなギャグを?」
「ないしょ。本番で爆笑しなさい」
*
本番の収録は、一発で終わった。二階堂は朝イチでイメージトレーニングを繰り返していたし、江戸川はさすがのプロだ。
「──あれ、笑うところって、どこかありました?」
二階堂はO.K.を出した江戸川に怪訝な顔で尋ねた。
「またまたあ、今、必死で笑うの堪えてるんでしょ?」
「え?」
「え?」
沈黙、2秒。調整室でその様子を聴いていたみなもは「ギャグってどこだった?」と小室に尋ねたが、小室も首を横に振るだけだった。
江戸川は、しょぼん、とうなだれて立ち上がり、録音ブースから調整室へ続くドアを開けた。そこでくるりと振り返り、ビシッ、と二階堂を指差した。
「覚えてろ、来週こそ、爆笑させてやるぅ! うわあああん」
だだだっ、とその場で小走りの真似。なんだろう、この小芝居。
その時ふと、二階堂は察した。ギャグを思いついたというのは、周囲のスタッフの前で急のシナリオ変更を受け入れる流れを作るための便法だったのではないか。
二階堂は立ち上がり、江戸川に深々と頭を下げた。江戸川はその様子を見て、んー、と首を捻った。
「それはえーと、待ってよ当てるから、んー、素っ頓京四郎の真似だね?」
「え、それ、芸人さんですか?」
「ううん、今作った」
二階堂は苦笑した。この人とは無駄に話が長くなる。でもそれが嫌ではない。「喋り」のプロとして長年かけて培われたキャラクターの故だろうか。
「ともあれ、お疲れさま。帰る前にちょっとアナウンス部に寄ってくれる?」
二階堂とみなもたちは、江戸川に先導されて渡り廊下を戻り、促されてロビーのソファに腰を下ろした。江戸川はそこから川方向に折れた廊下の先でドアを開け、中を覗き込む。そこがアナウンス部なのだろう。
「なぎらっち、ちょっと来て! 県庁の二階堂さん来てるから」
中から出てきた柳楽修を伴って、江戸川は二階堂のところに戻る。
「二階堂さん。先日の放送では、使うべきではない映像を使ってしまい、本当に申し訳ありませんでした。正式には報道部長が消費生活室に謝罪に伺うと申しておりますが、まずは柳楽の直属の上司として、心よりお詫び申し上げます」
江戸川は頭を下げた。さきほどまでのおちゃらけた人気アナウンサーの顔ではなく、組織の管理職としての真面目な顔だ。その隣で柳楽も硬い表情で同じように頭を下げている。おそらく局内でたっぷり絞られたのだろう。
「いや、そんな、頭を上げてください」
二階堂は慌てて両手を振った。
「結果的には、県民への注意喚起としてとても良い〆だったと、みんな言ってますから。香守さんと小室君もそうでしょう?」
二人が口々に同意するのを聴いて、江戸川はにっこりと笑った。
「そういっていただけると、助かります。なにせこいつは」がしっ、と柳楽の方に右腕を回し「いいジャーナリスト魂を持ってんですよ。ただまだ経験が足りないから、やらかすこともある。自分のやりたい方向に無闇に突っ走るんじゃなくて、周囲と信頼関係を構築して映像に表現できるようになれば、大成すると思ってます。──思ってるんだぞ、俺は」
江戸川は柳楽に微笑んだ。それから身を離して両手でメガホンをつくって口に当て
「いよっ、すまテレの星! 俺を養って!」
「養うのは勘弁してください」
「えー、だめなの? ちぇっ」
皆が笑い、柳楽の表情もようやく緩んだ。
「なぎらっち、せっかくだから皆さんを玄関まで見送ったげてよ。俺は会議があるからさ」
*
ガラス張りの一階ロビーは駐車場側と央梁川側の二方向に開けた構造だ。みなもはガラス越しに、央梁川前のイベント広場で犬の着ぐるみが動いているのに気付いた。
「あ、すまいぬだ」
「今日は県の広報枠で使うアクションシーンの収録があるんです。見ていきますか?」
柳楽の言葉にみなもは思わず笑顔を浮かべた。すまいぬを生で観たい気持ちが半分。もう半分は、近くにいる筈の恋人の仕事姿を補給したい気持ちだ。期待に満ちた表情で振り向いたみなもに、二階堂は微笑みを返した。
「県のマスコットキャラクターの撮影現場も、インターンシップの趣旨に合うよ。ラジオの収録も短時間で終わったし、次の予定には余裕があるから、見ていこうか」
「はい!」
柳楽がディレクターに話をつけ、撮影の邪魔にならない位置に一同を案内した。ディレクターの近くにいた秀一がみなもに気付き、小さく頷く。みなもは手を振りたいが、我慢。心の中では思いっきり振っている。
先ほど玄関で見かけた同僚女性の姿は周囲に見あたらなかった。
左右に広がる川に面した広場は、秋の心地良い陽光の下、爽やかな風が吹いていた。広場の中心にいるすまいぬのスカーフも心なしそよいでいるように見えた。準備運動だろうか、すまいぬは脚を肩幅に開いて上体をゆっくり右へ、左へ回し、それにつれて両腕が体に巻き付き、膝が柔らかく浮き沈みする。余裕のある着ぐるみなので、中の人の動きは外から窺えるよりも大きいのだろう。
みなもと小室がその様子を眺めている間、二階堂は柳楽の様子を気にしていた。先日の取材時に比べて、今日は口数が少ない。
「柳楽さん、もしかして、随分叱られちゃいました?」
「まあ、ちょっと……すごく」
柳楽は目を合わさずに答える。
「すごくかあ、はは。でも、後悔はしてないみたい」
二階堂のこの言葉で、柳楽と視線が合った。
「おや、分かりますか?」
「なんか、そんな顔をしてたので」
「あー、修行が足りないなあ、俺。謝罪の相手に、反省してないことを見抜かれてる」
柳楽は右手を挙げ、指で髪の毛を梳いた。
「でも──何年も取材の仕事を続けていると、感じるんですよ。みんなマイクを向けると、心の中の本音と違う事を喋ってる。隠したいことがあったり、自分をよく見せたかったり、あらかじめ考えたシナリオをなぞっていたり、咄嗟に世間から期待されているとおりの役割を演じたり。
「ほら、子供向けイベントの取材でカメラを向けて『どうだった?』と聴くと『楽しかったです』とか、『平和が一番だと思いました』とか、微笑ましい定型句があるでしょう。子供は分かりやすい。大人は、心がひねてんのか、もっと分かりにくくて複雑だ。
「あ、でも、二階堂さんは分かりやすかったですよ」
「え、私?」
「インタビューの時、シナリオ読むなっていわれて苦労したでしょう。最初は記憶したシナリオを読み上げるのに必死で、目の焦点が合ってなかった。ちょっと技を使ってスムースなテイクを撮れたけど、それでも作文であることには変わりない。でもね、一旦撮影を終えた後のリラックスした二階堂さんからは、本当の声が聞こえました。放送しちゃったあの場面も、悪質業者と戦い消費者を護る最前線の澄舞県庁担当者として、魂の籠もった叫びでした。あれは使わない手はないだろうと、今でも思ってますよ」
二階堂は、使わないでといった映像を使われた、いわば被害者だ。しかし、表面上は弁解と捉えることもできる柳楽の言葉を、素直に聴くことができた。柳楽の言葉に嘘はない。この人は信頼できるというあの時の印象は間違ってなかった、そう思った。
「柳楽さんの今のこれも、魂の叫びですね?」
「あ──うん、そうですね」
柳楽は言われてやっと気付いた風だ。
「俺はね、本当はディレクター志望だったんですよ。人間に興味があって、ドキュメンタリーを撮りたくて、すまテレに入った。アナウンス部に配属になった時は正直凹んだけど、直接取材対象と会話を交わして相手の本音を引き出す仕事に、今はとてもやり甲斐を感じてます。──でもまあ、今回のことでしばらく謹慎ですけどね」
「えっ」
月曜朝のすまいぬインタビュー事件のことを知らない二階堂は、自分の件だけで謹慎処分は重すぎると驚いて、柳楽の顔を見た。
「大丈夫、しばらくテレビへの露出が減るくらいの話です。二階堂さんに見抜かれたように、後悔はしてません」
本番行きまーす、とディレクターが大きな声を上げた。映像撮りだけで音声は必要のない場面と聞いていたが、自然と皆が口を閉ざす。
すまいぬが、すっ、と両手を胸の高さに挙げてから上体を捻り、歩き出す。地面に大きな円の軌跡を描きながら、身体は右へ左へ自在に転変し、両の腕はうねるように動く。なんだかダンスのようだなと、みなもは思った。
中国拳法の中でも難易度の高い八卦掌の套路(型)だが、そうと知る者はこの場には他に誰もいない。孤高の武を「彼女」は演じていた。
「彼女も本当の自分を押し殺して生きている一人なんだよな……」
柳楽が無意識に呟いたのを、みなもは聞いていた。自分たちを除いて、撮影現場には男性しかいないように見える。敢えて言えばすまいぬだが。
「すまいぬって、男の子って設定ですよね?」
恐る恐る尋ねたみなもに、柳楽は「あ、ええ、そうですね」とだけ応えて、そのまま口を閉ざした。
[25]インターンシップの終わり
*
午後はいよいよインターンシップの仕上げとなる啓発素材作りだ。16時半にはプログラムを全て終了するから、実質3時間余りしかない。その時間のなさが、却って「何を作るか」の選択肢を絞ることに繋がった。
昨日の夕方、小室とみなもが選んだのは、短い動画の制作。悪質商法被害防止のシナリオを作り、その演技を消費生活室の備品のデジタルカメラで撮影するのだ。
「俺、簡単な編集ならノートパソコンでできるから」
小室はプリインストールされた動画編集ソフトで友人のサークルPR動画制作を手伝った経験があり、3分程度の動画なら30分あれば編集とエンコードが可能だという。
「じゃあ私は、シナリオ作ってくるよ」
澄舞大学総合文芸研究会は、年に一度文芸同人誌を発行しており、みなもも毎年手慰み程度の短い物語を書いている。だから昨夜は秀一と甘い時間を過ごした後、そのまま寝てしまいたいのを我慢してパソコンに向かいシナリオを書き上げた。
今朝、動画を作ると聞かされた野田室長は、目を丸くした。
「さすがYouTube世代だねえ。うちもプロに頼んでいくつか動画を作ったけれど、機材も俳優も編集も自前で作る発想はなかったな」
「それで、実は室長と二階堂さんにもちょっとした役をお願いしたいんですけど」
「ほう」
「あら、私も? 喜んで」
二階堂は先日のインタビューでカメラ度胸がついたようだ。というよりも、癖になりかけてる?
昼休みが終わる13時ドンで読み合わせ開始。自分は絶対にダマされないといっていた高齢男性(小室)が老人ホーム入居権詐欺にあっさりダマされそうになり、寸前で娘(みなも)に止められる。野田は練蔵をだます悪質業者役で声のみの出演、二階堂は最後に手口の解説と注意を呼びかける役だ。
「衣装は用意してるの?」
二階堂の問いにみなもは、そこはどうしようもないので私服のままで見立てるつもりだと答えた。
「いやあ、それは勿体ない。ちょっと待っててね」
二階堂は一旦席を外し、2分ほどで戻ってきた。手にした段ボールを机上に置き、蓋を開いて中身を取り出す。髪の薄いかつら、サザエさんの波平が家で着ているような着流しの和服、サザエさんのようなエプロン。いずれも安物ではあるが、私服よりは役柄に近づくことのできる衣装類だ。
「えーっ、なんでこんなのあるんですか?」
驚きの声を上げるみなもに、二階堂はVサインをして答えた。
「ふふーん、すごいでしょ。消費者向けイベントで、寸劇って有効なのよ。おじいちゃんおばあちゃんたちが楽しく見たり参加してくれる。だから、少しずつ衣装や小道具を揃えてきたの。課の忘年会でも、センター職員で寸劇したりね」
小室は三脚にデジカメを据え付け、画角を決める。時間がないからカット割りはしない。最小限の切り貼り編集はできるから、とちったら少し戻ってやり直し。衣装をつけてとちりまくりの撮影は笑いに満ちていた。楽しげな様子に、相談員たちも代わる代わる見に来た。
そして二階堂の出番。解説の最後に、脚本家みなもはあの台詞を用意していた。二階堂もそれを気に入り、「どうせなら、このラストは、センターみんなでやろうよ」と執務室にいた職員全員に声をかけた。幸い相談者などの来客はいない。わらわらと集まって総計14人。小室は演出変更に対応するため三脚をグッと後ろに下げ、全員が入る画角を確保した。
撮影開始、終了。小室が動画を確認して「OKです、クランクアップ!」というと、皆が一斉に歓声を上げて拍手をした。なんだか学園祭みたいだ、とみなもは思った。
野田がポンと手を叩いて皆に告げる。
「さあ、我々は一旦仕事に戻ろう。完成したら上映会ね」
15時を少し過ぎていた。ここから小室の編集作業がはじまる。撮影は小室がシャッターを押してそのまま役者として登場したから、パンやズームといったカメラワークのない固定撮りだ。解像度を犠牲にすれば同じ事は編集作業で行える。みなもは横でその作業を、まるで魔法を見るかのように眺めていた。
50分後、作品は完成した。
*
小室の声でタイトルコール。画面は「練蔵じいさんの、わしゃダマされんぞう!」の書き文字に、かろうじて高齢男性といえばそう見えなくもないみなも画伯の絵が添えられている。明るいBGMは著作権フリーで使えるネット素材を見つけてきた。
私服の上から和服を羽織った小室が登場。カツラは少し抵抗があって着けていない。
「わしの名は練蔵、悪質商法にはダマされんぞう! さて、今日の郵便物を確認するかのう」
手にした封筒の中からパンフレットを取り出す。ブツは適当な有り物だ。練蔵はパンフレットに思いっきり顔を近づけたり、遠ざけたり。
「これは、老人ホームのパンフレットじゃな? 優しい家族と一緒に暮らすわしには、こんなものはいらんぞう。ぽーい」擬音を口にしてゴミ箱にパンフレットを放り込む練蔵。
そこに電話の呼び出し音。練蔵が受話器を取る。
「はい、もしもし」
「こちらは澄舞福祉協会の悪野(わるの)と申します」
相手の声は野田だ。少し高めの優しい声音。
「はあ」
「実は新しい老人ホームを建設中なんですが」
「わしゃダマされんぞう!」
「ああ、いえ、セールスではないんです」
「セールスでは、ない?」
「はい。実はそこにどうしても入居したいという独り暮らしの高齢者がいらっしゃるんですが、パンフレットの届いた人しか申込みできなくて、困っておられます。練蔵さまにパンフレットが送られていると聞きまして、どうかお名前を貸していただけないでしょうか」
「名前を貸すだけか」
「はい、お金を出す必要はありません」
「そうか、ならダマされる心配はないな。困っている人の助けになるなら、名前を使ってもらって構わんぞう」
「ありがとうございます、感謝します!」
電話を切ってテーブルに置く。
「ふっふっふっ、良いことをすると気持ちがいいぞう」
再び電話が鳴る。
「はい、もしもし」
「私はあーせい厚生労働省の悪川(わるかわ)というものだが」
野田の二役、今回は低くドスの効いた声だ。体格が大きいから迫力が違う。練蔵じいさんも少しびびった様子だ。
「あなた、老人ホーム入居権の名義を他人に貸しただろう。それは法律違反だ! じきに警察が逮捕に行くことになる」
「ええーっ!」オーバーに驚く練蔵。
「今日の午後3時までに20万円の供託金を振り込めば、警察を止められる。金は後日全額返すから、すぐに振り込んでくれ」
「はははいいっ!」と返事をして電話を切る練蔵。
「大変だ大変だ、通帳通帳、カードカード」
練蔵が右往左往するところに、娘役のみなもが登場。
「お父さん、どうしたの?」
「たいへんだぞう、実はかくかくしかじか」
「かくかくしかじか! お父さん、それ、最近流行ってる詐欺よ!」
「ええええーっ!」
練蔵はカメラ目線になる。情けない顔、情けない声で「わしの名は練蔵、ダマされたぞう。とほほ」
オチのついた音楽。テーブル越しに正面からカメラを向く二階堂に切り替わる。手口の解説、ここはみなものシナリオではなく二階堂の知識と経験に任せた。
悪質業者は人の心理の裏をかくプロ、自分はダマされないと思っている人ほど足下を掬われる。お金が絡まず名前を貸すだけという安心感、困っている人を助けたという満足感。そこに急転直下の事態が起こり、威圧的に迫られる。ジェットコースターのような感情の起伏を喚起するのが、心理コントロールの手口なのだ。加齢とともに、それに抗することは難しくなるのが自然の摂理。家族や地域の人たちの見守りが鍵となる。振り込みの前に止めるのが大事、振り込んでしまったら被害回復はとても難しい。
二階堂のアップ。ここからは、あの台詞だ。
「でも、そこで諦めちゃダメ! 黙って泣き寝入りはやめよう!!」
画角がズームアウトし、みなもと小室、センター職員がずらりと二階堂の後ろに並んでいる。全員で最後の決め台詞。
「消費生活センターは正義の味方、困った時は電話番号188、『だまされるのは「いやや」』まで!」
*
二人の作った動画は、当然ながら完成度という面では公式広報として使えるものではなかった。それでも、しばらくセンター内の閲覧スペースで上映して、来訪者に見てもらうことになった。
「正直いって、まさかこの短時間で動画作品が作れるとは思わなかったよ。私たちの広報の固定観念を離れたアプローチで、びっくりした。最小限の経費で動画が作れるなら、室長、うちもYouTubeを使った自前の動画広報を考えてもいいかもしれませんね」
二階堂の言葉に野田は頷いた。
「そうだね。これまでの直接広報がマンネリ化して効果が頭打ちだとすれば、SNSを使った広報はこれから必要になる。ちょっと来年度に向けて考えてみようか」
技術力のある職員が必要なこと、事務量を考えればスクラップアンドビルドによる広報手段全体の再検討が必要なことは、敢えて口にしなかった。そうした事務のリアリティは、今後自分たちが引き受けることだ。今は課題をやりきったインターンシップ生2人の健闘を称えよう。
最後の挨拶セレモニーを予定している16時半まで、あと少し時間がある。もうじき小峠課長と河上補佐もこちらに来る手筈だ。
「三日間やってみて、どうだった?」
野田は挨拶の頭の整理になるように二人に水を向けた。小室とみなもは顔を見合わせ、みなもが(お先にどうぞ)と掌を向けたのを受けて、小室が口を開いた。
「行政実務の幅広さを実感できたような気がします。特に、実際の悪質業者との対応を間近に見ることができて、刺激を受けました。法律の勉強って、抽象的な条文と具体的な事件の関係を捉えるんですけど、日頃は判例から法律の意味合いを理解して行くんです。でも行政や法律家の実務は、目の前の事件を解決するために法律をどう解釈して適用するか、そこが一番大事なんだなと。新鮮でした」
「さすが、三日間でそこが分かるなんて、すごい。私は法律に苦手意識を持ったまま消費室に異動してきたから、どうすれば目の前の違法行為を取り締まれるのか、散々頭を悩ませたんだ。法律の条文と、その解釈と、実務運用の蓄積に照らして、この事件は白か黒か。担当者として判断を下して終わりじゃない。それを県庁組織の意思決定にまで漕ぎつけられるか、侃侃諤諤議論してね」
不利益処分は相手方が納得しなければ行政不服審査や取消訴訟にまで発展する。そのため処分の意思決定に際しては、そうした第三者判断にも耐えられるくらい処分の必要性・妥当性の根拠を整理しなければならない。
「ほんと頭の体操よ。最近、法律って面白いかも、と思い始めたところ」
「ああ、そういうの、ワクワクしますね。公務員になりたい気持ちが高まった気がします」
「あら、来年澄舞県庁受ける?」
二階堂が食い気味に身を乗り出したので、小室は苦笑いをした。
「今のところは、国と五百島県庁を受けようかと」
「残念。でも、国でも五百島県でも、澄舞県庁と仕事の繋がりは割とあるのよ。もしかすると数年後にまた出会ったりするかも。試験、頑張ってね」
続いてみなもの番だ。
「なんか似たような話になっちゃうんですけど、私も県庁の仕事って幅広いんだなと驚きました。役所がどんなことをするところか正直あまり知らなくて、ひたすら机に向かって仕事をしている事務仕事のイメージだったんです」
秀一から聞かされる仕事の様子は華やかさもあったが、広報課の仕事は県庁の中では例外的だとも言っていた。
「でもこの三日間、事件の被害者に対応したり、悪質業者とバトルしたり、放送局で収録したり、広報啓発のためにみんなで賑やかに動画を作ったり。本当にアクティブというか、そんな感じで。仕事って楽しいんだなと思いました」
みなもの言葉を聞いた野田と二階堂は苦笑いをして、顔を見合わせた。
ひとまず二階堂が口を開く。
「ありがとう、魅力を感じて貰えたならなによりよ。インターンシップとしては予定していなかった事件対応とか、ある意味で大事な部分を見てもらえたのかな。ただ……」
二階堂はちらりと野田の顔を見た。野田が後を続ける。
「我々の日常の仕事の大半がデスクワークなのは、確かだよ。事務仕事は役所の活動を支える基盤といってもいい。ボールペンを買うのも、郵便物を出すのも、放送局との番組制作契約も、事務仕事だからね」
野田は2人を恐縮させたくないので敢えて言わないが、例えばインターンシッププログラム自体もそうだ。学生に仕事を理解してもらって就職の選択肢としてほしい県側と、学生の就職を支援したい大学の間で、仕組みの調整を行う。次に、大きな県庁組織の中で数日間学生を受け入れてくれる所属を調整する。所属はインターンシップの趣旨に合ったプログラムを作成して、具体的な準備をする。インターンシップ本番が終わった後は、報告書を作成して人事課に提出。そんな様々な事務仕事が、この三日間を支えていた。
「感じ取って欲しいのは、そういう地味な事務仕事やメディア対応のような派手な仕事の全体で、何を実現しようといているかということなんだ。言い換えれば、役所のミッションだね。我々のミッションは……さて、なんでしょう?」
野田がにっこりと笑って2人を見た。小室もみなもも思案顔でしばらく声が出ない。「ほら、初日に話した、あれよあれ」と二階堂が助け船を出し、小室が思い当たって口を開いた。
「消費者基本法第1条、ですね」
多くの行政分野には「基本法」の名を持つ法律があり、その分野の根本的な理念や行政の責務と役割分担などを定めている。消費者行政におけるそれが、消費者基本法だ。みなもも初日のレジュメに書かれていたことに気付き、手元の資料をめくって目を走らせる。
消費者基本法(昭和43年法律第78号)
(目的)
第1条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
「──国民の消費生活の安定及び向上を確保する、ですか?」
「うん、そのとおり」
野田は目を見開いて顔を輝かせた。まるでひまわりのようだ。
「更に根源を辿るなら、地方自治法の「住民の福祉の増進」に辿り着く。 いずれにせよ、抽象的でしょう? その抽象的な目的を大小様々な具体的な事務が支えている。地味で面倒で大変で、時には華やかで時には危ない本当に多様な仕事を通じて、法律が行政に与えたミッションを実現すること、少なくともそう努力することが、公務員の役割なんだ」
「勉強になります。日々の実務が忙しくて、そういう理想を忘れがちになるのが、つらいですね」
横から二階堂が殊勝な顔で頷き、皆が笑った。
「そうだね、理想と現実が一致しないのは世の常。初日に「60点でも成功」って誤解を招きそうな言い方をしたけど、それもまた公務現場の現実だよ。そういうところも含めて、二人には、自分の進む道を考えるきっかけにしてもらえればいいな」
澄舞県庁生活環境部生活環境総務課消費生活安全室の野田彌室長と二階堂麻美主任は、これから社会に出る二人の学生に心からの笑顔を見せた。香守みなもと小室隆朗は、やはり笑顔で「はいっ」と大きく応えた。
*
やがて小峠美和子課長と河上直補佐が姿を現し、セレモニーは5分ほどで終わった。拍手の中を小室とみなもは出口へ歩み、澄舞県消費生活センターを退室した。 エレベーターで1階に下りる。澄舞駅まで歩くという小室は南玄関へ、県庁前でバスに乗るみなもは北玄関へ向かうことになる。
「それじゃあ、お疲れ様」とみなも。「うん、お疲れ様」と小室。
言葉少なに二人は別れた。一期一会。大学も、専攻も、おそらく今後の進路も違う二人は、よほどの縁がない限りもう会うこともない筈だった。
[26]次のステップへ
*
帰宅時間の目処が立たないから晩御飯は職場で出前を取ると、秀一から返信があった。この半年余りでそういう日の寂しさには慣れた。みなもは帰路にスーパーで自分用のお弁当を買って、アパートでそそくさと夕食を済ませた。
公務員は定時退庁、というイメージとはかけ離れた実情を、秀一が就職して初めてみなもは知った。
「部署や時期にもよるみたいだけどね、22時に退庁して庁舎を見上げると、まだいくつも窓の灯りがついてたりするよ」
新規採用1年目の秀一は、過重労働にならないようそれなりに配慮されているらしい。それでも定時で帰れるのは週に1~2度で、20時台がザラだ。時間外勤務手当が割増になる22時以降はよほど急ぎの作業がない限り退庁を命じられるが、時には日付が変わることもある。
社会人って、大変なんだな。
みなもの労働経験は家庭教師のみ、サラリーマン的な働き方とは違う。父しゃんも秀くんもサラリーマンだ。会社や役所という集団の中で仕事をする、それはどういう感じなんだろう。
みなもにとって、今回のインターンシップは非常に刺激的だった。漠然と抱いていた「お役所」のイメージとは大きく異なる世界。しかしインターンシップ生が垣間見るものもまた、公務組織のほんの一場面でしかない。
ぼんやりと頭を廻らせながら、パソコンに火を入れる。メーカーロゴが浮かび、まもなくwindowsのログイン画面。パスワードは指が覚えている。
学務に提出するインターンシップ報告書を作らねばならない。しかしみなもの思考はその先に向かっていた。来週月曜日の文化人類学ゼミ、卒論構想の報告だ。ひとまず報告書様式のワードファイルを開いたものの、指はキーボードの上に触れたまま、動かない。
何かを生み出そうと脳内で思考を巡らす時の集中力。例えば、サークル同人誌の課題で小説を書かねばならない時、目は開いていながら物を見ていない。音は鼓膜に届いても意識が向かわない。五感とりわけ視覚と聴覚が、脳内で紡がれるイメージに置き換わっている。今、その状態が降臨していた。
これまで文化人類学の講義で聴いてきたこと。見慣れたものを、見慣れぬものにする。異文化に触れ、潜り、細部と全体構造の連環を把捉する。厚い記述。他者理解と自己理解。骨格と血肉。
「県のミッションと具体的な事務を繋ぐものとしては、後で『澄舞県長期計画』の体系図を見てごらん」
夕方に野田室長から聴いたひとことが蘇る。
マウスでブラウザを立ち上げ、google検索から計画PDFを開く。目次からそれらしいページを辿ると、三角形の図が現れた。頂点に澄舞の将来像、続いてそれを実現する五つの政策の柱、政策を具体化する施策群と、実際に県庁組織で行う事務事業。なるほど体系的に編まれている。
「消費生活センターは正義の味方!」
たまたまニュースで見た二階堂の啖呵の意味、その少なくとも一端を、みなもはおばあちゃんの事件を通して感じ取った気がする。計画書のどこに位置づけられているかを探すと、政策の柱「それぞれの地域で安全・安心な生活ができる澄舞づくり」の下に施策「消費者対策の推進」、その下に事務事業「悪質商法事犯対策の推進」がある。
「60点でも合格というのが、現実なんだよ」
美しく整えられた行政計画の事業体系と、限られたリソースで実務に取り組む公務員たちの現実の姿。骨格だけでは血肉の細部の動力は窺えない、血肉だけでは骨格の総合的な作用は見えない。
文化人類学の基本はフィールドワークだ。研究者は研究対象となる異文化集団に密接に関わり、共に暮らし、五感で観察する。その集団の血肉と骨格の総体を感じ取り、民族誌(エスノグラフィ)としてまとめる。
──よし、これだ。
みなもは心を定めた。ファイルの新規作成。指が滑らかに打鍵を始めた。
*
月曜日の文化人類学ゼミは、3年生の卒業論文構想報告会だ。該当者5人の中でも、香守みなもの報告は、ちょっとした波乱をゼミに引き起こした。
「澄舞県消費生活センターのフィールドワーク(仮)」
そう標題を掲げたA3版の2in1資料を元に、みなもは構想を説明していく。インターンシップで見聞きしたこと。「お役所」というものへの自分の先入観に気付く経験。悪質商法の実態とそれに対抗する行政権限の仕組み。そして、それを支える一人一人の公務員の姿。
「胸を張って正義の味方だといえる仕事が、公務員のどのような働き方に支えられているのかを観察することが、このフィールドワークの目的です」
持ち時間の20分を5分ほど余らせてみなもは報告を終えた。それはつまり、続く10分の質疑応答が15分に伸びるということでもある。「人間サンドバッグ」と呼ばれる4年生の中間報告に比べれば、3年生段階での構想報告は手心が加わる「人間パンチングボール」と表現される。
真っ先に手を上げたのは、ただ一人の二年生、吉本範香だ。いつもの柔らかな表情と異なり、何故か目に厳しい色が宿っていた。
「インターンシップで少し経験したからそこでフィールドワークをするって、安易過ぎませんか? 思いつきで何かを観察して、意味のある民族誌が書けるとは思えません」
いきなり重たい拳がみなものみぞおちを襲う。学術トレーニングである討論は真剣勝負、というのがこのゼミのモットーではあるが、それにしても学生間で相手を正面から「安易」と評するのは希だ。教室内にいくつかの笑い声が起きたが、戸惑いの色をまとってすぐ消えた。
真剣勝負だからこそ、報告者は正面から打ち合わねばならない。
「ご批判ごもっとも。ごもっともだけれども、ビビビッと来たんだよね」
この時に起きた笑いは、緊張した空気を緩和したいゼミ生たちの衝動も手伝って、大きかった。
「確かに、たった三日間経験しただけで、私は澄舞県庁のことをほとんど知りません。でも、知らない世界だからこそ県庁は異文化で、人類学的に調査をする意味はある筈だと思ってます。知っている人が当たり前の前提にしていることを、知らないからこそ根っこから考えられる、というか」
入華陽染(いりはな・ひそむ)教授が声を出さずに苦笑した。講義で話している台詞をなぞっていたからだ。入華が感じたことを、範香が言葉にした。
「その論理は、知らない世界をフィールドワークすれば誰でも良い研究ができる、と聞こえます。でもそうじゃないですよね」
鋭いフックによろめくみなも。
「香守さんの報告は、講義で聴いたことのある人類学の理屈めいたものを、自分のやりたいことにただくっつけただけに思えるんです。それは何も明らかにしたことにならない。何かを明らかにできる目処があるのなら、教えてください」
アッパーが顎に決まった。みなもは天を仰ぐ。
「……今は、目処はありません。何かがあるに違いないという直感だけです」
完敗。石川耕一郎准教授が助け舟を出した.
「まあ、フィールドワークはその過程で見えてくるものの方が大事だからね。問いは調査までにもう少し丁寧に設計した方がいいけれど、入口は直感的着想でも悪くはないと、僕は思います」
石川先生、やさしー。
「それより気になるのは、そもそも県庁の参与観察って、受け入れてもらえるのかな。何か約束みたいなものでもしてるの?」
「いやー、特には。インターンシップみたいに大学から話を通してもらうようなわけにはいか」
「いかないねえ。インターンシップは県庁の公式事業で大学も連携してる。卒業研究は私的活動。そこは基本自分でやらないと」
石川先生、容赦ねー。
「センターの担当さんとは仲良くなったし、メアド交換したので相談はできると思ってます」
ここで入華教授が口を開いた。みなもに対する助言であると同時に、ゼミ生全員に向けたレクチャーでもある。
「仲良くなったというのは、錯覚だと思ったほうがいいよ。インターンシップでは県庁側はホスト、学生はお客様。社交上の笑顔に過剰に期待しちゃいけない。
「フィールドワークというのはね、調査者側の都合であって、インフォーマント(被調査者)には負担ばかりで何もメリットがない。相手に信頼してもらって受け入れてもらうのは、とてもデリケートで難しいことなんだよ。キャリアを積んだ研究者でも、研究したいと思う社会集団にいくつもフラれて、ようやく巡り会えた条件下でフィールドワークに臨むんだ。ある意味での偶然と幸運の上に、調査は成立するといってもいい。
「役所をフィールドワークの対象にしたいというのは、成功すれば画期的なことだよ。でもハードルは高いよね。役所でも民間企業でも、普通は人員に余裕はなく本来業務で手一杯だ。学術調査なんて受け入れて入れる余地はないでしょう。ましてや消費生活センターなんて、消費者相談や悪質事業者のデリケートな情報だらけで、部外者を受け入れることは基本的にタブーだろう。
「さっきの石川先生の問いかけは、そういう問題が背景にあるんだよ」
「ですね」入華の振りを石川が引き取った。「今回のインターンシップで香守さんがデリケートな消費者行政の一幕を見聞できたのは、家族のトラブルという偶然の上に成立したものだよ。それがどれだけ興味深くても、偶然に二度目はない」
みなもは気持ちがしゅんとなった。せっかくビビビッと来たのに、やっぱり難しいのかなあ。その沈んだ表情を、範香はじっと見つめていた。
入華はレジュメに目を落とし、4秒黙って何かを考え、徐にいう。
「とはいえ、アタックする前から諦めることはないさ。幸い三年生にはまだ時間がある。正面から調査できない場合は、できるやり方を考えればいい。偶然に二度はないけれど、もしかすると香守さんは幸運かもしれない。ね、石川先生、気付いた?」
「ええ、いますね」
石川もレジュメを見た。末尾には、最終日に作った啓発ビデオのラストシーン、消費生活センターのみんなと全員で映った画像を載せていた。余白の穴埋めのつもりだった。
「香守さん、この写真の右の方にいる体の大きい人、野田彌さんだよね?」
石川の口から突然野田の名前が出て、みなもは驚いた。
「あ、はい、そうですけど」
「役職は?」
「消費生活安全室長です。兼務で消費生活センター長も」
「管理職だね、しかもセンターの責任者か。ふーん」
石川と入華が曰くありげに顔を見合わせ、笑った。
「香守さん」石川がいう。「もしかすると、本当に微かなものだけど、希望があるかも知れないよ。ただ、仮にうまくいったとしても、県庁の参与観察はとても大変だと思う。本気でチャレンジする気は、ある?」
一瞬、指導教官の示唆するところを捉えかねて、みなもは固まった。微かな希望──フィールドワークに入れる可能性。それは願ってもないことだ。
「はい、あります!」
みなもは元気に応えた。
大丈夫。私は、やる時はやる女なんだから。
<第一話ドラフト稿 了>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
