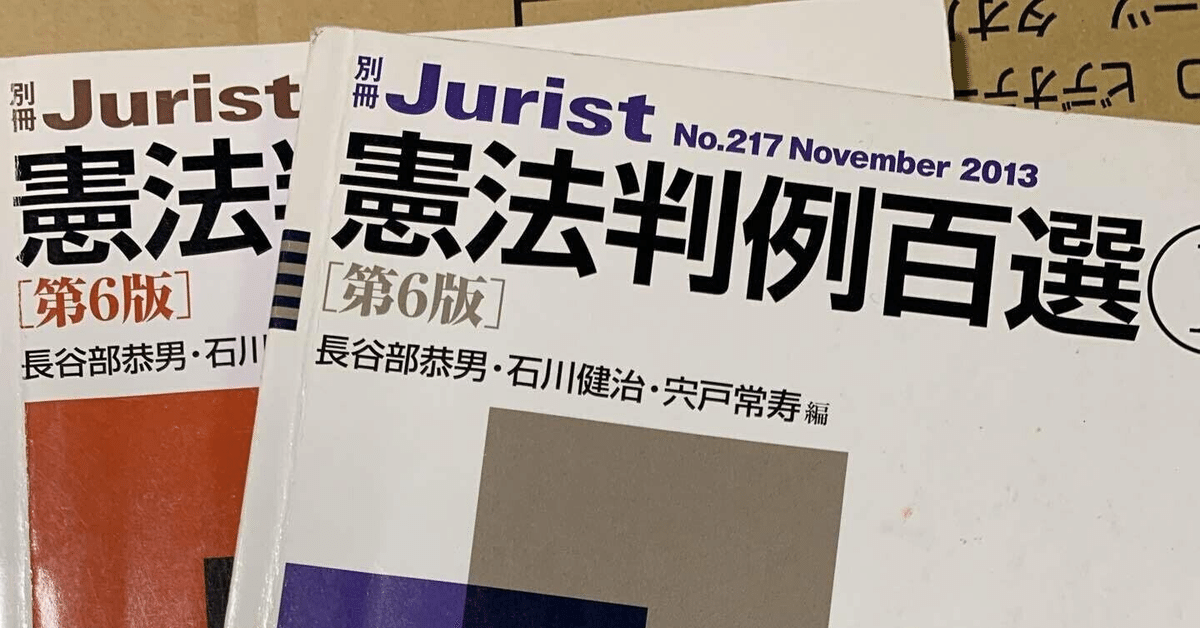
1046:法律は人の有り様の反映だから
法律学習を淡々と進めている。記憶しなきゃとは思わず、素直に講義を聴いてふむふむなるほどと理解しながら愉しむ感じだ。
今日聴いた講義(違憲審査周り)は、これまで憲法の条文に沿って確認してきた様々な論点をあらためて体系的に確認する回で、面白かった。特にハンセン病国家賠償訴訟は、判決確定の数年後にハンセン病所管部署に異動して県出身者との交流事業などにも僅かながら関与したこともあり、印象に強く残っている。
判決についての解説がとても興味深かった。この16年前の判例である重度身障者在宅投票制度の立法不作為国賠請求事件では「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反している」時でない限り国賠法上の違法ではないと規範定立したことから、国賠の道は極めて細いものとなっていた。しかしハンセン病問題における国の人権侵害は明白であり、賠償の道を探りたい。そこでハンセン病国家賠償訴訟で熊本地裁(国が控訴しなかったので確定)は、極めて重大な自由の制限にかかる本件と判例事件とでは全く事案が異なるとした上で、判例の上記規範について「立法行為の国家賠償上の違法性を認めるための絶対条件ではなく、立法行為が国家賠償法上違法と評価されるのが、極めて特殊で例外的な場合に限られるべきであることを強調したにすぎない」との解釈を行って、国家賠償を認めた。
これは凄いなあ。「事実上」とはいえ束縛される判例を、表面的な言葉としてではなくその意を汲み取って解釈することで(それは新たな意味の創造でもある)、目の前の事件に当てはめ、賠償の道を開いた。
ここまで憲法の講義を受けながら感じてたけど、法律家の仕事って本質は具体の事件を妥当な解決に導くものなんだ。普通のテクストならば文章の意味は書いた人の意図が支配的になるけれど、法律の場合はそうじゃない。法解釈学的ルールに基づきながらも、目の前の事件の解決のために「法と現実」を照らし合わせる作業が裁判官の仕事だと、様々な判例講義を聴きながら感じていた。弁護士も検事も、立場によって依頼人の利益か社会秩序かという違いはあっても、根っこは同じだろう。
30年前に公務員試験受けた時、また入庁後十年くらい過ぎるまで、法律は小難しいものに思えて毛嫌いしていた。その後実務の中で行政法を中心に法律の魅力を感じるようになったけれど、公務員を辞めた今になってあらためて法律って面白いと感じている。それは、つまるところ、人間が面白いんだ。法律は人の有り様の反映だものね。そんな当たり前の事に気付くのに30年掛かってんだから、まったく。
正直資格試験勉強のつもりで義務的にちまちまやっている間は、全然身が入らなかった。今、のんびりじっくり枝葉だらけの丁寧な講義を聴いて、ようやく自分の琴線が震えだした気がする。思い切って講座を切り替えたのは私の場合は正解だと思うよ。まだまだ長い道のりだけれど、焦らずゆっくり愉しむさ。
--------以下noteの平常日記要素
■前回以降の小説進捗
進捗なし。
■前回以降の法律学習ラーニングログ
【学習時間3h24m/リセット後累積75h18m/リセット前累積330h42m】
講義動画2本。
■前回以降摂取したオタク成分
『豚のレバーは加熱しろ』第10話、半分くらい席を外してて観て無かった。『不滅のあなたへSEASON2』第13話、暫くぶりで話忘れてる。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
