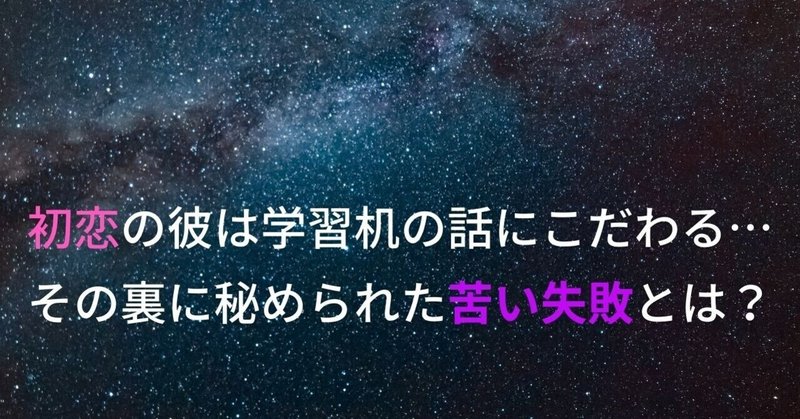
【青春推理】机
高校の夏休み。亜衣実は久しぶりに生まれ故郷に帰省し、初恋の幼なじみ天池美佐男と再会する。だが美佐男は、なぜか亜衣実が愛用していた「学習机」の話にこだわる。その真意とは?
1
開け放たれた窓から西風が吹きつけ、風車がカラカラまわった。車内に取りつけられたピンクや白や黄色の華やかな風車が、一両編成のローカル線にやさしい色合いを添えている。
中心都市を発って一時間。収穫前の青々と育った稲田が延々と続く。まるで同一画家による同じテイストの作品を見ているようだ。
無人駅、下車。
駅舎を抜け出ると、一台の軽トラック。長靴を履いたふくよかな女性が手を振った。近所に住む架純おばちゃんは私がこの村へ帰郷するたびに迎えに来てくれる。
「亜衣実(あいみ)ちゃん、元気だった?」架純おばちゃんは私が背負ったリュックを軽々と私の肩から外すと、私が助手席に乗り込むのを待って、「はい」と返した。私はそれを足下に置いた。「お父さんもお母さんも元気?」
「元気です」私は事務的に答えた。
「ははは。そう固くならんでちょうだい」とおばちゃんは笑った。
いつからだろう。昔はどんなことでもタメ口で話せた相手に対してさえ、いつの間にか自然と敬語で話すクセがついてしまった。
笑っていても、どこか表情が引きつってしまう。心の底から笑えていないようなもどかしさ。これも成長過程ではありがちなことだろうか。
ガタガタと砂利道を進む。振動が心地わるい。夏だというのに窓から吹きつける風がほんのちょっぴり冷たかった。
「寒かったら閉めて」とおばちゃんは言ってくれたけれど、私は「大丈夫です」と答えた。外気に触れていないと車酔いしそうだった。
「美佐男(みさお)も帰ってるよ」とおばちゃんが言った。
天池(てんち)美佐男。私の幼なじみ。おばちゃんの一人息子。私より二つ年上のお兄ちゃん。現在は東京の大学に通っていて一人暮らし。
そして、私の初恋。
美佐男とは、子供の頃によく神社の境内や川で遊んだけれど、中学に進んだ頃から、たまに帰省しても、どこかよそよそしく、目が合ってもお互い変に意識していたのか、どちらからも近づこうとしなくなった。
最後にあったのは、おじさん――美佐男のお父さんが亡くなって一年忌。あれからもう三年になる。
古い民家の中庭まで車を入れる。昔はもっとボロ屋だった記憶があるけれど、屋根を修繕してくれたのだろう。
だけど匂いは昔のまま。田舎の匂い。おばちゃんが時々鍵を開けて、空気を入れ替えたり、中を掃除してくれているらしい。「あんたたちがいつでも帰って来られるようにね」
四年生のとき、私たち家族は父親の仕事の都合で村を出て東京に移り住んだ。東京では家族三人狭いアパート暮らしだったから、それまで使っていた家財道具をそのまま移すわけにはいかなかった。だから村を出る時すべて処分した。
「寝袋でいいの? 使ってない布団貸すけど」おばちゃんはいつも気にかけてくれるけれど、私は「大丈夫です」と決まり文句のように返した。
「今夜はバーベキューよ」とおばちゃん。軽トラックの荷台には市場で買ってきたフルーツや肉、野菜が積んであった。
「いらっしゃい」美佐男が笑顔で出迎えてくれた。「久しぶりだな」とすっかり背が伸びた高い位置から、美佐男のバリトンが降ってくる。大人になったんだ――と私は美佐男を見て思った。声だけじゃない。たくましく鍛えられた体つきを見ても、そう思う。
「ずいぶん綺麗になった」と美佐男が言った。「昔は、机に座っていると頭も隠れてしまうくらい小っちゃかったもんな」
「そこまで小っちゃくなかったでしょ!」背が低かったことを揶揄われたと思った私は、特に何も考えずに「ははは」と笑った。
2
陽が沈みかける時間になって、私たちは庭でバーベキューを楽しんだ。
「あんたたち本当に仲良かったものね」おばちゃんが昔を懐かしみながら缶ビールを飲んでいる。アルコールが入るとなおさら饒舌になるおばちゃんの生態を、私はすっかり忘れていた。
「私はね、てっきりあんたたち二人が結婚するもんだとばかり思っていたよ」あっけらかんとした口調でそう言うのだ。
美佐男があわてて「やめろよ」と止めた。私は返す言葉がなく黙っている。顔が火照っているのは夏の夜風のせいばかりではない。
「でもあんた、東京で彼女つくっちゃったもんねえ」とおばちゃんが口惜しそうに言った。「ごめんね、亜衣実ちゃん」
「あ、い、いえ……」どうして私にあやまるのだろう。私は戸惑った。考えてみれば美佐男も大学生。彼女がいても何ら不思議ではない。
美佐男が私のほうを向いて、「そういえばさ、昔、亜衣実が泣きながら俺のところにやってきたことがあったよな」
「そうだっけ?」私は記憶になかった。
「どうしたんだ?――ってきいたら、机の引き出しが開かないって言って号泣したんだ」
少しずつ記憶がよみがえってきた。――なるほど。そういえばそんなこともあった。「よく憶えてるね」
小学校の低学年だったと思う。あの時、机の奥にプラスチック製の定規が引っかかって、引き出しが抜き出せなくなっていたのだ。大事なテスト前だったこともあって、焦って泣き出した記憶がよみがえる。
結局、美佐男が力づくで引き抜いてくれたけれど、引っかかっていた定規は奥の方で真っ二つに折れていた。「あのあと、美佐男お兄ちゃんが新しい定規を買ってくれたよね。自分のお小遣いで」
いつの間にか、おばちゃんは眠りについている。美佐男が揺さぶって起こそうとするのを、私は止めた。「寝かせといたら?――疲れてるよ」
「トシを取ったな」と美佐男はつぶやいた。「なあ……。あの、さあ……」
「ん? 何?」
「さっき、東京で彼女がいるって話しただろ?」
「うん」
「とっくに別れてんだよね」美佐男がぼそりと言った。
「へえ。そうなんだ」私は返事に困惑した。そんなこと言われたって、私としてはどう答えるのが正解か、見当がつかない。
「あのさ……」
「何?」
まだ言いたいことがあるのか。美佐男を見ていて、私はふと彼の少年時代を思い出した。身体は大きく成長していても、臆病な性格はあの頃と少しも変わっていないのではないか。
言いたいことがあってもはっきり言えずにモジモジして、うまく気持ちを伝えられない。そんな美佐男を、私はいつもじれったいと感じていた。
「あのさ……」もう一度繰り返す。
「はっきり言っちゃえば」私はうながす。
「机のことなんだけど」
「机?」意外な言葉が飛び出した。このタイミングで、どうして机なのだろう。「机がどうかした?」
「いや。何でもない。ははは」美佐男は吹っ切るように笑い、「忘れてくれ」と言った。「あれは、なかったことにしてくれ」と美佐男はあらためて強い口調で言った。
私には彼の言っている意味が分からなかった。「あれ」とは、何を意味しているのか――。
3
美佐男が何を言いたかったのか、彼の真意を私はその日の夜、知ることになる――。きっかけは父親の滋との電話だった。
「美佐男の奴、元気にしてたか?」と滋が切り出した。
「うん。背もずっと伸びていて、声もすっかり大人になったって感じ」
「そうか」と滋は言った。「お前に何か言ってなかったか?」
「何かって?」
「たとえば、机のこととか」
「机?」いったい何?――美佐男といい、滋といい、どうしてそこまで「机」にこだわるのか。「机が何だって?」
「なんだ、あいつから何も聞いてないのか」滋は嘆くように言った。「しょーもない奴だな、まったく」
「何が?……」
「じつはな、あの机の引き出しの中に、手紙が入っていたらしいんだ」
「手紙?」
「ラブレターだよ」
「ラブレター?」滋の口から飛び出した、あまりにも意外な単語に、私は意表を衝かれた。「そんなの、私はいま初めて聞いたんだけど」
そこまで言いかけて、
(そうか、だから――)
この時、私は大凡のあらゆることを察した。
美佐男がラブレターを私の机の引き出しに入れたのは、たぶん私たち家族が引っ越しをする前日のことだ。あの日、学習机は滋が知人から借りてきた軽トラックの荷台にあった。臆病な彼にしてみれば、想いを伝える千載一遇のチャンスがあるとしたら、その時以外考えられない。
私たちはその机を、いや家財道具のすべてを処分するつもりでトラックに積んでいたのだ。
でも、だけど、当時小学生だった美佐男はそれを知らなかった。引っ越し先でも私たちがその家財道具をまた使うものだと勝手に思い込んでいたのだ。
だから、美佐男は私が机の引き出しをあけたとき、ラブレターを読んでくれるものだと信じていた。
おそらくあの夜、辺りが暗くなるのを待ってから、他人の目を避けるように軽トラックに近づいて荷台に積んだ机の引き出しにラブレターを忍ばせたのだろう。自分の気持ちをストレートに伝えられない、いかにもあいつらしい行動――。
「何て書いてあった?」問題は中身だ。
「俺は読んでないよ。天池さんの一年忌のとき、俺も保(たもつ)から初めて聞かされたんだ」保というのは、滋の同級生で、あの日、軽トラックを貸してくれた人だ。
処分場へ持って行ったとき、保は机を荷台から下ろしたあとでもう一度引き出しを開けた。何か貴重品を取り忘れてないか確認しようとしたのだ。そのときになって初めて手紙が入っていることに気づいた。
「そうだったんだ」私はおどろいた。いまのいままで、何も知らなかった。どうして言ってくれなかったんだろう。「手紙はどうしたの?」
「見つけたときには、俺たちはもう村を出たあとだったからな。今さら渡しても遅いと思ったのだろう。あいつが処分してしまったらしい」
「で、手紙には何て?」
「お前のことが好きだという気持ちと、それから、夏休みに帰郷することがあったら、神社に来て欲しいということが書かれていたそうだ」
それを聞いて、私はすべてを理解した。中学生になって帰郷したとき、美佐男が妙によそよそしい態度を見せていたのは、私のほうに原因があったのだ。いや、私は何も知らなかった。だが美佐男は、私が何も知らないことを知らない。
私はてっきり、美佐男のあの態度は、思春期特有の照れ隠しと思い込んでいたけれど、本当は違った。あれは、帰郷した日に神社に来なかった私に対する失望だったのだ。
――ラブレターの返事はNO!
彼は、そう解釈した。ラブレターを贈った相手が約束の場所に来てくれなかった。イコールふられた。そう受け取られても仕方がなかった。
私の初恋は、こうして終わっていたのだ。
私の知らないところで。
再会したとき、美佐男は何度も「机」の話をした。直接聞くのが怖かったのだ。ラブレターの返事を。だから遠回しに、私の気持ちを確かめようとした。
小学生の淡い恋を、いまだに引き摺っている。――いや、再燃したというべきか。だから東京でできた彼女と別れた事実を、わざわざ私に伝えた。
「たまにはデートぐらいしてやれ」滋が言った。
そうしよう――私も思った。あいつは、私がラブレターを読んでいなかった事実をまだ知らない。誘われたら、いつでも会いに行くつもりだ。
今ならきっと笑い話になるだろう。保さんの悪口でも言ってやろうか。すべての元凶はラブレターを無断で処分したあのおじさんにあるのだから。
(完)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
