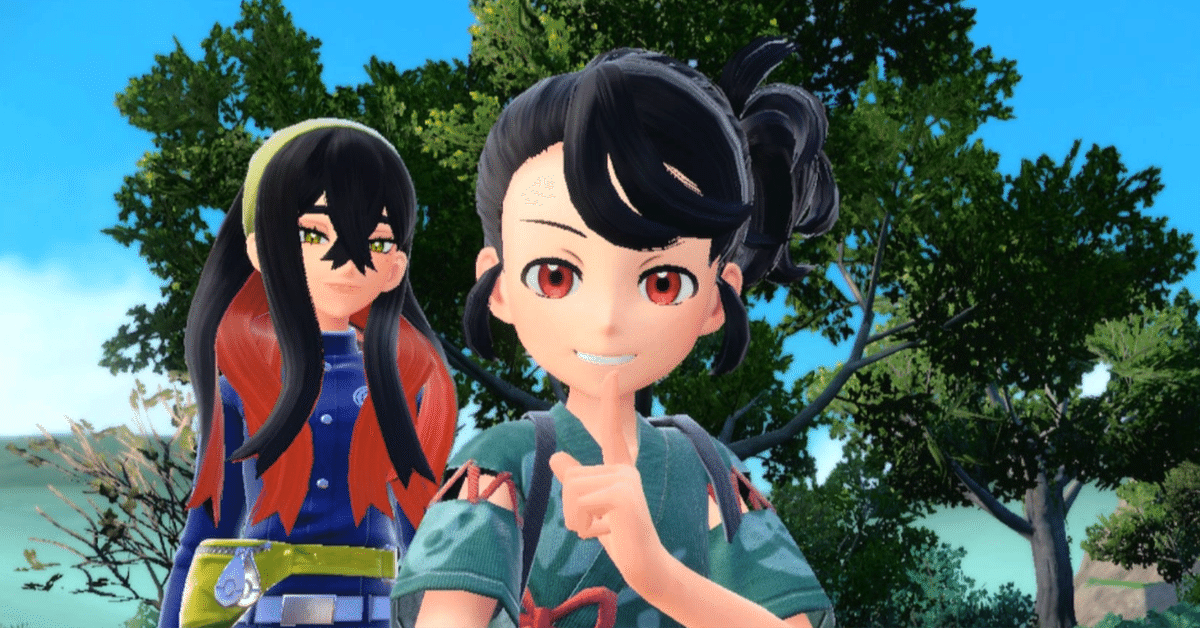
『碧の仮面』って三太郎か? について考える。
クリアした後のネタバレ入り与太話です(挨拶)。
前置き
トップ画像は可愛い僕のトレーナーを見て欲しかっただけなので関係ありません。
この考察はただの与太話なので、あまり深く考えずにお読みください。
詰めが甘いし、記憶を頼りに書いているのでところどころ間違っている可能性が多いに有り得ますが……まあ、プレイログみたいな感じで読んでいただければ幸いです。
なんやかんやで、僕はポケモンというゲームが、その世界観が好きなんだなぁ……みたいな、そんな感じの、ほぼ二次創作めいた、ただの考察です。
DLCの興奮冷めやらぬ皆様の一助となれば幸いです。
モチーフについて考える
桃太郎
『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝「碧の仮面」』について話しますけれども……あれはなんだ、桃太郎モチーフなわけですよね。
まあ前情報からして、「イイネイヌ」「マシマシラ」「キチキギス」という犬と猿と鳥をモチーフにしたポケモンが出てきていて、あとなんか仮面を被った、鬼? っぽいものも示唆されていて、「おいおいおい〜! 桃太郎じゃんかぁ!」と僕は思っていて……で、実際、プレイしてみると、これは桃太郎モチーフの物語であるように思えた。一旦、ゲームをプレイ中は、そこまで考えた。
実際、スイリョクタウン……というか、「ともっこプラザ」にある看板を見てみると、それがちゃんと明示されている。

この看板には、このようなことが書かれている。
むかしむかし キタカミの里に
恐ろしい鬼が おったそうな
鬼は 村の裏山を 根城にし
山へ 入った人を 驚かしておった
ある日 怒り狂った 鬼が
山より 下りて 村の者は 怖れたが
偶然 そこに いあわせた
イイネイヌさま マシマシラさま
そして キチキギスさま
3匹の ポケモンたちが 命をかけて
鬼を 山へと 追いかえしたそうな
勇気ある 彼らを 村人は
親しみを こめて ともっこと 呼び
亡骸を ていねいに 埋葬し
その上に ともっこの像を 建てた
なるほど、確かに桃太郎モチーフだろう。
ただ、何かがおかしい。看板を見てみると、何故か……右側に、人間らしき人物が描かれている。
これはなんだ……?
この物語は、どう考えても「桃太郎」がモチーフである。だが、肝心の「桃太郎」が、作中、出てこない。いや、ゲームプレイ中、僕はなんとなく、「自分が桃太郎役を務める」か、あるいは「スグリが桃太郎を務める」んだろうと思っていた。そういうつもりでプレイをしていたのだけれど——実際のところ、村の一部の家庭にのみ伝わる本当の伝承は、「桃太郎」とは逆であった。
つまり、鬼(オーガポン)はむしろ温厚で、大人しいポケモンであった。自分のトレーナーと一緒に、慎ましく暮らしていたのである。だが、犬(イイネイヌ)、猿(マシマシラ)、雉(キチキギス)が悪事を働き、それに激怒した鬼(オーガポン)が復讐をした、という筋書きである。
あれ、桃太郎いなくね?
桃太郎がいない。不在なのだ。
まあでも、物語として別に破綻しているわけじゃないし——そもそも上記の看板からして「嘘の伝説」なので、描かれている絵に不備があっても、支障はない。なんとなく、「ミスリードなのかなぁ」程度に思っていた。
で、つい数時間前、「そう言えば後編っていつ出るんだろう?」と思って公式サイトを見ていたところ、後編に登場すると思しき新キャラクター一覧が載っているページを発見した。あんまりちゃんと情報を追っていなかったので、ここぞとばかりに確認してみることにした。ゼイユちゃんとかサザレさんは、DLCをクリアするともう会えないので、せっかくだし面でも拝んでおくか、という気持ちであった。

そんな中、「ブルーベリー学園」関係者が紹介されている箇所を見つけた。このうち、前編の『碧の仮面』に登場するのは、「ブライア」という教職員だけである。他の5名は、未登場(のはず)。なのできっと、彼らは後編の『藍の円盤』で出てくるのだろう……ん? 何か既視感がある。なんだ……。

あ、あー……確か、Xのリポストか何かで見たことがある。男の娘なのか女の子なのかという議論で盛り上がっていた新キャラクターだ。公式サイトの情報を見ると、「ブルーベリーグ」の四天王の一人らしい。へー。見た感じ女の子っぽいけど……確かに男の娘っぽくも見えるか? まあ、見た目上の性別はどうでもいいとして……名前がなんか……男の子っぽ……え? ……た、タロ……?
タロ!?
タロってお前……タロってお前……そ、そんなに分かりやすい名前なことある!?
モモタロさんてこと!?
いやもちろん、ポケモンの登場人物はほとんど植物に縁のある名前だから、タロイモとかが語源なんだろうけれども……お前……本当は、桃太郎なのでは……?
ということについては、なんか、色んな人が考察していそうなのだけれども、最近SNSとかちゃんと見ていないので、このことに気付いた瞬間に思い至った『碧の仮面』に対する考察を、自分の整理のためにも、書こうと思ったわけである。
浦島太郎
後編の『藍の円盤』のメインポケモンは、亀である。

しかも、後編の舞台となる「ブルーベリー学園」は、学校のほとんどが海の中にあるらしい。
そんなのはもう浦島太郎ではないか。
竜宮城ではないか。
気になるのは、浦島太郎には「時間経過」というギミックが用意されている点だ。「桃太郎」がパーティを組んで魔王を討伐する、現代で言う「剣と魔法のファンタジー」系譜であるのに対し、浦島太郎は「玉手箱を開けると時間が経過していた」という、なんとも衝撃的なオチのある昔話である。SFに近い。
しかし、はて、時間経過……。
考えてみるに、そもそも『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』は、時間をテーマにした作品である。「コライドン」は過去、「ミライドン」は未来に存在したポケモンだ。これが「エリアゼロ」と呼ばれる場所にある、超絶科学者であるペパーの親が作った「タイムマシン」の力によって、現代にやってきた……というのが、そもそものストーリーだ。
加えて、上記した「テラパゴス」は、本編の時点で言及されていたポケモンである。「オーガポン」やら、「イイネイヌ」「マシマシラ」「キチキギス」やらに比べると、もっと物語本編の根幹に関わってくる可能性が高いのだ。
仮に「ブルーベリー学園」を「竜宮城」とした場合、「玉手箱」らしきものが発生する可能性が極めて高い。しかも、こいつは「ブルーベリーグ」の四天王である。

いやしかし、そうなると「浦島太郎」の特異性のもうひとつ、「時間経過」のギミックとは別に、「桃太郎」とは異なる特筆点が消化出来ない。
すなわち、乙姫の存在である。
「浦島太郎」は決して、助けた亀に連れられて竜宮城へ行くだけの話ではない。キーアイテムである「玉手箱」を、乙姫によって託されるシーンがなければ成立しない。つまり「浦島太郎」において、乙姫は必要不可欠な存在なのである。
しかしながら、現在公開されている登場人物紹介の中に、乙姫っぽい存在は確認出来ない。タロを仮に「桃太郎・浦島太郎」的なポジションと考えると、乙姫は不在ということに……な……
ならない……のか?

いや、超怪しいやつがいたわ。
しかも美人で、姫っぽい雰囲気がある。
てことは、こいつが乙姫なのか……?
よくよく見てみると、このブライア先生、服装がおかしい。「紫ジャケットに赤パンツ」という組み合わせが、ファッションセンスの観点から見ておかしい、という意味ではない。
この配色、「スカーレット・バイレット」である。
ていうかこの服、よくよく見てみると、左右で意匠が異なる。ブライア先生から見て左側は、「スカーレット」のタイトルロゴの模様だし、右側は「バイオレット」のタイトルロゴの模様だ。どう考えても何かある。
いやそもそも、何かない方がおかしいようなキャラクターだった。林間学校の引率という役割しか与えられていなくて、しかも登場回数もやけに少なかった。唯一、ブライア先生の出番があったとするなら、キタカミの里の中心地にある「てらす池」で、我らがゼイユちゃんと一緒にミロカロスを倒した際に——違和感アリアリで登場したシーン、くらいなものである。
てらす池……。
いや、一旦、置いておこう。とにかく、ブライア先生はどう見ても重要人物であり、後編『藍の円盤』が「浦島太郎」モチーフであることを考えると、彼女が「乙姫」ポジションを担う可能性が高い。逆に言えば、「タロ」はミスリードの可能性すらある。この物語は「桃太郎・浦島太郎」をモチーフにしているわけではなく、あくまでも本編の流れに沿った、「時間」をテーマにした物語であると思える。
そう、浦島太郎が本命なのだ。「時間」と言えば、浦島太郎である。
しかし何か引っかかる……「桃太郎・浦島太郎」と来て、もうひとり、太郎がいたような……「三年寝太郎」でもないし、「力太郎」でもないし……でもDLCは「前編・後編」の二種類だから、さらに太郎をモチーフにするような余裕はなかったような……。
金太郎

いや居た。
金太郎をモチーフにして、且つ、「スカーレット・バイオレット」を繋ぐキャラクターがいた。
サザレさんである。
これはもはや周知の事実かと思われるが、「サザレ」のデザインは、過去作である「LEGENDS アルセウス」の主要キャラクターである「セキ」と酷似している。だからつまり、子孫である可能性が極めて高い。
それが何を意味するのか。
「セキ」がリーダーを務める「コンゴウ団」は、「時間」を重んじる派閥である。「シンオウ神話」とか「シンオウ昔話」については各自調べて欲しいが、ポケモンという世界観の起源を考える上では、「シンオウ地方」及び「ヒスイ地方」は避けて通れない。というか、「アルセウス」というポケモンが全ての始祖である。地球とか宇宙とか、そういう規模で「はじまりのポケモン」なのである。
そんな「アルセウス」が生み出した2匹のポケモンのうち、「時間」を司るのが「ディアルガ」である。他方で「シンジュ団」が信仰している「空間」を司るポケモンは「パルキア」なのだが……この「シンジュ団」のリーダーである、「カイ」に似たキャラクターは、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」及び、DLCの「ゼロの秘宝」には出てこない。
なんでだろうと思っていた。
あるいは後編の『藍の円盤』で出てくるのかなー? くらいに思っていた。
思っていたが——「時間」という軸で考えると、納得である。
今回の物語は、あくまでも「時間」がテーマだからだ。だから「空間」を司る「パルキア」及び「シンジュ団」の系譜は出てこないのだ。当然である。
だからと言って、サザレさんのねじ込み方は少し突然過ぎない? という気もする。いや、サザレさんは可愛いし、青少年の性癖を破壊してくれる最高のキャラクターなので登場してもらう分には全く問題がないのだけれど——それにしたって、「ただの旅するカメラマン」であり、「ガーディが相棒」というくらいしか特色がない。いくら「時間」がテーマの物語だからと言って、学園生活と無関係の一般人をねじ込むには、少し無理があるような……。

いや、あった。
ガチグマである。
サザレさんとのミニイベント、ポケモン撮影のクリア報酬的な位置づけとして捕まえられる、「アカツキ」と呼ばれるガチグマである。これは、「LEGENDS アルセウス」で「ヒスイ地方(現在のシンオウ地方)」に生息していたポケモンだが、長い年月を掛けて海を渡ってきた……というような発言があった。
まあ、キタカミの里は東北地方なのだろう。
つまり「サザレ」というキャラクターは、この「アカツキ」のイベントに参加することにより、いわゆる「三太郎」の一角を担うポジションを確立したのだ。だからなんだという話なのだけれども、大事なのはあくまでも、
「三太郎=時間」
という関係性が成り立っていることである。
太郎関連の昔話ひとつに、「時間」による物語が関連していると見ることが出来る。先に述べた「浦島太郎」は、物語そのものが時間をモチーフにしていて、玉手箱だの、竜宮城だの、後編に期待出来るギミックが多いにある。「金太郎」に関しては関連性こそ薄いが、「時間」を信仰していた「コンゴウ団」の子孫であるサザレさんが、「写真」という、これまた「時間」に関連した道具を扱っているのが憎い。「時間を永遠にする」というのが、写真の特色と言える。DLCによって、本編で扱われてきた「時間」というモチーフが、さらに拡大した解釈を与えられているのだ。
いやしかし、そうなってくると……『碧の仮面』のモチーフであるはずの「桃太郎」とは、一体なんだったのか……?
「桃太郎」、延いては『碧の仮面』から、どのようにして「時間」の要素を考察すれば良いのだろう?
三太郎と時間が密接にリンクしていることを考えると、どうしたって、「桃太郎」にもその役割があって然るべきである。
地方の歴史について考える
キタカミの里
以上は、なんとなくゲームを遊んだり、インターネットをしていれば考えつきそうなことである。考えつきそうなことを、あえて「僕が思いつきました!」みたいに書いてみたが、多分みんな気付いていると思う。
重要なのはここからだ。
僕の考えでは、「桃太郎」も「浦島太郎」も「金太郎」もミスリードである。「DLCは、三太郎モチーフなんだ!」という引っかけだ。これの裏には、必ず「時間」が関連している。先に述べた通り、「浦島太郎」はモチーフ自体に、「金太郎」は過去の「コンゴウ団」や「写真」などと言った関与が考えられる。
では「桃太郎」とは、前編『碧の仮面』とは何だったのか。
考えるに、これは「てらす池」、延いては「テラスタル」「エリアゼロ」という、本編のメインイベントと地続きのお話なのである。
林間学校で追加コンテンツ、などではない。
正統な続編であり、むしろ本編を深掘りする上で、重要な物語だ。
キタカミの里のマップを確認すると、「てらす池」はマップの中心に存在することがわかる。「エリアゼロ」も、パルデア地方の中心である。
また、「てらす池」周辺には、「エリアゼロ」にのみ生息していた「キラーメ」「キラフロル」の生息も確認出来る。明らかに、「結晶体」のエネルギーによって生み出された、あるいはそのエネルギーを主成分として繁殖しているポケモンと考えられるだろう。即ち、「てらす池」は「エリアゼロ」とほぼ同一の構造を有しているということになる。まあこれは、ゲーム内でブライア先生も述べていた。
さて、ではこの「てらす池」に、何故、(日本から見て)国外の大穴深くに存在した「テラスタルオーブ」の元となった「結晶体」が、遠く離れた日本の、しかも東北地方に存在しているのか、という疑問が発生する。これについては、恐らくは「オーガポンのトレーナー」が持ち込んだと考えるのが妥当だろう。昔々に結晶を手にした「男」がいて、その「男」が「オーガポン」と一緒にキタカミの里を訪れた。が、「男」と「オーガポン」は、日本人から忌み嫌われた……というような説明がゲーム中にある。
いや……待ってくれ。
異国から来た「男」が、村人から嫌われて、「鬼」と呼ばれた……。
いやいや、これまんま日本に伝わる、鬼の話だ。
海外との交易が始まった昔の日本において、初めて外国人を見た日本人が、彼らを指して「鬼」と評した逸話は有名かと思う。この物語は、まさにそのオマージュであろう。「男」と「オーガポン」は、村に馴染めず、ひとりと一匹で暮らしていたというような話が作中で語られていた。
しかし引っかかる。
「人間」ではなく「男」に固執する理由はなんだろう。
別に、昔話なんだから「女」でもいいだろうに。そもそも、性別について結構うるさく言われる昨今、性別を特定するような表記って、あんまりしない方が得策なような気がするんだけど……いや、待てよ?
そう言えばオーガポンって、メスだったよな……。
あれ、これ……シンオウ昔話では……。
夫婦だった……? ってこと……?
ともあれ、つまり、「男」と「オーガポン」は恐らく、パルデア地方からやってきたのだろうと推察される。彼らがやってきたのが何年前なのか? ということは推測しか出来ないのだけれども、これは「スカーレット(バイオレット)ブック」の発行年、及び「LEGENDS アルセウス」から考えることになる。
「スカーレット(バイオレット)ブック」が発行されたのは、およそ200年前とされている。この著作者である「ヘザー」が、200年ほど前に大穴を探索し、その冒険を本にまとめたものとされているからだ。
ヒスイ地方
さて、「LEGENDS アルセウス」の時代について考える。「アルセウス」で最も目立つ建造物と言えば、「ギンガ団」アジトだ。これのモデルは北海道は札幌市に現存する「赤れんが庁舎」こと「北海道庁旧本庁舎」である。1888年に完成した建物であるので、「アルセウス」の時代は、少なくとも現在から見て150年程度昔の話と考えられる。つまり明治時代だ。ポケモンの歴史が日本の歴史に即しているとは思わないけれども、1876年頃に「廃刀令」というものが下されて以降、日本からは帯刀文化=武士という存在が消えていった。「LEGENDS アルセウス」にはそうした、武士や武家というキャラクター造型が見られない。だから、1888年以降という読みは当たっていそうに思える。
さらに時代を狭めてみる。「アルセウス」で特徴的なのは、「コトブキムラ」にある写真屋だ。

グラフィックこそ簡易的だが、その構造から見るに、これは1880年代頃に「暗箱/暗函(あんばこ)」と呼ばれていた頃の写真機に似ている。加えて、この写真屋ではかなり簡易的に写真撮影を行えることから、「ロールフィルム」による撮影を行っているように思われる。要は、扱いやすくて安価なフィルムであり、それ以前にあったフィルムと比べると、手頃になったのである。
そう考えると、やはり1890年代から1900年代と考えるのが妥当だろう。ちなみに、1903年には手提暗函(てさげあんばこ)という、持ち運び可能なカメラが一般に普及し始めた。まだ「写真を撮る」という技術が特別持て囃されていることを考えると、「アルセウス」は1900年頃が妥当だろう。
つまり100年、ないし120年くらい前、ということになる。
つい先日、2023年9月1日に「関東大震災」から100年という節目を迎えた。ヒスイ地方は北海道が舞台であるので、もし100年前だったとしても被害は多くなかったように思えるが——放牧的で文化的な「ヒスイ地方」及び「コトブキムラ」を見るに、やはりそうした大規模な災害が起こる前、明治時代後期とするのが妥当だろう。明治時代は1868年から1912年までの45年間を指す。なのでざっくり、1900年頃、明治33年とか、その辺が想定される。まあこの辺はざっくりでいい。
何が言いたいかというと——要はたった120年程度の昔でさえ、「ポケモン」は「恐るべき生き物であった」ということだ。これを念頭に置いて、話を進める必要がある。
シンオウ地方
先に触れた「シンオウ昔話」は、「アルセウス」よりもさらに古い時代の出来事である。簡単に話すと、「人間とポケモンは普通に結婚したりしていた」という昔話が、「ダイヤモンド・パール」で出てくる。昔話と神話がごっちゃになるが——「神話」の方は創世記に当たるので、日本で言う「天照大神」とか「木花之佐久夜毘売」とかが出てくる「古事記」よりもさらに古い話になる。「古事記」が8世紀くらいの話なので、ほんと、1世紀とか、紀元前とか、そのレベルだろう。
で、時が流れて、「シンオウ昔話」が語られるようになる。土地柄を考えると、これはアイヌ神話、いわゆる「天地開闢(てんちかいびゃく)」の内容を準えているようにも思える。まあ「天地開闢」と「古事記」は割と内容が似ているのでどちらを選んでもいいのだけれど……とにかく、「シンオウ昔話」と「アルセウス」の時代は、まったく別であると考えられる、という話だ。
ざっくり120年前とした「アルセウス」の時点ではまだ、「ポケモンは危険生物である」という思想が罷り通っていた。が、逆に言えば、「シンオウ昔話」で触れられているような「対等の立場」からは若干、逸脱しているように思われる。昔は、ポケモンと人間は同じと考えられていた。しかし、「アルセウス」の町並みを見るからして、既に人間は「人間」という個別の地位を確立している。建物を建築し、囲いを作り、ポケモンを「ポケモン」として認識するようになった。
言わば、その時点で既に、地球の支配者となっていたわけだ。
地球の支配者になるとはどういうことか。
既に「シンオウ昔話」にあったような、「ポケモンと人間は同じであった」という文化は失われている、ということである。にも関わらず、「男」と「オーガポン」には密接な関係を見出すことが出来る。
つまり、「男」と「オーガポン」に関する出来事は「アルセウス」の時代よりも前に起こったと推測出来るわけである。
さて——ここでようやく『碧の仮面』の事件が起きた時代を特定したい。
要するに「ともっこ伝説」が生まれた時代のことである。
冒頭で触れた「桃太郎モチーフ」のポケモンである、「イイネイヌ」「マシマシラ」「キチキギス」の三匹。こいつらは何なのかという話になる。一体、いつの時代の話なのか? 時代を考察する鍵は「仮面」と「石像」であるが、木工や石工の技術はもう何百年も前から存在している。これが日本の話であれば、時代の特定は難しい。
だが、重要な鍵がもうひとつある。
「テラスタルオーブ」である。
正確には「結晶体」かもしれないが——とにかく、「オーガポン」が被っている仮面には、そうした「結晶体」が埋め込まれている。要は、後天的に「オーガポン」は野生の「テラスタルポケモン」としての特性を得た。ではその「仮面」に埋め込まれた「結晶体」は、どのようにして持ち込まれたのか? そう、これこそが「オーガポンのトレーナー」である「男」が持ち込んだものであり、同時に「てらす池」に撒き散らした、「結晶体」そのものであると考えられる。
そう考えると、人類が初めて「パルデアの大穴」を調査した200年前から、「当時を知る者が全ていなくなった」までの期間が、「ともっこ伝説」の生まれた時代と考察される。何故「当時を知る者が全ていなくなった」時代と仮定するのかと言えば、スグリによる説得が功を奏したという背景に着目しているからだ。「スイリョクタウン」の長老的存在である管理人のおっちゃんですら、スグリに反対せず、事実を受け入れている。当時を知る老人であれば、こんな反応は絶対にしない。つまり、価値観がアップデートされた証左である。
であれば、「伝説」が生まれてから、150年以上は優に経っているだろう。ゼイユの年齢は明言されていないが、およそ13歳から18歳程度と仮定する。弟は年が離れていそうなので、両親を40歳程度と考える。となると、仮面職人の祖父は、時代も鑑みて、60歳後半から70歳前半くらいか。さて、そんな爺ちゃんが口伝によって言い伝えを聞いているわけだが、当時を知る人物は既にこの世に存在しない。であれば、爺ちゃんの曾祖父、さらにその上——くらいが、最初に「仮面」を作った人物と推測される。
そう考えると、ざっくり150年前くらいの出来事と考えるのが妥当な線だ。
つまり「アルセウス」よりも昔の話だ。余談だが、「アルセウス」の時点、つまり120年前に20代から30代くらいの「セキ」の子孫が、現代で20代くらいの「サザレ」であるとするなら、「セキ」から見た「サザレ」は、「玄孫(やしゃご)」ということになる。まあもっと若くして子孫繁栄していれば、さらにその下の「来孫(らいそん)」の可能性もあるが……とにかく、そのくらい昔の話だから、現代の「スイリョクタウン」で「スグリ」が村のみんなを説得出来たというのも、なんとなく納得である。言ってみれば、村のみんなはただ「伝説」として「ともっこ」を祀っていただけであって、正直言ってそれの善悪などどうでもいい、ということなのだろう。文化の継承というのは、得てしてそういうものである。100年は少し短いが、150年くらい経つと、感情によって生まれた文化は、跡形もなく消え去るものだ。
パルデア地方
話が逸れたが、パルデア地方の歴史についても考える。
というか、「桃太郎」の「時間」とは、一体何なのか? という、メイン考察について考える。
上記したように、「結晶体」が発見され、(恐らく)採取されたのは200年ほど前。「ともっこ伝説」が生まれたのは、150年前くらいと仮定出来る。そして「アルセウス」は120年前。
まず「アルセウス」を考える。プレイ済の方ならわかると思うが、この時代、ポケモンは超危険な野生生物だ。人間に普通に攻撃してくるし、最悪死に至る。それより30年ほど前、「キタカミの里」においては、「鬼が暴れる」という事件が起きた。そう考えてみると、当時の「キタカミの里」の住人が「オーガポン」の暴力性に恐れ戦き、「ともっこ」たちを祀ったのも順当と言える。「オーガポン」はまさに、鬼そのものだったのだ。トレーナーに使役されることもなく、圧倒的な力で(草ポケモンのくせに、毒タイプの「ともっこ」を粉砕していることからも、かなり強いことが伺える)捻じ伏せたわけである。
そしてその力の源は、「テラスタルオーブ」である。
あるいは「結晶体」だ。
200年前というのは——「スカーレット・バイレット」の発売を考えると、1822年頃。日本は文政5年である。
さてここで、参考のひとつとして、日本の実際の歴史と照らし合わせる。
キタカミの里は日本の東北地方が舞台であろう。
一方で、パルデア地方はスペインが舞台とされている。
日本とスペインは繋がりの深い関係性がある。興味がある方は自分で調べて欲しいが、1549年に言わずと知れた「フランシスコ・ザビエル」が到来したのを皮切りに、日本とスペインは友好的な関係を築く。日本に根強く残る南蛮文化の元は、スペインからの輸入品がほとんどだ。カルタだの、タバコだの、カステラだの、南蛮由来のものが今でも多く残っている。しかしながら、一時期を境にして、日本は「鎖国」に入るので、一定期間、交流は途絶えることになる(実際には色々あったんだろうが、歴史的にはそういうことになっている)。
さてその後、1868年に日本とスペインは「修好通商航海条約」というものによって国交を再開する。もっとも再開したは良いものの、その当時は既に日米間で別の条約が結ばれていたり、他の国との国交も盛んに行われていたので、ザビエル期の南蛮国交よりは希薄だったようだけれども——とにかく1868年に、そういう条約が結ばれたのだ。
2022年から数えると、実に154年前ということになる。
うーん……なんだか、しっくり来る時代設定だ……。
この条約が結ばれたということは、国間の行き来は実にスムーズになったということだ。
以下は単に想像によるものだが——約200年前に発見された「結晶体」はパルデア地方で研究され、「テラスタルオーブ」という形で、あるいは宝飾品として加工されるにまで至った。その後、関係者のひとりが日本に渡った。この時、「オーガポン」が一緒にいたかどうかまではわからないが——「キタカミの里」の住人が彼らを「鬼」と判断したということは、「オーガポン」は「キタカミの里」及び「ヒスイ地方」ですら見ることが出来ない、異国のポケモンだったのだろう。となると、彼女もまたパルデア出身、という説が濃厚になってくる。
さてここからは完全に与太話になるが……日本に渡った「男」の目的こそ本編では明言されていないが、彼の行動から推察するに、「男」は「結晶体」の培養を目的としていたと考えると、辻褄が合う。パルデアの大穴には危険が多く、また自然発生する「結晶体」を採取は出来るが、それを人工培養することは出来なかったのだろう。
各国を転々としたのか、あるいは「男」と似たように、世界中に「培養地」を探していた研究者がいたのかは定かではないが、とにかく「男」は「キタカミの里」を訪れ、そして「てらす池」に、その可能性を見た。
だって彼、村八分にされているわけでしょう。
鬼だなんだと言われて、嫌われていたわけでしょう?
「オーガポン」という超強力なポケモンを連れている「男」が、「キタカミの里」の村人たちに嫌われてなお、その土地に居続ける理由がわからない。逃げちゃえばいいのに、わざわざ近くに住む理由ってなんだろう? 土地でしょう。土地に用事があったと考えるのが妥当なのだ。つまり「てらす池」の水質に用があったと考えれば、辻褄が合う。水質こそが重要だった。だからその場を離れられなかった。嫌われても、家がなくても、「男」と「オーガポン」が「キタカミの里」にこだわった理由として成り立ってしまう。
こうして考察してみると——DLC『碧の仮面』のストーリーは、本当に途中の途中、というか、本編『スカーレット・バイオレット』で語られなかった、「結晶体」の培養を目的とした物語と見ることが出来る。しかし、何故培養などする必要があったのか。そして何故、これが「時間」と関わってくるのか。それについての最後の鍵となるのが、「オーガポン」の行動原理である。
ポケモンについて考える
オーガポン
何故、キタカミの里に居続けたのか。
そして何故、最終的に主人公に捕獲されたのか。
先に述べた通り、「オーガポン」が「キタカミの里」にやってきたのは150年前と推定される。ということは、「オーガポン」は150年近く、「男」の帰りをひとりで待っていたことになる。
あまりに長すぎる。
「てらす池」にて培養された「結晶体」の一部が、あんなに巨大化してしまうほど——長い月日が流れたのだ。
であれば、どうして今更になって、主人公についていこうとしたのか。
そもそも……何故「オーガポン」は、150年もの間、待ち続けたのか。
この考察の総括として、ひとつの結論が導き出される。
「男」は、過去にも「時間移動」をした経験があるのではないか、ということだ。
ポケモンの寿命は個体によって異なる。そもそも「アルセウス」に至っては創世記から存在しているのだから、今更「オーガポン」が何年も生きているのは不思議ではない。
だが、「男」は人間である可能性が高い。
つまり「オーガポン」は過去にも、「男」を待ち続けた過去があるのではないだろうか。既に本編にて「タイムマシン」が登場しているので、今更トンデモ考察でもないとは思うが——要するに、200年前にオーガポンと共に「結晶体」を見つけた研究者は、各地を転々としながら、「結晶体」の一部をめぼしい培養地に落とし、時間を飛んで、その可能性を見たのではないかという考察が成り立つ。たった一年でも、「培養地として適切か」という判断は付きそうなものだ。だから「男」は、各地のめぼしい培養地に「結晶体」を落とし、その度に一年近く飛んで、当たり外れを確かめた。
そして、「キタカミの里」の「てらす池」で、いよいよ腰を落ち着けることになった。
いやいや、オーガポンも連れて行けよ、という気もするが、時間を飛んだ先で、その土地を守っている相棒が必要だと考えると辻褄が合う。要は、命に限りのある研究者である「男」は時間を飛び、長寿のポケモンである「オーガポン」は、生活拠点と培養地を見守りながら、「男」の帰りを待っているのだ。
だから150年もの間——「オーガポン」は、「男」と暮らした洞窟を守りながら、「てらす池」も見守った。「ともっこプラザ」の看板にも、
鬼は 村の裏山を 根城にし
山へ 入った人を 驚かしておった
という記述がある。つまり、「てらす池」を守っていたわけである。「オーガポン」はそうすることしか出来なかった。盗まれたお面を取り返そうと「ともっこ」たちを襲ったのも、「結晶体」の重要性を認知していたからと考えられる。
加えて「男」は、「ともっこ」に襲われて以降、姿を消している。
亡骸があるわけでもない。姿を消したのだ。
どこに行ったのか。
何故帰ってこないのか?
そう、未来に飛んだからである。
研究者の勘なのか、タイムマシンの誤作動なのか、あるいは「てらす池」にて培養に掛かる時間をそう算出したのか——真偽は不明だが、「男」は150年以上先の未来に飛んだ。あるいは「ともっこ」に襲われ、自分の治療のために、さらに未来の技術に託したとも考えられる。とにかく「男」は未来に飛んだ。「オーガポン」は未来でまた「男」に会えると信じて、ずっと待った。洞窟の中で、ひとりで待ち続けた。でも、いつまで経っても「男」は戻ってこない。もう、「男」は戻ってこないのかもしれない。そんな折に——自分のために、自分の大切な宝物である「男」との思い出の品、あるいは「結晶体」そのものである「仮面」を、主人公が取り戻してくれる。
それが『碧の仮面』の時間軸である。
「オーガポン」は、一年に一度の祭りを唯一の楽しみにしていた。
それ以外は、やることなどなかった。
もう、「結晶体」の培養は終わった。
守るべきものもなくなった。
しかし、いつまで経っても「男」は戻ってこない。
もう「男」は戻ってこないのかもしれない。
これ以上、待ち続けるのにも疲れてしまった。
だったら、この「人間」と一緒にいるのも、悪くないかもしれない。
「オーガポン」を取り巻く物語は、『碧の仮面』において、ようやく終わりを見た——とするのが、僕なりの考察である。つまり「オーガポン」の使命とは、日本という土地における、「結晶体」の培養だったのだ。
ともっこ
さて最後に、最初の疑問に戻る。
桃太郎は誰なのか、という謎だ。
冒頭で掲載した、「ともっこプラザ」にある看板をもう一度見て欲しい。

お気付きだろうか。
僕はかなり後になって気付いたのだが……実は気付いていない人も多いかもしれない。
というか、「謎の人物」に気を取られて気付いていなかった。
実はこの三匹、よく見ると、毒の鎖がないのだ。

特に分かりやすいのが「キチキギス」であるが、このポケモンが飛行したら、普通、腹部に毒の鎖が見える。なのにそれがない。
「イイネイヌ」の首輪も、「マシマシラ」の緊箍児(きんこじ)らしきものも見当たらない。
これが何を示すか。
僕はこう考察した。
「看板に書かれた物語と、ともっこを祀った像は、別の伝説なのではないか」
というものだ。

とは言え、「看板が建てられた時代」と「ともっこ像が建てられた時代」は一致すると思う。口伝の中で、あるいはキタカミの歴史の中で、「毒の鎖前後」の「ともっこ」が混濁しているのではないか、というものである。
ともっこ像を見れば分かる通り、毒の鎖を彷彿とさせるお供えがなされている。だが、看板にはない。加えて、この三匹は「けらいポケモン」という分類になっているので、そもそもが「群れて悪さをする」性格の悪いポケモンではなかったのではないかと考えられる。
恐らく、彼らにはまだ、語られていない歴史がある。
150年前に「オーガポン」たちがやってくるより前に、「キタカミの里」には、本当に鬼が来ていた。それを追い払った人物こそが、三匹のポケモンを使役したポケモントレーナー。つまり「桃太郎」である。
DLC後編『藍の円盤』では、この「太郎」と「時間」による物語が展開すると予想している。あくまで予想だが……そのキーアイテムとして、「玉手箱」が利用されるのかもしれない。毒の鎖によって悪に染まる前の、純粋であった、「桃太郎」の「家来」であった三匹の「ともっこ」が、別フォルムという形で登場するのではないだろうか。
つまり、「桃太郎」とは、結局のところ、一周回って、「主人公」になる気がしている。「毒の鎖」による悪化が起こる以前の「ともっこ」を使役して、主人公は「桃太郎」となる。あるいは「テラパゴス」を使役して、「浦島太郎」となる。さらに言えば、「アカツキ」に跨がって、「金太郎」とも成り得る。
僕はこの「ともっこ」たちに、さらなる活躍があると見ている。
まあただの与太話なんだけれど……『碧の仮面』で終わらせてしまうには惜しいくらい、よく出来たポケモンたちだと思うので、そう願っている。
総括
さて、最後に総括である。
喋りたいことは喋ったので概ね満足だが——主人公が「太郎」だとするなら、「鬼」は誰なのかという話になってくる。
これが「スグリ」だ。

前編をプレイした方なら分かると思うが、どう考えても闇落ちしている。
この「スグリ」の暴走から世界を守るのが、主人公、つまり「太郎」の仕事である。そしてそのために、「ともっこ」たちは真の力に目覚めるのだ。
犬(イイネイヌ)と、
猿(マシマシラ)と、
雉(キチキギス)と、
亀(テラパゴス)と、
熊(アカツキ)と、
鬼(オーガポン)を引き連れて——無敵の「太郎」となり、鬼を退治する。
そういう筋書きであれば——なんか、美しいんじゃないかな、と思った。
さて最後の最後に余談だけれども、「オーガポン」のトレーナーが「男」と言及されているのに、正直違和感があった。というのも、「研究員」でも「トレーナー」でも「異国の人間」でもどうとでも表せるのに、頑なに「男」と表現したのはどうしてか、考えてみた。
「オーガポン」がメスだから?
いやいや……それこそ、今のご時世、結婚が「オスとメス」という考え方はナンセンスだ。公民館のトイレの色使いを、「男は赤」「女は青」としたポケモンらしくない。超余談だけど、「レッド(男)」「ブルー(女)」と考えると非常にポケモンらしいと言えなくもないけれど、若い世代には伝わらないだろう。
さておき、どうして「男」と限定したのか。
それは「スカーレット(バイオレット)ブック」の著者である「ヘザー」が、「男」と明言されているからだ。レホール先生の授業において、「ヘザー」が「男」であることは明言されている。
まあ、これは本当に与太話もいいところだけれど——わざわざ「男」と明記した意味を見出そうとすると、「オーガポンのトレーナー」=「ヘザー」という可能性が考えられるわけだ。
そうなってくると、「ブライア」の存在にも、意義が強まる。
未来へ飛んだ「ヘザー」と「ブライア」が対面する、というような妄想も捗るわけだ。
……まあそこら辺は蛇足のような与太話だけれども、とりあえず、『碧の仮面』を遊んだ直後の僕はそんなことを考えました、というのをどこかに残しておきたかったので、考察記事みたいな形で書いてみました。
めっちゃ長くなっちゃいましたが、読んでいただいた方がいるようであれば、ありがとうございました。まあみんなもそれぞれの考察をしてみると楽しいかもね、というところで。
後編の『藍の円盤』を実際にプレイして、「いや自分の考察全然ちげーし!」と笑える日が来るのを待ちましょう。
そんなわけで以上、『碧の仮面』の考察でした。
次回は後編、『藍の円盤』考察でお目に掛かりましょう。
さようなら。
追記
書き終えて読み直して、2個触れていない場所があったので追記しておく。
「何故培養などする必要があったのか。」と書いている。これは、「結晶体」を培養する必要についての説明であるが、書き漏らしていた。
これを考えるためには、そもそも「タイムマシン」というトンデモ装置について考察する必要があるわけだが——まあ、掻い摘まんで言えば「テラスタル」及び「結晶体」には、ポケモンを強化するという用途の他に、時間跳躍に関するパワーが秘められているのではないだろうか、とする考察である。
本編『スカーレット・バイオレット』において、「パラドックスポケモン」と呼ばれる、「エリアゼロ」にのみ生息するポケモンが登場する。これらは、「過去/未来」からやってきたポケモンである。しかしながら、このポケモンたちは、「オーリム/フトゥー博士」が「タイムマシン」を発明するよりも昔から、存在が確認されている。
であれば、そもそも時間跳躍の要は「タイムマシン」ではなく「テラスタル」にあると考えるのが妥当だ。わざわざ「パラドックス」などと不思議そうに言わずとも、単に「結晶体には時間跳躍の効果がある」とすれば、それによって「パラドックスポケモン」たちは、人工的にではなく、自然発生的に、過去と未来を行き来している可能性がある。そう考えると、辻褄が合う。
さて、そんなトンデモ鉱物である「結晶体」を培養し、増殖させ、人類の発展を目指そうとするのは、そこまでおかしな話ではない。だから「男」は、「キタカミの里」の「てらす池」において、培養をする必要があった——というか、培養して増やしたかったのだ、と考えることが出来るというものだ。
もうひとつ、「ともっこ像」のお供えについても書き忘れていた。
僕は「看板に描かれたともっこの絵には毒の鎖がない」と言及していた。そして同時に「看板の時期とともっこ像の時期は一致すると思う」などと書いたが、多分これは誤りで、看板は新しく建てられたものと考えられる。
というのも、ともっこ像と看板を見比べると、明らかにともっこ像は古いことがわかる。屋根の褪せ方が特徴的だ。


なので、本来は「ともっこ像」が先に立ち、これは「鬼退治伝説」の時に既に存在していた。一方で、次に起きた「オーガポンによる復讐」の伝説を期に、「看板」が建てられ、伝承は文字化されたと考えられる。まあ「塗り直しました」と言われたらおしまいだが、だったらともっこ像の方も直してやれ、という気はする。
要するにふたつの異なる伝説が後世で混ざり合い、「本当の鬼退治」と「鬼の復讐」が、ひとつの伝説としてまとまったのだろう。ともっこ像に「毒の鎖」によるお供えがされているのは、二つ目の伝説によるもの。一方で、「看板の絵」や「ともっこ像」本体は、毒の鎖以前の、善のともっこを祀るためのものと考えられる。
まあ与太話なので無理ある考察ではあるが、実際、帽子や前掛けや外套がお供えされている様は、なんとも違和感がある。やはり、当時の「ともっこ」は、毒の鎖がなく、それが「桃太郎」の消失により、悪化したのではないかと考える。
別段それがどうかという話でもないのだけれど。
今のところ、個人的に違和感を覚えずに済むとするなら、そういう無理やり考察をするしかない、という感じである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
