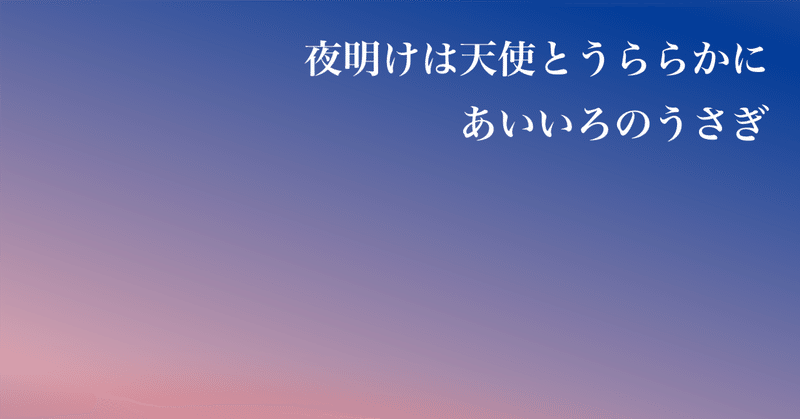
夜明けは天使とうららかに 1-3
〇 〇 〇
「菖太さん、おはようございます。朝ですよ」
朝の柔らかな陽光が差し込む中、聴きなれない優しい声が耳元に響いた。まだ寝ぼけている僕はぼんやり声のする方を向いて、その姿を目にして、飛び起きた。
驚きすぎて声も出ない。知らない人がそこにいる。それも外国人だ。ツインテールにした金髪が陽の光に当たってキラキラ輝いていて、僕を見つめる瞳は青い。身に纏ったワンピースは眩しいほど白くて、光っているのかと錯覚するほどだった。
「おはようございます、菖太さん」
そう言ってニコッと微笑んで見せるけど、僕はパニックだ。いきなり知らない人が僕の部屋にいて、僕の名前を当然のように呼んでいる。しかも日本語が流暢だ。いや、そんなことはよくて。
「だ、だれ……?」
僕が混乱する頭でどうにか絞り出した言葉を聞いて、相手は目を丸くした。
「私としたことが、自己紹介がまだでしたね。初めまして。私はリセ。人間の方に分かるように言うと、存在としては天使のようなものです」
言われてもよく分からなかった。ただ、心の奥底なのか、本能ってやつなのか、分からないけど、とにかく『人とは違う存在』であることはどこかで直観した。内側から柔らかく光っているようにすら見えるその姿はあまりにも可愛くて美しかったから。
けれど、もしも目の前の人が天使だったとして、どうして僕のところにいるんだろう。
何も分からない僕に、リセと名乗った天使が言う。
「菖太さん、昨日、祈ったでしょう? ご両親に謝れるように、その後何も聞かれないように、嫌がらせを受けないように、ご両親に迷惑をかけないように」
そうだ。突然のことに驚いて、それで頭がいっぱいになっていたけど、僕は確かに、昨日お父さんとお母さんにトゲのあることを言ってしまって、夜空に願ったんだ。
「じゃあ、願いを叶えに来てくれたの?」
思わず期待の乗った声で僕が言うと、天使は困ったような顔をした。
「本当はそうしたいのですが、生憎私には奇跡を起こす力がありません。私にできるのは、ただ隣で寄り添うこと。ですから、菖太さんが願いを叶えるところを見守る、といった形になりますね」
しばらく言われたことを頭の中で繰り返した。
「じゃあ、魔法が使えないってこと?」
「まあ、分かりやすく言えばそうなりますね」
「……何しに来たの?」
「あなたに寄り添いに」
ベッドに腰掛ける僕の隣に天使が座る。ふわっと陽だまりの良い匂いがしたかと思ったら、僕の頭に天使の手が乗った。そのまま僕の頭を撫で始める。
「菖太さんがとても優しい人であることを、私は知っています。大切なご両親を思うあまり、自分のことを話せずにいるのですね。その優しさを、少しでもご自分に向けてくだされば、と思うのですが……それはまだ、少し難しそうなので、私が来ました。私になら何でも話してくださって結構ですよ。学校のことも、ご家族のことも」
僕の頭を撫で続けながら、天使は微笑みかける。それを見て、なぜか安心した。僕の心の中を知っているんだから、怖くなってもおかしくないはずなのに、僕は天使の言葉を聞いて安心した。撫でられる度に心の中の隙間が温かく埋まっていくような気さえする。
「本当に、なんでも言っていいの?」
「ええ、なんでも」
「……あんまり言っちゃいけないことも?」
「菖太さんが言っちゃいけないと思っていることの大半は言っても良いと思いますよ」
「……言わなくても伝わってるんじゃない?」
「それでも、自分で自分の心の中身を出すことが大事ですから」
「……」
自分で自分の心の中身を出す。
言われて見たら僕が全然やってこなかったことのような気がする。お母さんには当然言えないし、お父さんにも遠慮して、僕は学校が楽しいフリして笑ってた。
だけど。
「……知ってるみたいだけど、昨日、お父さんとお母さんに、酷いこと言っちゃった」
僕はゆっくりと口を開いた。
「お父さんもお母さんも、僕のこと心配してくれたのに」
お父さんとお母さんの傷ついたような表情を思い出す。
「でも、僕が……僕が、学校で、その、いじめられてる、なんて知ったら、お母さんが元気じゃなくなっちゃうから。お父さんだって、何て思うか分からない。もしかしたら余計な問題を増やしたって思われるかもしれない。だから、やっぱり言えないよ」
僕の言葉は途切れ途切れで、なんでか分からないけど涙も出てきた。天使はただ黙って、僕の背中をさすりながら話を聞いている。
「いじめられるのは、怖い。すごく怖い。昨日だけでよく分かった。本当は学校にも行きたくないよ。でもそれも言いたくない。『どうして?』って絶対聞かれるから」
泣きじゃくりながら僕は言った。
「僕、どうしたらいいんだろう……」
しばらくの間、天使は背中をさすってくれていた。僕の嗚咽が納まるまで。僕は泣いて泣いて泣きじゃくったのに、不思議と気持ちは軽かった。むしろ泣けてスッキリしたという感覚なのかもしれない。けれど、僕がどうしていいのか分からないのは事実だから、天使が口を開くのを待っていた。
僕の呼吸が落ち着いてきたところで天使は言った。
「まずは昨夜のことを謝って、それからお父様にお話ししてみるのはいかがでしょう?」
「……でも、お父さんに迷惑かけちゃうよ」
「お父様はすでに菖太さんに『何かがあった』と察されています。きっと心配されていますよ」
「……」
それは、その通りだな、と思った。
結局カレーは半分くらい残してしまったし、お父さんが僕に何かあったと思って問い質そうとしていたのは、分かる。きっと心配してくれているけど、でも。
黙ってしまった僕に天使が続ける。
「菖太さんは、お母様が寝込んでいる時に『迷惑だな』と思いますか?」
今まで目を合わせられなかった天使と思わず目を合わせた。僕の顔には『信じられない』と書いてあったことだろう。それを見て、天使はふわりと微笑んで言った。
「そういうことです。お父様は心配こそすれど、菖太さんを迷惑だなんて思いませんよ」
僕は目を丸くしてしまった。
「それに、信頼というものは頼ってみてから生まれるものです。本当はもっと小さな頼み事から始めた方が良いのですが、菖太さんとお父様なら大丈夫ですよ」
天使はそう言って、僕の頭をポンポンと撫でた。
正直、そう言われてもまだちょっと不安ではある。もしもお父さんに受け入れてもらえなかったら、その時は、もうどうしようもないのだから。
でも。
もしお父さんが僕の事情を理解してくれるなら、すごく安心できる。
「……話しても、いいかな?」
僕は天使に聞いてみた。出会ってからまだ十五分と経っていない気がするけど、僕のことを知っているせいか、僕が自分のことを吐き出したせいか、不思議と天使のことを信用していた。僕が僕のことを話したのが『頼る』に入るなら、なるほど、確かに頼ってみてから初めて信じられるらしい。
天使は期待通りに微笑んで、頷いて、僕の手を取って、言ってくれた。
「菖太さんの望むようになさってください」
一階のダイニングに降りると、お父さんが新聞を読んでいた。お母さんの姿はない。寝室を確認するのを忘れていたけれど、まだ寝ているんだろうか。
僕に気づいたお父さんは新聞から目を離して、
「おはよう」
といつも通りに声をかけてくれた。
「……おはよう」
僕は昨日の後ろめたさと、今から話すことの緊張とでいつも通りに挨拶ができなかった。
それに気づかないお父さんじゃない。僕は昨日みたいに問い詰められるんじゃないかと身構えた。
けど、お父さんは新聞を置くと、いつもみたいに、
「今日は朝ごはん何にしようか」
と聞いてきた。
ちょっとだけ驚いて、ずっとお父さんに話すことばかり考えていたから、咄嗟に朝ごはんを何にするか思いつかなくて
「ツナマヨにする」
と昨日と同じことを言ってしまった。
だけどお父さんはふっと微笑んで、
「お父さんもそうしようかな」
と、二人分のツナマヨトーストを用意し始めた。
意を決して来たのに、ここにはあまりにも当たり前の光景が広がっていて、ちょっぴり気が緩む。
トースターからパンの良い匂いがしてきて、チン! と合図が鳴るとお父さんがパンを手早く取り出して、和えておいたツナマヨを乗っける。
その様子を何となく眺めていたら、お父さんが口を開いた。
「緊張していたみたいだったけど、今は大丈夫そうだね」
一瞬、図星すぎて固まった。お父さんには何でもお見通しらしい。
「昨日は無理やり問い質そうとしてごめん」
お父さんから全く予想していなかった言葉が聞こえてビックリした。僕は慌てて、
「そんなことない!」
と口にして、それから、
「僕も、酷いこと言って、ごめん」
と謝った。
すると、お父さんは不思議そうな顔をして、何かを思い出すように視線を巡らせて、笑った。
「あぁ、確かに驚いたけど、大丈夫だよ。でも謝ってくれてありがとう」
僕はその反応を見てまたビックリしてしまった。てっきり気にしているものだと思っていたから。
お父さんは作り終えたツナマヨトーストをテーブルに置いて席に着くよう僕に促す。その目線を汲み取って、僕は慌ててお父さんの向かいの椅子に座った。
お父さんが手を合わせて「いただきます」と言ったから、僕もそれに続いて手を合わせて、ツナマヨトーストに噛り付いた。
いつもの味がした。
パンもマヨネーズもツナ缶も、変わったものを使っていないから、いつもの味になるのは当たり前と言えば当たり前なんだけど、今の僕にはその当たり前が嬉しかった。
「……あのね、お父さん」
お父さんの顔を見ながらは言えなくて、一口齧ったツナマヨトーストをぼんやり見ながら僕は言った。
「聞いてほしいことがあるんだけど、いい?」
お父さんはトーストを食べるのをやめて、
「もちろん」
と返して、僕の方を向いてくれる。
僕はやっぱりお父さんの方を向けなかったから、この時お父さんがどんな顔をしていたのかは分からない。でも、どんな顔だったとしても、この後お父さんがショックを受けたのは間違いないみたいだった。
「僕ね、昨日ね……いじめ、られたんだ」
お父さんの持っていたトーストが落ちた。お皿が受け止めていたから僕は少し安心したけど、お父さんはそれどころじゃないみたいだった。長い沈黙があった。怖くてお父さんの表情を確認できなかった。でも、お父さんは沢山の僕に聞きたいこと、言いたいことを飲み込んで、まずこう言った。
「話してくれてありがとう。それから、無理させてごめん」
ポロリと僕の目から涙が零れた。それから驚いた。自分が泣いていることに。
お父さんは僕の隣の席について、ただ黙って背中をさすってくれた。ちょうどさっきの天使みたいに。僕の目からは何故だか涙があとからあとから流れ出してきて、止まらなかった。
「……嫌なことがあったのは、昨日だけ?」
難しい質問だ。いじめられたのは昨日だけだけど、僕が居心地の悪さを感じていたのは昨日からじゃない。
「……嫌なことがあったのは、昨日だけ。でも、嫌な気持ちだったのは、もっとずっと前から……かな」
僕は正直に言ってみた。そしたら抱きしめられた。
「ずっと我慢してたんだな」
そう言われて、やっぱり何故だか分からないけど、泣いた。
「我慢させてごめんな。無理させてごめん。ずっと母さんと父さんのことを考えてくれてたんだな。ありがとう」
分かってくれたんだ。そう思えた。不思議だ。僕は一回もお母さんたちを気遣って、なんて言ってないのに、お父さんはそれを分かってくれた。
僕が泣き止むまでお父さんはずっと僕を抱きしめてくれた。ようやく落ち着いた頃に、僕の顔を見て、お父さんはこう言った。
「嫌なことがあったら真っ先に頼っていい。父さんも母さんも、菖太の味方だ。気を使ったりしなくていいんだよ。何があっても、菖太のことを嫌いになったりしないから」
あんまり真面目にそう言うから、僕は少し恥ずかしくなって顔を逸らした。でも、すごく嬉しかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
