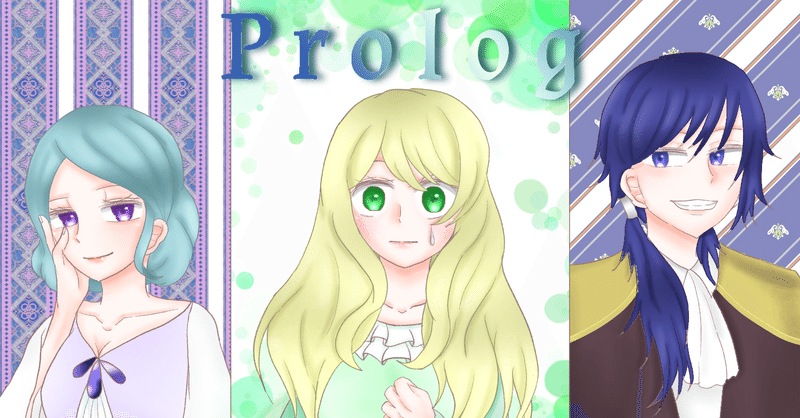
第2話プロローグPart4(小説版限定ストーリー)
何とか手紙全文の報告が終わり、ようやく国王夫妻から解放されたハイデマリーは、廊下を歩きながら長く息を吐き出した。手紙は書庫に保管しておくように命じられた為、これからこの足で城の隅にある書庫まで歩いていかねばならない。
(疲れるけれど、仕方ないわ。これもわたくしの務めだもの)
そっと手紙を抱き寄せ、ハイデマリーは奥へ奥へと歩いていく。誰もいない城の廊下は、豪奢に飾りつけられているにも関わらず、彼女にどこか無機質で冷たい印象を与えた。
動いているのは自分だけ。そんな静かな空間に身を置いた彼女は、ふとレザンが出発する前夜を思い出していた。
(あの日レザン様は、騎士もつけずに身一つでわたくしの部屋までやってきた)
小さな背中と震える声を思い出し、ハイデマリーは側の壁によりかかって、きつく目を閉じた。
──────────────
レザンとポムが地球へ向かう前日、城では見送りの為の宴が開かれていた。王都にいる者は貴族から平民まで皆城に出向き、各領地からは領主とその側近たちが訪れた。王族と折り合いの悪い大聖堂の聖職者達ですら、媚びへつらうように貢物を用意して城にやってきたそうだ。
ハイデマリーはその最中、レザンの側近として忙しく立ち回り、息を着く暇もないほど応対に追われていた。その為か、宴の最中のレザンの表情はあまり思い出せなかった。
ハイデマリーが彼の変化に気がついたのは、宴が終わり、城に設けられた従者用の寝室に戻った時だった。侍女を帰し、自分の為にお茶を入れて寛いでいると、突然扉がノックされたのだ。
「はい。どなたでしょう?」
「……僕だよ。ちょっと、いいかな?」
声の主はレザンだった。自室に戻ったとばかり思っていたハイデマリーは、驚いて立ち上がると、直ぐに彼を中に入れた。どうやら彼は、他の従者達を誰一人連れて来ず、一人きりでここまでやってきたらしかった。同じ城の中とはいえ、王子の部屋と召使い達の部屋にはかなり距離がある。おまけに今日は城に沢山の人々が寝泊まりしている。ふとした瞬間に命を狙われてもおかしくないのだ。
「レザン様!? 側近のひとりもつけずにこんな所へ来るとは何事ですか!? ちょっとこちらへいらっしゃい。お説教しなくてはね」
つい、まだ『姉』として彼を叱っていた頃のきつい口調に戻ってしまったが仕方ない。命が危なくなってからでは遅いのだ。ハイデマリーはレザンを自室の椅子に座らせ、頬を膨らませながらも彼の顔を覗き込んだ。
そこで、ハイデマリーは初めて、レザンが泣いている事に気がついた。
「……どう、なされたの?」
驚きのあまりそれしか口に出す事ができなかった。ハイデマリーは今まで、レザンの泣いた顔を見た事がなかった。どんな時でも春風のような笑顔をたたえ、例え逆境の中だとしても余裕のある仕草で乗り切っていく事が出来るのが彼だった。
そんな彼が、静かに静かに、涙を流している。背後に、眠れないよと枕を抱えていた小さな男の子の姿が重なって見えた。このまま叱っては駄目だ。このまま返しては駄目だ。ハイデマリーはそっとレザンを抱きしめた。
「姉上……」
レザンに肉親の姉はいない。自分の事だと咄嗟に分かった。学舎に入る七つの頃まで、レザンはハイデマリーの事を姉上と呼び、本当の姉のように彼女を慕っていたのだ。その後も、事あるごとに彼はハイデマリーに向かって姉と呼びかけ、ハイデマリーが「わたくしのような側近を姉上と呼ぶなんて」と半ば笑いながら諭すのが恒例であった。
けれど、その日の彼女は、レザンの言葉を否定するようなことはしなかった。ただゆっくりと頷き、どうしたの、と問いかける。
随分と大きくなったと思っていたけれど、背の丈はまだハイデマリーの方が高い。腕を回した背中は、驚く程に華奢だった。
「僕…………怖いよ」
体が震えていた。何があっても決して他人に弱みを見せなかった彼が、今日、ここで初めて泣いたのだ。彼の上に重たくのしかかる物の正体が何なのか、ハイデマリーは知っていた。それでも彼女達は、この国の国民達は、自身の安寧の為にレザンを神に仕立てあげなければならない。罪悪感を噛み締めながら、ハイデマリーは最後の本音を漏らした。
「大丈夫、貴方にはわたくしがいます。忘れないで。わたくしは貴方の帰る場所。わたくしはいつでも、貴方の、姉です」
耳元で小さく息を吸い込む音が聞こえた。ハイデマリーが体を離すと、こちらを見上げてはにかむレザンと目が合った。
「お茶を飲んでいく? ぐっすり眠れるハーブティなの」
「うん。姉上の淹れるお茶は美味しいから」
もう言葉など、交わさなくても大丈夫だ。ふわりと漂うお茶の良い香りに混じって、「ありがとう」と、レザンの小さな呟きが聞こえてきた。
──────────────
あれで本当に良かったのだろうか。ハイデマリーは自問自答する。少なくとも、彼の気持ちを晴れやかにする事は出来た筈だ。
けれど……
(わたくしは、あの子に姉と慕われる資格など無い。もし、わたくしが血の繋がった本当の姉だったならば、)
ハイデマリーは深呼吸すると、しっかりと手紙を持って再び長い廊下を歩き始めた。
(決してあの子を行かせたりはしなかった)
