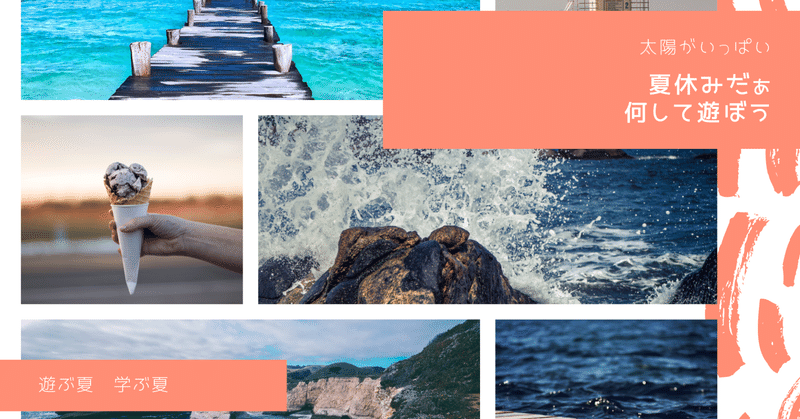
夏休みどう過ごす? 大いに遊び学ぼう
最近、「夏休み」の過ごして方について思うところがあったのでSELの観点から記事を書いてみました。特に「子どもたちが」「子どもと保護者が」どう過ごすか?について書いてみたいと思います。
ちなみに、「夏休みの宿題はきっちり全部やるものと思っている方」や、「小学生だけど塾の夏期講習に行かないと思っている方」「たくさんの宿題を子どもに出している学校の先生」は、きっと不快に感じると思いますので、読まれないことをお勧めします。
学ぶとは何か?
「大いに遊び学ぼう」とタイトルに書きましたが、まずは「学ぶ」とは何か?から考えてみたいと思います。
「学ぶ」とは 何でしょうか?
学ぶの語源は一説には
真似る(まねる)+遊ぶ(あそぶ)=学ぶ(まなぶ)
と言われますが、幼い子どもは周囲の大人の振る舞いや対話を真似ることで例えば、言葉や対人的な対応を学びます。また、遊ぶことを通じて例えば、お飯事による擬似体験や、友達やお兄ちゃんお姉ちゃんとの遊びから虫取りや自然との向き合い方を経験的に学びます。
特に子どもの学びとは、多様な人との関わりから真似ることで学び、遊びから経験として学ぶことです。
こうした多様な人からの学びや経験からの学びは、これから向かえる思春期においても自分との向き合い方や自分が困った時に助けを求めることができるなど大いに助けになる学びです。
夏休みは日が長く、朝から夕方まで近所の子どもたちが集まり山野を駆け回り多くを学ぶ機会が得られる絶好の時期ではないでしょうか。
つまり、子どもにとって夏休みは机に向かって勉強する以上に大切なことがあるということです。中学生になれば高校受験を控え勉強する時間を増やすことになりますし、部活が忙しくなる子もいるでしょう。小学生までは大いに遊び夏休みで良いと私は思います。
多すぎる夏休みの宿題
私が小学生の時もそうでしたが、夏休みの宿題が多すぎてそもそも終わらない。
毎日のように半日は机に向かうとかしないと終わらない量の宿題が出ます。
先に述べたように、せっかくの夏休みに机に向かっているなんて勿体ない。
そこで、大いに遊び学ぶためのご提案です。
多すぎる夏休みの宿題を的を絞ってやり抜いてみませんか?
具体的にはやる宿題とやらない宿題を決め、やると決めた宿題は覚悟を持ってやり抜きます。
こんなことを書くと宿題をやらないと成績が悪くなると思う方もいますよね。
ご自身の経験も思い出して欲しいのですが
宿題と学力は関係がない
・宿題をちゃんとやる子は成績が良いでしょうか?
・夏休みの宿題を全部やったらテストの成績がよくなったでしょうか?
そうです。宿題と学力は関係がないのです。
イヤイヤやっても身につくはずもありません。ましてや親が宿題の一部をやってあげたりすれば親の努力と能力であって、子どもの能力と学力には全く関係がなくなります。
ではなぜ、多くの大人(先生や保護者)が宿題をさせようとするのでしょうか?理由は至ってシンプルです。
「自分もちゃんとやったから」「宿題は文句を言わずやるもの」という固定概念があり、人は自分がやったことを子どもに教えようとするものだからです。
大人でも会社の上司から「あまり意味がないなぁ」と思う仕事をさせられて期限に納めるように日々、口うるさく催促されたらどうでしょうか?
ムダだと感じたり、「だったらお前がやれよ」って思ったり、生産性は低く、成果のクオリティは低いでしょう。
子どもだって同じです。「多すぎる夏休みの宿題を全部やる」ことを目的にしてしまい、毎日のように「宿題やったの?」と言われれば、時間を費やすばかりで得るものは極めて少なく生産性が著しく低いことになります。
多すぎる夏休みの宿題から選んでやり抜く
ここまで書いてきたように、多すぎる夏休みの宿題を全部やることは、あまり価値がありませんので、宿題を選んで的を絞って取り組みます。ここでは、その取り組み方についてご紹介します。
1. どの宿題をやるかは、必ず子どもが自分で決めます
子どもが迷ったら相談に乗りましょう。ただし、何をするか決めるのは必ず子どもです。大人が「これにしたら」と誘導したり、「だったらこれをやりましょう」と決めてはダメです。
2. 取り組む宿題を決めたら、実行計画を自分で作ります
子どもが自分で実行計画をカレンダーやノートに書き込みます。いつまでに何をするか、どのように進めるかを書きます。やり方や必要なものを調べることからはじたり、材料を揃えることからはじたり、何を体験することから始めたり、何からどのように取り組むかを実行計画に反映します。このとき、家族のレクレーションなどの予定がある場合は、その予定も考慮に入れるよう情報提供してください。
3. 実行計画ができたら、誰に何をいつ手伝って欲しいか書き出します
自由研究や工作など、子ども1人では難しいこともあるでしょう。その場合は、子どもが自分から、誰に何をいつ手伝って欲しいか(○○に連れてって欲しい、○○を買いに行きたいも含め)?を書き出し、手伝って欲しい相手に了解を得ます。
4. あとは見守る
実行計画に基づいて進めているか?手伝ってもらうことは実行できているか?見守ります。子どもが主体的に進めることが大切ですので、口うるさく言うこと避けましょう。計画通りに実行していることは、実行しようとしているが上手くいかないことも含めて取り組む姿勢を認めて褒めてあげましょう。認めて褒めてあげたら同時に「次は何をするの?」と計画を子どもに問いかけましょう。子ども自ら計画を確認して話すことが大切です。
計画通りに進まないこともあると思いますが、計画通りに進めることを目的にしないでください。計画を見直したり修正や変更することも学びになります。
夏休みの宿題の取り組み方から得られるSEL的学び
・自分で決めることの大切さ:主体性
・やり抜く力を育む:GRID
・自分で関係することを調べたり、あれこれ試してみる:探究学習
・他者に手伝いを求める:共感力、対人関係能力
・計画の見直し修正や変更:柔軟性、楽観性
この夏休みへの取り組みは、主体的な学びであるアクティブラーニングであり、一連の学びは、プロジェクトベースドラーニングと言えます。こうした学びが、その後社会人になってからも「生きる力」として活かされます。
ちなみに、自分で決めたことで上手くいかないことがあっても悔しいと糧になります。他人が決めたことで失敗すると心に傷が残ります。
繰り返しになりますが、子どもが自分で決めることからはじめましょう。
私たちTHdesignは、クリエイティブに日本の教育課題の解決を図るエビデンスに裏付けられた提案を行っています。
誰でも気軽にSELやEQが学べる「EQ SEL School」を開催しています
1.5時間の1話完結のオンラインセミナーで
全国どこからでも参加頂けます
詳しくはこちらへ
https://www.thdesignjp.com/events/eq-sel-school
セルフサイエンスを広める活動のサポートをお願いします。サポートは、セルフサイエンスプログラムを日本全国に広める活動費として使わせていただきます。
