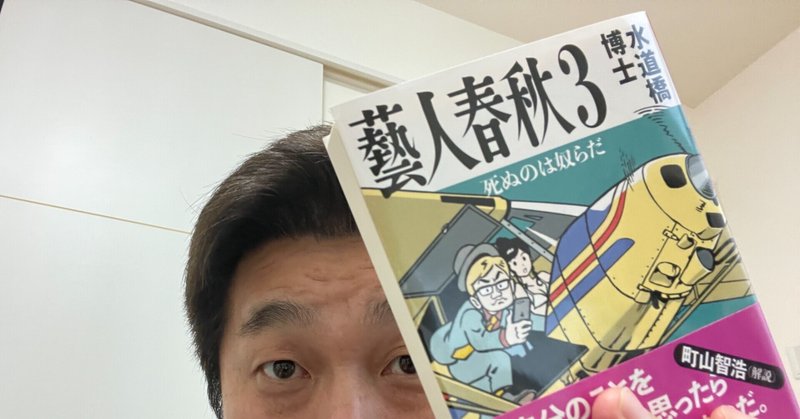
「藝人春秋3」~死ぬのは奴らだ~水道橋博士を読んで
「人間愛の詰まった一冊」からどんな本に?
藝人春秋2において、僕はこの本を「水道橋博士の人間愛が詰まった一冊」と紹介させていただいた。
「文筆家」としての博士を楽しむ
今回の藝人春秋3を読み終えて、すぐ、僕の頭の中にはいくつかのキーワードが浮かんできた。読後感としてあまりにもいろいろ感情が沸き起こる。それは博士自身が本の中に数限りない「罠」というべきか、「仕掛け」と言うべきか、上手く言えないが様々な感情の起伏の琴線に触れる記述がある。
そのことを整理しつつ、本書の楽しみ方を僕なりに考えてみた。大きく分けて2つある。一つは、博士本人が語るように、「ひとりの文筆家として腕は確実に上がっている。」(というニュアンスを博士は語っている。)要は博士の文章芸を楽しむ読み方だ。事実その技は「文章設定」「韻を踏んだ文章の数々」「壮大なる前フリとオチ(伏線回収)」「裏付け取材による正確な描写」「人間味あふれる物語」etc.が随所に散りばめられており、初めて博士の本を読まれる方はその文才に驚き、引き込まれ、単なる「小銭稼ぎのコメンテーター」ではないことはものの数行を読めば、すぐに分かるだろう。
「人間・水道橋博士」を楽しむ
では、もう一つの楽しみ方とは何か?
やはり、それは「人間・水道橋博士」を楽しむものではないのか?
冒頭、「僕の頭の中にはいくつかのキーワードが浮かんだ。」と書いた。
そこには「因縁」「007」「看過できない」「死」「ほっとけない」「芝浜」「言い訳」「俯瞰で見続ける男」・・・そんな言葉が頭を過っていた。
博士の身近に触れ合うものの一人として「博士、そこまでやらなくて委員会!」と言いたいほど、危険なやり方で、危険な橋の下を歩いている!!ずっとそんな印象を持っている。事実、「たかじんNOマネー降板事件」ではテレビ屋の一員としてどんな理由があるにせよ、生放送中の降板は「職場放棄」という最悪の仕事のやり方であり、もっと違うやり口があったのでは!?という思いはある。しかし、この本の出版を以ってすべては過去のこととして次に向かうのではないか。
そう、本書には「人間・水道橋博士」の隠しようがない姿勢がにじみ出ている。本書に出てくる「石原慎太郎」「橋下徹」「見城徹」のお三方について言えば、蜜月とまではいかないまでも、一時期、相手の才能、振る舞いにおいて「心酔」していた時期があったのではないか?僕自身も石原慎太郎さんのそばにおり、差別発言のひどさを目の当たりしながらも圧倒的な「男のホモッ気」(いわば、男が男に惚れる振る舞い)を何度も体感した。見城さんにしてもその著書「編集者としての病」を読み、そして師匠であるテリー伊藤さんの番組にゲストで来ていただいたこともあり、「顰蹙は金で買ってでもやれ!」「新しく出て行くものが無謀をやらないで、一体何が変わるだろう。」「小さなことにくよくよしろよ。」など感化され、さらには尾崎豊、五木寛之、郷ひろみをはじめとする名立たる著者(タレント)との「距離の縮め方」や「信頼を得るとは何か?」と、いろんな面で僕も影響を受けた一人だ。
博士の立場で言えば、石原さん、見城さん、橋下さんへの思いも、僕とは比べ物にならないほど、より深いことは容易に想像がつく。それはいわば「愛」だったがいつしか、「愛の深さゆえの憎しみや悲しみ」に変わったのではないか?という思いもにじむ。見城さんの安倍総理へのすり寄り方はきっと博士には許しがたいことであろう。権力へのすり寄り、百田尚樹のずさんな「殉愛」は、「人間・水道橋博士」として看過出来ないものであろう。
そして実名こそ出さないが周囲の者ならば、明らかに分かる形で制作会社「ボーイズ」のAに対し、「死ぬのはオマエだ!」と言い放つ。スパイという設定ではあるものの、あまりにも強烈な一言だ。もっと、違う戦い方があったのでは?という思いも過るが、博士の持つ、圧倒的なピュアさや正義を貫く姿勢は、かっこ良く言えば「少年ジャンプに出てくるヒーロー」であり、悪く言えば「あまりにも不器用すぎる男」でもある。ただ、誤解を恐れずに言えば、僕もまた不器用な男であり、「カッコ悪い事はなんとカッコいい事だろう」という考えの持ち主である。それであるがゆえに勇猛果敢に攻め入る博士の姿に憧憬の念さえ、抱くのだ。
今回の設定は編集長ではなく、読者に雇われたスパイというものだ。これを僕なりに解釈すると、スパイとは秘密工作員であり、江戸時代においては「忍者」である。忍者は隠密行為をしながらも普段は、「農家」の仕事をしている、なんて話も思い出す。
そう、考えると博士は
時に「マッチメーカー」として「武井壮VS寺門ジモン」をぶちたて、「石原慎太郎VS三浦雄一郎」の因縁をメイクする。
また、時には「発掘屋」として「田原総一郎のテレ東時代の仕事」「徳田虎雄の経歴」を掘り起こす。
また、ある時には「中二病を引きずる若手芸人」として、エピソードを紡ぐ。そこには華々しき芸能界の憧れと今の地位とのギャップが見え隠れする。
読了後、この本のサブタイトルは「死ぬのは奴らだ」とあるが、個人的には「ハカセは2度死ぬ」のほうがしっくりきた。それは「たかじんNOマネー降板事件での死」と「うつになったハカセ」と言う意味だ。それはまさに「人間・水道橋博士」として偽りのない姿であり、愛や哀しみ、苦しみ、怒り、全てをにじませた一冊であり、それこそ死んでもまだ「それでもやるんだよ!」というそんな博士の声が聞こえてきたからである。
さあ、そしていよいよ、博士が3月18日に「阿佐ヶ谷ヤング洋品店」を起ち上げる。
本を読み、浅ヤンならぬ「アサヤン」を観よう!
戦い続ける博士がそこにいるはずだ!
私のが手掛けるPlanet of Foodは、世界の主婦3人と柴犬による食にまつわるトークショーです。こちらは、「好きなスープを恋愛で例えてみたら?」
人気シリーズ「ずっと見てられる調理風景」
執筆者:島津秀泰(放送作家)
Twitter:@shimazujaoriya
Instagram:hideyasushimazu
是非、フォローをお願いします。
宜しければサポートをお願いします。あなたの応援を、私のエンジンにさせてください。
