
【資格試験勉強法】漢検準1級:概論 [勉強期間:だいたい1ヶ月]
はじめに
この記事は
「漢検準1級に合格した人が、その勉強法の全体的な話について
ダラダラと書きなぐる文章(個々の大問についての各論的な話ではない)」
となっており、対象としている読者の方は
・漢検準1級に興味がある方
・すでに漢検準1級の勉強を開始されている方
などを想定しております。
なお、独断と偏見と私見を多分に含みますのでご容赦願います。
<<追記>>
各論を記載しました。こちらからどうぞ。

1.そもそも漢検準1級ってどの程度の難易度なの?
決して「簡単です!」とは言えないけど、雲の上ではない…!と思う
漢字検定といえば、世間的なイメージでは
「学校で宣伝してる検定試験」
「テレビで『漢検●級の問題です!』ってたまに聞く気がする」
「いつだか分からないけど受験したなぁw」
というようなものが主なのではないでしょうか?
その中でも、漢検1級と準1級は雲の上で、何やらヤバい漢字、見たことない漢字、「木乃伊」みたいな当て字がたくさん出てくる、というイメージが強いかと思います。
僕も最初はそう思っていましたし、遠い昔に2級に合格して「次は準1級だ…!」と勇んで本屋に行ったものの、あまりの分からなさに何も買わずに本屋を立ち去ったのを記憶しております…w
しかし、自分でも思い出せないのですが、ある時にフっと「漢検準1級、ものすごく合格してぇ…!」となり一念発起。手探りでしたが、何とか1ヶ月ほどで合格にこじつける事ができました。
実際、準1級を合格してみた人間としては「決して簡単とは言えないけど、合格は十分可能な検定だと思う」と言えるのではないかと思います。
この記事では漢検準1級に2回合格した人間の所感やら勉強法について、総論的な話を主観と偏見を多分に含んで牽強付会にご紹介してみたいと思います。
(牽強付会は準1級出題の四字熟語!)
ご注意
なお、読み進める中で「そりゃ当たり前だろ!」と思われることも多々あるものとは存じます。が、なぐり書きのようなものであるという点、そして、案外そういったものの中に何か一つでもお役に立てるものがあればと思って執筆しておりますので、何卒ご容赦ください。
また、この記事はあくまで漢検準1級の合格を目的とした記事になります。よって、日々の語学学習・漢字学習の方法については邪道ないし活用できないことも多々含まれるものと思います。こちらも併せてご容赦ください。
ところで書いてる人はどんな人なの…?
僕は年3回開催されている漢検の、令和5年の第1回と第3回に合格しました(第2回は所用で受験できず…受験したかったですにょろ…)
わざわざ開催回を書いているのは、後述しますが「漢検準1級は開催回によって合格率が大きく異なる」からです。この理由は後述します。
とりあえずは令和5年で一番合格率が低かった第3回に合格できた、という状況ではあるので、少しは説得力が増すのかな、というせめてもの足掻きです(はい)
また、先述したように漢検は学生時代にやっていて、何級からかは忘れましたが、ステップアップしながら2級まで順に合格してきました。
そこからずいぶん時間が経ってからではありますが、社会人になって準1級に合格することができました。
遠い昔ではあるが、一応2級までは合格している、という人間です。はい。
2.2級以下と違うところ、同じところ
同じところ:市販のテキストをやれば準1級は合格できた
漢検をはじめ、資格・検定試験で当然と言えば当然なのかもしれませんが、市販のテキストをやれば合格することができました。
具体的には、私は後述する2種類のテキスト・問題集を購入しただけでした。
あ、1級はそれだけでは無理、というのが通説のようです。まさに魔境。
同じところ:2級以下とやることは同じ
これも当然と言えば当然なのですが、2級以下とやることは同じだと思います。
すなわち「問題集を解き、知らない漢字や言葉を調べ、覚える」ということの繰り返しです。身も蓋もないと言われればそうなのですが、正直それ以上は言えないと思います…w
違うところ:でも、その勉強量がたいぶ違うと思う
やっぱり一番の関門はここなのかな、と思います。シンプルで分かりやすい違いではあると思いますが、これに尽きるのではないかと思います。
出題漢字数、必要な語彙数、語句の意味の多彩さは2級までと段違いと思います。
そして、後述するように、高い合格基準が要されます。何となく、ではなく、より正確な知識や理解が要求される、ということです。ぶっちゃけ、2級以下とは比べものにならないくらいの「定着させなきゃ…!」の心持ちでした。
違うところ:準2級以下と比べて合格基準点が高く、(調べた限りでは)合格基準点が変わったことがない
これも最初はビビり散らかしていたことでした。
準2級〜8級は合格基準点が7割の140点ですが、準1級は8割の160点です。先ほどの話と繋がるところですが、より正確な理解が必要ということが分かると思います。
そして、それ以上に大きな違いと思われるのが「合格基準点が変わらない」という点です。2級以下は受験者全体の出来具合によって合格基準が変わることが多々あるとされています。
例えば、準2級〜8級では7割は140点ですが、実際の合格基準点が130点代になることがちょこちょこあるようです。
しかし、準1級は変わったことがないようです。どんなに簡単な問題であろうと、そしてどんなに難解な問題であろうとも、160点が絶対ラインとして君臨しているようです。
これはすなわち、難易度は高いのにミスの許容量が少なく、また試験問題の難しさによる慈悲はない、ということです。それゆえ、簡単な問題の時には合格率は高く、また、難しい問題の時には合格率はダダ下がりのようです。
僕が初合格した令和2023年度第1回試験は合格率26.6%で、ここ数年で最も高かったようですが、第3回試験では13.2%と結構差が大きく、また、最恐とされる2021年度第2回試験では5.5%という恐ろしい低さの合格率でした。
違うところ:試験全体の戦略が必要になると思う
このように、漢検準1級は合格基準点が変わらないとされ、それが脅威となっているのですが、その問題構成と配点も長期間変化がないようです。
ここに攻略の鍵があると思います。
「事前に戦略を練って挑むことができる」と思えるからです。
これについては各論となり、長くなってしまいそうですので今回は割愛させていただきますが、漢検準1級は難易度が高く6割取れれば超上出来な大問、確実に9割は得点したい大問などが混在している試験と思います。これらを戦略的に勉強・対策することで合格が近づくものと信じております。
(とはいえ、もちろん今後変化する可能性も十分に考えられるわけですが…漢検1級も得点源とされていた部分の配点がちょっと前に下がったようです…怖…)
3.具体的な戦略
落としちゃいけない問題を落とさない
では、その戦略なのですが、私の思う個人的な戦略としては「落としてはいけない問題を落とさない」、これに尽きると思います。
またまた何言ってんだ、当たり前じゃないか!と思われるお話ですが、やっぱりそれに尽きると思うのです…w
ここでいう落としてはいけない問題は「頻出問題・既出問題」「出題範囲が限られている問題」の意味です。
頻出問題・既出問題
漢検準1級は出題漢字が3000文字、かつ日常生活であまり見ない漢字が多数出題されますが、これらすべての漢字が同じような割合・頻度で出題されるわけではない、というのは、とても重要かつ見過ごしてはならない事実だと思います。テキストをやっていても「この漢字、前も出てきたよな…」とか「別の大問で出てきた漢字が形式を変えて問われている…!」となること多々です。
しかし、当然といえば当然ですが、何がそういう問題なのか、分かるはずもありません…w
そこで大活躍してくれて、マジで心から僕が神書籍だと思っているのがコレです。

あまりにも有名、かつ良書すぎて皆さんが挙げている本ではありますが、やっぱりそれにはそれなりの理由があると思います。とにかく素晴らしい対策本だと思います。論拠が示せず、また記憶の話になってしまいますが、どなたかが「この問題集の内容を完璧に習得した場合、本番の試験で何点取れるか」ということを検証されていたのですが、合格基準に毎回届いていたようです。カバー率問題集を信じろ。
具体的にはこれをただただ繰り返しました。多分結局3,4周くらいはやったのかなと思います。
1周目はどうせ分からない問題ばかりだろ!と思っていたので、書き問題は頭に思い浮かびさえすればOKと進めていました(=すなわちほとんど書いていませんでした!)。分からない問題はすぐに解答を見て、文字の形を確認。その場で書かずに文字の形を覚えていました(めちゃくちゃややこしそうな漢字は一回書いてみたりしましたが)。読みも知らなければ「ヘェー」ってくらいに読み進めていました。
雑!と言われてしまいそうですが、個人的には「まずは大雑把でいいので1周する」ということが何よりも大事だと思います。自分がどれだけ足りていないのか、あとどれくらい頑張ればいいのか、漢検準1級がどれくらい難しいか、が掴めるからです。
2周目はさすがにそうはいかず、解けなかった問題の書き出しをおこないました。どうやって書き出していたかは、またまた長い文章になってしまう気がするので、今回は割愛させていただきます。何も特殊なことはしていないのですけどね…w
3周目は2周目で解けなかった問題をやる!という方もいらっしゃるのではないかと思いますが、僕はまた全部やっていました…w
3周目を始めるころにはだいぶ定着してきているものと思いますので、スピードが段違いになります。2周目と同じように解けない問題の書き出しをおこないました。
4周目はさすがに3周目で間違えた問題だけをやっていたと思います。
そして、どこで述べればいいのか分からず、ここで述べてしいますが…僕が購入した問題集はもう1冊でした。
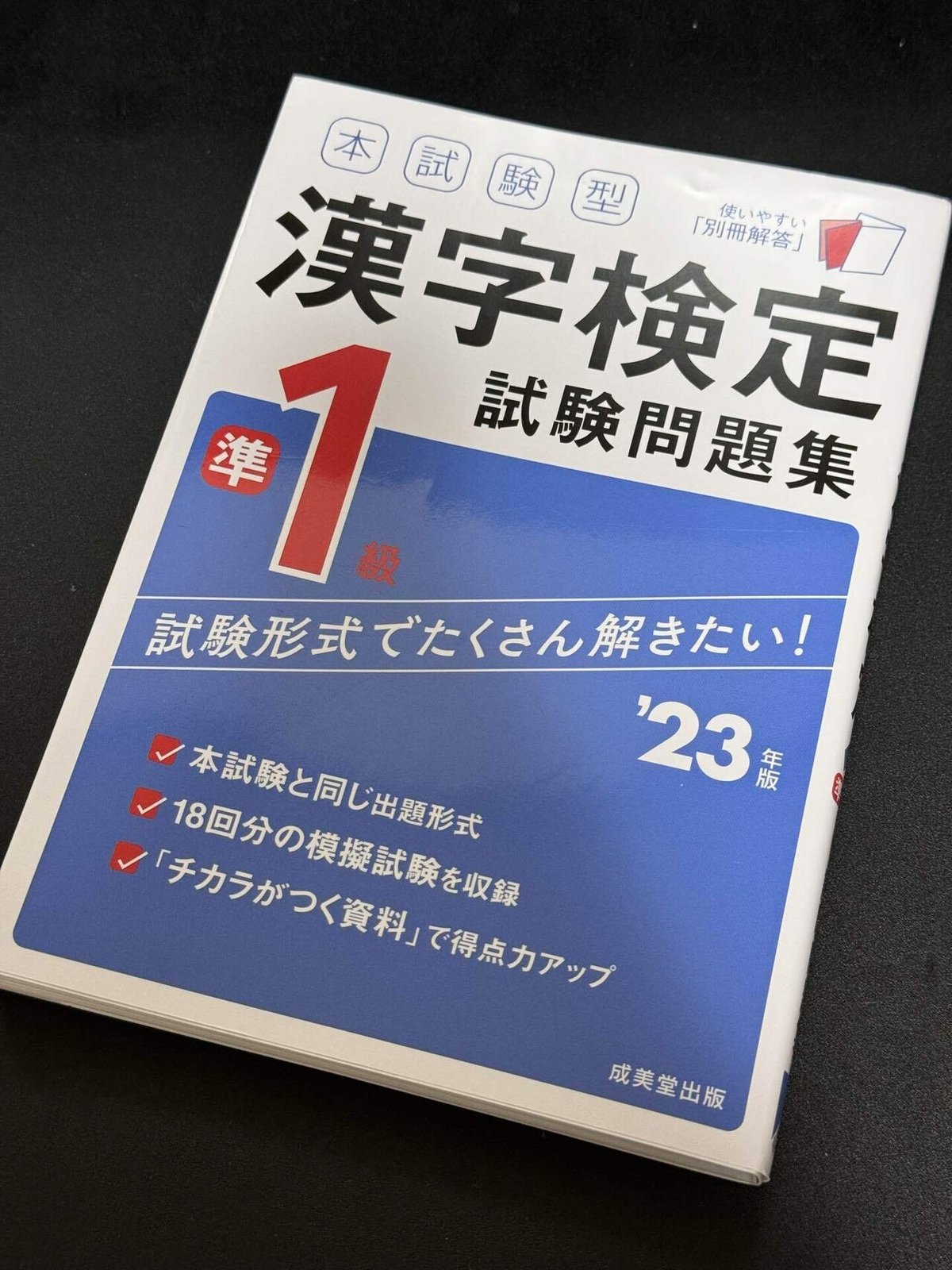
とはいえ、この問題集が是非ともいい!という決め手があったわけではなく、演習形式の問題集が1冊欲しかった、収録回数が多かった、という2点が決め手でした。
正直なところをいうと、本を決める際に立ち読みをしていましたが、どの問題集でも同じなのかな、とも思いました。
まだ本文は続くのですが、個人的にこの記事のまとめは
「カバー率問題集をベースに学習し、演習問題集で補強する」
であると集約できると思います。
出題範囲が限られている問題
そして、もう一つ、落としてはいけない問題があります。
それは「出題範囲が限られている問題」です。
例えば、大問4の「共通の漢字」は語彙力が必要となる問題です。出題される漢字は常用漢字、果ては小学校学習範囲のものが解答になることもザラなのですが、その必要となる語彙力が広い…!本当に広い…!
「退蔵」「弊履」「深更」…知らんがな!という具合でしたw
これも通説という言い方にはなりますが、最も得点しにくい問題で、かつ頻出傾向のある問題、というのもほとんどないようです。
逆に出題範囲が限られているものもあります。ここが狙い目だと思います。
具体的には、
・大問2「表外の読み」
・大問7「四字熟語」
・国字
・干支の読み(音読み・訓読み)
です。これらは出題範囲が比較的限られているうえ、得点に繋がりやすい問題と言えると思います。
勉強のスタートは四字熟語がいいと思う
という点で、「頻出で、出題範囲が限られている問題」を優先的に進めた方がいいということは当然と言えば当然なのですがお伝えできたかと思います。
そういった点で、最初に取り組むべき大問・科目は「四字熟語」であると強く思います。
四字熟語は、純粋な準1級の出題範囲(漢検漢和辞典で準1級のマークがついているもの)という点だけで見ればかなりの数となりますが、合格ラインに必要な記憶量は比較的少ないように感じられ、現に僕は四字熟語に関しては先述の2冊の問題集しかやっていませんが、2回の試験とも9割以上を得点することができました。
そして、もう1つのおすすめする理由、というより、こちらが大きい理由かもしれませんが
「他の大問に通ずる知識が多数学べる」
ということがあると思います。
四字熟語を学習すれば、主に漢字の音読みが学べますし、漢字の意味も学べます。また二字熟語+二字熟語という構成のものも多数あり、それぞれの熟語の意味も学べます。加えて、同義の二字熟語2つ、対義の二字熟語2つによるも四字熟語であれば、大問8の「対義語・類義語」の学習にも繋がります。故事に繋がるものも多々ですから、大問9の対策にもなります。
ということで、四字熟語は「勉強するだけで、大問7に直結するし、この他の大問の知識もたくさんついてきてお得」だと強く信じています。
たしかに最初は聞いたことない言葉や見たことない漢字に辟易してしまいますが、そこを乗り越えて着実に進んでいけば、確実に漢検準1級の合格力が身についていくと思います。
とはいえ、分からないものだらけでモチベーションが下がってしまうのも本末転倒です。やってても虚しいですよね…!
そんなときには好きな分野の問題を息抜きに少しずつ進めるのはもちろんアリだと思います。僕は表外の読みが好きなので、ちょこちょこ現実逃避にやっていました…w
問題を解く順番を決めておく(大問1から解かなくていい)
あと、これはあまり述べられている方はいらっしゃらないような気もするのですが、(たくさんいらっしゃったらごめんなさい!)僕は漢検の問題を大問1から解いていません。
具体的には、発想やら機転やらが必要ない定型問題を確実に得点したいという思いから、やっぱりそういう点でまずは大問7の四字熟語、そして大問9の故事・諺から解き始めています。
その次に、少し考えたり、記憶の奥から掘り出さなくてはならない問題、具体的には大問6の誤字訂正、大問8の対義語・類義語に行きます。問題を一通り見て解ける問題は先に埋めてしまいますが、分からないものはとりあえず空欄にしておきます。個人的な感覚ですが、こうしておくだけで「頭の片隅で、脳が勝手に考えていてくれ、記憶を掘り起こしてくれている」感覚がします…w なんとも胡散臭い…!
ですが、実際、僕が受検した時も、最初見た時は分からなくても、全く他の大問を解いているときに「あっ!」と突然思い出したり、他の問題を見て思い出したり、ということが少なからずありました。
思考や記憶の掘り出しに長い時間を割ける、という点では、試験時間の始めの方に大問6・8を解いて見ておくというのは、一定の効果があるのではないかと思います。あ、大問4ももちろんこの部類に入るとは思うのですが、解けなさすぎて焦ってしまいそうなので、この段階ではまだ取り組みません…w
その後は、大問1から順に解いていってます。
ということで、漢検準1級に関する概論をまとめてみた記事になります。
ほとんど中身がないお話だったかもしれませんが、いかがでしたでしょうか…w
別の記事で是非とも各大問ごとの各論的な戦略について触れていきたいと思いますので、もし執筆した際には見てやってくだされば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
