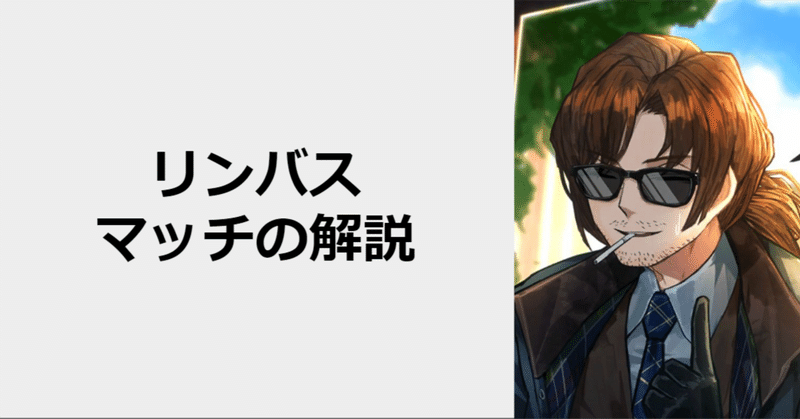
[LimbusCompany]マッチについての解説[20240316]
以下の記事は2024.3.16時点での情報をもとにしております。
間違いなど誤情報があればお知らせください。
この記事を作るうえで LimbusCompany攻略Wiki および各配信者様の動画を参考させていただいた部分が多くあります。
いつも編集・動画の投稿、本当にありがとうございます。
この場を借りてお礼申し上げます。
また、コンテンツの発展のために、本記事の内容は全て転載可能とします。
ただし、転載する際は下記のことを守っていただければと思います。
・執筆者の詳細がわかるように記載すること
・Project moon様の二次創作ガイドラインに従うこと
・転載によって発生した問題に対し執筆者は責任を持たないこと
0. かんたん説明
スマホゲーム「Limbus company」の戦闘システムの重要な要素「マッチ」の仕様について、初心者向けの方にまとめた記事になります。
内容は「マッチ」の仕様や行動順、攻撃加重値など多岐にわたります。
※疑問に思った点やおかしいなと思ったら、遠慮なくコメントください。
1. 前提知識と「マッチ」の概要
ここでは、先の説明において前提となる知識について解説します。
1-1. 戦闘の種類
このゲームの戦闘は「通常戦闘」と「集中戦闘」の2種類に分けられます。
雑魚敵などの戦闘は前者、幻想体などのボスは後者になります。両者の違いは、各ユニットのスキル使用対象を指定できるかできないかです。通常戦闘の場合、ユニットのスキル使用対象はプログラムに従ってある程度きまり、こちらから制御できる部分は少ないです。一方で、集中戦闘ではスキルの使用先をこちらで制御できます。
1-2. 攻撃スキルの概要
すべてのユニットが使用するスキルは、基礎威力とコイン威力が設定されております。ここではその仕様について軽く触れます(詳細については後日解説予定です)。
例として、図1-1を示します。

画像の通り、大きく分けて基礎威力、コイン威力、コイン枚数が存在します。コインには表裏があり、表がでた場合はコイン威力だけ威力上昇、裏がでた場合は変化なしとなります。
このスキルの場合、威力の最大値と最小値は以下の通りになります。
<最小値>
コイン3枚をすべて裏で引いた場合
4+( 0+0+0 ) = 4
<最大値>
コイン3枚をすべて表で引いた場合
4+( 2+2+2 ) = 10
実際にスキルで敵を攻撃する場合、コインの枚数だけ攻撃を行います。そのときの威力は、コインごとに決定され、コイン1枚目なら基礎威力+コイン威力×1、コイン2枚目なら基礎威力+コイン威力×2となります(表が出た場合)。
ちなみに、コインの表裏確率は精神力という数値によって決定されます。
精神力の解説は以下の記事に記載しております。
1-3. 「マッチ」とは?
ここで、メインの内容である「マッチ」について話します。
「マッチ」とは、味方のスキル使用先と、敵のスキル使用先が一致するときに発生する現象(状態)です。マッチが発生した場合、ユニット間でスキルの威力勝負をおこないます。マッチが発生している場合の例を図1-2に示します。

マッチが発生している場合、そのユニット間は黄色い矢印でつながれます。この場合、グレゴールの1つ目のスキルとK社職員の1つ目のスキル間でマッチが発生しております。
1-4. 「マッチ」を制するものはリンバスを制す
マッチにはさまざまなメリットがあります。代表的な例を以下に記載します。
<マッチのメリット>
マッチに勝利すると
・敵の攻撃を潰せて、かつダメージを与えられる
・精神力が上昇する
・特殊な効果が発生する(バフや敵へのデバフ)
・ギミックが発動する(幻想体戦など)
マッチに負けたとしても
・敵のダメージを減らせる
・マッチ敗北による効果もある
このゲームの戦闘では、敵の攻撃をマッチで勝利して潰すことが最も重要です。「マッチ」を制するものはリンバスを制す、そういっても過言ではないほどです。
2. 「マッチ」の具体的な仕様
ここでは、マッチの具体的な使用について説明します。
2-1. マッチの対象選択と条件
※かなり長いです。結論のみを知りたい方は、この項目の最後の部分をご覧ください。
まず、マッチの対象選択と、マッチするための条件を説明します。
図2-1のような状況を例として考えます。

幻想体「路地の番犬」との集中戦闘です。番犬の胴体部位から5本の赤矢印が飛んでいますね。これは一方攻撃を意味しております。また、攻撃スロット上部にある数字はその部位の速度を表示しております。
この状態のままでは、敵の攻撃を受けて大ダメージを受けます。そこで、マッチの出番となります。

図2-2のように、画面下部のチェーンパネル内のスキルをタップ&ホールドします。そうすることで、スキルの使用先を選択できます。

そして、図2-3のように、ホールドしたスキルを敵のスロットに重ねると、黄色い矢印に変化しましたね。この状態でホールドを解除すると…

図2-4のようになり、マッチ状態になります。
まとめると、マッチの基本操作は以下のようになります。
<マッチの基本操作>
1. チェーンパネルからスキルを選択
2. ホールドしながら、マッチさせたいスキルスロットに重ねる
3. ホールドを解除すると、マッチ状態の完成
次に、マッチする人格の変更について話します。
一つの敵や部位に複数人で攻撃したい、けどマッチする人格は選びたい。そんな場合はたくさんあります。
その場合、最後にスキルを重ねた人格(スキル)がマッチ状態になります。
例として図2-5を考えます。

路地の番犬の胴体スロットのスキルに対し、ファウストがマッチして、ウーティスが一方攻撃(青矢印)となっている状態です。

この状態で、図2-6のように、ウーティスのスキルを、ファウストのマッチ先のスロットに重ねると…

ファウストが一方攻撃、ウーティスがマッチ状態になりましたね。
このように、複数人が同一の敵や部位を攻撃先にしている状態では、そのスロットに最後にスキルを重ねた人格が、攻撃対象とマッチ状態になります。
敵のマッチ威力強い場合等では特に有効なので、ぜひともおさえておきたいテクニックです。
しかし、ここで重要となる要素があります。それは、ユニットの「速度」です。各ユニットや部位には、すべて速度というものが設定されており、(基本は)速度が速い順から行動が行われます。これが、マッチに大きな影響を与えます。
その例を説明します。まずは、図2-8のような状況を考えます。

イサンが路地の番犬の攻撃対象になっている状況です。
この状況において、イサンへの攻撃スキルに、イサンのスキルを重ねると…

イサンのスキル使用先と、番犬のスキル使用先が一致したため、マッチ状態になります。これは、ここまでの説明通りですね。
しかし、イサンのスキルを他のスロットに重ねると…

マッチ状態にならず、一方攻撃になってしまいます。
これは、イサンの速度が番犬の胴体部位の速度より遅いからです。
マッチの仕様として、「こちらの速度≦攻撃先の速度」
の場合、その攻撃先のスキルで狙われてない限り、マッチ状態になりません。類似した例として、図2-11を示します。

速度9のファウストが速度5の部位のスキルで狙われています。この状態で、速度5のドンキホーテがそのスロットにスキルを重ねても、「こちらの速度≦攻撃先の速度」のため、マッチ状態にはならず、一方攻撃となります。
逆に、「こちらの速度>攻撃先の速度」の場合なら、あるユニットへの攻撃を、別のユニットでマッチをとることが可能です。
その例を説明します。まず図2-12のような状況を考えます。

ドンキホーテが2つの攻撃スキルで狙われている状況ですね。この状況では、ドンキホーテは1つのスキルしか持ってないため、1つの攻撃スキルにしか対応できません。
そこで、図2-13のように、速度8のムルソーのスキルで攻撃スキルのうち1つに重ねると…

ドンキホーテを対象としていたスキルが、ムルソーに移り、マッチ状態になります。このように、「こちらの速度>攻撃先の速度」の場合なら攻撃スキルの使用先の移動が起こり、一人に集中しているスキルを分散させたり、各ユニットにマッチさせたいスキルの制御をおこなうことができます。
※ちなみに、これは守備スキルなどでも同様の処理が行われます。
長くなってしまいましたが、マッチの基本仕様をまとめると、以下のようになります。
<マッチの基本操作>
1. チェーンパネルからスキルを選択
2. ホールドしながら、マッチさせたいスキルスロットに重ねる
3. ホールドを解除すると、マッチ状態の完成
<マッチの仕様>
・味方のスキル使用先と、敵のスキル使用先が一致するときに発生する
・複数人が同一の敵や部位を攻撃先にしている状態では、そのスロットに最後にスキルを重ねた人格が、攻撃対象とマッチ状態になる
<マッチと速度>
マッチ状態になるかならないかは、各ユニットの速度に関係する
・味方の速度≦攻撃先の敵の速度 の場合
攻撃先のスキルで狙われてない限り、スキルを重ねてもマッチ状態になら ない
・味方の速度>攻撃先の敵の速度 の場合
攻撃スキルの使用先の移動が起こり、味方への攻撃を自分に向けさせたり、マッチしたいスキルの制御が可能となる
2-2. マッチ時の処理と判定
ここでは、マッチが起きた際の処理と判定について述べます。
マッチが発生すると、該当するユニット間で、攻撃スキルの威力勝負をおこないます。これは、簡単に言うとサイコロの出目勝負と似たようなものです。
マッチが発生すると、図2-14のような演出が起こります。

両者のスキルが表示されておりますね。
この状態で、マッチは下記のように進行します。
<マッチの進行>
1. お互いのスキルのコイン表裏を決定
2. スキルの基礎威力+コイン威力×表の数 +その他 で最終威力を決定
3. 最終威力の大きさで勝負し、負けた方はコインが1枚破壊される
4. 1-3をどちらかのコインがなくなるまで繰り返す
5. マッチに勝ったユニットが、残ったコインで負けたユニットを一方攻撃する
2-3. マッチの有利不利判定
マッチに勝てるかどうか、その目安は、マッチの有利不利判定が参考になります。判定は、図2-15上部のように、二つのスキルの間に表示されます。

有利不利判定は、スキル威力や精神力、バフデバフ、レベル差などを総合的に考慮して表示されます。判定は下記の5段階に分かれます。
<判定の段階>
非常に有利:基本的にこの状態が望ましい
有利:やや不安が残るものの、まあ信頼してもよい
均衡:できれば避けたい
不利:この状態になるなら守備スキルを用いたほうが良い
非常に不利:絶対ダメ
※説明は個人の見解です
この判定は目安にはなりますが、あくまで目安です。
特に、数値分だけコイン威力を0にする麻痺のデバフを付与されているときや、減算コインのスキルがある場合は注意が必要です。判定があまりあてになりません。
2-4. マッチの威力表示
マッチ状態にあるとき、画面上部の数値表示が参考になります。
数値についての説明を図2-17に示します。

複雑ですね。重要な部分は、スキル名の上に表示される、マッチ威力の最小値と最大値です。ここの部分をみて、判断したいですね。
2-5. 守備スキルのマッチと相殺
厳密ではマッチではありませんが、一応記載します。
守備スキルを敵のスキルに重ねた場合、マッチ状態にはなりませんが、速度次第で、攻撃スキルと同様に攻撃対象の移動などは起こります。
また、守備スキル同士をぶつけた場合、相殺という現象がおきます。
例として、図2-18を示します。

ウーティスの守備スキルを、敵の守備スキルに重ねた場合です。
画面上部に相殺と表示されておりますね。この場合、両者の守備スキルが相殺し、守備スキルが使用されずに戦闘が進行します。
守備スキルには、防御、回避、反撃の三種類があります。
反撃以外は、守備スキル同士をぶつけることによって相殺ができます。
詳しくは、後日守備スキルについて解説する予定です。
2-6. 加重値2以上の攻撃(広域攻撃)とマッチ
ここでは、攻撃加重値と加重値2以上の攻撃におけるマッチについて説明します。
すべてのスキルおよびEGOには、攻撃加重値というものが設定されております(図2-19参照)。
攻撃加重値とは、簡単にいうとスキルを使用した際に攻撃できる人数です。より詳しくいうと攻撃できるスロットの数のことです。
さらに厳密にいうと攻撃先のスキルや部位の加重値を考慮します。
加重値2以上の攻撃を、一般に「広域攻撃」と呼びます(正式名称ではありません)。
※前作「Library of ruina」では似たようなシステムとして広域攻撃というものがあり、またシーズン1~2のころは広域攻撃等の表記があったため、いまでも複数人を同時に攻撃できるスキルを広域攻撃と呼ぶことは多々あります

例えば、加重値1なら敵1体を攻撃できます(通常のスキルのほとんどがこれに相当)。加重値3なら同時に3体に攻撃できます。
重要な点として、加重値2以上のスキルを使用してマッチする場合、敵の使用するスキル1つのみにマッチでき、ほかの敵に対してはすべて一方攻撃になります。このとき、マッチ先以外の攻撃対象はこちらから指定できません
(ただし、後述する方法である程度制御は可能)。
例として、図2-20、2-21を示します。


図2-20は、敵が広域攻撃を準備している画面です。赤矢印が広域攻撃のメインターゲット、点線矢印が一方攻撃になります。
この攻撃に対し、こちらもファウストのEGO「水袋」(加重値5)でマッチしたのが図2-21になります。ファウストのほうが速度が速いため、マッチが成立します。こちらの青点線矢印も、赤点線矢印と同様に一方攻撃になります。
このときの加重値5の振り分けは、スロットにある黄色い四角の数でわかります。この場合、電信柱部位(左から2番目のスロット)に2コ、ほかの部位に1コずつ振り分けられてますね。
ここで重要なのが、敵の数(部位数)<加重値の場合、余分な加重値の分追加ダメージを与えるといったことはないということです。図2-21の場合、部位が3つありますが、「水袋」のダメージはそれぞれ1回分しかはいりません。加重値2振り分けれている電信柱にも1回分ですし、2スロットある頭部位にも、1回分のダメージしか入りません。
似たような例として、腕部位の攻撃スロット4つあった場合を考えます。腕に対して加重値4の攻撃をおこなっても、この場合ダメージは1個分になります。
この攻撃加重値2以上のスキルもしくはEGOを使用する際に重要なテクニックがあります。
それは、あらかじめ広域攻撃を使用するキャラ以外で攻撃させたくないスロットをマッチすることで、広域攻撃の攻撃対象を制御できます
例として、図2-22を示します。

例として皮膚の預言者を挙げます。本体は反撃を持ち、まわりの蝋燭を攻撃することで本体の耐性を下げられます。この際、あらかじめ本体のすべての攻撃にスキルをマッチした後、広域攻撃をろうそくにマッチさせることで、広域攻撃の対象がすべてろうそくに向きます。その後、本体にマッチさせていた攻撃を蝋燭にうつすことによって、安全に蝋燭を処理できます。
2-7. マッチ不可攻撃とその対象方法
一部の敵は、マッチ不可攻撃というものを使用します。文字通り、マッチできません。その対処方法について記載します。
対処方法は、大きく分けて2つです。
1.先に混乱させる
2.回避を使う
1については、そのままですね。マッチ不可攻撃を使用する敵(部位)を先に攻撃して、混乱させスキルの使用を中止させます。
2について、マッチ不可攻撃はマッチは不可ですが回避はできます。なので、マッチ不可攻撃に対し、回避スキルを使用することにより、対処可能です。
3. 関連する情報とテクニック
3-1. 威力表記の違い
このゲームには、さまざまな威力表記が存在します。
ここでは、それらをまとめたものを記載します。
・基本威力(基礎威力)
スキルの基本となる威力
・コイン威力
コインで表をひいたときに加えられる数値
・最終威力
基礎威力やコイン威力、バフデバフなどすべて足したあとの威力
・マッチ威力
マッチ時の威力
・加算コイン威力
コイン威力がプラスのものであるコイン威力
・減算コイン威力
コイン威力がマイナスのものであるコイン威力
よく混同しやすいバフとして、基本威力増加と最終威力増加があります。
これらは、加算コインのスキルに対しては意味は同じになります。
しかし、減算コインに対しては意味が変わります。
例えば、人格「シンクレア 握らんとするもの」のスキル3「自滅的浄化」を考えます。このスキルは、基本威力30にコイン威力 -18 × 3 の減算コインスキルです。ここで、2つの例を考えます。
1.基本威力増加+1の場合
基本威力は30+1=31となる。コイン3枚すべて表を引いた場合、最終威力は31+(-18×3)=0になる
2.最終威力増加+1の場合
基本威力は30のまま。コイン3枚すべて表を引いた場合、最終威力は、30+(-18×3)=0に1を加えて、1となる
最終威力増加は、コイン判定後に加えられるため、最終威力が0になるような減算コインスキルでは意味が変わります。
また、ヘルプをみると乗算コインなるものも存在します。もし実装された場合、基本威力増加の効果が極めて大きくなると思われます。
3-2. マッチ威力と攻撃レベルの関係
ステータスの1つとして、攻撃レベルが存在します。この攻撃レベルの数値が、マッチにおいて影響を与えます。内容は以下の通りです。
・マッチ威力に対する補正
マッチにおいて、味方スキルの攻撃レベルと敵スキルの攻撃レベルの差に応じて、マッチ威力に補正が加わる
レベル差3につきおよそ威力1の補正が加わる
(ヘアクーポンさんや鏡ハードのマッチ威力が高いのはこの補正の影響)
3-3. 編成順番とスロット数および行動順番の関係
このゲームにおいて、戦闘に入る前に編成画面にて戦闘に参加するキャラを選択しますが、このときの編成画面の選択の順番が戦闘における行動スロットに影響を与えます。
重要なのは以下の2つです。
1.速度が同じ人格がいる場合、編成した順に左から並ぶ
2.通常戦闘においてターン経過に応じてスロットが増える場合、編成した順番でスロットが増えていく
下記の図3-1および図3-2を見てもらえれば、わかると思います。

シンクレア→イシュメール→ヒースクリフ→グレゴールおじさん→ホンル→イサンの順番

1番目に選んだシンクレアのスロットが増えている
また速度が同じシンクレア・ホンル・イサンは編成の順番通り左側から並んでいる
スロット増加については、1番目のスロットが増える→2番目のスロットが増える→3番目が……という風に増加し、一周すればまた1番目のスロットが増えます。
通常戦闘におけるスロットの最大数は12個であり、二人編成ならそれぞれスロット6個、三人編成ならそれぞれスロット4個のように増加します。
集中戦闘の場合、スロット数の限界は参加できる人数の数になります。6人参加できる場合はスロット数6個が限界となります。
3-4. 敵味方の速度と行動順の関係
戦闘において、敵味方の行動は基本的には速度に応じて行われ、最も速度が速いユニットから行動します。
幻想体のように同部位で同速度の攻撃のを持つ場合、一番左のスロットから攻撃がおこなわれます。複数部位で同速度の場合、一番右側にある部位の一番左スロットから行動します。
ただし、実際にはスキル3のカットイン、広域EGOの仕様、敵HPの削り具合などの処理によって行動順が前後する場合があるようです(要検証)。
3-5. 精神力とコイン表裏確率
スキル使用や観測イベントの際、コインの裏表を判定して威力が決定されます。このときのコインの表裏の確率は、精神力によって変動します。
確率については、現在下記のようになっていると推測されております。
<コインの表裏確率>
精神力0において表率50%
精神力の増減値1につき表裏確率が1%変化
精神力最大(45)のとき表率95%、精神力最小(-45)のとき表率5%
ちなみに、精神力を持たない敵については表率50%と公式からお知らせされております(2023.4.7のニュース参照)。
4. 終わりに
やや駆け足となってしまいましたが、マッチの解説は以上です。マッチは、戦闘を有利に進める上で極めて重要な要素です。ぜひおさえておきたい点です。
この記事は、アップデートに応じて更新していく予定です。
良ければ、X(旧Twitter)のフォローやスキ・いいねをお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
