
アトランティスロック大陸 3 1969~70
風の記憶、岩の夢
My United Stars of Atlantis
谷口江里也 著
©️Elia Taniguchi
目次
第20歌 Playing in the Band グレイトフル・デッド 1969
第21歌 With a Little Help From my Friends ジョー・コッカー 1969
第22歌 Girl from the North Country ボブ・ディラン 1969
第23歌 クリスマス ザ・フー 1969
第24歌 21世紀の精神異常者 キング クリムゾン 1969
第25歌 Whole Lotta Love レッド・ツエッペリン 1969
第26歌 ダウン・オン・ザ・コーナー
クリーデンス・クリアウオーター・リバイバル 1969
第27歌 ブラック・マジック・ウーマン サンタナ 1970
第28歌 Song for You レオン ラッセル 1970
第20歌 Playing in the Band 1969
グレイトフル・デッド
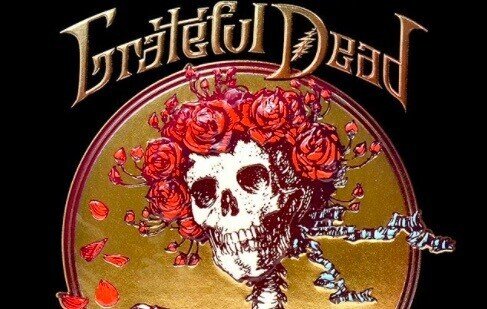
理性を信じる
なんてことを言う奴がいるけど
そいつらが信じてるのは自分自身
俺は何にも信じない
つまり、なるようになるのさ
もう一度言うけど
もうすぐステージも始まることだし
分かってくれたらいいんだけど
要するに、人間は人間だってことさ
音楽は音楽、演(や)ってもいいし、聴いてもいいけど、要するに、みんなで楽しむためのもの。何かを託したりするものでもなければ、そこから何かを学ぶためにあるのでもない。ましてや、命を賭けるようなものなんかじゃ、決してない。
60年代末期という時代の、異常なまでのテンションの高まりの中で、多くのミュージシャンたちが自らのアイデンティティを賭けて疾走した。歌詞や言動に反体制的なメッセージを込めるものもいれば、ジミ・ヘンドリックスのように捨て身のパフォーマンスに命を燃やすものもいた。
そんな中で、音楽は音楽、それ以上でもなければそれ以下でもない。何かのために音楽があるのでもなければ、音楽のために何かがあるのでもない。大切なのは、人間が発明した最もすばらしい楽しみである音楽を、十二分に楽しむことだといわんばかりに、とにかく音楽を演奏し、そしてそれを観客に直接聴かせることにこだわり続けたグループがいた。グレイトフル・デッドである。
人間から一切の装飾を剥ぎ取った骸骨(ガイコツ)と、それとは逆に、人間特有の無駄の極致ともいえる美の象徴であるかのような薔薇(バラ)をトレードマークとするデッドの音楽からは、どこからともなく、こんな声が聞こえてきそうだった。考えてもみろよ。音楽より楽しいものがいったいどこにある? 勉強が大好きだなんて言う変な奴も、もしかしたらどこかにいるかもしれないが、まあ極めて稀なケースだろうね。
スポーツ? たまにはいいかもしれないけど大変だよ。汗はかくし疲れるし、遊びで適当にやるのはまだしも、やって見せる方は大変だよ。上手くなろうと思えば練習だって、人一倍しなくちゃならないしね。
美味しいものを食べるのもいいけど、若いうちから美食にこだわるというのも、あんまりかっこいいもんじゃないよ、けっこう金もかかるしね。グルメなんてのは結局、中年になって他に面白いこともなくなってからの楽しみだね。食べて太っても、なんだしね。
もちろん、愛し合うのは最高だね、人間は愛し合うために生きているんだと言ってもいいかもね。ただ、ふられたりするとこたえるよね。それに考えてみると、お互いに愛し合っていると心底思える時間って、結構少なかったり短かったりするんだよね。
その点、音楽はいいよ。悲しいときに悲しい歌を聴けば、どっぷり涙にくれて悲しみを洗い流すこともできるし、うれしいときに楽しい歌を聴けば、もっと気持ちが乗ってくる。でも音楽というのは、もともと、みんなで一緒に楽しむものだね。
演ってもいいし聴いてもいいけど、とにかくみんなで音楽をやれば、たちまち同じ空気がみんなを包む。ステージからあふれ出る音がそこらじゅうに広がって、その音の中で、みんなが同じ時をすごす。みんなの顔がステージから見える。踊っているのもいればや歌っているものもいる。みんなの声が拍手が、波のようにステージに帰ってくる。音の魔法が、みんなをひとつにする。だから……
バンド演奏、バンド演奏
大地の夜明け、大地の夜明け
答えを求める奴や、戦いを求める奴
景色を見るためだけに
木のてっぺんにいたがる奴もいる。
おれには君の未来が分かる
手相を見さえすれば分かるんだけど、たぶん今
近づいてきているのは、バンド演奏
デッドは、演奏者と観客を区別すること自体がすでに、音楽的ではないと思っていたように見える。また、どこそこのコンサートホールで何月何日の何時から何時までと、場所や時間をあらかじめ決めて、それを契約のように後生大事に守って、そのとおりやるというのも、決して音楽的な行為とはいえないと思っていたようにも見える。
音楽とは、人が集まるところに自然に発生する人間的な行為であり、あるいは、音を介して大勢の人が一体感を得る、一種のカタルシスにほかならない。その意味で、演奏者と観客とが確信犯的な共犯者、といって聞こえが悪ければ、関係と時間の美である音楽を、自らの好みに会ったものとして成立させるための仲間たちとともに音楽をやる。デッドはそれが一番だと最初から思っていたフシがある
パブリックな予告などなしに突然始まり、少なくとも半日をかけて、気が済むまで延々と果てしなく続けられるライブ。そのことを当たり前のように知って、どこからともなく現れ、その場をいつのまにか埋め尽くしてしまうデッド・ヘッドたち。
そんなかれらの密かな証であるかのような、あるいは冗談半分のピクニックの記念品のような、Tシャツをはじめとする雑多な販売グッズ。レコードはそんなデッド祭りの断片的な残像にすぎず、カメラを持ち込もうが録音機材を持ち込もうが、一切お咎めなしで通した結果、市販アルバムよりはるかに多い、何が海賊版かオフィシャルか、ほとんどわからなくなってしまった無数のアルバム。
その代わりにというべきか、野外だろうとどこだろうと、たちまちのうちに組み立てられ、会場を、レコードでは決して味わえない彼らの音で一杯にする彼ら独自のPAシステム。そんなこんなで彼らが獲得した、他に類を見ないファミリーと呼ばれる、圧倒的な信者にも似た支持基盤に支えられ、またそんな彼らを、昨日と同じように今日もシッカリ楽しませる、不変不屈の、あるいは毎度おなじみのデッド・サウンド。
誰だって、苦しいよりは気持ちがいいほうがいい。不幸なよりハッピーなほうがいい。喧嘩をするより愛し合ったほうがいい。楽しみは短いより長く続いたほうがいい。戦争で殺しあうより、みんなで音楽を楽しむほうが、ずっとずっとずっといい。
1967年に、サンフランシスコのフリーライヴ・バンドとして登場したデッドは、その彼らの独自のスタイルと基本線を、長い活動を通して、結局のところ貫き通したように見える。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
