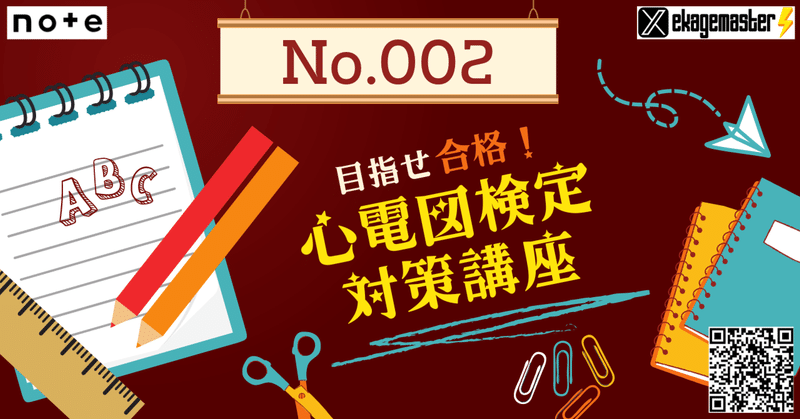
心電図検定対策講座【問題2】
対策問題002-1 (出題: 2024/3/11)
54歳,女性の心電図を示す【図2-1】。

【問題2-1】心拍数の数値として最も適切なものはどれか。
(a) 75/分
(b) 110/分
(c) 60/分
(d) 90/分
(e) 50/分
対策問題002-2
64歳,男性の心電図を示す【図2-2】。

【問題2-2】心拍数の数値として最も適切なものはどれか。
(a) 100/分
(b) 125/分
(c) 150/分
(d) 200/分
(e) 75/分
対策問題002-3
80歳,女性の心電図を示す【図2-3】。

【問題2-3】心拍数の数値として最も適切なものはどれか。
(a) 120/分
(b) 240/分
(c) 150/分
(d) 210/分
(e) 180/分


皆さん,こんにちは。えかげますたぁ|Dr.ヒロです。
『心電図検定対策講座』2024/3/11出題
第2回は3問出題しましたが,いかがだったでしょうか?...簡単でしたか?
既にお気づきかとは思いますが,今回のテーマはズバリ,
心拍数の計算①:300の法則
でした。心拍数を自分の“計算で求める”手法としては,最も基本的な手法かと思いますので,是非マスターして下さい。いったんわかれば全然,難しいことではありません。
◆マス・目盛りとオンザライン
まず,お話をする上での“共通言語”から。これはボクだけの独特な言い回しかもしれません,用語を2つばかり。
次の図を見て下さい【図2-4】。

一つ目は,心電図の描かれる方眼用紙の格子に関する用語です。
まず,5mmサイズの太線で描かれる四角(=正方形)を「マス」,一方で小さな1mmサイズ,細線で描かれる“最小単位”的な四角を「目盛り」
(≒時にメモリとも表記)と呼ばせて下さい。
次にもう一つだけ。
心拍数の定義は,1分間の心臓の収縮回数ですから,基本的な作業はQRS波の個数を数えることです。しかも1分のね。R-R間隔がレギュラーな場合,そのQRS波同士の“距離”,すなわちR-R間隔を測る操作を行います。この距離の物差しが,マス・目盛りであり,カウントしはじめるQRS波のどこかが太線の上に乗っていると数えやすいと思いませんか?
ボクはこれを“オン・ザ・ライン”(On-the-line:OTL)と呼ぶんです。その方がわかりやすいよね,という話だけです。
ですから,ボクが自分で心拍数を測る際,全体の波形を見渡して,スタートのQRS波は絶対に“OTL”(この略語はあまり使いませんが,面倒くさい時には使用します)の箇所を選ぶようにしています。
いいですか?...まずは,この用語を理解して下さい。
【図2-5】のAならR波,BはS波,CならR'波の部分がオン・ザ・ラインなことがわかると思います。慣れてくると,吸い付くようにOTL部分に目が行くようになります。

◆「300の法則」とは?
以上を踏まえた上で、心拍数の求め方を考えます。心拍数を自分で計算しようとする場合、プロセスは次の通りです。
1)R-R間隔は整 or 不整?
2)整なら1拍分のR-R間隔から計算する
①300の法則
②はさみうち等分足し引き法
3)R-R間隔:不整または“こだわらない”場合
〈A〉カンニング法
〈B〉検脈法
今回の問題のように、R-R間隔:整(レギュラー)の場合,前回(第1回:https://note.com/ekagemaster_hiro/n/na8744417b5cf
)にご紹介した3)〈B〉検脈法ないしは,コンピュータによる自動計測値をそのまま転記―ボクはこれを“カンニング法”と名付けています―のいずれも適用することは可能です。
ただ,今回は2)①300の法則を解説します。これはR-R 間隔がマス(数)“ぴったり”になるラッキーな場合で,
R-R 間隔がN マスなら心拍数は300÷N(/分)
というやり方です。
R-R間隔をx(マス),心拍数をy(拍/分:bpm)とすると「xy=300」という双曲線を描くことができるわけです。つまり,1マスなら300bpm,2マス=150bpm,3マス=100bpm,・・・のような感じです。何度も使うので,ボクも10マス(30bpm)までは覚えてしまっています。具体的な図で見るとわかりやすいですよね【図2-6】。

ですから,OTLなQRS波を見つけ出し,1つ先(ないし手前)までのR-R間隔がマスぴったりなら,瞬時に心拍数を計算することが可能です。
少し端折って説明していますので,丁寧な解説をご希望な方は拙著をご参照下さいませ。
【参考文献】
・杉山裕章.心電図のみかた,考え方[基礎編].中外医学社,2013.
◇Amazon:https://bit.ly/44qvnch
◇楽天ブックス:https://bit.ly/3pDH53V
◇Yahoo!ショッピング:https://bit.ly/43bh1e3
→第9章(必殺!心拍数計算法①)参照

【解答2-1】 (a) 75/分

これは“300の法則”様々(さまさま)の問題,知ってれば瞬殺です。
心拍数を計算するための基本2プロセスは,
①R-R間隔はレギュラー?
②300の法則
です。まず,通常目にする形式に近くした【図2-1】を提示します。

①R-R間隔:
レギュラー(整)で良さそうです。肢誘導の胸部誘導の“つなぎ目”には注意。キャリパーを持って,QRS波のピーク部分が等間隔に並んでいることを確認すれば最高。
②300の法則:
肢誘導がOTL(オン・ザ・ライン)「だらけ」ですね。隣り合う2つのQRS波(R-R間隔)は,ぴったり4マスです(たとえばIIに注目して下さい)。
したがって,心拍数としては,300÷4=75/分(bpm)として良いでしょうかね。
今回は,マスクしているので不可能ですが,通常の状況でしたら自動計測値(「74/分」と表示されていました)を転記したり,前回ご紹介した“検脈法”で「72/分」としてもらっても大丈夫です。いずれの方法でも誤差は比較的小さくなっています。
なお,胸部誘導の方も原理的にはOTLが継続するはずですよね?・・・でも,2拍目以降でOTLではなくなっています。ただ,R-R間隔としては,“ほぼ4マス”状態が続いていますね。
呼吸性洞不整脈とまでは言わないまでも,洞結節の発火には“ゆらぎ”(変動)が存在すると言われており,そのせいと考えましょう。
もともと心拍数の数値には「絶対性」を求めてはダメなので,このようなやり方で十分かと思います。それくらいの感覚で接する感じで大丈夫なのです!

【解答2-2】 (c) 150/分

2問目も同様です。この問題はX/Twitterで公開してみましたね(https://x.com/ekagemaster/status/1766956704166731884?s=20)。気になるアンケート結果から示します(42名の方,ありがとうございました!)。ほとんどの方が正解を選べていて安心しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
