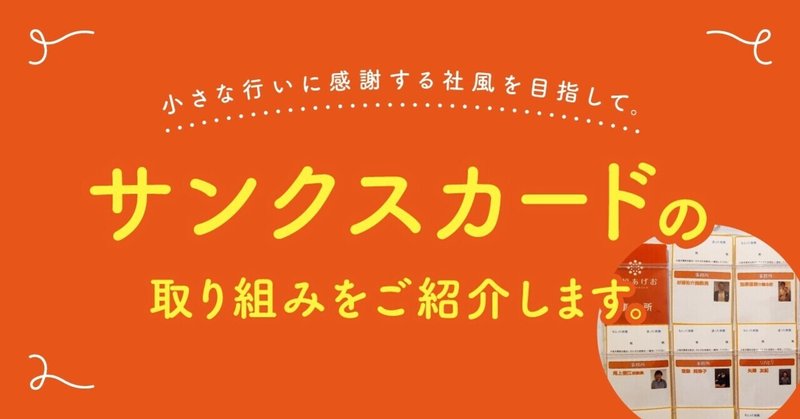
小さな行いに感謝することで感性を磨く。「サンクスカード」の取り組みをご紹介します
こんにちは、副理事長の永嶋です。
EIJUSOグループでは、社員同士がつながる仕組み作りの一つとして、「サンクスカード」を導入しています。
今回は、この取り組みについてご紹介します。
施設の自発的な取り組みとしてスタート
「サンクスカード」の取り組みが始まったのは、2018年。まずは今羽の森から始まり、続いて扇の森WESTでもスタート。そこからシニア事業部に波及していきました。
グループとしてTOPダウンで旗を振り、「こういう取り組みをしよう」と始めたわけではありません。最初は、幹部の集まる会議の場で「他社さんやホスピタリティが高いと言われる他社ではこういった取り組みがあるらしいよ」と紹介しただけでした。
そこから、「うちの施設でやってみよう」と取り組む施設が次々と出てきて、現在に至っています。
どのような良い取り組みであっても、強制的に始めるのでは続きません。個人的にも必要性を感じていた取り組みでしたが、トップダウンで始めたら尻切れトンボになってしまうのではという感覚があったのです。
そのため、こちらから「やってほしい」と言わなかったのは、本当にいいと思ってくれたところが自発的に取り組んでみてくれたらうれしいという思いがあってのことでした。
あえて「アナログ」にこだわっています
当初は市販のカードを使っていた「サンクスカード」。全施設に導入されたのち、アプリやソフトを導入して運営しようかとも考えましたが、今もなおアナログで行っています。
感謝の気持ちを伝える手段として、やはり手書きに勝るものはありません。業務は積極的にデジタルツールを採り入れて利便性の向上を図っているEIJUSOグループですが、ここだけはアナログにこだわって続けていこうと思っています。
本格導入から3年。あえて目標をつけました
2019年から「サンクスカード」を本格導入し、3年が経ちました。正直、まだまだ会社の文化になっているとは言い切れないと感じています。
そこで、2020年ごろから幹部に対し月に20枚書いてもらうことを1つの目標として設定。導入当初は強制ではありませんでしたが、あえて目標を付けることで、会社の文化として根付かせたいと思っています。
ただ続けるだけではなく、枚数に応じて表彰を行うといった取り組みに発展させられれば、もっと広がりを見せていけるかもしれません。
「サンクスカード」を始めたからといって、何か目に見える変化がすぐに表れるわけではありません。しかし、「ありがとう」の積み重ねの可視化は、書く人も貰った人も互いに気づきを得る機会となり、感性が磨かれ、最終的には自己肯定感の高まりにつながっていくのではないでしょうか。
なお、職員アンケートには、「サンクスカード」の効果について、以下のような声が寄せられています。
・仕事に対するやる気アップ。他職種への関心を持つようになった
・自分が行ったことに対し感謝されることで、仕事のやりがいを感じられた。他スタッフとチームで仕事をしようという意識を自分の中で高められたと思う
・相手がどのような事をしてもらえるとうれしいのか、助かるのかがわかりやすい
・今まで気付かなかったスタッフの良いところを発見できる
・スタッフ間のコミュニケーションが増えた。感謝の言葉が自然と伝えられるようになった
次回は「ほめ育」について紹介します
「サンクスカード」を始めた2019年ごろから、「ほめ育」という研修も社内に浸透させていきました。こちらもまた、施設内の雰囲気をより良くすることに一役買っているのではないかと思っています。
次回は、「ほめ育」を上手く事業所内で使っている事例について、スタッフに聞いてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
