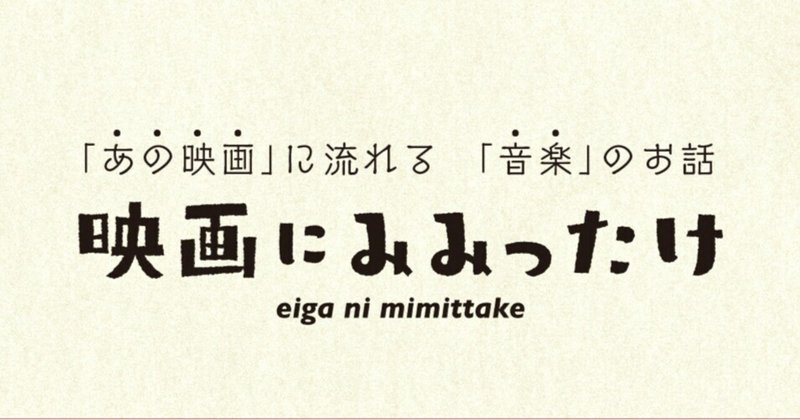
#67【レオン】ep.1「レオンのこの雰囲気、世界観。」
※この記事はPodcast番組「映画にみみったけ」内のエピソード#67にあたる内容を再編集したものです。
下記のアドレスでは投書も受け付けております。
■info@eiganimimittake.com
twitterでも配信情報を随時更新中です。
■https://twitter.com/mimittake
【レオンについて】
1994年公開(日本1995年公開)
監督:リュック・ベッソン
音楽:エリック・セラ
作曲家紹介
エリック・セラさんは、フランス出身の有名な作曲家であり、映画音楽の分野で幅広い活動を展開してきた才能あるアーティストです。
彼の音楽は、多くの映画作品で重要な役割を果たしており、その特徴的なサウンドは映画音楽愛好家に広く愛されています。
1980年代から現在にかけて、リュック・ベッソン監督との協力が特に多く、彼の音楽はヒット映画「ニキータ」や「フィフス・エレメント」そして今回取り上げる「レオン」などで際立った存在感を発揮しています。
作風としては、電子音楽とオーケストラの要素を組み合わせて、独自のサウンドを生み出すこともしています。
作曲家作品
007 ゴールデンアイ
ローラーボール
バレット モンク
(リュック・ベッソン作品)
最後の戦い
サブウェイ
神風 (制作)
グラン・ブルー
ニキータ
アトランティス
レオン
フィフス・エレメント
ジャンヌ・ダルク
WASABI (制作・脚本)
バンディダス (制作・脚本)
アーサーとミニモイの不思議な国
アーサーと魔王マルタザールの逆襲
アーサーとふたつの世界の決戦
アデル/ファラオと復活の秘薬
The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛
LUCY/ルーシー
ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ! (制作・脚本)
ANNA/アナ
登場人物
レオン・モンタナ:
主人公。トニーからの依頼で仕事を行う殺し屋。
マチルダ・ランドー:
レオンのアパートの隣に住む少女。
ジョセフ・ランドー:
マチルダの父親。麻薬の運び屋。
マージ・ランドー:
マチルダの義母。
ジョアン・ランドー:
マチルダの義理の姉。
マイケル・ランドー:
マチルダの弟。
ノーマン・スタンスフィールド(スタン):
麻薬取締局の刑事。裏で麻薬の密売を行っている。
トニー:
レオンの雇い主でイタリアンマフィア。
あらすじ
舞台はニューヨーク。
主人公であり殺し屋のレオンさんは、同じアパートに住むマチルダさんという少女と出会います。
頬にアザのある彼女は、父親から虐待を受けていました。
そして家庭に居場所のない彼女は、大切な弟だけを心の拠り所にして孤独な生活を送っていたのでした。
ある日、麻薬密売組織を仕切るスタンさんが手下を引き連れてマチルダさんの住む部屋へと訪れます。
スタンさんと麻薬の取引をしているジョセフさんが、麻薬をくすねていたというので報復にやってきたのです。
そして偶然外出していたマチルダさんを残し、一家は全員スタンさんの手によって銃殺されてしまいます。
やがて帰宅したマチルダさんは家族が殺害されたことを察知し、そのままレオンさんの部屋へと逃げ込み、保護されることになりました。
大切な弟を殺されたマチルダさんは、復讐のためレオンさんに殺しの仕事を教えてほしいと頼みます。
当然断るレオンさんですが、マチルダさんがその場で銃を発砲してみせたことで根負けし、マチルダさんに殺し屋としての手ほどきをすることになりました。
こうして奇妙なコンビとなった二人は、アパートを離れホテルで暮らしはじめます。
マチルダさんに銃の扱いを教えるかたわら、かわりに彼女から読み書きを教わるレオンさん。
いつしか二人の間には信頼関係が生まれていました。
そんなある時のこと、マチルダさんは事件のあった自宅へと忍び込みます。
そして隠してあった現金と、弟の形見のぬいぐるみを持ち帰ろうとするマチルダさんですが、そこへタイミングよくスタンさんが現れます。
復讐相手の素性を突き止めるため、彼を尾行するマチルダさん。
タクシーで行方を追っていくと、驚いたことに彼が入っていったのは麻薬取締局のビルディングでした。
スタンさんは麻薬の取締官でありながら、裏で麻薬を密売していたのです。
こうしてスタンさんの居場所をつかんだマチルダさんは、配達員のふりをして単身麻薬取締局に潜入するのですが、
彼女の存在に気づいたスタンさんによって逆に捕まってしまいます。
そしてマチルダさんの残した置き手紙に気づいたレオンさんは、彼女を救うため麻薬取締局に乗り込みます。
【映画の持つ世界観】
今回は映画が持つ雰囲気について見ていこうと思います。
まずこの作品に出てくる内容をまとめると、イタリアの掃除屋、少女、麻薬、麻薬取締局の刑事、イタリアのマフィア、が登場するアクション映画です。
めちゃくちゃざっくり内容に触れると、掃除屋が麻薬取締局に一家を殺されてしまった少女を保護、その少女が麻薬取締局の刑事に復讐を誓い、掃除屋としての訓練を積み、少女と共にレオンは麻薬取締局と衝突する、といった内容です。
なので、映画音楽としては非常にシンプルですね。
この内容から連想される音楽ジャンルは「アクション音楽」「バラード」「サスペンス」「ホラー」これらのジャンルがベーシックにあることになります。
作曲というのはとても多角的に考えて作られていて、どのシーンにどのような音楽の雰囲気を与えるかが決まります。
ホラーとアクションのシーン
例えば、
2:38
レオンさんの掃除屋としての仕事を観客が初めて見るシーンです。
この時はまだレオンさんが敵か味方かを観客は知りません。
ただ、冒頭の依頼のシーンや相手がマフィアであることでどことなくレオンさんが味方である雰囲気だけを掴んでいる状態ですね。
そんな情報量の中とにかく強いレオンさんが、マフィアをバッタバッタと、しかも姿をほとんど見せずに倒していきます。
この時の音楽はアクションというよりかはどちらかといえばホラーです。
もちろんアクションの要素もあります。
ということはホラー音楽とアクション音楽が2つ合わさった楽曲になります。
そしてこのシーンではマフィアサイドの映像が多く使われています。
そのマフィアは焦り、とても怯えていて慌ただしくしています。
容赦無く発砲してくるマフィアがアクション音楽の要素で、そのマフィアを姿もみせずに倒していくのがホラー音楽の要素ということになります。
そのため、レオンさんがマフィアを倒したり、大きな音がなる時には音楽がストップしています。
これもホラー音楽の要素ですね。
それに対して、慌ただしく動くマフィアの動向はアクション音楽によって彩られています。
そのため、マフィアの動向を追っている時はパーカッションが強く強調されています。
冒頭のシーンではこの2つの要素が映画の雰囲気を作っていることになります。
映画としては腕利の掃除屋であること、それと掃除屋は仕事で、自らの意思ではなく依頼であることなどを読み取れる情報ですが、音楽ではその腕利の掃除屋がホラーなくらいに腕利で、この映画がアクション映画であるということが表現されていますね。
そしてこれは映画全体にも言えますが、メロディラインの表現にどこかヨーロッパな雰囲気を併せ持っています。
このヨーロッパさが映画全体の雰囲気を強めていて、ニューヨークの街並みなのに、どこか海外映画の雰囲気があります。
映画自体もフランス映画ということと、舞台はニューヨークのリトルイタリーであり、レオンさんがイタリア人であることがヨーロッパを感じさせる意味になってきます。
このように映画は音楽のジャンルが根底にある状態で、その音楽に世界観や雰囲気を表現するための作曲が施されます。
さらにシーンのエネルギーや動きに合わせて、細かく映像にリンクさせています。
ということで、「バラード」と「サスペンス」も見てみます。
バラードのシーン
34:55
かくまったマチルダさんから殺されてしまった家族の話を聞きレオンさんが励ますシーンです。
このシーンでは、家族の死に対して弟さんを殺されたことが悲しみの全てであることを聞きます。
ジャンルは悲しいバラードですね。
しかしこのシーンは会話がメインのシーンです。
マチルダさんの話とレオンさんが励ますために豚の真似をするなどの、重要な会話が続くためメロディは控えめに書かれています。
しかし最低限の音数で悲しいと感じさせるために、ハーモニーには気を使い、会話のリズムが小節の切り替わりになるように書かれています。
小節の切り替わりにはメロディアスな要素をなくし、途切れ途切れの会話の隙間を縫うようにメロディが配置されているのは見事ですね。
こういった細かな気遣いが映画の印象をガラッと変えるものです。
サスペンスのシーン
次にサスペンスの要素です。
37:59
マチルダさんはレオンさんに家族のことを打ち明けた後、ミルクを取りに行ったレオンさんのバッグに大量の銃器が入っているのを見つけます。
この時観客はすでにレオンさんが暗殺家業に身をやつしていることを知っています。
しかし音楽は衝撃的な雰囲気で恐怖を煽ります。
これは2つの意味で捉えることができます。
ひとつは、マチルダさんへの感情移入です。
この時の観客は不幸な事件で弟さんを亡くしてしまったマチルダさんに感情移入しています。
なので、何の仕事をしているかわからないけどよくしてくれるレオンさんが銃器を大量に持っていることへの疑心と恐怖と期待がこの時にサスペンスフルな音楽を演奏させています。
もうひとつは裏の仕事という一般的な感覚からみた疑心と恐怖です。
この映画は観客の目線から、犯罪者が味方で警察が敵という構図になっています。
これは世間的には逆で、銃はやはり怖いものですし、犯罪者も怖いです。
なので、今一度この映画は世直しではないということを再確認させます。
まあスタンさんは汚職も汚職で悪い人ではあるんですけどね。
しかし多角的な視点からみると、誰が悪で誰が正義かは分かりづらいということも同時に教わりますね。
この2つの要素を合わせるとこのシーンではうまい誘導がされています。
マチルダさんに感情移入しやすくする方法として、世間的に怖い銃器への疑心と恐怖、それとマチルダさんが感じる誰とも知らない命の恩人レオンさんへの疑心と恐怖という感情をうまく誘導することで、マチルダさんに感情移入したように感じさせます。
ということはマチルダさんの敵である汚職刑事のスタンさんも同時に敵と認識します。
ここまでの流れではスタンさん一応は刑事ですし、暴力を振るうダメ親父を手にかけているので、なんとなく悪いやつじゃないという目線で見えてしまう可能性があります。
もちろん映画的には悪役なのですが、よく考えたら悪くなくない?ってなってしまうとそれがノイズになってしまいます。
マチルダさんからみて完璧に嫌なやつとして敵対して復讐をはっきりさせるために、弟さんを手にかけてその話のあとにこのような誘導の仕掛けも作ることで、観客の感情がとっ散らかってしまうことを避けています。
さすがの一言です。
すばらしいとされる映画にはこのような何度も見ないと気づかない仕組みを、初見でなんとなく感じさせる力がありますよね。
【程よく混ざるシンセサイザー】
後半は程よく混ざるシンセサイザーの世界を見ていこうと思います。
電子楽器とオーケストラの組み合わせはエリック・セラさんの作家性でもあって、今回レオンでも多く使われています。
ではなぜ、電子楽器が使われているかというと、それは音の自由度の高さです。
通常アコースティック楽器は楽器ごとに特性となる倍音という音が含まれていて、その倍音によりその楽器らしい音を出すことができます。
例えば同じ高さのC5をピアノとギターで聴き分けられるのは、含まれている倍音がピアノの音とギターの音で違うため聴き分けることができます。
C(ド)を弾いてもG(ソ)やオクターブ上のC(ド)などが同時になっています。
細かくいうと数えきれないほど多数の音が同時になることで、ピアノやギターなど楽器ごとの音として聴き分けているのが仕組みで、それを聴き分けられるのほどに人間の耳は優秀というわけです。
もしもC(ド)になんの倍音も含まれていない場合は、サイン波という「ピー」という音になります。
ですので、アコースティックの楽器がオーケストラで演奏されている時の譜面には8種類の音が同時に演奏されていても、数えきれないほどの他の音も含まれているということになるんですね。
同じ音のサイン波だけで音楽を作ると、譜面的に間違えてなくても面白みのない音楽に聴こえてしまいます。
そんな中、シンセサイザーは多数の波形の組み合わせで、倍音のような表現やアコースティック楽器には存在しない音を再現する自由度の高さが高く評価されました。
その中で、オーケストラに電子楽器を組み合わせることで、今までのオーケストラの音にさらに自由な表現が加わり、表現できる幅が一気に広がりました。
最近では映画音楽でもよく使われていて、その中でエリック・セラさんも有名な音楽家の一人というわけです。
特に映画音楽でよく使われるのがドローンのようなPAD系のシンセサイザーです。
今回のレオンでも使われています。
シンセサイザーの使われているシーン1
2:38
映画の冒頭で、麻薬を取り扱っているマフィアの掃除を頼まれたレオンさんが乗り込むシーンです。
この時のベースに注目してみると、一見チェロかコントラバスのようなサスティーンのベースが聴こえます。
しかし音はゆっくりと唸るように揺れていて、その音もザラザラとした音質です。
これはアップルミュージック レオン オリジナル モーション ピクチャー サウンドトラック7曲目に収録されている「ファットマン」という楽曲で聴くことができます。
非常に緊張感のある楽曲で、メロディらしいメロディがない楽曲です。
前半でも話したアクション音楽とホラー音楽の楽曲ですね。
このマフィアの名前は劇中に登場しないのですが、この時演奏されている楽曲がファットマンなので、あだ名や通り名なのかまでは分かりませんが、もしかしたらファットマンと呼ばれているのかもしれませんね。
こういうところからも映画への想像力が膨らんでいいですね。
シンセサイザーの使われているシーン2
意外な音として使われているのが、
1:08:36
新しい宿泊先を追い出されて、また別の宿泊先を探すシーンです。
この楽曲はパーカッションも多く使われていて、リズムカルな要素を含んだ準備をするようなシーンなどで使われる、映像のアクションレベルが低いアクション音楽というジャンルに属しています。
この時に遠くでなっているストリングスのような音はシンセサイザーです。
ストリングスではない理由は全体の音の馴染み方が優先されているからだと思います。
自由度が高いため音馴染みのいいように音作りをすれば、ストリングスより目立ちすぎずに必要な音を追加できます。
このような意外なところにもシンセサイザーが使えるんですね。
この映画は電子楽器だとすぐに判断できるような音作りをしていないのも特徴の一つです。
サブスクリプションSP24でお話しした、もののけ姫に以外にも多くの電子楽器が使われていたケースと近いですね。
映画の雰囲気は電子楽器が登場するような世界観ではありません。
この場合は近未来やメカニックのような機械工学が映画には登場しないのが理由の一つですね。
しかし幅の広い表現ができるシンセサイザーの音は結構使われていて、縁の下の力持ちといった感じで登場しています。
シンセサイザーのバリエーション
ここで少し脱線しますが、シンセサイザーとサンプラーの違いについて触れてみたいと思います。
シンセサイザーとは、電子楽器の総称のことなので、サンプラーもシンセサイザーの一種なのですが、ここでは一旦切り離して話したいと思います。
ちなみに、エレキギターやエレクトリックピアノなどは電気楽器と言われて、楽器自体に音の発信元があり、それを電気的に音を大きくするものは電気楽器です。
楽器ではないですが、マイクと同じですね。
それに比べて電子楽器は楽器自体に音の発信元はなく、電気信号を発信しているので電気そのものを発信源にしているのが電子楽器となります。
同じようで少し違うんです。
話はもどして、シンセサイザーにはアナログシンセやFMシンセというものが存在します。
これらはオシレータといわれる単純な波形を合成することで音を作るシンセサイザーのことです。
今回映画レオンで使われているシンセサイザーはこのタイプですね。
非常に複雑なため僕の行ったバークリーという音楽大学でもアナログシンセの学科がありました。
僕もそこそこには詳しいですが、聞けば聞くほど奥が深い楽器なので、全てをマスターしきれていません。
そのくらい奥深い楽器ということですね。
それにFM合成という周波数変調を使っているのがFMシンセです。
こちらはアナログシンセの操作方法を応用しているので、アナログシンセが触れたら大体触れます。
これらのシンセサイザーはあくまでも波形を倍音成分に似せて作ることで音を作っているので、サイン波のモジュレーションをしているということになります。
しかしデジタルシンセというものが登場します。
ここからサンプリング音源などを用いて、音の再現度が飛躍的に向上します。
というのもサンプリング音源とは実際の楽器の音を録音してキーボードを弾くことで、アサインされている音が鳴る仕組みになっています。
なので実際の楽器の音が鳴るわけですね。
なので、再現度は非常に高いです。
なら実際に演奏した方がいいんじゃない?という声も聞こえてきそうですが、この技術が後に音楽の制作現場をよりスピーディーなものに変えていきます。
それがソフトウェアシンセサイザーというもので、このラジオを録っているのもそうなのですが、DAW(デジタルオーディオワークステーション)というアプリケーション上で使うデータ上に存在するシンセサイザーです。
このシンセサイザーで先ほどのサンプリングされた音を使うことで、制作は飛躍的に楽になります。
例えば、今までは譜面を書いてオーケストラに演奏させないと音の全貌がわからなかったものを、いまでは全体がわかる程度のディテールで再現できてしまいます。
音楽家は譜面でどのように鳴るかある程度想像できますが、音楽家ではない人が確認するのに音のイメージがすぐに伝えることができるようになったわけです。
しかしサンプリングではやはり多少の違和感が出てしまうので、生演奏には現状勝てないのですがいまだに重宝されたくさんの音源がいまだに発売されています。
このように、波形をいじって音を作っていたのが、いまでは楽器を録音してそれを鳴らすようになったのはおおきな違いですね。
少し話はそれましたが、映画音楽でよく使われる電子楽器と言われたらアナログシンセサイザーのことで、ソフトウェアシンセを使うことはあまり多くありません。
ただ、予算の関係で生演奏が録れない場合などに使うこともあるので、今まで聴いて生演奏だと思っていたものが、シンセサイザーの音かもしれません。
【エンディング】
今回は映画の雰囲気と電子楽器の使用について話してきました。
全体を通してレオンという映画の雰囲気の話で少し音楽とはみたいな話にもなっていましたね。
シーンや映像のエネルギーレベルなどに合わせたジャンル選びと、会話のテンポや観客に与えたい情報、それに映画の世界観を作曲の種にして、曲を書いていくという話、それとエリックセラさんの作家性として登場した電子楽器の使用や、電子楽器の歴史みたいなものに軽く触れました。
次回はサブスクリプションで「フィフス・エレメント」をやるので興味のある方はぜひ聴いてみてください。
エリックセラさんとリュック・ベッソン監督の共同作ですね。
こちらも楽しみにしていてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
映画にみみったけ、放送時のパーソナリティはヨシダがお送りいたしました。
podcastのエピソードは毎週日曜日に配信中ですので、そちらでもまたお会いいたしましょう。
ではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
