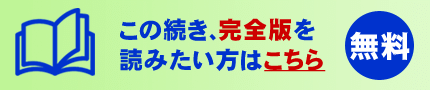なぜ人間関係でストレスをため、コミュニケーションがうまくいかず、職場、学校で孤立、孤独を感じてしてしまうのか?
人間関係でのストレスから自由になる方法
職場や学校、近所づきあいでの人間関係でストレスや悩みを強く抱える人
あがり症や対人恐怖、社会不安障害、うつ病などで苦しんでいる人
不登校のお子さんについて、大部分が共通していることです
現在生きる上で不都合な状態を抱える人の理由の一例を書き並べました。
なぜ人間関係に遅れをとるようになったのか?
親が過度に強かったり、厳しかったり、怖かったりすると、子供は萎縮してしまいます。
自己主張が出来ない子供になってしまう。
そうなると、親の顔色をうかがうようになってしまうのは必然的といえるかもしれない。
子供によっては、自分の子供心を抑圧して、いい子を演じて、親から認めてもらおうと努力します。
それだけならいいんですが、家庭の外に出たとき、親への萎縮、親の目を気にすることが、他者にリンクしてしまうと、他人に身構えやすくなる子供になってしまう。
また親に必要以上に「こうあるべき、こうしろ、なぜこうならない」と言われ続け育てられると、冒険できなくなる子供になってしまうパターンが多い。
逆に過保護でも親に依存してしまうため、外部の空気に触れたとき、もろくなりやすく、他人の目を気にしやすくなる。
そういう子供は、考え方の視野が狭くなる。
与えられたものでしか見られなくなるから。
「こうあるべき」と言われ、「こうあるべき」という理想が職場や学校で思い通りに行かなくなったとき、「どうしよう」と焦り、不安に思ってしまう。
しかしプライドは高くなり、理想と現実のギャップで苦しんでしまう。
親からの感情的抑圧を強いられ、自己肯定感を得られない
例えば、親が勉強しろと言う。
それでいい成績を取っても、「まだまだ」と言われ褒められもしなかったとき、子供の心とエゴは充たされない。
認められたというプラスの感情経験がないため、迷いが生じ自信もなくなる。
これから先、ずっと自信が得にくい心になってしまう。
褒められようと、より一層頑張ったとしても、評価や愛を親が表現しなかったり、表現するのが下手だったとき、ますます子供はジレンマに入る。
エゴが充たされない子供は何かがあったとき、崩れやすくなる。
実態のない自信がないからだ。
常に寂しさを感じ、満たされない空虚さを持って、多感な思春期になり、その時点ですでにプラスよりもマイナスへの感受性が病的に強まってしまうと、一生大人になって老人になっても、同じ精神状態をより強化しながら生き続けることになる。
抑圧せずエゴを満たして生きてきた人は知らず知らずタフな心を手に入れている
一方、わがままの子供は充たされやすい。
エゴが充たされているとは、自分そのものの存在価値を知らず知らず自己肯定しているということだから、自信をもった人間になっていく。
少しばかりの荒波も乗り越えられ、傷つくどころか、ますます自信と糧に出来る。
世間的評価を気にする家、保守的な家や環境で育ったとすると、近所、社会の眼、職場の眼が…
↓↓↓↓↓
脳覚醒の魔術師 岩波英知(岩波先生)の言葉集を読みたい方
他人に対して嫌な経験値を持ってしまった人はますます生きづらさが増す
自己主張もできずエゴも抑圧、うまくやれる想像もできないジレンマ
人は自分の地を見せない、エゴを抑圧する人間には案外冷たい
…
↓↓↓↓↓
※ この文章に当てはまる方は、こちらのプログラムが効果的です
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?