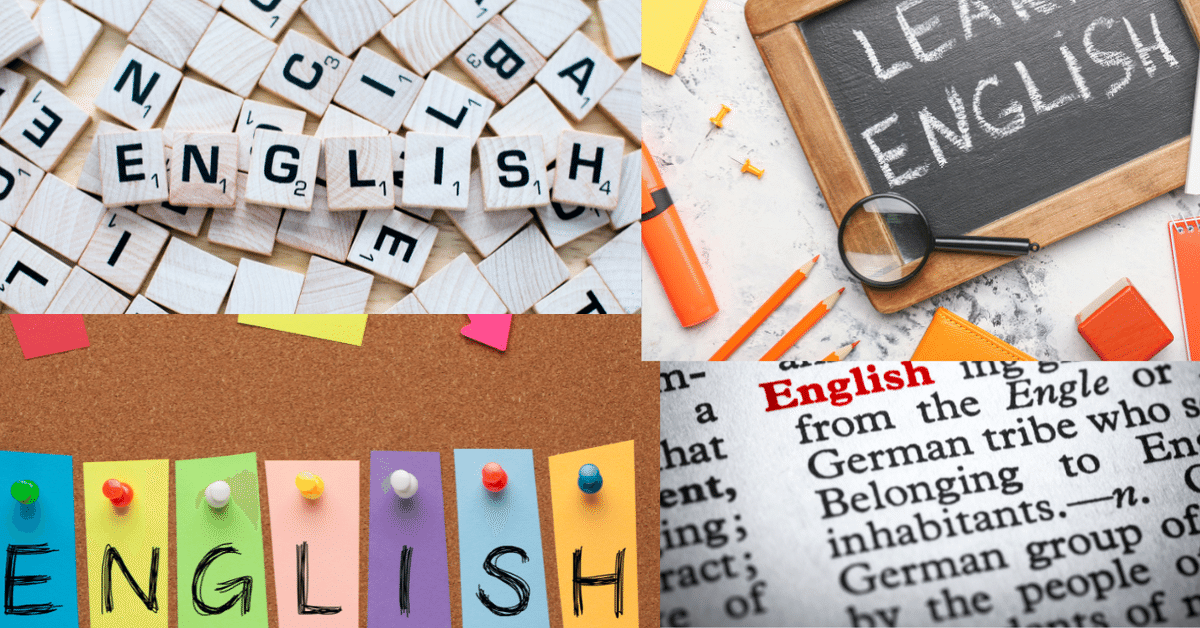
【アメリカ駐在】スパルタ英語
こんにちは、アンバサダーの葉子です。
2024年もあっという間に半分が過ぎ、この夏いよいよ渡米! というご家庭もあるのではないでしょうか? 私たち家族が渡米したのも、やはり夏でした(子どもたちは当時5歳、7歳、11歳)。7月半ばだったので、9月に学校が始まるまで、連日のように母子でアメリカの広いスーパー通って楽しんだり、水遊びができる公園をまわったり、サマーキャンプを体験したり、とてもよいタイミングだったように思います。
それから早11年……。帰国して4年近く経ち、その間に子どもたちの高校・大学受験を経験し、Edubalを通して帰国生受験の怖ろしさ大変さをリアルに知るにつけ、まあノンキな幕開けだったよなあ……なんて私は思うのですが、子どもたちに聞くとそうでもなかったようで。
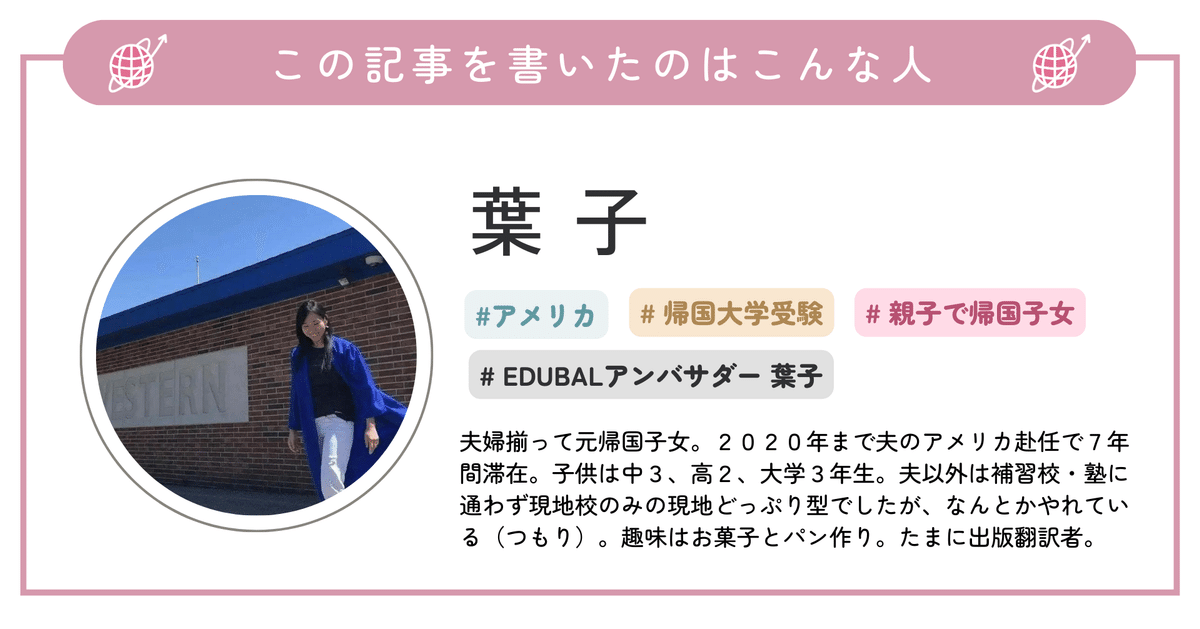

英語、教える? 教えない?
プロフィールにもあるように、我が家は夫婦揃って元帰国子女です。夫も私も小学4、5年生~中学2、3年生まで、それぞれアメリカのミシガン州とニュージャージー州に住んでいました。そのため夫婦ともに英語でのコミュニケーションに問題がなく、子どもたちも私たちが手取り足取り(とまではいかなくても)助けてくれるものと思っていたようでした。ところが現実は……

上の記事は、別のアンバサダーが書いてくれた、Edubalの大学生インターンでもある長女のインタビュー記事なのですが、その中にこんな言葉がありました:
『私の母自身も帰国子女なので、その経験も踏まえてなのか「基本的に自分の力で頑張って!」みたいなスタイルでした。笑』
そう、教えませんでした。むしろ、意地悪と思われても仕方がないようなことさえしていた記憶があります。
教え「ない」!
このnoteを書くにあたり、長女に何か覚えていることはないか聞いてみたました。すると、「アメリカに着いたその日の夜に家族で外食したとき、メニューがまったく読めない&理解できなくて困ってるのに、『自分で注文しな』って言われた……」と返ってきました。なかなか衝撃的だったそうで、よく覚えていることの1つだそうです。それ以外にも、「大体どこの店もチーズバーガーはあるから、メニューが読めるようになるまではチーズバーガーを頼みなさい」というようなことを言った記憶もあります(酷い……)
長女は「何でわかってるのに教えてくれないの?」という憤りもあったそうでしたが、私の「助けないから!」というスタンスも感じていたといい、最終的には期待しないことにしたそうです……^^;
教えなかった理由
頑なに自分では英語を教えなかった/助けなかった理由は、英語は自分で苦労したほうが身につくことを、自分自身の経験からよくわかっていたからです。それに加え、英語が得意な親が(日本の英語の参考書を使ったりして)熱心に教えた結果、逆効果となっていたケースを見聞きしたことがあったのも大きかったように思います。
ちなみに、2023年秋に「集まれ!親子で帰国子女」というイベントがあり、そこに長女と登壇したのですが、

このイベントレポートの最後のほうにあるように、私自身が子どもの頃に父の転勤でアメリカに住んだ際の英語習得に関して、大人になってから次のように感じるようになっていました:
『私の場合は、親がまったく英語ができなかったので「すごい!自分にはできない!」と言われ続けてきたことが、いま振り返ると自分にとってはよかったのかなと思う』
当時も今も、早ければ1年もしないうちに、現地語において子どもが親を追い越してしまうケースは多いのではないかなと思います。でも、それで良いんです。少なくとも私は、「すごい」と親から褒めてもらえたことで、どんどん英語を吸収できたと思っています。
教えない……けど
最後に、私が単なる意地悪ばあさんではないという話で締めくくらせてください。長女の言葉をそのまま借りるなら「(英語を直接教えてはくれなかったけど)裏で活躍してくれてたよね」とのこと。これを聞いて、オオ~わかってくれていたのね~と母は目頭が熱くなる思いでした。
たとえば、渡米2年目のミドルスクールに入学してすぐの頃の話です。いつまでも(といっても、あくまでも2年目……)ESLにいるせいで、現地の子たちと同じ英語の授業を受けられないのが嫌だ! という長女のために、年度終わりのテストをパスしなければESLは卒業できないというルールは承知の上で、ESLに籍は残したままにする・年度終わりのテストは合格するまで受ける・通常の英語クラスでついていけないと感じたら潔くESLに戻る、という条件付きで、後期からは通常の英語のクラスに入れてもらえるよう、校長やESLの主任に直接交渉しました。ちなみに、その年の年度終わりのテストに晴れて合格し、そのままESLは卒業と相成りました。このように、長女に限らず、次女や長男に対しても、裏で学校とコミュニケーションをとり、それとなく問題解決に導く、ということは何度かしました(次女と長男も気づいてるかな~?)
その他にも、日本のテレビ番組や動画を一切見せない(自分も見ない←ここ大事)、日本でバレエを習っていた長女と次女のために渡米前からダンス教室を探しておき、渡米して2週間後にはサマーキャンプに放り込む……
そんなスパルタ母を恨むでもなく、長女からは「直接的なところは自分でしなきゃいけなかったけど、お母さんは環境を整えてくれていたよね。(日本断ちしたような環境だったので)ひと昔前の帰国子女のような体験ができたと思う」と言ってもらえたのでした(感動)
さいごに
上の「集まれ!親子で帰国子女」のイベントレポート記事の最後に、これまた現在進行形で海外在住中または本帰国後の帰国子女の親に是非届いてほしい長女の言葉があるので、ぜひ紹介させてください。
『母が話していたブレない軸の話も、子どものために常にベストのことをしてあげたいという気持ちからくるものだと思う。「私のことわかってない」と思うことがあっても、ずっと心の中で母の気持ちを感じていた。親との関係性は海外生活を経て縮まったと思う。それは日本に帰ってからも、辛いことがあってもチャレンジできるという自信につながっている。親も子どもも揺らぐことはあるけれど、親のみなさんには親が子どものことを考えてくれていることを、子どもとしてはきちんと受け取っていることを伝えたいと思う』
今まさに頑張っているお母さん、お父さん、届いているようですよ!

⭐こちらの記事へのコメントやEdu-more plusへのご意見・お問い合わせは
メール(info.edubalmore@gmail.com)でお気軽にどうぞ!
