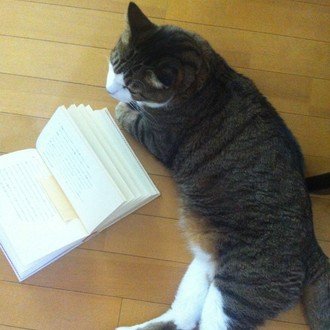批評家の家計簿
「在野研究」をテーマにしたトークイベントに呼ばれたことがある。会場は五反田のゲンロンカフェ。ほかの登壇者は東浩紀、辻田真佐憲、荒木優太といった方々だった。新型コロナのせいで会場に観客はおらず、YouTubeの配信のみだった。
たしかに大学に属してないという意味で、在野と呼べるかもしれない。けれども、ぼくは研究をやりたいと思ったこともないし、やったこともない。御三方にくらべても、「在野研究」について話す資格はない。そう思ったので、当初、依頼を断った。それでも良いからと言われて、まあ、登壇料は交通費込みで四万円。悪くない額だし、東京で別件の打ち合わせもあったので、お引き受けしたのだった。
だが、やはり言いたいことはなかった。はっきり言って、制度や設備といった点で在野であることにアドバンテージなんてない。研究したければ、大学に残ったほうがいいに決まっている。それでも在野で研究したい人はやればいい。けれども、ほとんどの人は仕事や生活に追われて続かなくなる……としか考えてなかった。
もちろん、「在野研究」が注目された背景には、大学院制度の問題点やポスドクや非常勤講師の厳しい労働環境がある。とはいえ、ぼくは別にアカデミズムの住人ではないし、自分が言うべき問題とは思えなかった。また、大学に所属すること自体が恥ずかしいと思える人も減ったので、在野の意義なんて語ってもさっぱり理解されないだろう、という気持ちもあった。
やる人はやる。やらない人はやらない。こちらがアドバイスしても、小手先で工夫したところで、なんの意味もない。研究をやりたければやればいいし。もちろん、それは人生を捨てる覚悟のうえで……みたいなことをぼくは発言した。まあ、あまりに否定的だし、身もふたもない話だ。イベントの終わりごろに東浩紀氏に「もちろん、生活保護をもらって研究もできますよ。けれども、うまくやればマネタイズできるし、きちんとしたライフプランを立てるべきですよ」と苦言を呈されるほどだった。
ゲンロンカフェには視聴者のコメントがリアルタイムで表示されるモニターがあった。ぼくの発言に気分を害した視聴者がこんなコメントを残していた。
「無頼を気取ってんじゃねーよ、若いうちだからそんなこと言えるんだ」
けれども、いまでもあまり考えは変わっていない。やる人はやるし、やらない人はやらない。
ある大学の創作科の講義にゲストとして呼ばれたとき、打ち上げで就職を控えた学生と同じテーブルになった。春からはシステムエンジニアとして働き始めるが、仕事をしながら小説を書いて新人賞を狙いますと熱く語っていた。おお、その意気やよし、と応援したくなったが、やはり難しいだろうな、と思ってしまった。
学生のころ、ぼくは読書会をよく開いていた。ミクシィやはてなで参加者を募集した。ルカーチ『歴史と階級意識』とかアガンベン『バートルビー』とか、一人で読み通すにはちょっと難しい人文書を無理やり読み通すためだった。参加者の多くは創作や批評に興味がある学生たち。読書会のあとは文学や思想の話をしながら酒を飲んだ。読書はあまりお金がかからない。図書館で借りれば無料だし、学生にうってつけの暇つぶしだ。
しかし、そういう楽しい時間は一瞬で過ぎ去る。大学の卒業が迫る。就職して会社で働き始めると、ほとんどの人が文学や思想の話をしなくなった。初任給で文学全集を買ったとか、DVDを揃えたみたいな話は聞いた。けれども、仕事やプライベートがどんどん忙しくなって、いつのまにか離れて行ってしまう。あいかわらず、ぼくはモラトリアムにすがりついていたので、遠くなった彼らの姿をさびしい気持ちで眺めていたのだった。
かくいう自分も働き始めると、どうも本を読めなくなった。執筆と仕事と両立するぞ、なんてぼくも思っていた。しかし、すぐにそれどころではなくなった。働き始めた1年間はずっとお腹を壊していた。ストレスだ。そして、酒の量も増えた。休日は二日酔いで寝てばかりだった。
就職したのが出版社だったので、ほかの業種にくらべて、読んだり書いたりできそうだった。しかし、お金をもらって読む本ほどつまらないものはない。仕事のため。企画のため。うんざりしてくる。休みの日ぐらい、そういうものを忘れたくなる。
もちろん、うまく両立させる優秀な人もいる。知り合いの書き手は、朝早く出勤して、会社近くの喫茶店で執筆するそうだ。しかし、ぼくみたいな、ぐうたらした人間には難しかった。結局、自分の興味のある本を読めるようになったのは、うまく仕事をサボ……要領よくこなせるようになった頃だったし、ぼくが初めて本を書いたのも、会社をクビ……辞めてプラプラしているときだった。
優秀な人はもちろん両立させる。それはそれでけっこうなことだ。しかし、どうしても続けざるをえない人は、労働のほうがダメになって、いつのまにかこっちに舞い戻ってくる。三十歳をすぎて自分のまわりを見てみても、大学なんて属さずに、いまだに文学だの思想だの言っている連中は、どうもうまく働けずにプラプラしているやつばかりだ。
会社をうつで休職して、詩を書いているやつ、親の金をたかって映画を見まくってるやつ、シェアハウスに住みながらフォロワーに買ってもらった哲学書を読んでるやつ……これは創作にかぎらない話だと思う。だから、いまでもやはりこう思うのだ。やる人はやるし、やらない人はやらない。その人の生き方に染み込んだ体質みたいなものだと思う。
とはいえ、最近になって、「無頼を気取るな」と怒っていた人の気持ちもわかってきた。ぼくのいうことなんて織り込み済みだったと思う。しかし、そのうえで「研究」を続けるにはどうしたら良いのか。「仕事」や「お金」のことを考えずに、好きなことを打ち込めるのは若いときだけだ。そのうち、家族や子供ができたり、両親の介護も必要になってくる。そんなときに、いやおうなく「人生」の問題がのしかかってくるんだ、と。
無頼を気取っていたわけではない。けれども、たしかにぼくは「人生」という問題から逃げてきた。大学院に進んだのも、就職活動から逃げるためだったし、出版社に就職が決まったのも、インターンをやってたら採用の話が転がり込んできて、うまい具合に大学院から逃げ出したのだった。こうやって本を書き出したのも、会社を辞めて新しい仕事探すのがダルいなあとプラプラしていたら、たまたまそういう依頼が来たわけで……自分から主体的に物事を決めたことはほとんどない。人生すべてなし崩し的に進めてきたのだった。しかし、というか、やはり、というべきか。なるべく見ないように近づかないように。そうやって逃げ回ってきた「人生」が追いかけてきたのだ。
どうやってあの人は食っているのかーー同業者の書き手の飲み会でたびたび出る話だ。とくに「純文学」系の文芸誌で執筆する人たちは、原稿料や印税だけで生活していくのはかなりむずかしい。批評家にしろ、小説家にしろ、別の仕事を持っている人が多い。たとえば、『コンビニ人間』で芥川賞を受賞された小説家の村田沙耶香さんも、コンビニで働いていたのは有名な話だ。
批評や評論系の書き手の場合、ぼくが見知っている範囲だとやっぱり大学の先生が多い。きちんとした研究をやりつつ、本業の片手間に批評を書いている。もしくは、もともと在野の批評家だった書き手が、大学の創作系コースに教員として迎えられる場合もある。中学校や高校、塾の先生といった教育関係のほかは、編集者やライター、デザイナーや校正者といった出版業界の人も多い。あくまでもぼくの印象だが。もちろん、ラーメン屋のバイトやビルの清掃員といった執筆とはあまり関係ない仕事をしている人もいる。
正業についたり、バイトしたりして生活費を稼いでいる、きちんとした人がほとんどだ。しかし、こういう真っ当な人ばかりであれば、「どうやって食っているのか」なんて話で盛り上がるわけがない。そう、やっぱり、なかなかの「無頼」もいるのだ。「主夫」といえば聞こえはいいが単なる「ヒモ」だったり、親が大企業の社長やえらいお医者さんで仕送りをもらって暮らしていたり……。
他人様の生活ばかり詮索するのは、あまり良い趣味ではない。だから、ここではぼくの収入も明らかにしつつ、文筆業がどんなものかをみていこう。印税や原稿料の具体的な数字をあげたほうが、リアルにわかってもらえると思う。まあ、あくまでもぼくの知っている範囲の話なので、思想や文学系の話がメインになる。業界全体のごく一部の話でかたよりがあることを先にお断りしておく。
ここ数年間、ぼくの収入は本を出したときの「印税」と雑誌に寄稿したときの「原稿料」が大半だ。たまにトークイベントの謝礼があったりした。そのほか、文字起こしやインタビューの構成、注釈の作成、文学賞の応募作の下読みといった仕事もやったことがある。
まずは印税から見ていこう。
最初の本『「差別はいけない」とみんな言うけれど。』は初版3000部×価格2200円。印税10%なので、収入は66万円ぐらい。
次の本『みんな政治でバカになる』は初版4500部×価格1700円。同じく印税10%なので、収入は76万円ぐらい。
最近出した本『「逆張り」の研究』は初版4500部×価格1800円。同じく印税は10%なので、収入は81万円ぐらい。
本の価格や部数を決めるのは出版社だ。採算を取れるラインを設定してくるので、ぼくよりももっと有名な書き手であれば、さらに部数は増える。
いっぽうで、専門性の高い難しい本になると、想定できる読者数は少なくなる。なので、部数は減って1000部以下になったり、価格も引き上げられて5000円ぐらいになる。さらに売上が見込めないケースになると、印税のパーセンテージを下げられたりそもそももらえなかったり、場合によっては著者本人がお金を払って出版するみたいなケースもある。出版社ごとに刷り部数(印刷した部数の分だけ印税を払う)とか実売部数(実際に売れた部数の分だけ印税を払う)といった契約の違いもあったりする。また、Kindleといった電子書籍の収入もあって、ぼくの場合は配信業者から入金された金額の20%ぐらいもらえる契約になっている。
もちろん、重版すればさらに印税が入る。たとえば、最初の本は5刷で累計1万2000部、次の本は2刷までで累計6000部で、それぞれ印税は264万円、102万円だった。業界全体で重版がかかる本は1、2割ぐらいと聞く。ありがたいことにぼくの本は版を重ねてくれたが、何が売れるかはいまだにわからない。最初の本はそんな売れない。次の本はもう少し期待していた。というのが正直なところだ。しかし、結果は真逆だった。
まあ、どういう本が売れるかわかっていれば、いまでも編集者を続けていただろうし、そもそもこういう文章は書いていないわけだ。だから、売れ行きに一喜一憂してもしょうがないので、いまでは自分が書いていて面白い、楽しいと思える本を書こうと思っている。
とはいうものの、生活費に当てているので、ある程度、採算を考えなくてはいけない。そうなると、確実に計算できる初版部数をもとに考えるしかない。いまのぼくの場合だと、本一冊書けば70万円前後の収入が見込めるわけだ。つまり、一年に最低2、3冊の本を出せば、なんとか執筆だけで食っていけるようになる。
しかし、おわかりのとおり、ぜんぜんできていない。ぼくがぐうだらしているというのもあるが、やっぱり一冊の本でも書くのに時間がかかる。有名人であれば、構成担当のライターがついたりして、何時間かペラペラ話せばたちまち本が出来上がるが、実際に自分で本を書くとなると、早くても半年間、下手したら一年以上かかる。これでも専門性の高い本を書く人からすると短いぐらいだ。
そして、当然ながら資料を集めたり、人に会って話を聞く必要も出てくる。資料費や取材費といった経費を差し引くわけで、実際の収入は……となる。時給に換算したら、どれぐらいのお金になるのか。恐ろしくて計算できない……何も考えたくない……。
しかも、この初版部数はどんどんと減少している。出版不況で。年配の編集者と話すと、出版業界が栄華をきわめたころは、名も無い新人のデビュー作が初版一万部だったみたいな話も聞くので、まあ、いまや、かなり厳しい商売になっているわけだ。
次に原稿料。雑誌やウェブメディアに記事を書いたりすると、原稿料がもらえる。これは本当にピンからキリまで媒体によって全然ちがう。たとえば、文芸誌やカルチャー誌に評論を書いたりすると、400字詰め原稿用紙一枚で1000円から5000円ぐらいもらえる。ひどいところは原稿料がタダの媒体もある。むかし働いていた太田出版では『atプラス』という思想系の雑誌を出していたが、原稿料は3000円前ぐらいだった。週刊誌や新聞になると、ググッと原稿料はよくなって、2000字ぐらい書いて3〜5万円ぐらいもらえる割の良い仕事だが、ぼくの場合はそんな頻繁に依頼は来ない。
新しく本を出すとトークイベントに呼ばれることもある。謝礼は書店が主催だと1〜2万円ぐらい、ネット配信があると1〜4万円ぐらい。観客数や視聴者数で変動するところもある。交通費込みが多いので利益が出ないケースもあるけれど、新刊の宣伝にもなるので引き受けることも多い。
繰り返しになるが、あくまでもぼくの知っている範囲の話だ。実際に文筆業だけで食っている人もいるし、もっと支払いのいいところはいいと思う。といっても、やはり評論系は全体的に安い気がする。当然、原稿料の場合でも、ここから資料を読んだり、取材をしたりした経費を差し引くわけだし、そのほか執筆するための時間がかかる。時給に換算したら、どれぐらいのお金になるのか。恐ろしくて計算できない……何も考えてくない……。
もちろん、勘違いしないでほしいが、経済的利益が少ないからといって、「文学」や「思想」といった営みがなくなるわけではない。なくなるはずがない。やるひとはやるからだ。ぼくがこういうのもおこがましい話だけれども。とはいえ、資本主義社会で生きていくかぎり、そういった営みにさえ「お金」の話がつきまとってくるわけだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?