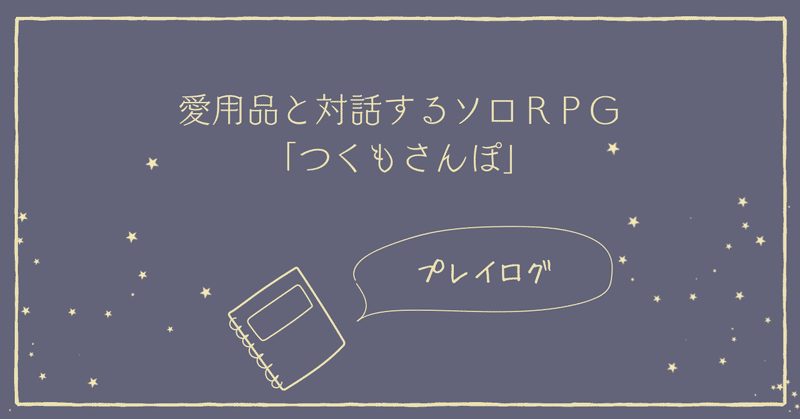
PBWの子で行く「つくもさんぽ」、プレイログ
●「はじめまして、こんばんは」
「ねぇ、起きなよ」
聞き慣れぬ声が耳元でして、俺はゆっくりと覚醒する。目を開けてもなお夢の中に居るような心地だ。それは、東京ではもしかしたら少し良くない兆候なのかもしれないが、声の主の姿を見た時不思議と危険なものだとは思えなかった。
ただ、やっぱり一目見て人間ではないとわかる容姿はしていたのだけど。
端的に言うなら、それは頭がインク瓶の形をした男だった。体格は俺と同じくらいに見えるからけっこうでかい。
「あんたは?」
寝起きの掠れた声で俺は問いかける。目も口もないつるりとしたインク瓶は、どこから発声しているかわからないが男の声で答えた。
「つくも神」
「つくも……なるほど、カミサマか」
付喪神とは、長い年月を経た道具などに精霊が宿ったもののことだ。言われて改めてその姿を見れば、彼の正体ははっきりとわかった。特に着ているスーツの、レザーのような質感に覚えがある。
「俺のノートカバーは、付喪神が憑くほどは長い時間使ってないと思うんだけどな」
「でも、お前の持ち物の内どれか一つにチャンスが与えられるとしたら、俺だろ?」
俺は小説家だ。それも、外に出てかなりしっかり取材をするタイプの。だからノートカバーを付けたノートは常に持ち歩いて、いつでもメモを取れるようにしている。しかも、このノートカバーは俺の一番大事な人がくれたものだから。
「月の神様の力を借りて、一晩だけ付喪神になったんだ。話がしてみたかったから」
つくも神はそう言って、顔のない頭を揺らし楽しそうに笑った。
●「さんぽにいこう」
「せっかくの機会なのに一晩じゃ、遊べるところほとんどないんだけど」
「そうかな。東京の街は眠らないんじゃなかったっけ」
ともあれ、外に出ようということになった。自分の足で歩けるようになったのだから、歩かなきゃ損というものだろう。
適当にぶらぶら歩いていると、河川のせせらぎが聞こえてきた。
「ここには来たことがあるね」
なんて言うから、俺は笑ってしまう。
「あんたとは来たことがある場所ばかりだと思うけどな」
「そうだな。いつも一緒だ。なんなら悪夢の中だって」
思えばいつだって連れ回しているのだ。眺めると、月明かりに照らされたスーツに沢山の傷が付いているのが見えた。見覚えのある傷ばかりだ。大事に使っているつもりだし、手入れを欠かしたこともないんだけど、それなりに無茶もする俺が四六時中どこにでも持ち歩いているせいで傷が絶えないのだろう。
「改めてみると、申し訳ないね。あちこち傷がついちゃって」
インク壺頭がこちらを振り返った。ちゃぽんと音をたてて夜色の液体が波打つ。
「別に。これは俺にとっては勲章みたいなもんだし」
肩を竦めてカミサマは言った。
「お前は、俺を一番連れて歩くんだ」
その姿がちょっと誇らしげにも見えて、俺は思わず笑ってしまった。
●「いっしょにたべよう」
「大丈夫だとは思うけど、フードしっかりめに被っててね」
「オーケイオーケイ、安心してくれ。人間ロールプレイは完璧だからな」
「本当かな-?」
次に入ったのはファミレスである。二十四時間営業かつ、入りやすそうな店としてここが一番手頃だった。問題は、カミサマがぱっと見明らかに人間に見えないところだろう。下手をすると侵蝕と間違われ、対策室を呼ばれる可能性すらある。
時刻は既に零時をまわっている。利用者は少なく閑散とした店内は昼とはまた違う雰囲気で、だからだろうか、意外とカミサマの異形にも気付かれることはなかった。
ドリンクバーで二人分の珈琲を淹れテーブルに戻ると、注文したドリアとフライドポテト、ミニピザが並んでいた。
「食べれるの? それ」
「問題ない。人間が食べられるものは神だって食べられる」
そういう意味で言ったんじゃないけど、と目も口もないインク瓶を見つめる俺の心の内など気にならないようで、カミサマは律儀に手を合わせて「いただきます」と言った。
カミサマは人間がやるのと同じように、フォークを使って口元にあたる位置へと食べ物を運ぶ。そこですっとドリアが消えてしまうのは、なんだか不思議な光景だった。
ぽかんとその様子に見入っていた俺に、ふとカミサマは声をかけた。
「無理はしてないか?」
唐突にかけられた言葉に、俺は何のことかわからず瞬きをする。それは今のこの状況のことだろうか? であれば否だ。俺は今のこの状況を結構楽しんでいるし。
それに、たとえこの状況を指したものでないとしても、俺にはその言葉を貰う心当たりがなかった。だから、
「してないよ」
少しの逡巡の末、俺はそう答える。嘘はなかった。
●「おまいりをしよう」
帰り道の途中、通りがかった神社に入ろうとカミサマが言うので立ち寄ることにした。
夜の神社はしんと静かだ。どこか空気が澄んでいる感じがして、心地が良い風が吹き抜けていく。
「カミサマもお参りとかするの?」
冗談めかした俺の言葉に、カミサマも肩を竦めて答える。
「どうだろうな。まあ人間同士だって、挨拶くらいするだろうよ」
拝殿へ向かい、二人並んで手を合わせる。がらがらと鳴らした神楽鈴の音がいつもより大きく、存在感のあるものに感じられた。
「なにお願いしたの?」
「お願いというか、お礼」
「お礼」
「こうやってお前と話をすることができた」
俺は思わず頭上を見た。ぽっかり浮かんだ月はだいぶ傾いてきていた。もうすぐしたら、白々と夜も空けてくる頃だろうか。
そんな俺の様子を見て思うところがあったのか、カミサマはのんびりとした調子で言葉を続けた。
「俺は、贈り物として選ばれてお前に贈られただろ。贈り物を選ぶ時の人間の想いを知っているし、贈られた側の喜びも知っている。そこから始まったことを光栄にも、思っている」
砂利を踏む音に、ちゃぷちゃぷとインクが揺れる音が涼しげに重なる。
「だから、もちろん今日は特別で良い日だけども。今までの日々だって変わらず良いものだったよ。これからの日々もきっとそうだと信じてる」
俺達の東京はいつだって不確定で明日だってわからないのだけれど。
カミサマの声は、彼の表情のわからない顔がきっと朗らかに笑っているのだろうと確信するような色をしていた。
「それならいいけど。俺は結構、あんたがいないと駄目だから」
「はは! ならば、今後とも宜しく。大事にしてくれとは言わないよ。何処でも連れて行ってくれ、いつも通りに」
●「おやすみ、またね」
俺達はそっとマンションの部屋に帰宅した。同居人が起きないようにそろそろと部屋へと戻る。
窓枠の形をなぞるように、月の光がくっきりとサイドデスクの上に落ちているのが見えた。そこが本来、俺のノートとトートカバーの定位置である。
「明日には全部元の通りだ。君たちの世話になならないから、そこは安心して良い」
「ん、わかった。今日はありがとね」
少し不思議で特別な日。こういうことがあると俺は大抵小説として書き残してしまうのだけど、今日のことは書かない気がする。なんとなくそういう、胸の内にそっと置いておくだけの出来事があってもいい。何より、ノートにメモを取っていないし。
「おやすみ、また明日ね」
そうして俺は眠りにつく。次に目を覚ますのはいつも通りの朝なのだろう。
うちの子はこの子。PBWは結構『思い入れのあるアイテム』を頂いたり手に入れたりしやすいから、つくもさんぽは親和性高いんじゃないだろうか⋯⋯。
とてもいい遊び体験だった。またやる(*ˊ˘ˋ*)
