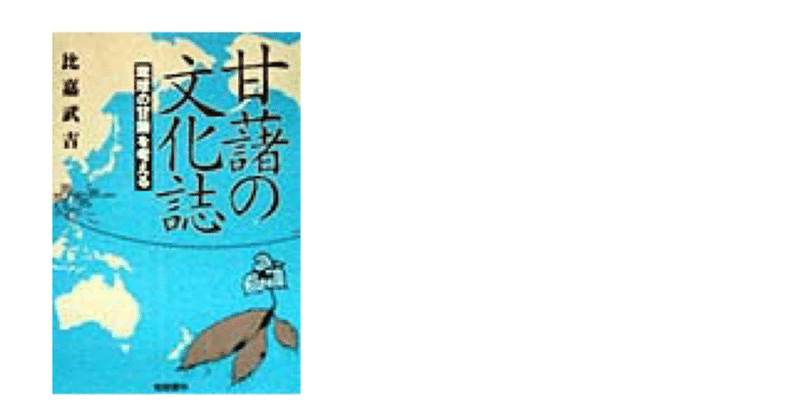
沖縄の甘藷文化を振り返る
「甘藷の文化誌」 比嘉 武吉 (著) 出版社: 榕樹書林 (1999/02)
琉球の文化と深く関わっている甘藷。
甘藷がどのように琉球に伝播したのか、甘藷の品種発達、
琉球語ウムの語源、甘藷の農耕文化、甘藷の食生活など、
様々な側面から甘藷を見直す。
沖縄の甘藷の歴史を総合的に検証した優れた本です。
残念ながら、故比嘉 武吉さんと呼ばなければなりません。
以前比嘉 武吉は、「農務書を読む」で記事にしました。
http://tomiton.ti-da.net/e2354143.html
甘藷の輪作体系技術は、昭和の初期まで下記のようでした。
1.在来種の読谷山(ユンタンザ)は5年株出しができるさとうきびでした。
このさとうきびで、砂糖を作る期間は、12月から2月の末でした。
2.田植えは、3月末までに行われていた。
3.農作業の〆の清明祭を行い、休養を取り、次の作物「甘藷」への鋭気を養った。
4.甘藷植え付けの作業の前に、株立ちが悪くなったきび畑の耕起作業があり、これは重労働でした。
5.4月に植え付けし、10月末までに必要な分だけを収穫していた。
6.11月からは、大豆、そら豆、えんどう豆、小豆、紅豆、緑豆、粟、だいこん、胡麻などを植えていた。または、混作していた。ちなみに秋植え甘藷には、だいこん、にんにく、からしな、りゅうぜつさい(うさぎの耳)、きくにがな(くだんそう)を植えてました。
7.さとうきび、甘藷、大豆の5年3作の輪作体系は優れた農業です。
※稲作地帯の田畑転換技術
1.在来種の名護穂赤(なぐふうあか)は、収穫時期が7月中旬から末
2.水田から水を抜き、株を取り除いた後に、甘藷を植え付けた。
3.やんばるの昔の水田地帯はこの農法でした。
※甘藷の台風対策
1.1783年の球陽に新技術が記述される。
2.渡名喜島の亀上原氏が、チガヤやすすきで苫を作り、暴風を防いだ。
とありました。
昭和初期までの輪作技術は、我謝栄彦著の「改訂 沖縄農家便覧」に詳しく載っているとのこと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
