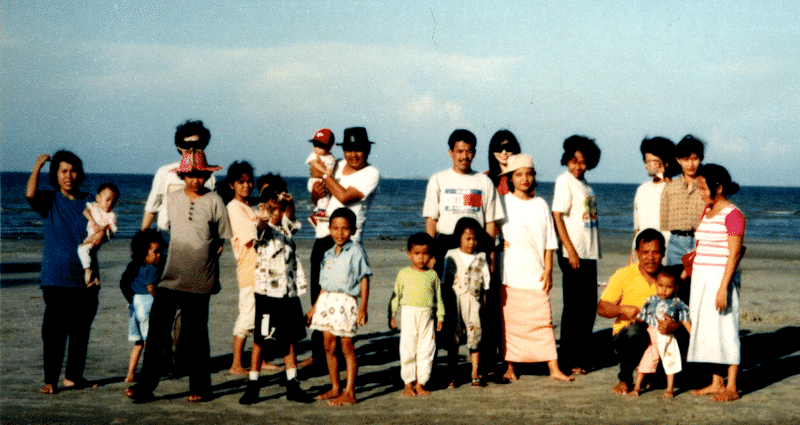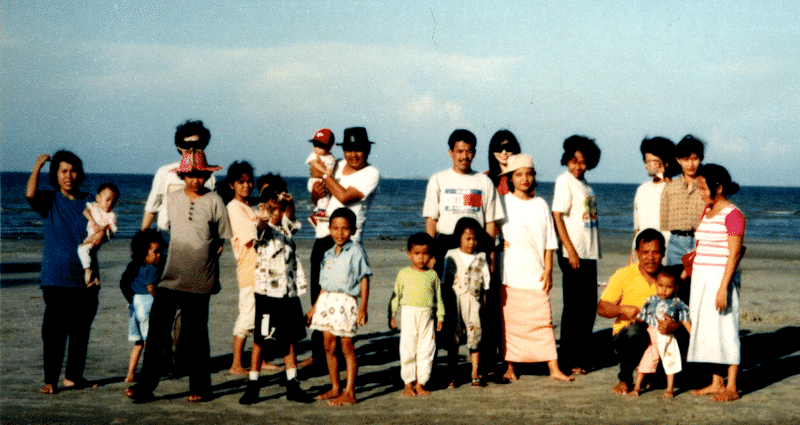イエス・キリストの歴史と真理 マタイ福音書ノート
―天国の福音―「アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図。」
使徒マタイによるイエス・キリストの系図[ギリシャ語genesis]。マタイは、イエス・キリストの十二使徒のひとり(マタイ10:3)。自分に関して「取税人」とわざわざ肩書のように記しています。マルコもルカも、肩書なしのマタイとだけ紹介しているだけなのに(マルコ3:18,ルカ6:15)。エピソードの順序を時間順ではなくテーマごとにまとめて書いているマタイが、自分の出自を福音書9章に置いているのは、罪が赦