
日本人のルーツについて②
【現代日本人はいつ頃形成されたのか?】
「日本人のルーツについて」というタイトルで続編を書いてみます。
それにともない、前回の記事を①に、今回の記事を②とします。
現代日本人の形成について従来広く支持されてきた仮説は、二重構造モデルと呼ばれるものです。
縄文時代には日本列島に縄文人だけがいたが、弥生時代になると大陸から渡来してたきた人々がいて、縄文人と弥生人が混血することで現代日本人が形成されたという説です。
様々な物的証拠も二重構造説と整合性があります。
縄文時代の日本列島は人口分布が東日本に偏っており、西日本にはほとんど人が住んでいませんでした。
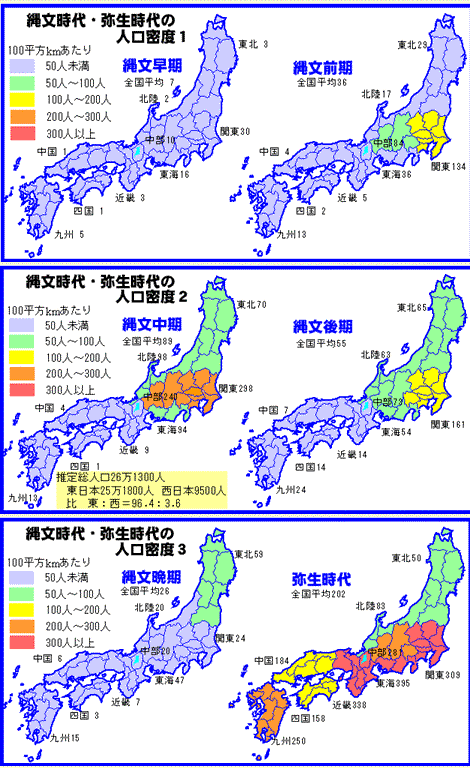
弥生時代になると大陸から渡来してきた人々が稲作文化をもたらしました。
最初のうちは玄界灘沿岸地域のみでしたが、一旦そこから出ると弥生人は短期間のうちに西日本の広い地域に拡散していきました。
遠賀川式土器の分布範囲がそれで、縄文人があまり住んでいなかった地域と重なります。

やがて縄文人が多く住んでいた東日本にも稲作文化は伝わります。
下の図は稲作がいつ始まったかを地域別に示したものです。
日本列島での稲作開始時期は地域によって大きく異なり、「玄界灘沿岸地域」、「西日本」、「東日本」の3つに大別できそうです。

発掘された弥生時代の人骨からも同じような傾向が見られます。
西日本には弥生系、東日本には縄文系という分布です。

その後、ヤマト政権による全国統一がなされ、列島内で人の移動も増えて、縄文系と弥生系の混血が進み、現代日本人が形成されたというものです。
なお、北海道は稲作に適さなかったので弥生人の移住や入植はなく、アイヌには縄文人遺伝子が多く残っています。
日本人は弥生時代にはすでに現代人と同じだった?
ところが、今まで支持されてきた日本人形成モデルを覆す可能性のある研究データが最近発表されました。
弥生時代中期の北部九州における弥生人の遺伝子解析を行った結果、その弥生人の遺伝子は現代人と同じだったのです。
下の図で、福岡・弥生人の遺伝子は現代日本人と同じところに分布されています。

弥生時代後期の山陰地方における弥生人の遺伝子解析の結果も同じでした。
下の図で、青谷上寺地遺跡で発見された人骨から抽出した遺伝子は現代日本人と同じところに分布されてます。

縄文人と弥生人が混血することで現代日本人が形成されたのではなく、弥生時代中期の北部九州ですでに現代日本人が形成されていた可能性が出てきたのです。
「北部九州の弥生人=現代日本人」ということになります。
北部九州の弥生人(=現代日本人)が全国に拡散して人口を増やし、東日本にいた少数の縄文人を飲み込んでしまったという日本人形成シナリオになります。
ただし、古墳時代から奈良時代にかけても渡来人がかなり来たと考えられていて、縄文人と弥生人の混血によって一旦は縄文寄りに振れたが、その後、渡来人によって大陸寄りの遺伝子に戻されて、日本人の遺伝子は現在の分布位置に収まった可能性もあります。
どのくらいの人数の渡来人が来たのか、当時の全人口の中で占める比率がどのくらいだったか、その渡来人の遺伝子がどうだったかが不明なので、あくまで可能性に過ぎません。
遺伝子研究は近年著しく進展してきている分野なので、日本人の成り立ちについて今後も新しい発見があるでしょう。
このシリーズの他の記事へのリンク
日本人のルーツについて①【縄文人は本当に日本人の祖先なのか?】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
