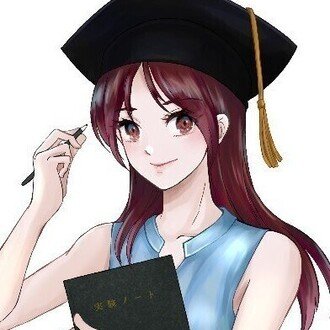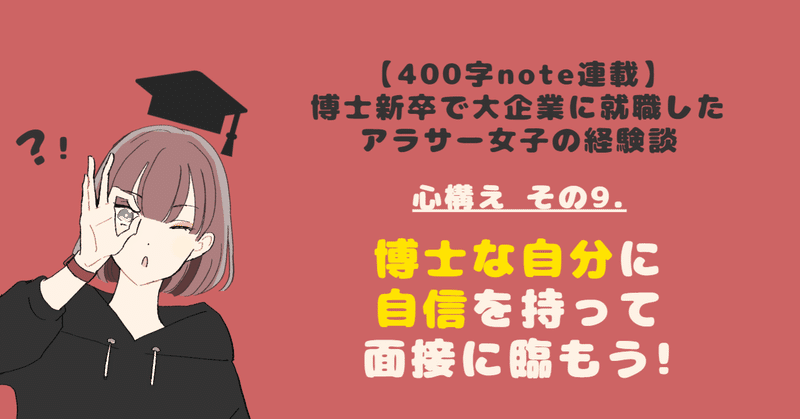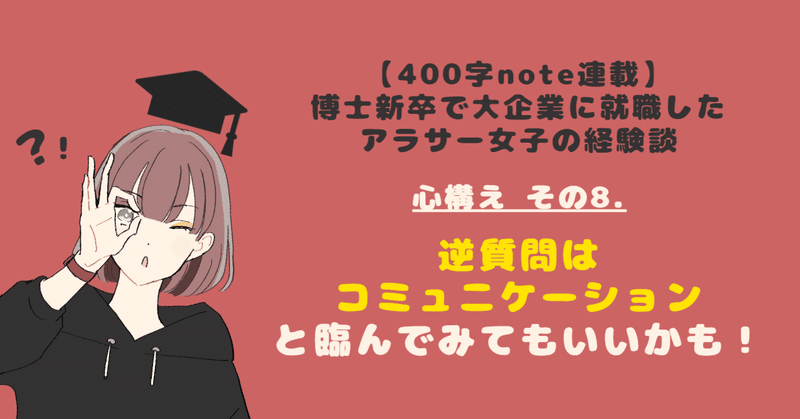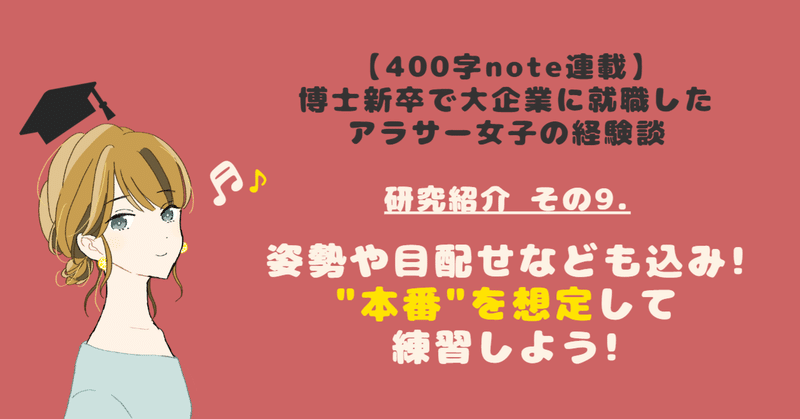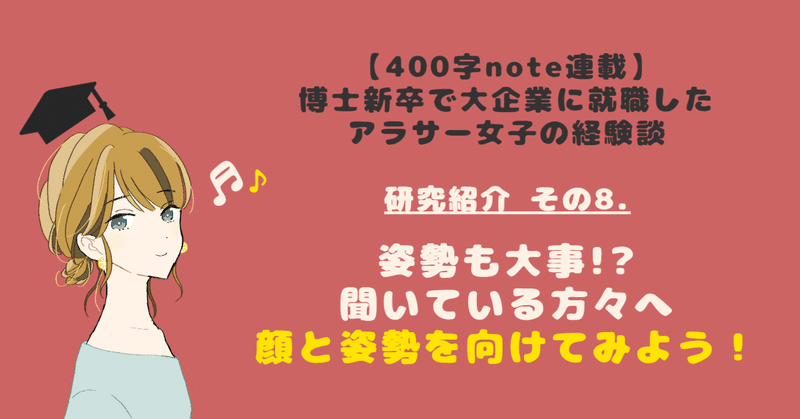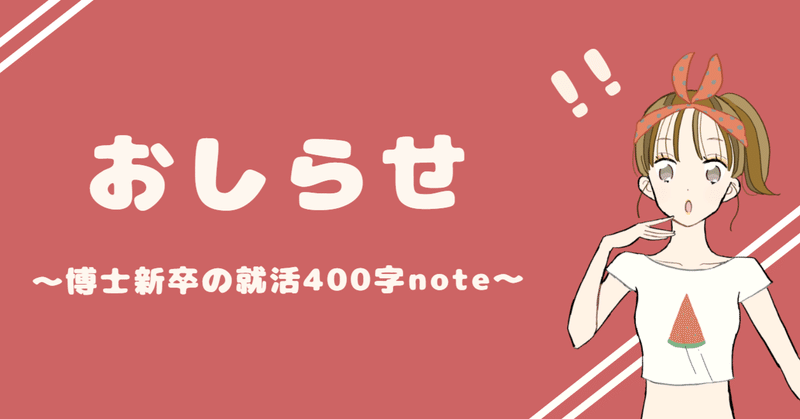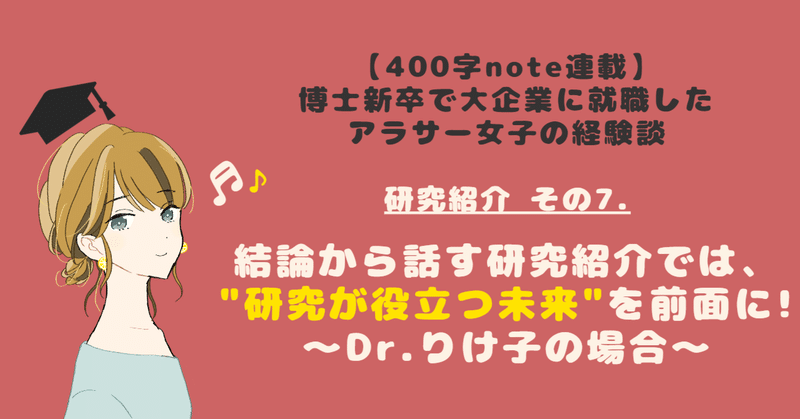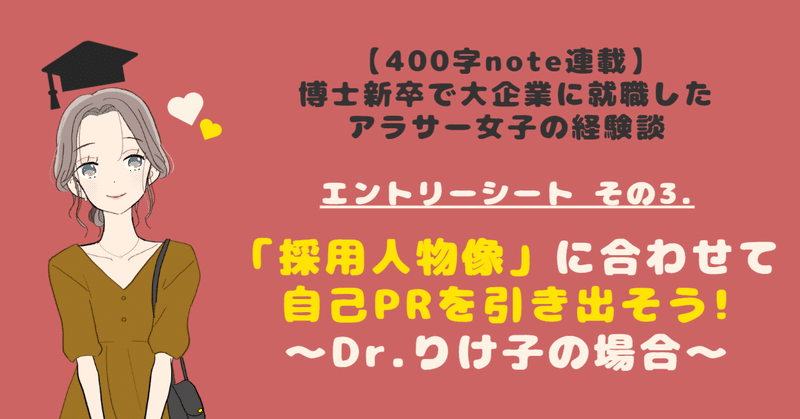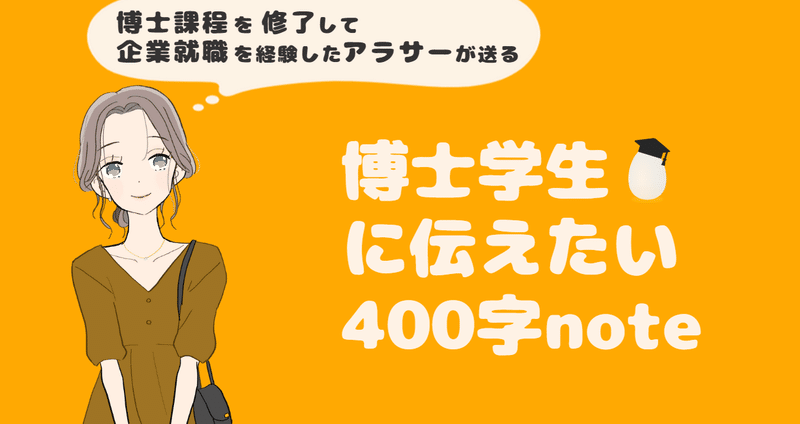
物理化学系の博士課程を修了し企業就職を選んだ私が、博士学生に伝えたいことを400字で綴る連載マガジン。2023.05.08より、毎週月曜日に更新💡
在学中や社会に出てから感じた、…
もっと読む
- 運営しているクリエイター
#博士
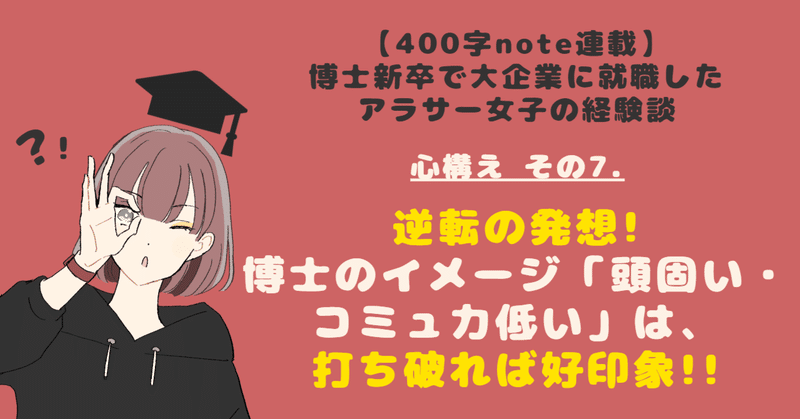
【博士の新卒就活】心構え⑦:逆転の発想! 博士のイメージ「頭固そう・コミュ力低そう」は、打ち破れば好印象!!【400字note】
”博士”には、「頭固そう・コミュ力低そう」という負のイメージが付きまといがちです(本人の意識・行動で変えられます!この件はまたいつか)。 こんなことを書くと、絶望する博士学生が出てくるはず。 ですが! 「負のイメージを覆せたら、好印象に転換できる!」と思ってみましょう。 私の経験談ですが、「博士新卒の就活400字note」に書いていることを就活で実践して、複数社の人事の方から、高評価やスカウトをいただきました。 博士積極採用な企業に応募したので、負のイメージは比較的