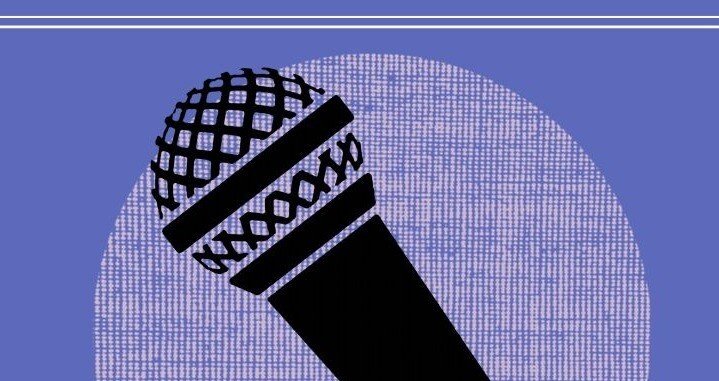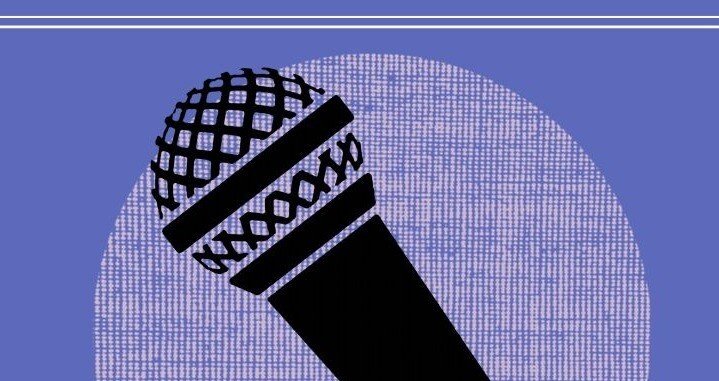1944年のフランク・シナトラ
若者と表現者たちの解逅、それは「不条理」の果てに
②1944年のフランク・シナトラ
かつて一世を風靡した「ロストジェネレーション」や「フラッパー」たちの享楽的華やかさが、混迷を極める国際情勢の中ですっかり遠い過去になっていた1944年。
ラジオから流れてくるビング・クロスビーのささやく歌声に魅了され、歌手を志したフランク・シナトラは、トミー・ドーシー楽団の所属歌手として発表した『I'll Never Smile Again』が大ヒットしたことをきっかけに、自身もまたスター