
どこよりも詳しいVulfmonまとめ /// おげんさんのサブスク堂でもおなじみ、謎多きアーティストを徹底解説!!!
KINZTOのDr.ファンクシッテルーだ。今回は「どこよりも詳しいVulfpeckまとめ」マガジンの、53回目の連載となる。では、講義をはじめよう。
(👆Vulfpeckの解説本をバンド公認、完全無料で出版しました)
今回はVulfpeck(ヴォルフペック)のリーダーである、Jack Strattonのソロプロジェクト――Vulfmon(ヴォルフモン)について、どこよりも詳しく解説していきたい。
日本では、Jack Strattonのソロ・プロジェクトであるということよりも、NHK「おげんさんのサブスク堂」で何度か紹介されている注目のアーティスト、といったほうが分かりやすいかもしれない。
松重豊さん扮する、豊豊(ほうほう)さんが特にお気に入りのアーティストで、2022年8月6日の番組初回で「How Much Do You Love Me?」が、2024年1月9日の回で「Nice To You (Little Yacov Version)」が紹介された。
Vulfmonは、もちろんおげんさん(星野源さん)にとってもお気に入りだ。そもそも彼らは、VulfmonだけでなくVulfpeckも大好きなので、折に触れて彼らの話題を出してきたし、昔から注目の存在だったということだろう。
(Vulfmonにとっても番組で紹介されたことは嬉しいことだったらしく、度々Twitterで「おげんさんのサブスク堂」の番組アカウントへメンションを飛ばしているのが確認されている)
さてさて――しかしこのVulfmon、ほとんどと言っていいほど、どんなアーティストなのかということが解説されていない。どのサイトにも「Vulfpeckのリーダー、Jack Strattonのソロ名義」という説明しか書かれていないのだ。これでは、サブスク堂でVulfmonを知ったリスナーの方々の知識欲を満たすことは難しいだろう。
そこで今回は、たっぷりと長い記事でVulfmonについて――初めてVulfmonやVulfpeckを知ったという方の目線で――彼がどんなアーティストで、どういう活動を行っているのかを解説していこうと思う。
この記事を読めば、あなたもVulfmonについての知識は十分! そんなボリュームと内容を目指して、この記事は進む。ぜひ最後までお付き合いいただきたい。
それでは、始めよう。
Vulfpeckについて
さて、本マガジンの読者であれば既によくご存じかもしれないが、初めてここに来た方のために、まず少しVulfpeck(ヴォルフペック)について解説をしておきたい。
Vulfmonを理解するためには、結局のところ、どれだけVulfpeckを理解できているか、というのが非常に重要になってくるのである。
ここを飛ばさずにしっかりと解説しておくことで、この記事全体の理解度がグッと上がるはずだ。

画像出典:Wikipedia "Vulfpeck"
Vulfpeckは2011年にミシガン州アナーバーで結成されたファンク/ポップスバンドである。現在は世界的な知名度を得るまでに成長し、Bonnarooなど、アメリカを代表するようなフェスの常連アーティストとなっている。
写真の一番右側の男性、Jack Stratton(ジャック・ストラットン)がリーダーとなって、母校であるミシガン大学の学生を集めて4名体制でスタートした。
2016年からは7名体制を基本として、2019年には世界で最も有名なアリーナスタジアムと言われるマディソン・スクエア・ガーデンで単独ライブを敢行。
Vulfpeckは、基本的にすべてJackと仲間たちだけで運営されるバンドであり、Jackの自主レーベルに所属。大手レーベルや、外部マネージャーなどの力は一切借りていない。
2019年のマディソン・スクエア・ガーデンのライブも、大手レーベルの力は借りずに行われ、Instagramの無料投稿による宣伝だけでチケットを完売させて14000人を集めたことは大きな話題となった。
(このあたりは私の著書👇に詳しく記してある。無料なので是非ご一読いただきたい)
さて……マディソン・スクエア・ガーデンでのライブは実際に行われたが、それとは別に、基本的にVulfpeckはインターネットを活動の中心に据えて成功を収めてきたバンドである。
ライブ頻度はかなり少なく、ツアーに出ることも稀だ。これは大手レーベルに所属していてはまずありえない活動方法である。
“In the normal world, you create your online efforts so that you can hopefully play as many shows as you can live,” Stanley says. “But Jack’s thinking was the opposite: Let’s do as much as we can online and only play live when we feel like it. And you know, it’s worked.”
アントワン・スタンレー:普通だったら、「できるだけ多くのライブを行うために、オンラインでも活動しよう」と考えますよね。しかし、ジャックの考えは逆でした。「オンラインでできる限りのことをして、ライブは気が向いたときだけやろう」って。そして、それがうまく行ったんです。

少ないのはライブだけではない。レコーディングに使う時間も非常に短く、基本的にメンバーはほとんど一緒にいない。そもそもライブやレコーディングのためのリハーサルは一切なく、いつもぶっつけ本番で全てを完結させている。
これは、リーダーのJackの考えによるもので、JackはVulfpeckを存続させるために、あえてVulfpeckの活動時間を最低限に抑えようとしている。
一見意味が分からないかもしれないが、つまり、これは「メンバー個人のソロ活動を成功させることが、バンドが長続きする秘訣だ」というJackの持論によるものなのである。
I can assure you our band has the least amount of time spent together vs. international success in history, I will assure you that.
ジャック:私たちのバンドは、一緒に過ごした時間が、国際的な成功と比較して、歴史上最も少ないと断言できる。
“The core vision has always been sustainability, and a big part of that is even trying to have other projects succeed simultaneously with it,” Stratton said. “So I think Theo doing his thing, Joe, Woody and me doing our stuff are all important to the sustainability of Vulfpeck counterintuitively."
ジャック:コアとなるビジョンは常に「持続可能性」であり……それはバンド以外のプロジェクトも同時に成功させようとしていることだ。だからティオがソロ活動をしていることも、ジョーやウッディや私がソロ活動をしていることも、ヴォルフペックの持続可能性にとっては逆に重要なことだと思うんだ。
これは現代におけるバンド活動のまったく新しいやり方のひとつであり――実際に、Vulfpeckに参加しているCory Wong(コーリー・ウォン)は、グラミー賞にノミネートされるほどの人気ギタリストに成長したが、Vulfpeckの活動頻度が少ないために、いまだにバンドのすべての活動に参加し続けている。
Coryは一年のほとんどをツアーとレコーディングに費やしているが、そうした彼のソロ活動を邪魔しないためにも、あえてVulfpeckは活動時間を抑えているのである……。

画像出典:VULFPECK /// Sauna
と、いうのがVulfpeckのストーリーだ。
そして、メンバーが各々ソロ活動に忙しくしているあいだ、我らがリーダー、Jack Strattonは何をしているのだろうか?
もちろん、答えは決まっている。自分のソロ活動だ。
そしてそれが――Vulfmonなのである。
Vulfmonとは

画像出典:Jack Stratton Mixing Masterclass (Trailer)
それでは、満を持してVulfmonの紹介を始めよう。
前述のとおり――Vulfmon(ヴォルフモン)とは、Vulfpeckのリーダー、Jack Strattonのソロ名義だ。
Jackはオハイオ州クリーブランド生まれ。生年月日は非公開だが、こちらで判別した大学卒業年から、1987年~1988年生まれだと類推されている。
音楽経歴としては7歳からドラムを始め、10歳で父親のユダヤ音楽のバンド「Yiddishe Cup」に参加。その後、15歳でバークリー音楽院のサマープログラム(夏期講習)にドラマーとして参加した。
高校では「Calvin Coolidge」、大学では「Groove Spoon」というバンドを結成して活動。
大学卒業直後、Groove Spoonを解散させ、2011年にVulfpeckを結成。リーダーとしてバンドを成功に導いた後、2022年からVulfmonとしてのソロ活動を本格化させた。
VulfmonはJackが住むロサンゼルスを活動の中心として、Jackの友人や、Vulfpeckのメンバーなどをゲストに呼んでレコーディングを行っている。
Jackはドラムをメイン楽器として、キーボード、ベース、ギターを弾きこなし、最近では自ら歌うようになった。さらに大学ではレコーディングを学んでいるため、録音やミックスも自分で行い、いま流行りのDIYアーティストとして活動しているのがVulfmonなのである。
アルバムとしては2022年に「Here We Go Jack」を、2023年に「Vulfnik」をリリースしている。
また、最近は「Tokyo Night」という曲をリリースして日本で話題となった。(この曲は歌詞翻訳で筆者が携わっている)
さて、ではバンドであるVulfpeckと、ソロであるVulfmonにはどんな違いがあるのだろうか?
これは、大人数のVulfpeckとは異なり、Vulfmonでは最低限のミニマルな編成でレコーディングされている――というのがもっとも大きな違いであると言える。

基本的に1曲のレコーディングに関わるメンバーは2~3人、多くても5人を超えることは稀だ。多重録音が使われることも多く、これは7~8人で一発録りをするVulfpeckとは全く異なったやり方だと言える。
個人的には、ここにVulfmonの表現者としての魅力が詰まっていると思う。👆の画像で紹介している「How Much Do You Love Me? 」など、たった2人でレコーディングされ、Jackはひとりでキーボードとドラムを同時に演奏している。それなのに、生まれるサウンドはまるでバンドのようで、まったく「足らなさ」を感じさせない。
もともと「ミニマルファンク」と呼ばれるようなシンプルさを追求してきたのがVulfpeckだったのだが――Vulfmonでは、Jackはさらにそのミニマルな美学を推し進め、レコーディングで表現しようとしているのだ。

逆にそれ以外の内容は、かなりバンド(Vulfpeck)と似通っている。基本的な楽曲はファンキー&ポップであり、これはJackがVulfpeckで作曲してきた曲たち(Animal Spirits、It Gets Funkierなど)の延長線上にある。
YouTubeの動画やサブスク配信を中心として、インターネットで活動しているのも、Vulfpeckと同じだ。Vulfpeckではライブの頻度を減らしているが、Vulfmonはそもそも一切ライブを行っていない。
大手レーベル、マネージャーなどの力を借りていないのも同じ。レーベルはVulfpeck同様、Jackが創設したVulf Recordsからリリースを続けている。
というように、Vulfmonとは、ミニマルファンクとして活動してきたVulfpeckでJackが自ら作ってきた音楽を、さらにミニマルに表現しようとしているプロジェクトだと言える。
どの曲も必要最低限(ミニマル)な人数で構成され、減らせるものは極限まで削ってレコーディングされている。

画像出典:Never Can Say Goodbye - Vulfmon (feat. David T. Walker & Solomon Dorsey)
Vulfpeckのサイド・プロジェクトであるThe Fearless Flyersというバンド(Jackがプロデューサーとして関与している)も、やはり別の方向でミニマルさを追求していることからも分かるとおり、Jackにとって「ミニマルであること」は自己表現の柱であり、個人を特定するシグネチャーなのだ。

以上が、Vulfmonというアーティストの概要である。
Vulfmonの歴史
Jackはこれまで、「DJ Paradiddle」「Mushy Krongold」など、複数の別名義を用いて活動してきてた。「Vulfmon」もその別名義のひとつだったのだが――それを頻繁に使うようになったのは、2022年以降の話である。
だが、その誕生は少しだけ時を遡る。JackがVulfmonという名義を最初に使ったのは、2011年1月22日にリリースされた、「It Gets Funkier」だった。
ここではJackがひとりで演奏からレコーディング、ミックスまで完成させており、数か月後にVulfpeckでレコーディングされるバンドアレンジの「It Gets Funkier」のデモ音源という立ち位置になっている。
またその翌年、2012年に「Wait For It」をVulfmon名義でリリース。こちらはSly & The Family Stoneの「If You Want Me to Stay」 をオマージュしたもので、やはり2013年にリリースされるVulfpeckの「Wait for the Moment」のデモ音源のような存在であった。
しかし、ここから約10年の間、Vulfmonの名義のリリースはなかった。その間は別の名義を使っていたのである。それが、Mushy Krongold(ムシー・クロンゴールド)だ。
Mushy Krongold、短く「Mushy」と書かれることもあるこの名義は、2000年代末~2015年ごろまでJackが個人でどこかに登場する時に使われてきた。クレジットにJack Strattonと書くのではなく、「Mushy」もしくは「Mushy Krongold」と書かれてきたのだ。
Mushyはただのソロ名義ではなく、Jackが演じるコメディーのキャラクターでもあった。不安定で神経質なキャラクターで、2010年代前半のJackがボソボソ喋ったりオドオドしている時は、Mushyを演じていたのである。
スペンサー(インタビュワー):あなたが演じるムシー・クロンゴールドは、とても魅力的な分身ですね。ムシーはどうやって生まれたんですか?
ジャック:ザ・ジャーキーボーイズ(筆者注:いたずら電話をするネタで有名な、アメリカのコメディグループ)のキャラクター、「ソル・ローゼンバーグ(筆者注:不安定な性格で早口に喋る、ユダヤ人男性。いたずら電話で相手を困らせる)」にヒントを得た。当時、私とルームメイトは、ミシガン大学で暇をつぶすためにいたずら電話をしていた。私たちが開発したのは、もう少し声が高くてゆっくり喋る、それほど攻撃的ではないソル・ローゼンバーグだ。
このキャラクターの名前については、父と作り上げた。父は「クロンゴールド」という名前を思いつき、私は「ムシー」という名前を思いついた。そして「ムシー・クロンゴールドって、ちょっと詩的な名前だな」と思ったんだ。それから、私はムシーとしてビデオ撮影を始めた。探せば、ムシーとしてKickstarterで失敗したページがどこかにある。
そのKickstarterはちょっと中途半端なアイデアだった。ムシーがクリーブランド周辺で偽のドキュメンタリーを撮影するというものだ。考えてみれば、Kickstarterでひどい失敗をするのは、彼らしいとも言える。でも、これもアート作品の一部なんだ。近いうちに、もっと彼らしいことをするつもりだ。「Thrill of the Arts(2015)」の最後に、彼に瞑想をしてもらう。彼は「JewBu」、つまりユダヤ教の仏教徒(Jewish Buddhist)のようなものだ。ムシーがこれからどうなっていくかが楽しみだね。
「ムシーがこれからどうなっていくかが楽しみだね」とJackは語っているが、2016年以降、Mushyが登場することはなくなっていった。そこからしばらくは別名義を使わず、常に「Jack Stratton」という表記で通していたし、ソロアルバムもリリースしていなかった。
この時期はVulfpeckが(活動頻度は少ないとはいえ)忙しくなり、さらに2018年にThe Fearless Flyersという別プロジェクトも立ち上げ、2019年にVulfpeckをマディソン・スクエア・ガーデンに連れていくという大仕事を達成するために、Jackはそれらにかかりきりになっていたのだろう。
しかしその後、2020年にコロナ禍に突入すると、いろんな情勢が一気に変化した。
もっとも大きな変化は、このタイミングでCory Wongが世界的な知名度を得て、一年中ツアーをするようになったことだろう。それ以外に、VulfpeckでCoryの次にソロ活動が盛んなTheo Katzmanも活動が軌道に乗り、以前よりVulfpeckに使える時間が減った。
もともと少ない頻度で活動していたVulfpeckが、さらに少ない時間で動くようになったのである。これにより、Vulfpeckは初期からずっと貫いてきた「年1回アルバムを出す」という活動ができなくなった。
そしておそらく、その余った時間を使い、バンド以外の自己表現を、という流れでスタートしたのが、「Vulfmon」なのである。
まったく新しい名前を使わずに、約10年前に使っていた名前を引っ張り出してくるのがJackらしいユーモアだと言えるだろう。
「Vulfmon」が久しぶりに登場したのは、2022年6月4日。「How Much Do You Love Me?」の動画だった。
ここでは一切のVulfmonに対する解説もなく、またこの後も、JackはVulfmonについてインタビューなどで語っていないので、Vulfmonを再登場させた意図は分かっていない。
ただ、ここからはVulfmonを名乗るタイミングが非常に増えた。例えばVulfpeckでも、「Earworm」という曲でわざわざ「feat. Vulfmon」と記載してみたり、それ以外でもさまざまな場所にJack Strattonと書く代わりに、Vulfmonと書かれていることが多い。
2010年代前半にMushyと名乗っていたように、今は事あるごとに「Vulfmon」を名乗る時期に突入しているのだ。
名前の読み方と、その意味
Vulfmonの読み方は、「ヴォルフモン」だと筆者は考えている。
これは最も大きな理由が、公式のアルバムジャケットに日本語で「ヴォルフモン」と書かれているから、というものだ。

Vulfmonは「Vulf」と「mon」の2語が繋がった造語であり、この「Vulf」は「Vulfpeck」の「Vulf」と同一である。
「Vulf」はドイツ語で「狼」を意味し、これは「ヴォルフ」と発音される、というのも、「ヴォルフモン」と読める理由のひとつである。(発音確認はこちら)
さて、では名前の由来について。
これは、バンドである「Vulfpeck」が「狼の群れ」であり、ソロである「Vulfmon」は「狼の個人」を意味している、と考えられる。
それについて語られているのが、こちらの動画だ。
アレグラ(インタビュワー):ヴォルフ・レコーズのもう一つの神話は、「ヴォルフマン(Vulf Man)」についてです。このシンプルなレコード会社の、リーダーのようなものですね。
ジャック:そうそう。意味的には、群れ(Pack)がいれば、そこに個人(Man)がいるのは理に適っているだろう?


ここでは「Vulfman」と語られているが、文脈からこれが2011年に登場したJackのソロ名義、つまり「Vulfmon」を指しているのは明確である。
もともと「Vulfpeck」の「peck」も、英語の「Pack(群れ)」を無理やりドイツ語らしい発音の単語に置き換えた造語であるため、
「Vulfmon」の「mon」も同様に、英語の「Man」を何らかの言語風に置き換えた造語だと考えられる。Jackはこの動画ではその本来の意味を示すために、あえて「Man」と語っているのだろう。
と、いうわけで――
バンドは「Vulf(狼の)」「Peck(群れ)」
ソロは「Vulf(狼の)」「Mon(個人)」
というのが、Vulfmonに秘められた意味なのだ。
Here We Go Jack(2022)
さて、それでは現在リリースされているアルバムについて解説を行っていこう。
まずは2022年にリリースされた「Here We Go Jack」だ。
このアルバムはJackがVulfmonとしてリリースした初のフルアルバムである。コンセプトとしては特に何も語られていないが、ジャケット写真にも登場しているアイコニックなサングラスを使ったMVがいくつか撮影された。

全体的には前述のようにミニマルな編成によるアレンジでレコーディングされているのが特徴で、JackがVulfpeckにおける作曲術をさらに発展させたような曲が多い。
特筆すべきは、やはり1曲目の「How Much Do You Love Me?」だろう。
Jacob Jeffries(ジェイコブ・ジェフリーズ)と共作されたこの曲の素晴らしさについては、下記の私のnoteに詳しく記してある。
Jacob Jeffriesはここでの共演をスタートに、Vulfmonだけでなく、Vulfpeckのレコーディングやライブにも必ず参加する、Vulfpeckの新たな8人目のメンバーになった(といっても過言ではないだろう)。現在、Jackにとってもっとも重要な音楽的パートナーのひとりになったのである。
バンドとなるVulfpeckではあまりカヴァーをレコーディングしないJackだが、Vulfmonではその縛りを無くし、どんどんカヴァーを録音している。
Gilbert O'Sullivanの「Alone Again, Naturally」、The Jackson 5のバージョンが有名な「Never Can Say Goodbye」、そしてBachの「Contrapunctus I」だ。
JackはBach(バッハ)が大好きなので、今作ではRich Hinmanというペダル・スティール奏者をゲストに呼び、Bachの讃美歌(BWV 151)を用いた「Bach Pedal」というレコーディングも行っている。
「Let's Go! Let's Go!」という曲だけ、レコーディングに参加している人数が多く、他の曲と雰囲気が違うが、これはVulfpeckの「Let's Go!」という曲のレコーディングトラックを使い、上にMile Violaのヴォーカル、Cory Wongのギターを乗せた作品になっているからだ。
また、表題曲の「Here We Go Jack」は、Jackが初めて歌声を披露した曲である。
これを機に、JackはVulfmonだけでなく、Vulfpeckでも歌うようになり、表現のフィールドを大きく拡げることになった。
Vulfnik(2023)
2023年にリリースされた「Vulfnik」は、「Beatnik(ビートニク)」をもじって名付けられたタイトルで、ジャケットもビートニクの詩人をイメージした衣装のJackの写真になっている。
今作も前作同様、ミニマルな編成&アレンジによって作られており、基本的な路線は変わっていない。
大きな特徴としては、Jacob Jeffriesとの共作が増え、リミックスを含めると10曲中5曲にJacobが参加しているという点が挙げられる。JackがJacobに深い信頼を寄せているのが分かるだろう。
また動画のサムネイルも、Jackが好んで使っていたVulfpeckのブルーバック形式を脱し、背景がそのまま使われるようになった。
前作からスタートしたJackの歌はさらに完成度を高め、「I Can't Party」ではラップのような歌唱にも踏み込んでいる。この曲はアルバムの代表曲のような存在となっており、先日のVulfpeckのライブでもバンドアレンジが披露された。

画像出典:Vulfpeck Live at Bonnaroo
そして今作では、Vulfmonとしては初めてVulfpeckのメンバーがゲスト参加した。Antwaun Stanleyのヴォーカル、Joey Dosikのサックスソロによるゴスペルの名曲「Lord Will Make a Way」だ。
これはかなりVulfpeckらしいグルーヴになっているが、Vulfpeckなら7~8人の一発録りになるところを、Jackが多重録音することで3人で完結しているところが、やはりVulfmonのアレンジである。
またこのアルバムではMVにもこだわり、新境地を開拓した。
「Ucla」ではミュージシャンでもありアニメーターでもあるLouie ZongにMVを依頼。独特の可愛らしいアニメで曲を彩ってもらっている。
「BLUE」では珍しくチルなLo-fi Hiphopのような楽曲を作り、それによく合う日本のアニメのようなMVを付けてもらった。
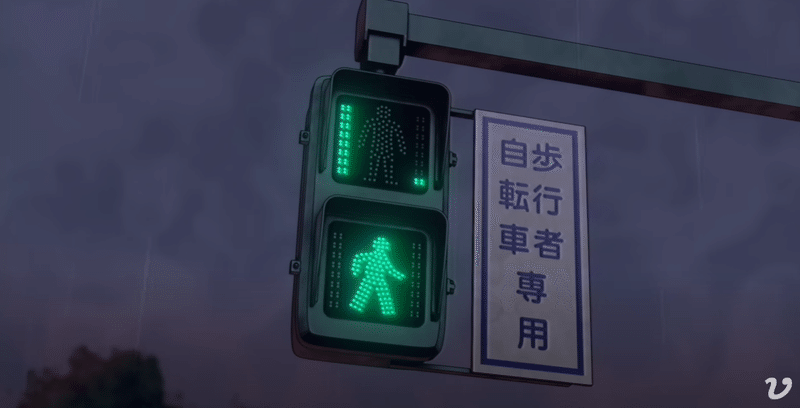
こちらのアニメ制作はLAのミュージシャン・ビデオクリエイターのPoint Loboによるもの。
こうした映像でのコラボレーション基本的にはVulfpeckでは行われないため、ソロプロジェクトのVulfmonにおける新たな試みだと言えるだろう。
また、新たな試みとしてもっとも興味深いのが、音楽ではなくコント作品も収録している点だ。
こちらはJack扮する黒服の男性が、モータウンのベーシストであるJames Jamersonが好きすぎるあまり、何を話してもJames Jamersonの話題に繋げてしまうというコントであり、学生時代からコメディの世界に深く傾倒していたJackらしい作品となっている。
このアルバムからは、収録された「Nice To You」をリミックスした「Nice To You (Little Yacov Version)」が、おげんさんのサブスク堂で紹介された。
リミックスによってJacobの声が高くなっているが、これはMicheal Jacksonのヴォーカル・モデルを使ってマイケルの声になるように加工したものだと👇で語られている。
以上が、「どこよりも詳しいVulfmon」だ。また新たなアルバムが出ると発表されているため、リリースされたら追記させていただくことにしよう。
◆著者◆
Dr.ファンクシッテルー

宇宙からやってきたファンク博士。「ファンカロジー(Funkalogy)」を集めて宇宙船を直すため、ファンクバンド「KINZTO」で活動。「KINZTO」と並行して、音楽ライターとしても活動しています。
■バンド公認のVulfpeckファンブック■
■ファンクの歴史■
■TwitterでVulfpeckやファンクの最新情報・おすすめ音源を更新■
もしよろしければ、サポートをいただけると、大変嬉しく思います。いただきましたサポートは、翻訳やデザイン、出版などにかかる費用に充てさせていただいております。いつもご支援ありがとうございます!
