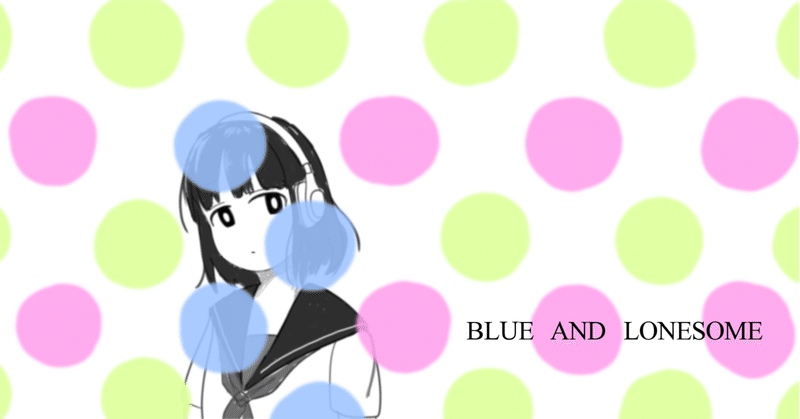
Roscoe Mitchell Sextet – Sound (1966)
1965年の秋、ブルースマンJunior Wellsはデルマーク・レーベルのサウンド・スタジオ・シカゴで名盤『Hoodoo Man Blues』を吹き込んだ。同スタジオではこうした60年代モダン・ブルースが生まれる傍ら、Roscoe Mitchellによるフリー・ジャズの金字塔『Sound』も録音(1966年)されており、本作はアメリカの前衛音楽団体AACMやArt Ensemble Of Chicagoの活動の起点となる記念すべきアルバムとなった。オリジナルのスリーブには〈AECシリーズの第一弾〉という文句が印字されていた。
Mitchellは『Sound』の録音の1年前から、リズム隊のAlvin FielderやMalachi Favorsと共にWUCBラジオ局のスタジオでセッションを行っていた。2011年に発掘された当時の音源を聴くと、あいまいだが純粋な破壊力を帯びたサウンドの応酬がジャズ・シーンの水面下ですでに繰り広げられていたことがわかる。
「Ornette」は言うまでもなくOrnette Colemanにリスペクトを捧げた賛歌だ。「One Little Suite」の前半部分ではウェスタン風のメロディが奏でられるが、それはすぐさま崩壊してリコーダーやハーモニカなど様々な〈非主流〉の楽器を駆使したアヴァンギャルドな展開へとなだれ込む。だがこの革新的なアルバムの白眉は、驚異的なLester Lashleyのチェロのプレイをはじめ音同士の間隔にまで神経を行きわたらせた「Sound」だ。Lester Bowieのホーンと左右で対をなすかのように行われるソロのやりとりには、後にAnthony Braxtonと繰り広げた対話式のデュエット・スタイルの原型が垣間見えることだろう。
