
「白鷺」





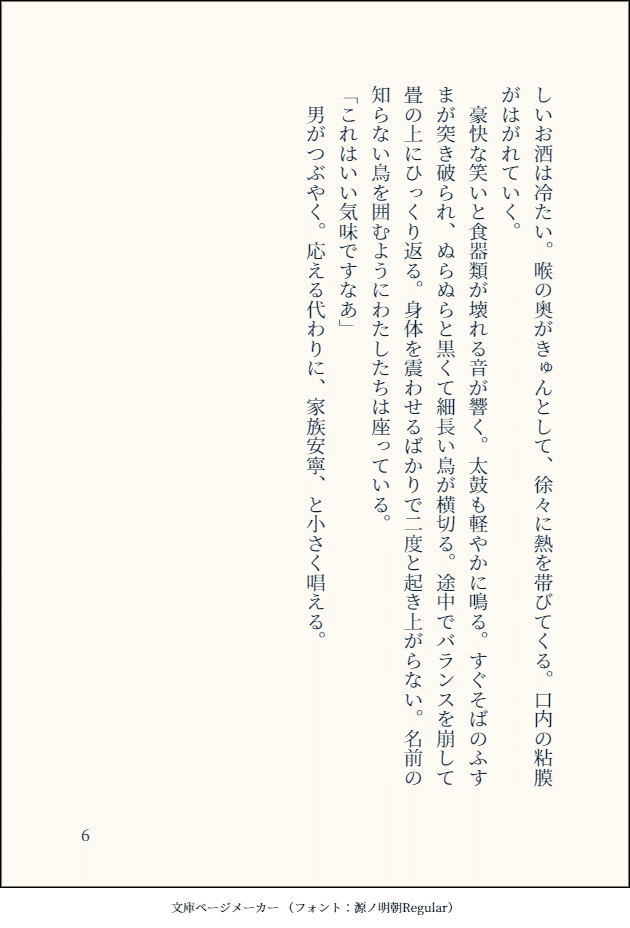
寝室のガラス戸をこつこつ叩く音がする。開けると、真向かいに白鷺が立っている。
「家族安寧、と三度唱えるのです」
白鷺はそう言って、すべるように退いた。それからぴゅんと真上に高く飛んで、去っていく。
わたしはウォークインクローゼットに入った。棚から紫色の小箱を取り出し、上蓋を開けた。紙の緩衝材の上で義父が眠っていた。教えられた通り、家族安寧、と三度くり返す。義父はさらに小さくなり、隙間へ落ちてしまう。底のほうでかすかに声が響いた。午睡から目覚めたらしい。ゆっくりと蓋を閉じて元の位置に戻す。
生温い風が入ってきて、背筋がぞぞぞと震える。ガラス戸を開けっぱなしだった。窓にはひびが入り、小さく放射状の円が広がっていた。クレセント錠を下ろしてカーテンを閉めた。二の腕が鳥肌で覆われる。荒々しく擦って温めた。
ぐえしゃらああああああ。
義母の強烈なくしゃみの音に驚くあまり、義父は一度死んだ。散骨を済ませたあと、伝達者と名乗る僧が現れる。あんな死に方をしたのだから極楽にも地獄にも行けやしない。彷徨う義父は最西の離島にたどり着く、と教えられた。
おやじを取り戻す。夫はすぐさま家を出た。取り戻すも何も骨にまでしたのに、と思ったけれど、それを口にする暇もなかった。義母はふさぎがちで家の奥にこもり、やがて自ら施設に入った。
こうして一人きりになった。無駄な空間ばかりが増えた気がした。ある日の午後、白鷺がわが家にやって来て、小箱を渡した。ベルベット地の立方体の中には小さな義父が入っていた。
一方、夫はいつまで経っても戻ってこない。
明け方、シャッターががしゃがしゃと響く。目覚めたわたしは廊下の突き当りのドアを開ける。ガレージ内は狭く、丸みを帯びた車のすぐ脇を通る。その間もシャッターがうるさく鳴る。半分ほど開いたところでモーターが止まった。白鷺が斜め向きに立っていた。
「本日は梨畑から来ました」
くわえているのはどう見てもカリンの実だ。嘴に挟んだままで、よく喋られるものだと感心する。ぐい、と口元を突き出してきた。受け取ると、白鷺は何も言わずに去った。長く助走をしてからようやく浮かび上がった。
仏壇にカリンを飾る。義父の遺影は外したけれど、毎朝仏間で手を合わせるのが習慣になっていた。
義父は小箱にちょうど収まるサイズに戻った。体調を悪くしたのか、三日ほど何も口にしていない。熟れかけのカリンを煮詰めて食べさせた。人さし指に乗せたどろどろの果実を義父は自らの小さな手ですくい、呷るように飲み込む。喉の通りがよくなったのか、夜遅くまで喋り続ける。そのほとんどを、なるほど、と機械的に応える。
義母から連絡があった。家の電話にかけてくるのは、彼女か電力切り替えを促すセールスくらいだ。義父が戻ったことを伝えても、義母は施設から出てこない。
わたしたちはよく無駄話をするようになった。義父にカリンをあげたことを報告する。義母はふぁいふぁいと笑う。受話器を持つ手の先から果実の甘い香りが漂い続ける。
夕暮れの終わり際、玄関に現れた白鷺は脚をけがしていた。羽にも艶がない。これは姿を変えた夫なのではないか。いよいよその思いを強くしているのだけれど、肝心なことを訊けない。白鷺は白い封筒をくわえている。
「わたしたちはとても元気です」
簡潔に力強く告げる。白鷺が逃げた。うまく飛べず、真横にひょんひょん跳ねる。そのまま浮かび上がり、すぐに小さくなる。
ドアの前に封筒が落ちていた。表面の一部が濡れていて、草と土が混じった匂いがする。中には晩餐会の案内状が入っていた。
門のそばには殺虫灯があり、じっ、と焼ける音がした。中庭が見える宴会場に入ると、食事が用意されてあった。集まっているのは見知らぬ人ばかりだ。きっちりとした白いスーツ姿が多い。部屋の四隅がうす暗い。会釈しながら空いた席に座った。
別の部屋から賑やかな声と余白の多い楽器の音が聞こえる。緊張しつつも膳にあるものをいただく。無表情の女性に注がれるまま、辛口のお酒を飲む。いい気分になったり、不安になったり、少し悲しくなったりする。新調したクリーム色のワンピースの裾を汚してしまう。次から次へと野菜を揚げた料理が出てくる。おいしいけれど異様に熱い。
本日はいかようなご縁で? と隣の男が尋ねる。
「白鷺が」
言葉が続かず、ごにょごにょとごまかす。ここに来れば夫のことがわかると思ったけれど、どのように説明していいのかわからない。
はあはあなるほどなるほど、それはようござんした。男は古い言葉を使う。新しいお酒は冷たい。喉の奥がきゅんとして、徐々に熱を帯びてくる。口内の粘膜がはがれていく。
豪快な笑いと食器類が壊れる音が響く。太鼓も軽やかに鳴る。すぐそばのふすまが突き破られ、ぬらぬらと黒くて細長い鳥が横切る。途中でバランスを崩して畳の上にひっくり返る。身体を震わせるばかりで二度と起き上がらない。名前の知らない鳥を囲むようにわたしたちは座っている。
「これはいい気味ですなあ」
男がつぶやく。応える代わりに、家族安寧、と小さく唱える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
