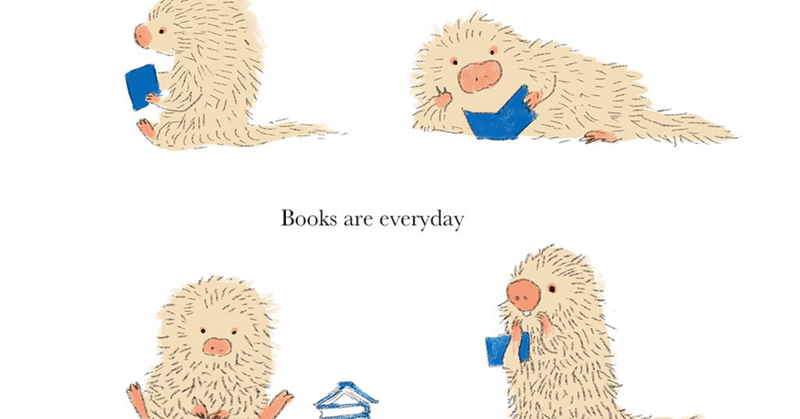
この本に出会えてよかった2021
今年も本を読みました。そして「出会えてよかった」と思える本にいくつも出会うことができました。息苦しさや先行きの見えすふなさが、どうにも拭えない一年。それでも、本はそばにいてくれた。足元を照らし、ここではないどこかに、窓を開いてくれた。特に印象深い10冊をまとめました。
1.「悪魔の細菌」
未知の細菌感染症に襲われた夫を救うため、科学者の妻があらゆる手を尽くして治療法を見つけ出すノンフィクション。科学の本であり、愛の本。春前ごろに読んだ本書は、一年を振り返ってみて最も胸が熱くなったノンフィクションだ。
これだ、という治療法を見つけたものの、効果は未知数で、リスクも高い。そこで直面する妻の葛藤が胸に迫った。自分は科学者として、治療法に賭けてみるべきなのか。それとも妻として、万が一にも最愛の人を死なせてしまう治療法を選択するのを避けるべきなのか。ひとは職業人として生きるだけではいられないし、家族としてだけでもいられない。矛盾を凝縮した難問だった。
本書に感動したとツイートしたところ、著者本人からリプライがあったことにも驚いた。本書をそれほどまでに普及しようというパッションを感じた。
著者は夫婦本人で、妻ステファニー・ストラスディーさんと夫トーマス・パターソンさん。訳者は坪子理美さん。中央公論新社、2021年2月25日初版。
2.「シカゴ・ブルース」
匂いと手触りのある小説。思い出すたびに、なぜか心強い気持ちになれる。1947年の作品が、2020年に新訳で出版された。名作は色褪せないどころか、新たな形で人の胸に迫るのだと教えてくれた。
作中で何度も登場するコーヒー。その香ばしい匂いが、読者の鼻先に漂ってくる。主人公はシカゴで路上強盗に父親を奪われた少年。彼がおじさんと共に犯人を探し回る時に、疲れを忘れるために必要なのがコーヒーだ。
自分にはそんな壮絶な過去はない。しかしながら、少年が経験したような「大人になるためのハードル」はあったように思う。いまは心の奥底に沈んだ思い出。それがコーヒーの香りと共に、ふと浮かび上がってくる。
静かで豊かな読書体験になった。
3.「ラスト・トライアル」
とにかく主人公が格好いい。思い通りにいかない人生。ここぞという時に思わぬ困難が降りかかる人生。「なんでこんな人生なんだ」と嘆いてもいいはずなのに、「やれやれ」とつぶやきつつ前に進む。そんな無骨な主人公の姿に勇気をもらう。
病に侵された老弁護士。ある日、彼の前に現れたのは、かつて彼が無罪を勝ち取った事件の余波で罪に問われたある女性の娘だった。なんと、女性は殺人の濡れ衣を着せられているという。「お母さんを守って」と、かつて追い込んだ相手である老弁護士に頼む少女。老弁護士は、女性や少女を守り切れるのか。
連作の3冊目。自分は最初にこれを読むという「暴挙」に出たのだけれど、それでも文句なしに面白かったことも印象深い。思わず1作目、2作目に遡って読んだくらい、圧倒的に引き込まれた。
老弁護士は1作目でそれまでキャリアを積んだ大学を追われ、2作目では親友が殺人の嫌疑をかけられる。これでもかと災難にぶつかるのだが、めげない。その姿勢はやや強すぎるけれども、物語の主人公はそれぐらいがいい。自分は米国版「半沢直樹」と思って読んだ。ちなみに4部作で、最終作が今後邦訳される楽しみが残る。
4.「クララとお日さま」
AIと人間はどのような関係になるのか、鋭く近未来を捉えたSF小説。世界中で最も読まれている作家の1人、カズオ・イシグロさんの最新作で、2021年待望の一冊でもあった。
AIを搭載した人工的な友人(AF)がポピュラーになった未来の英国。主人公は人間ではなく、このAFの一体であるクララだ。病弱な少女の家庭に購入されたクララは、その子を治すためには「お日さま」の力を借りなければならないと信じる。AIが「宗教」に傾倒するという、なんとも皮肉で深淵なイベントが中核をなす。
この他にも、あまりに重大で、答えのないテーマをいくつも内包する。AIと人間の友情は成立するのか。「完璧に設計された友情」は本当に友情なのか。AFが存在する背景として、人間に対する「改良技術」の存在も仄めかされる。そして、AFを持つ・持たざるの格差。
読むたび、思い起こすたびに味の変わる、繊細な料理のような物語。複雑化し、不確実さの増す現代においてまさにぴったりな、寄り添ってくれるストーリーだった。
5.「実力も運のうち」
今年は、いや、日に日に、この社会の競争は苛烈になっている気がする。それに疑問を投げかけ、楔を打ち込んでくれたノンフィクションだ。公共善に関する哲学論議で一躍有名になったマイケル・サンデルさんの最新作で、今年の話題をさらった。
テーマは能力主義(テクノクラシー)。「能力のある人間を評価する」という、現代社会において揺るがないシステムが本当に民主的で平等なのか、なにより「正義にかなうのか?」を問い掛ける。
タイトルは誤植ではない。「運も実力のうち」ではなく、「実力も運のうち」なのだとサンデルさんは言う。今風に言えば、人が努力で培ったと思い込んでいる能力もかなりの部分は「ガチャ」であるというのだ。
だから、能力主義は不公正で、社会の不満や分断を助長する。今の社会ってなんだか生きにくいなあと思ってる人には痛快な議論を展開してくれる。
「理想主義的で、能力主義社会への対案がない」という批判も聞かれる。それはたしかにそうで、改善策の論理的な強さは不完全な印象。でもかといって、能力主義の推進がいいわけでもなくないか?とは思う。
そんな議論に火を付けてくれたことが、まずは大きな意味を持っていると思っている。
6.「三体Ⅲ 死神永生」
この小説を読むために生きてきた。夏頃の刊行。「三体」を読むために生きようと言い聞かせた。中国発の超骨太SF3部作の最終巻。著者は劉慈欣。
あらすじを説明しようがないほどぶっ飛んでいる。1巻から続いてきた、人間よりはるかに高度な文明を持つ「三体星人」との攻防。2巻までに一応の決着をみたと思っていたのだが、なんとその戦いは宇宙全体を巻き込むより一層ハチャメチャな展開が待っていた。
太陽を3つの不規則な動きに翻弄される三体星や、宇宙版安全保障理論である「暗黒森林理論」など、「よくこんなこと思いつくな」というアイデア満載である三体シリーズ。今回も「どうしてこんなこと考え出したのだろう」と思うことの連続で、人間の想像力には底がないことが改めて示される。
これこそがSF、これこそが物語。全ての大変なことを忘れて、三体シリーズに浸る。その喜びがついに終わってしまったことだけが残念ではある。
7.「10代のための読書地図」
いま、本書に紹介された本を次々に読み進めるプロジェクトを個人的に進めている。その一つ一つが珠玉で、10代をとうにすぎた今でも、読めてよかったと思う。そんな本を一堂に集めてくれた、宝箱のような読書案内だ。
地図は大きく2部構成で、冒頭では書評家のみなさんが小中高生に推したい本をあーでもなこーでもないと議論して厳選。その後、青春や受験、部活といったテーマごとにおすすめの本を各推薦員が綴る。
大人が、10代にこそ読んで欲しい本を厳選する。それは一種のラブレターのようなもので、たくさんの想いが詰まる。たしかにそれらの本を読むと、10代のそのときにこそ読みたかったとの想いに駆られる。
誰かを思い本を薦める。そのバトンを受け取る。この作業の温かみがに触れられる本書は、この一年でことさら光る灯火になってくれたと感じる。
8.「トーキング・トゥ・ストレンジャーズ」
見知らぬ他者とどう関わっていけるのだろうか。分断が進みつつある社会でどう生きていくのか。この一年考え続けた問いだった。振り返って、最もヒントになる一冊はマルコム・グラッドウェルさんのノンフィクションである本書だった。
米国で、不審な車を止めた警察官と、止められた女性のトラブルを入り口に、「見知らぬ他者」と向き合う難しさを解きほぐしていく。米国の大学で起きた飲酒に絡むレイプ事件なども題材に、人と人の誤解や、なぜ人は時に他人を蔑ろにしてしまうかを考える。
その核心は「透明性のパラドクス」というべきもの。人は、他人のことをよく分かれるはずだと思う。一方で、自分自身は「世間一般」より複雑な存在だと思う。本来であれば相手も自分同様複雑だと考えるべきなのに、透明性を求めてしまうことに難しさがある。
本書に書かれているのは答えではなく、だからこそ他者と関わることはいまも難しい。しかし、少なくとも、他者は「自分が思うほどに透明ではなく、内面は見えにくい」ということは肝に銘じている。
小田急線事件や京王線事件など、他者の怖さが突きつけられる事件が相次いだ。それでも他者と生きるために、本書を再び参考にしたい。
9.「同志少女よ、敵を撃て」
師走に差し掛かって衝撃的な作品が飛び出した。圧巻の迫力。今年読んだ小説の中から一冊を選び出すなら、間違いなく本書を手に取る。逢坂冬馬さんのデビュー小説「同志少女よ、敵を撃て」。
思い起こしたのは伊藤計劃「虐殺器官」。同じくデビュー作ですさまじい世界観を打ち出し、読者を遠く遠くの世界に連れ出してくれた。
独ソ戦で激戦が繰り広げられたスターリングラードなどの都市。少女だけの狙撃隊。戦争における本当の「敵」。全てが精緻に組み立てられている。
ページをめくれば、そこには冬の風が吹く。血のにおいが立ち上る。戦場における女性の苦悩や、孤児として残された少女の痛みが浮かび上がる。
それでいて、紛れもないエンターテイメントなのだ。
次から次に、新しい才能は生まれる。それを見届けるためだけでも、この世は生きる価値があるのではないかと思わせれくれた。
10.「何もしない」
真っ白な表紙に、「何もしない」。徹底的な空白や拒絶を感じさせる見た目が斬新だ。でも本書は奇書ではない。この社会が、この時代が生きづらい人にとって、どっしりとした寄る辺になってくれる大樹のような本だ。
何もしないとは、「何もしないをすること」。それを実践することによって、加速する注意経済(アテンション・エコノミー)に抗おうとするのが「何もしない」の狙いである。
本書を読んで、加速的な社会に疑問を持つことは間違いではないと背中を押された。一方で、そこから逃げ出すことは出来ない。完全には自由になれない。だから「何もしない」のだという、非常に現実的な道を示してくれた。
何もしないとは、何かをする、つまりある一つの形に「決めること」を留保する態度でもある。これは、「自分自身は何者か」や「人生はどうあるべきか」という問いにも通じる非常に重要な姿勢でもある。私たちは、変わっていく。時代は流れていく。だからこそ、いまは何もしない、まだ決めないということも、大事なのだ。
読書もまた、終わりはない。今日まで考えたことは暫定解である。まだ、何もできていない。それでいい。だから明日も本を開き、何かをするための続きをしていけばよい。それでいいんだ。
------
来年もまた、たくさんの本に出会えますように。
「この本に出会えてよかった」はここ何年か続けています。2020年版はこちらです。
この本に出会えてよかった2019はこちら。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
